「戦後保守の巨星堕つ」中曽根康弘元首相-その功と罪

2019年11月29日、戦後7位の長期政権を運営した中曽根康弘元首相が逝去した。享年101歳。中曽根政権といえば、「三公社民営化(国鉄→JR、電電公社→NTT、専売公社→JT)」と、日米同盟の強化、とりわけ「ロン・ヤス」関係、さらに「戦後政治の総決算」スローガン、「不沈空母」発言を真っ先に思い浮かばれる方も多かろうと思う。
また、タカ派で保守政治家としてのゆるぎない政治信条から、現在でもその評価は、評価者の立ち位置によって激しく分れている。
ここでは、中曽根氏の政治家としての一貫した姿勢である「保守」の立ち位置に特にスポットを当て、その「功と罪」を振り返りたい。
1】「保守・タカ派・改憲論者」の政治家として
中曽根氏は1918年、群馬県高崎市の材木商の息子として生まれる。幼少時から秀才として知られ、静岡高校(現静岡大学)を経て東大法卒で内務省に入り、海軍主計中尉として任官され、現役時代は南方作戦に従事し、フィリピン、蘭印(現インドネシア)の作戦に従軍する。この時、乗船中の艦艇にオランダ・イギリス両軍からの直撃弾を受けるが、本人は無事であった。
よく中曽根氏は内務省→海軍主計という経歴の持ち主だから戦場経験は無い、と誤解されがちだがそれは事実ではなく、一歩間違えれば戦死の修羅場を生還している。事実、中曽根氏には弟が居たが戦死しており、これが後年、中曽根氏をして靖国神社参拝の動機のひとつに至らしめたという。
戦後、内務省を辞し、1947年の第23回衆議院選挙で立候補して初当選。ここから連続20回当選をして内閣総理大臣に登り詰める政治家・中曽根康弘が誕生するが、中曽根氏は当初から「改憲・再軍備・日米安保条約反対」のタカ派論者として知られた。
政治家・中曽根康弘氏を理解するうえで教科書的決定版だと筆者が考える『中曽根康弘-「大統領的首相」の軌跡』(服部龍二著、中公新書)より以下引用する。
一国の防衛の基本は、自らの意思で、自らの汗でやるべきです。いずれアメリカと同盟するにしても、日本は相応な再軍備をして、できるだけアメリカ軍を撤退させ、アメリカ軍基地を縮小しなければならない。さもないと日本は、永久に外国軍隊の進駐下にあり、従属国の地位に甘んじなければならない
出典:『中曽根康弘-「大統領的首相」の軌跡』服部龍二著、中公新書
中曽根は民主党総務会で「このような屈辱的条約(日米安保条約)に、われわれは責任を分担できない。アメリカは無差別爆撃で日本国民にたいへんな損害を与えた。われわれは、アメリカに賠償を要求すべきだ」と語気を強めた
出典:前掲書、括弧内筆者
中曽根は自派の会合などで「自主防衛」を説いた。「終局的には米国の核と第七艦隊以外は自主防衛にすべきで、そうでなければ安保条約は一九七五年ごろには情勢次第でやめるなど弾力的に考えるべきだ」
出典:前掲書、強調筆者
このように当選当初から中曽根氏は、強硬な対米自立論をぶつ姿勢であり、この姿勢は中曽根氏が当選1回目から生涯、貫き続けた思想信条でもある。
おりしも、時局は日本の講和と国際社会への復帰(サンフランシスコ講和条約)が実現され、同時に片務的な日米安全保障条約が締結された時代である。時の吉田茂内閣は、「軽武装、経済重視」の吉田ドクトリンを採用し、それが長らく日本では「保守本流」としての立ち位置として受け入れらたが、中曽根氏は当初から反吉田の旗色を鮮明にして、「憲法改正、自衛軍(国軍)の保持、自主防衛(対米自立)」をぶった。
この世界観は、戦後日本の保守政治家の基軸である「親米保守」の流れからすると非主流であり、実際に中曽根氏は自民党の派閥的にも非主流であり続けたのだが、やがてこういった「改憲・対米自立・自主防衛」は、概ね1970年代になると「新右翼」と呼ばれる既存保守(親米保守)への対抗軸として本格的に登場し、「YP(ヤルタ・ポツダム)体制打破」の気勢へと繋がっていく。
このような「保守本流」への対抗軸として、対米自立・憲法改正を中心とする「新右翼」の発想は、代表的なところでは石原慎太郎氏の『NOと言える日本』(1989年、ソニー会長・盛田昭夫との共著)に接続していき、やがて日本に於ける「新右翼・対米自立論者」の立ち位置の中核的存在と言えるまでなった。中曽根氏は明らかにこの「非主流派としての保守(当人は反吉田を意識して、”革新保守”と自称した)」の中心にいたことは間違いはない。
2】日米同盟深化と対米自立の矛盾
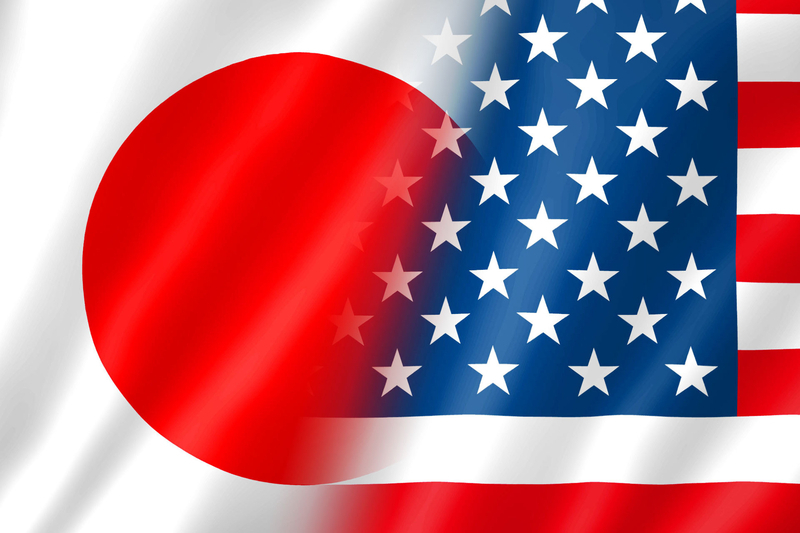
しかしながら、中曽根氏のこうした「改憲・対米自立・自主防衛」の強力でゆるぎない世界観は、中曽根氏が歴代内閣で科学技術庁長官、防衛庁長官などの要職を歴任して1982年に総理総裁の座を射止めると、筆者が冒頭で記したように、日米同盟の強化、とりわけ「ロン・ヤス」関係など、アメリカとの関係強化に腐心した事実と大きく矛盾するのではないか、という疑問が生じる。
要するに、日本の防衛力を高めようとアメリカに接近すればするほど、自衛隊はアメリカ軍と一体となり、対米自立・自主防衛の理想からは遠ざかる、という矛盾にぶち当たるのだ。とりわけ現代の電子戦においては、兵器をコントロールするソフトウェア等のコア部分をアメリカの技術が握っており、日米安保がある限り、幾ら自衛隊の装備を拡充してもアメリカの傘下から脱却するどころか、むしろ依存の度合いが高まる―という理屈もある。
果たして1982年に総理大臣になった中曽根氏は、自らの持論である「対米自立・自主防衛」と日米同盟強化にどう折り合いをつけたのであろうか。結論から言えば、この矛盾を放置したまま、中曽根氏は政権を竹下登に禅譲した。というより、中曽根政権にはそれ以外に選択肢は無かったとも言える。1982年はソ連がアフガニスタンを侵攻している真っ最中であり、1980年には西側諸国によってモスクワ五輪がボイコットされたばかりであった。
当時の国際情勢からすると、土台日本が米国の庇護を外れて自主防衛をするなどという選択肢はあり得なかったのである。そして、改憲-憲法改正をして自衛軍を創る、という機運も、国民世論としてはまったく盛り上がっていなかった(―現在でも、盛り上がっているかどうかは疑わしいが)。
そこで、中曽根氏を含め当時の新右翼は、「二段階自立論」ともいうべき対米自立構想をぶった。それは、
1)まずアメリカの庇護の元、自衛隊戦力の増強に努める
2)自衛隊戦力の増強が十分にかなったところで、一挙に憲法を改正して自衛隊を自衛軍に移行し、自主独立を達成する
という二階建ての構想である。事実、中曽根氏は政権担当時代、1)の課題に専心した。それまでの内閣(三木武夫以降)、防衛費をGNPの1%枠に抑えるという政策を撤回し、政権担当時代に防衛費は1%をわずかにだが突破した。が、それはあくまで政治的なパフォーマンスであり、飛躍的に自衛隊の戦力を高める、という中曽根氏の世界観の達成には程遠かった。
また2)の将来の自主独立に備えて、中曽根氏は防衛庁長官時代(佐藤栄作内閣)に核武装の研究を指示していた。
中曽根は、表向きに「非核中級国家」を標榜しつつも、防衛庁内では別の行動をとる。核武装の可能性について、防衛庁の技官らに研究を指示したのである。その結論は、二〇〇〇億円で五年以内に成算ありというものだった。難点は国内に核実験場がないことである。中曽根は、「広島・長崎の惨害を受けて、非核志向を提示すること自体は悪くないが、国際的には日本にも核武装能力があるが持たないという方針を示すほうが得」と判断していた
出典:前掲書
これが偽らざる中曽根氏の本心であった。が、こういった日本独自の核武装は今でこそ、与党野党を問わず国会議員が「議論の余地あり」と言うに憚らないが、中曽根時代には全くのタブーであった。よって中曽根氏が総理総裁になってから、日本の核武装に言及したことは一度もない。
が、このようなタカ派的な世界観を、中曽根氏は一貫して持ち続けた。そしてそれは全く達成できなかったにせよ、日本の新右翼に大きな影響を与えた。中曽根氏が科学技術庁長官として、原子力発電(核の平和利用)の推進に腐心したことは、この潜在的核武装論ともいうべき世界観と密接に関係している。
日本国内に商業発電用であれ濃縮ウランを保有することは、将来の日本の自主独立の為に有効であるという世界観は、新右翼の中ではほぼ共通の諒解事項となっている。であるから、「3.11」以降、所謂「保守派」が原発推進に拘ったのは、この潜在的核武装論が影響している。
しかしながら、商業用の濃縮ウラン(プルトニウム)は、核兵器向けのプルトニウムとはその純度が異なることから、商業原発を幾ら建設しても核兵器製造とは無関係、という見解もある。いずれにせよ、中曽根氏は日本の核武装を防衛庁長官として研究させていた潜在的核武装論者だったが、それは総理総裁時代にも達成できずに終わっている。
この構想が、「非核三原則を踏みにじる危険な発想」か、はたまた「日本の自主独立にとっての下準備」(―そもそも自主独立の前提が核保有という発想で正しいのかという議論はさておき)と見做すかは、後世の歴史家の評価が分かれるところであろう。
3】中国、韓国との友好関係構築の功績

中曽根氏には、戦前のアジア主義者的世界観が色濃く見える。それは中曽根政権の周辺国との外交関係の構築実績に顕著に証明されている。中曽根氏は日米の1国対1国の安保関係よりも、アジア全体での集団安保体制を構想した。勿論、その構想は実現しなかったのだが、特に中曽根政権発足後、中曽根氏が重視したのは韓国との関係である。
当時、日本の首相で韓国を公式訪問した人間はおらず、中曽根氏は政権発足後、初めての訪問国として韓国を選んだ。ここで中曽根氏はまだ軍事政権であった韓国の全斗煥大統領と会談。前掲書から当時のエピソードを引用する。
晩餐会では、全(斗煥)が中曽根の訪韓を「文字通り記念碑的なこと」と挨拶している。中曽根は「(日本が韓国に対して)不幸な歴史があったことは事実であり、われわれはこれを厳粛に受け止めなければならない」と述べ、今後は「互いに頼りがいのある隣人となることを切に希望する」と表明した。このスピーチで中曽根は、韓国語を多く交えた。中曽根が韓国語で話し始めると、韓国要人は驚いて耳を傾け、涙ぐむ者も多かった。
中曽根は晩餐会後も深夜まで、全と青瓦台、つまり大統領官邸の一室で懇談した。首相秘書官だった長谷川和年によると、全は「ナカソネさん、オレ、アンタニホレタヨ」と日本語で述べたという。
出典:前掲書、括弧内筆者
また、第三次内閣では蜜月の対韓関係に配慮して、日韓併合に関して不適切な発言を行った藤尾文部大臣を即座に罷免している。
藤尾発言とは九月一〇日発売の『文藝春秋』一〇月号で、韓国併合については韓国側にも責任はあったと述べたものである。中曽根は校正刷りの段階で原稿を入手し、発売日前の九月八日に藤尾を罷免した。
出典:前掲書
「日韓併合は合法で日本は朝鮮半島を植民地支配していない」などのトンデモ言説が与党国会議員のレベルでまかり通る現在では考えられないかもしれないが、当時の中曽根氏は本当にこういう事を躊躇なくやった。
一方中国との関係では、中曽根氏は一貫して日中友好論者であった。それは所謂戦前(殖産時代)のアジア主義が、中国を盟主とするアジア人の共同体的世界観であったからである以上に、当時の国際情勢が影響していた。中曽根氏は強烈な反ソ・反共主義者で、当時「中ソ対立」で同じ共産国のソビエトと対立する中国を「敵の敵は味方」と考えていた節が濃密にある。だが、外交的利害が一致したにせよ、中曽根氏が中国を単なる利害関係を超えた親しみを以て捉えていたことは事実である。
こちらも前掲書からの中曽根氏の訪中時のエピソードを引用する。
第二次内閣で中曽根は、最初の訪問先に中国を選んだ。胡耀邦総書記が一九八三年一一月に来日したとき、中曽根は訪中を要請されていたのである。(中略)
円借款については、注目すべき発言があった。中曽根は二四日、「対中経済協力につき謝意表明があったが、かえって恐縮しており、対中協力は戦争によりにより大きなめいわくをかけた反省の表れであり、当然のことである」と胡に述べたのである。円借款は中国の賠償請求放棄と公的には無関係なだけに、「反省の表れ」という発言は大胆といえる。胡は中曽根夫妻、長男の弘文夫妻らを中南海の自宅に招いて会食した。テーブルには、中曽根の好物である卵焼きと栗きんとんが並べられていた。李昭夫人、二男の劉湖や孫なども加わり、中曽根と胡は家族ぐるみで親交を深めていく。(略)
秋には胡が日本の若者三〇〇〇人を招待するなど、一九八四年は数千年に及ぶ日中関係史で最良の年といわれた。中国の存在がまだ巨大でなかったにせよ、日中提携と対米協調を両立できた指導者は、日本外交史をたどっても多くない。
出典:前掲書
このように、中曽根政権下、自らの靖国神社参拝(1985年)で中韓から抗議を受けたにせよ、中曽根政権下では中国・韓国との関係が蜜月であったことは特筆に値する。
中曽根以降、ゼロ年代以降の「保守」が、急速に「嫌韓・反中」一色になり、或いは「嫌韓・反中」さえ言っていれば「保守である」と自称するに憚らない昨今の「保守」と、中曽根時代の「保守」は、隣国に対する目線はこれほど違うのである。このことは、後世の歴史家が中曽根氏の歴史的功績として高く評価してもよいのではないか。
4】中曽根流「新自由主義」をどう見るか

最後に、中曽根政権での内政での実績について。最も大きなものは冒頭で記した通り「三公社民営化(国鉄→JR、電電公社→NTT、専売公社→JT)」の是非についてである。これは中曽根政権下ですべて達成されたことであるが、これを以て現在でも、中曽根政権の評価は真っ二つに分かれている。
つまり、中曽根政権での民営化路線は、小さな政府を志向した当時のレーガン(米)、サッチャー(英)に習う「新自由主義」の嚆矢として、現在でも賛否を含め様々な評価がある。だが、中曽根氏自身は「市場経済に任せておけばすべてうまくいく」という自由放任的経済観の持ち主ではなく、修正資本主義論者であった。修正資本主義とは、政府の介入・保護を前提とした資本主義体制を維持していくことであり、市場絶対主義とはまったく異なる。
事実、中曽根政権は修正資本主義を前提に、福祉国家の理想を掲げた。ただし、この福祉国家への流れは田中角栄内閣で1973年に提唱された「福祉元年」の潮流を受け継ぐものであり、日本が高度成長を1970年代初頭に終え、以後安定成長に向かっていた日本社会では、誰が政権を担当しても「日本の掲げるべき目標」として違和感なく歓迎されていた事であり、中曽根政権特有の発想とか世界観では無い。
さてこうした事実から、中曽根政権が取った民営化方針が果たして本当に「新自由主義」か否かには論争の余地があると筆者はみる。特に国鉄民営化について、当時、巨額の赤字を抱えていた国鉄が、中曽根以前から分割化の議論の対象になっていたことは事実である。
また、国鉄民営化の真の狙いは、強大な権力を誇った国鉄労組の解体と、その支持母体である社会党の弱体化を狙ったものであると中曽根氏自身が語っており、真に「新自由主義的理念」に基づいてこれらの民営化がなされたのかどうかは、議論の余地があるだろう。むしろ今となっては政治的な目的が強かったと言える。
こうした政治家・中曽根氏の実績を、「功」とみるか「罪」とみるかの分析は、一概に答えが出るものでは無い。しかし少なくとも筆者は、中曽根氏は「対米自立」という、反吉田の保守非主流から出発した「戦後保守」の典型的な巨星として、よく言えば国家観、悪く言えば民族主義的野心を内在した存在として、現実世界との矛盾に懊悩しながら良く時代を乗り切った宰相とみる。なぜなら現在の政治家には、少なくともこの「日米同盟深化と対米自立の矛盾」という懊悩すら、存在しないように思えてならないからだ。
5】矛盾を内包した「戦後保守」、中曽根康弘
「戦後保守」とはこのように、自己矛盾を内包しながら常にあるべき国家観と現実との落差の中で右往左往している存在であった。だからこそ、中曽根氏が当時「風見鶏」と揶揄されたのは、肯定的にとらえれば何ら違和感はない。このような懊悩すらない保守の政治家が繁茂している情勢こそ、保守にとっては痛打の筈だが、現在では迷わず、一直線にアメリカに追従することが国益と、ストレートに開陳することを憚らない政治家が多くなったように思う。戦争体験者の不在と戦争の記憶の風化が、政治家をして(―政治家ばかりではなく保守と名乗る言論人や学者が)直情的な対米追従に向かわせしめているのではないか。
中曽根氏はその個人的な対米自立という世界観を、政権担当中実現させることは出来無かった。それは冷戦時代という国際情勢がそうさせたのであり、中曽根氏がいかに一国の宰相とはいえ、どの道に転んでも実現は不可能であった。事実、中曽根氏があれほどこだわった憲法改正は今日に至るまで全く実行されていないし、実行する世論の沸騰もない。
「中曽根時代(1982~1987)」は、日本が世界に冠たる第二位の経済大国として、世界各国に瞠目するべき影響を与えた、まさに「日本文明の黄金時代」であった。その後、日本はバブル景気の絶頂を迎え、そして1997年を境に急速に経済は沈んでいく。それ以降の時局は、まさに語るべくもない。世界の成長とアジア各国の進展を横目に、日本は一方的に沈んでいく。
中曽根氏が想ったその「保守」の形が、現在とは全く異なるものであったことは歴史的事実として刻み付けるべきだと筆者は思っている。中曽根的な保守の宰相が、この国に再び現れるかどうかと問われれば、個人的にはNOだ。故人の御霊に合掌したい。(了)










