「日本版DBS」についてぜひ考えてほしいこと
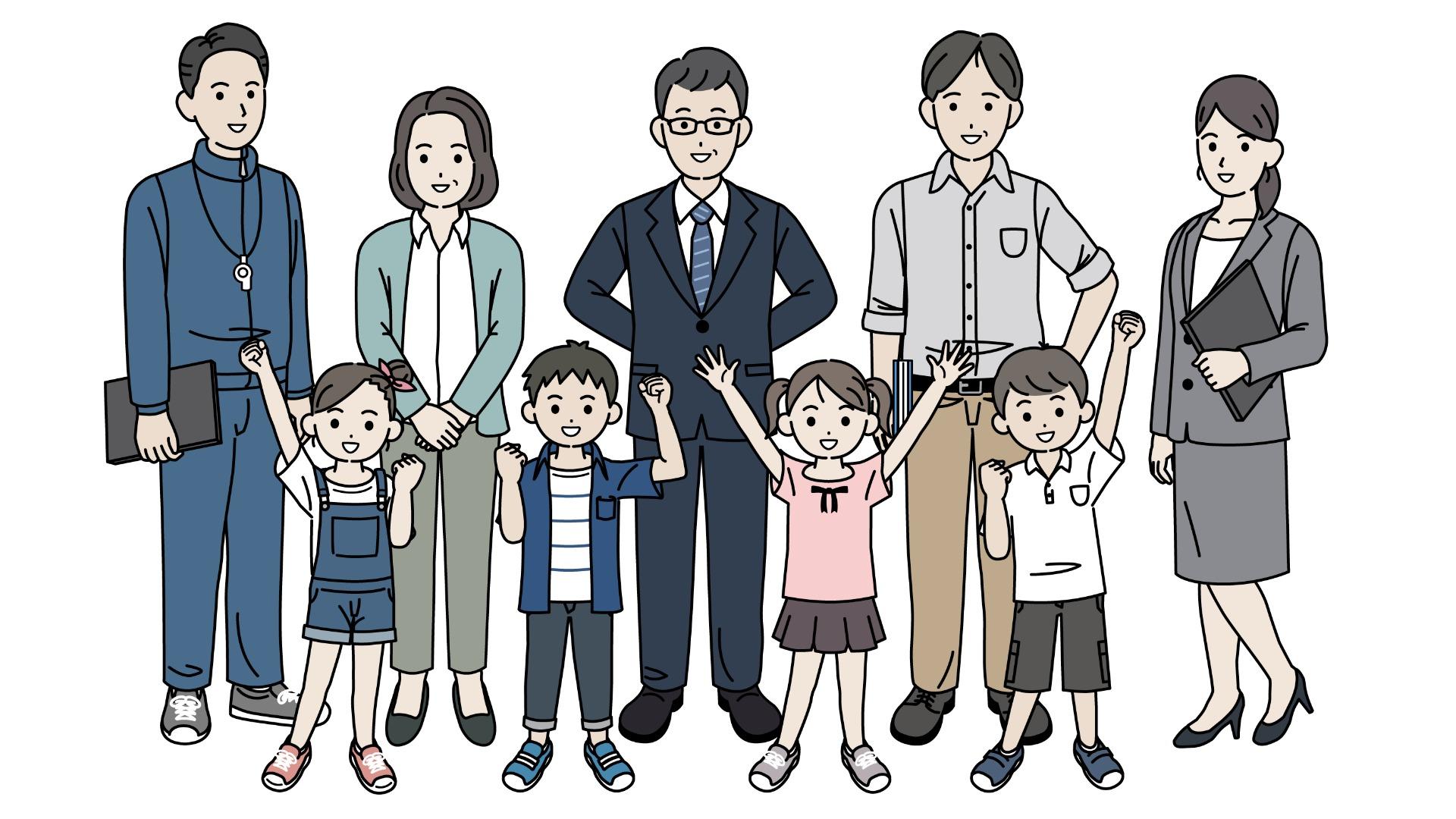
「日本版DBS」とは
「日本版DBS」とは、性犯罪前科のある者が教育に携わる職業につくことを制限しようとする制度であり、イギリスの制度に倣ったものである。今の国会に提出されている法案は、次のような内容である。(下図参照)

たとえばAがB保育園に就職を希望する場合、(1) B保育園はこども家庭庁に前科等についての確認申請を行なうとともに、(2) Aはこども家庭庁に戸籍情報を提出する。次に、(3) こども家庭庁はこれらに基づいて法務省に犯歴照会をかける。そして、(4) もしAに性犯罪の前科があれば、「犯罪事実確認書」をAに通知し、Aが就業希望を取り消せば、B保育園にこの内容が伝えられることはない。
このような制度であるが、これは今働いている人たちにも適用がある。その場合は、本人ではなく事業者に直接「犯罪事実確認書」が伝えられる(前科情報の民間流出)。事業者はその場合、該当者に配置転換などの措置をとることになる。職場によっては、退職を余儀なくされる場合もあるにちがいない。
ほとんどは前科のない初犯
このような制度だが、その一番の問題は、教育現場で起こる性犯罪のほとんどが実は「初犯」だといわれていることである。つまり、「日本版DBS」を導入しても前科前歴のない圧倒的大多数の初犯者の性犯罪は防ぐことはできないのである。
しかも、この制度は現職も対象としており、過去に過ちを犯したが治療を受けたり、過ちを悔い改めたりして、もう何年も問題なく普通に働いている場合であっても、その人の過去を詮索し、ほじくり返して、該当する人を排除する制度でもある。職場や家庭、地域社会で起きるかもしれない混乱には、たいへんなものがあるだろう。
性犯罪の前科前歴による人の選別と予防を目指すよりも、大事なのは初犯再犯にかかわらず性犯罪そのものが犯されにくい環境をどのように作るのかということについて、社会全体が知恵を出し合うことである。
さらにこの制度は、近年の刑罰についての考え方と調和するのかも問題である。
刑の消滅制度や拘禁刑創設と調和するのか
刑の消滅制度
そもそも「日本版DBS」は、刑法の「刑の消滅」(前科のリセット)の制度を大きく修正する制度である。
刑法第34条の2(刑の消滅) 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
刑の消滅とは、一定の要件を満たした場合に、刑の言い渡しの効力を消滅させる制度である。刑が消滅すると、そもそも刑の言い渡しがなかったことになり、そのため、前科による資格制限がなくなる。たとえば、弁護士や医師などの専門職では資格が制限され、公務員では禁錮以上の前科があれば当然に失職するが、刑が消滅すれば弁護士や医師、公務員になる資格は回復する。これは何よりも前科という個人情報が、社会復帰の妨げになるからであり、「日本版DBS」は、この刑法の制限をはるかに超えて、一線を踏み越えてしまった者の贖罪を妨げる効果がある。なお、罪を犯したという「前歴」は残るが、これが民間に出ることはない。
拘禁刑の創設
また、「日本版DBS」は、最近刑法改正によって行なわれた拘禁刑の創設(懲役刑と禁錮刑の区別の廃止)を導いた考え方と調和するのかも疑問である。
拘禁刑の創設は、従来、刑務作業を課すことを要件としていた懲役刑とそうではない禁錮刑の区別を廃止し、拘禁刑に一本化するものである。これは、実質的には「懲罰」(懲らしめ)という意味合いが強かった懲役刑から大きく転換し、たとえば再犯を防ぐための教育プログラムを受けさせたり、仕事に必要なスキルや、学力を身に付けさせたりなど、受刑者それぞれの特性に応じた処遇を行なうことによって、その立ち直りを後押しするという考え方である。
これは、刑罰のもつ犯罪者改善機能を重視するものであり、受刑に伴う苦痛を与えることに重きを置くよりも、受刑という時間を社会復帰に向けて最大限効果的に無駄なく活用しようとするものである。
これと、前科による選別を目指す「日本版DBS」ははたして調和するのだろうか。
いくら特別法であっても一般法の基本原則を超えることはできない
法案は、(特別な目的を追求する)刑法の特別法という位置づけになるだろうが、特別法でも一般法である刑法の基本原則は修正できない。たとえば、刑法は江戸時代にあった「むち打ち刑」や「入れ墨刑」などの刑罰を認めていないが、かりに特別法を作って特定の犯罪にこのような刑罰を科すことを規定することが許されるかといえば、いくら「特別法は一般法に優先する」という原則があっても、刑法の基本原則から逸脱することになる特別法は認められないのである。
法案を拡大する「要望書」
最近、一般社団法人SpringとBe Brave Japan、それに専門家である斉藤章佳氏の三者合同による「要望書」がこども家庭庁に提出された。
これは、法案のように犯罪事実確認の仕組みを、事業者の犯歴照会とするのではなく、こどもに接する一定の職業に就業を希望する場合には、あらかじめ性犯罪歴のないことを条件にこども家庭庁のデータベースに登録することを要求するものである。またこの登録は1年ごとに更新される。
これは、いわばホワイトリストの作成をこども家庭庁に義務づけるものだといってよいだろう。その意味では、法案のように前科情報が民間に流れる制度よりは評価できるが、次の2点においてなお疑問がある。
第一は、えん罪の問題である。
要望書では、たとえば痴漢行為などの条例違反も特定性犯罪に含まれているが、問題は、法案を拡張して、その「示談成立歴及び、起訴猶予による不起訴処分歴」も対象に含んでいることである。とくに電車内などの痴漢行為については、えん罪の問題がある。その数はもちろん分からないが、痴漢については示談や罰金などで済ますことにしぶしぶ同意したえん罪のケースも多いといわれており、社会問題になるほどの重大な問題である。当然、その人たちにも性犯罪の(前科はなくとも)前歴は残っている。
要望書では、「過去に実際に性加害していることが確実であるにも関わらず、『示談』『起訴猶予』に」なった事案がDBSの対象から漏れてしまうことを防ぐためだとしている。しかし、何年も前の事件で、だれが、どのような資料(証拠)にもとづいて、確実に犯人だということを判断するのであろうか。
第二は、職域が極端に拡大する可能性があることである。
要望書では、「(1) 18歳未満の児童に、(2) 1日1時間以上(家庭教師は1時間単位であるため)、(3) 有償無償を問わず、(4) 業として(反復継続性・事業遂行性)、(5) 接する者(直接・間接とも)」、を対象とすべきだとされている。
これは法案が予定している職域をさらに大幅に拡張するものである。たとえば少年野球やサッカーなどのコーチや世話人、子ども食堂のボランティアなどがすぐに思いつくが、さらにたとえば産婦人科医や小児科医、またそこで働く看護師などもこの条件に該当するだろう。しかも、この人たちは毎年登録を更新しなければならず、更新を怠れば罰則が科される。
また、このデータベースは一般にも公開することが予定されている。つまり、これを経年的にチェックすれば、だれが性犯罪を犯したのかが容易に推測されるようなものになっているのである。
結局、性犯罪歴で犯罪を予防しようとすることじたいに無理がある、といわざるをえないのである。(了)










