「おこづかい?おこずかい?」もう迷わない!日本語教師が教える「づ・ず・じ・ぢ」の書き方ルール
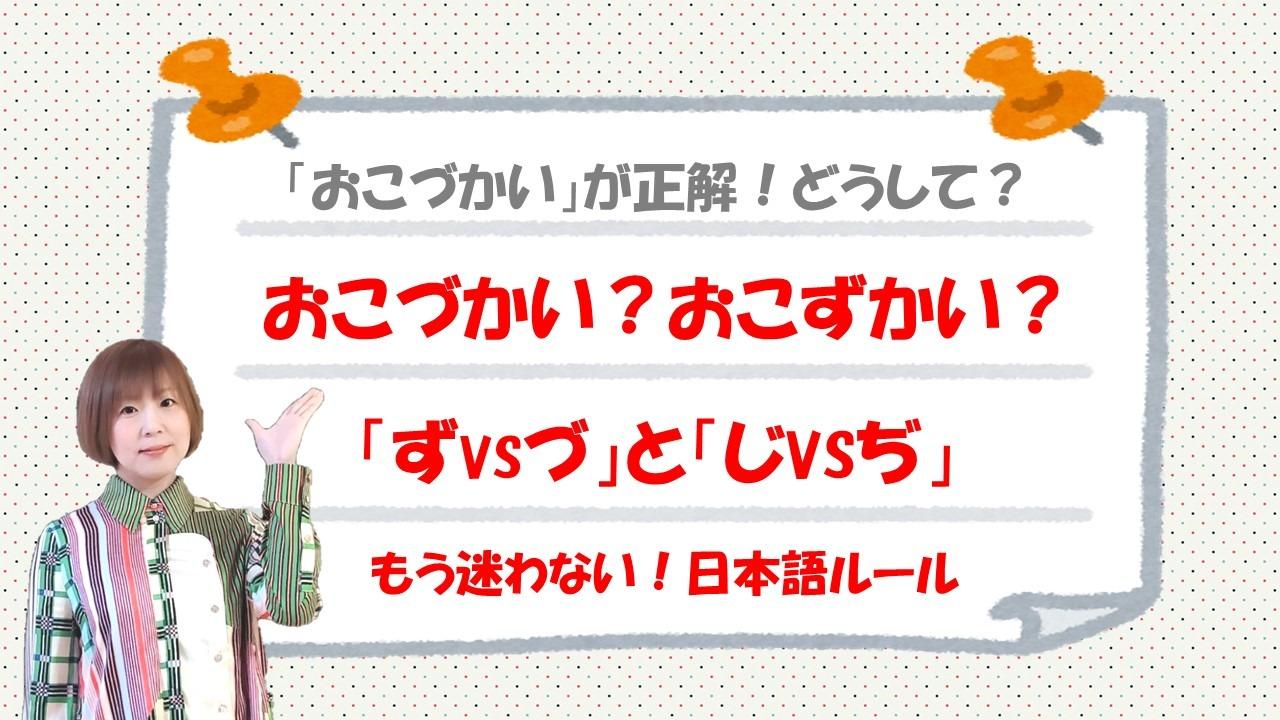
お読みくださってありがとうございます!日本語教師の高橋亜理香です。
みなさんは、「づ」と「ず」や「じ」と「ぢ」の書き分けに悩んだことはありませんか?
「おこづかい」VS「おこずかい」
現代なら、発音すればどちらも同じ音ですが、いざ入力しよう、書こうとするときにふと「あれ?」と止まってしまう人も多いのではないでしょうか。実際にネット上でも、「おこづかい おこずかい どちらが正しい?」などのようなサジェストが出てきたりするものです。今回は、この小悩みを解決できる、簡単な日本語ルールをご紹介します!
日本語の「かな」には「現代仮名遣い」という目安がある
実は、日本語の「かな」の書き方には「現代仮名遣い」というルールがあります。これはあくまで社会生活の上での目安で、厳格な規範的要素のものではありません。そのため、特殊な専門分野や芸術活動などについては、このルールが必ず適用されるわけではないのですが、一般的な文章の場合はルールに沿えば間違いのない指針のようなものです。
基本は「ず」「じ」、オプションは「づ」「ぢ」
現代の日本語の場合、「ず」と「づ」、「じ」と「ぢ」は音声も同じで、区別はしないものと考えています。そのうえで、現代日本語では「ず」と「じ」が一般とされ、基本は「ず」「じ」を使用するというのがルールです。例外のルールにはまるものが、特別に「づ」「ぢ」で表されます。
じゃあ、タイトルに出てきた「おこづかい」と「おこずかい」はどちらが正しいのかというと…結論からいえば、実は「おこづかい」が正しい表記です。なぜかというと、これは例外に当てはまるものだからなんですね。
では、「づ」や「ぢ」を使用するのが正しいときのルールをご紹介します。
1.「ちぢむ」→同じ音の連呼(連続)の場合は「づ」「ぢ」を使う
ひとつ目は、同じ音が2回連続する言葉の場合「づ」や「ぢ」を用いるというルールです。
例えば、「ちぢむ(縮む)」「つづく(続く)」などが、そのルールに当てはまります。ちぢまる、ちぢめる、ちぢこまる、つづみ(鼓)、つづる(綴る)、つづら…なども同様なので、ぜひ覚えておいてください!
※ただし、「いちじるしい(著しい)」と「いちじく(無花果)」は、このルールが適用外の特別な言葉です。
2.「はなぢ」→2つの語を連合した場合は「づ」「ぢ」を使う
日本語のルールに「連濁」というものがあります。「ガス」+「かいしゃ(会社)」→「ガスがいしゃ(会社)」のように、2つの語が連合したときに、後ろの語が濁るというルールです。
2つ目のルールは、この連濁が「つ」「ち」に起こった場合、「づ」と「ぢ」が適用されるというものです。
例えば、「はな(鼻)」+「ち(血)」→「はなぢ(鼻血)」のような場合です。この場合は、最初の語「ち」に濁点をつけることになります。
身近な言葉では、みかづき(三日月)、はこづめ(箱詰め)、こづつみ(小包)、つねづね(常々)、にいづま(新妻)、てづくり(手作り)、こころづくし(心尽くし)、うたれづよい(打たれ強い)…など。「身近な」も、このルールで「みぢか」です。タイトルの「おこづかい」も「こ(小)」+「つかい(遣い)」の連合なので「おこづかい」が正しいのです。
ただ、現代日本語として2語に分けにくくなっているような言葉は、基本の「ず」「じ」でよいとされています。例えば、「せかいじゅう(世界中)」「いなずま(稲妻)」「さかずき(盃・杯)」「ほおずき(鬼灯)」のような言葉です。これらは「ず」「じ」が基本ですが、「づ」「ぢ」を使っても間違いではないという扱いとされています。
また「ひとりずつ」や「ちからずく」なども、このルールにあてて「ず」「じ」でよいということになっています。
3.「じめん」→漢字の音読みが元々濁っているものは「じ」「ず」
3つ目は、これ。元々漢字そのものの音読みが濁っているものは「じ」「ず」を使います。そう言うと少しわかりにくいのですが、「じめん(地面)」「ぬのじ(布地)」「ずが(図画)」「りゃくず(略図)」といったものです。特に「地」は「ち」という読み方があるので、そこに濁点をつけるのかと思ってしまいがちですが、「じ」はそもそも「地」という漢字の音読みなのです。
日本語はルールがあるので、知れば迷わない!
今回は、ついついどちらか悩んでしまう「ず」VS「づ」と「じ」VS「ぢ」の日本語かなルールのご紹介でした!「どっちだっけ?」といつも迷っていた人は、これでもう大丈夫!ぜひこのルールを覚えて役立ててみてください。










