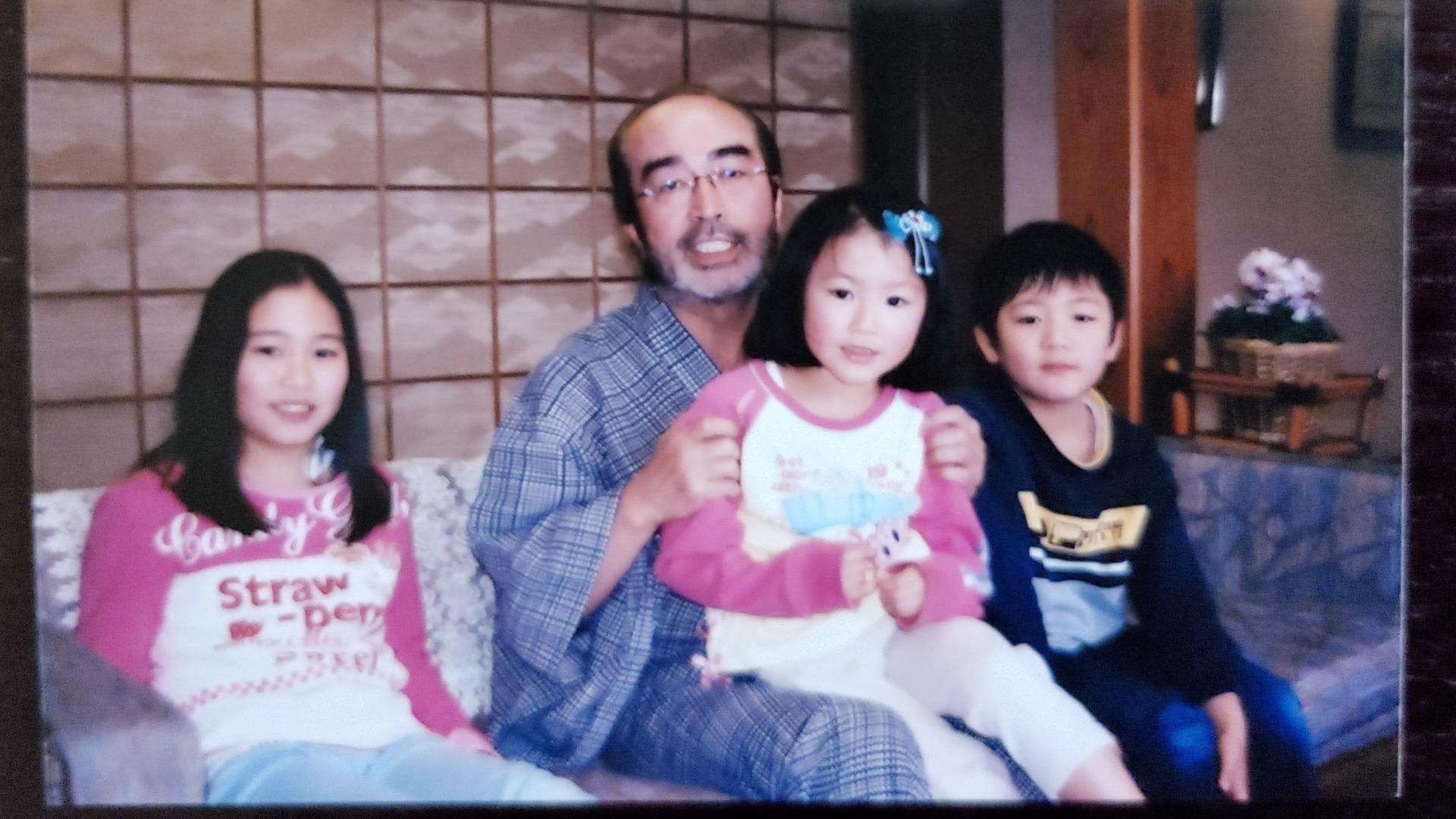育児中の親世代へ。父の不在を描く映画『こはく』が伝えること

幼児虐待事件などのニュースに触れるにつれ、おのずと親と子、それぞれの立場から家族や肉親との関係について考える場面が増えているのではないだろうか? 兄弟の父親探しを描いた現在公開中の映画『こはく』は、そうした家族間での痛ましい事件が起きている今だからこそ観てほしい1作だ。
井浦新と共に、お笑い芸人、アキラ100%が本名の大橋彰で主演を務めたことに話題が集まる同作だが、へんに親子の愛情を謳い煽ったような家族ドラマではない。親子関係について痛烈なメッセージを発した映画とも違う。ただ、なにか本来の親と子のあるべき姿を映し出しているとでも言おうか。現在の日本社会でどこか歯車が狂った親子関係について大切な「何か」を気づかせてくれる作品になっている。
記憶に蓋をしていた「父の不在」と向き合う
映画は、幼いころ、母と離婚して音信不通となった父親を、すでに成人して社会人となった弟の亮太と兄の章一が探す物語。手掛けた横尾初喜監督の半自伝的なストーリーになっている。今回、自身の体験を基にした理由を横尾監督はこう明かす。
「1番大きかったのは、自身の離婚。状況が自分の両親のときとほぼ一緒だったんです。父と母の離婚を兄は覚えていますが、まだ幼かった僕はあまり記憶にない。二人の息子がそれぐらいの歳で、僕も離婚してしまった。で、離婚に踏み切れたのは、自分が父がいなくてもまったく平気だったから。僕の感覚としては父親が不在でも普通に育つでしょうぐらいに考えていたんです。ところが兄は違った。あるとき、父の話になったら、ものすごく『恨んでいる』というわけです。今までそんな事ひと言も聞いたことがない。その瞬間、自分も息子から恨まれているかもしれない、『まじかと』(苦笑)。このとき、自分にとっての父親の存在と、父親としての自分と1度しっかり向き合わないといけないと思ったんです」
ここから自らの記憶をたどる旅へ。そこで自分でもまったく気づいていない自身の深層心理に気づくことになる。
「ほんとうに父の記憶がないんですよ。幼少間もないころでしたから、父の姿を覚えていない。だから、自分としてはもともと存在しないようなものですから、全然平気だと思っていたわけです。ただ、母に聞くと離婚した直後は『荒れてた』と。あと、小学生のときも、友達に自分から『うちおやじがいない』とか『母子家庭なんだ』とアピールして、相手が言葉に詰まるということがよくあった。当時はほかと違って面白いから言っていたつもりなんですけど、今考えるとたぶん傷つきたくなかったんじゃないかと思うんですよね。強がりで、相手に言われる前に自分で先に言っちゃう。相手の口封じで、自己防衛していたのかもしれない。そんな自分の中に眠っていた本心に気づいたんです」
おぼろげながら父の存在と忘れていた思い出もよみがえったという。
「母方で育ちましたから、親戚関係もあまり父についてはよくはいわないんです。当然といえば当然なんですけど。ただ、今回、客観的に調べていくと、写真がけっこう出てきて、自分を抱きしめてくれているものもあった。母にもがっつり(笑)取材したんですけど、兄が生まれたとき、すごく喜んでいたとか、自分たちをちゃんと愛してくれていたことがわかることが出てきた。父の知人からも話しを聞けたんですけど『すごく子どものことを気にかけていた』と。あと、離婚後に1度だけ父と会ったことがあるんです。劇中でそのまま回想シーンとして描いているんですけど、駅のホームで父が何か買ってやるといっている場面です。このとき、兄も僕も大号泣したんですけど、そこからなにか父について触れることは我が家ではタブーになった。話題にあげることは封印された。そういうエピソードに触れるにつれ、『父は自分を愛していなかった』という風に自分で作ってしまっていたところがあったことに気づきました」

一方で兄の怒りにも理解が示せたと明かす。
「僕は幼くて気づきませんでしたけど、父親から手紙が届いていて、その内容を兄は母親と共有していたみたいなんですね。つまり兄は父の情報がたびたび入っていた。あと、兄には父がいつか必ず迎えにくるという記憶が鮮明に残っていた。その上、苦労する母を傍らでずっとみていたから、長男だし自分が支えなきゃいけないとか、自分がしっかりしないといけないとか、家族を背負っている意識がどこかあったみたいです。僕は父を忘れることで平静を保っていたけど、兄は恨むことで平静を保っていたのかもしれない」
女優で妻の遠藤久美子が父親にさせてくれた
こうしたひとつひとつ自身の心に眠っていた気持ちを丹念に紡いでできた父親探しのドラマは、今改めて父親の存在をクローズアップ。イクメンなどの言葉が浸透しながらも、いまだ家庭での存在感が薄く煙たがられる人間として片づけがちな日本の多くの作品とは違う。父親の存在そのものをしっかりと見つめた作品となった。
「『父なんていなくて平気』と半ば豪語してたような子どもだった僕でしたけど、やはり父の存在は確かに大きかったんだなと。幼い子どもにとってはお母さんもお父さんも関係ないような気がするんですよね。どちらにも分け隔てなく愛情を求めてくる。現在、再婚した妻(※女優で今回の映画にも出演している遠藤久美子さん)との間の子どもが2歳半なんですけど、全力で愛情を求めてくる。それに対して、全力で答えようとしている自分がいて、なんで前の子どもたちのときにこういう気持ちが生まれなかったか悔やんでいます。だから、この父としての心を今はちゃんと覚えておきたいと思っています」
そのことに気づかせてくれたのは、現在の妻の遠藤久美子かもしれないと明かす。
「離婚して息子が2人いることは、お付き合いするから話していました。それで結婚して第一子が誕生するときに、彼女の方から、前妻と息子2人にきちんと報告をしたほうがいいよと言われたんです。はじめは『この人、何を言ってるんだろう?』と驚いたんですけど、彼女は『離れ離れになってはしまったけど、前の奥さんの子どもにとっての父親はあなただから、ちゃんと会ってあげてほしい』と。女性は強いなと思いました。と同時に父親としての男の弱さ、ダメさを見透かされたというか。『子どもから逃げないで、ちゃんと向き合って父親の責任を果たしなさい』とハッパをかけられたような感じで(笑)。現在の妻に父にならせてもらった気がします」
作品の内容は、父の存在だけではなく、家族のつながりについても言及。「絆」や「団らん」をキーワードに「親密さ」「仲の良さ」がなにか理想の家族の象徴とされるケースが多い中、本作は家族であれども、それぞれに自己がありほどよい付き合いの距離があることを教えてくれる。
「たとえば、男兄弟なんて多くの場合は、ある段階がきたらほとんど会話なんかかわさない。母を介して、僕だったら兄の現状を知ったりするわけです。でも、だからといって兄を無視しているわけではない。母にはたまに強い言葉を言ってしまうことがあるんですけど、それはいまだに自分の中に甘えがあって許されると思っているから。なんでも話し合って、しょっちゅう顔を合わせるのだけが家族じゃない。むしろ会話がさほどなくても、なんとなく相手のことが気になってつながっているように思えるのが家族なのかなと。そのあたりを素直に描いたら、こんな家族の物語になったんです」
この作品を自身ではこう感じている。
「ずっと『優しさ』ってどこからくるんだろう?そのことを、自分なりに突き詰めたいと思っていたんです。今回、撮影したのは地元の長崎。この場所を考えたとき、この土地で生きる人間はどこかで哀しみを知っている。劇中に登場する人物たちも哀しみを抱えている。その2つが重なったとき、哀しみを知る人間の本当の意味での優しさに触れた気がしたんですよね。単なるうわべの優しさではない、もっと深い愛情の込められた優しさというか。時に相手に厳しく助言するのも優しさだし、相手を気遣ってあえて何も言わないのも優しさ。そういう優しさがもっと今の社会にあっていいんじゃないかなと。僕の中では、半自伝的な映画であると同時に人の『優しさ』についての映画だと思っています」
最後にこう言葉を寄せる。
「僕にとっては今回はパンドラの箱を開けるといいますか。蓋をしていったんなきものにした封印した記憶を解き放った作業だった気がします。タイトルの『こはく』もそこからつけられていて、化石のように眠っていた記憶が発見されたみたいな感覚がありました。きわめて個人的な話かもしれません。でも、家族を持つ多くの人に届く作品になったんじゃないかと思っています」

「家族はこうあるべき」といった家族の在り方を問うた映画では決してない。ただ、元農水事務次官による息子殺害事件をはじめとした親子関係をめぐる事件が相次ぐ今、家族における自身について深く考える機会になるに違いない。また、親子で楽しむことができるホーム・ドラマであることも付記しておきたい。