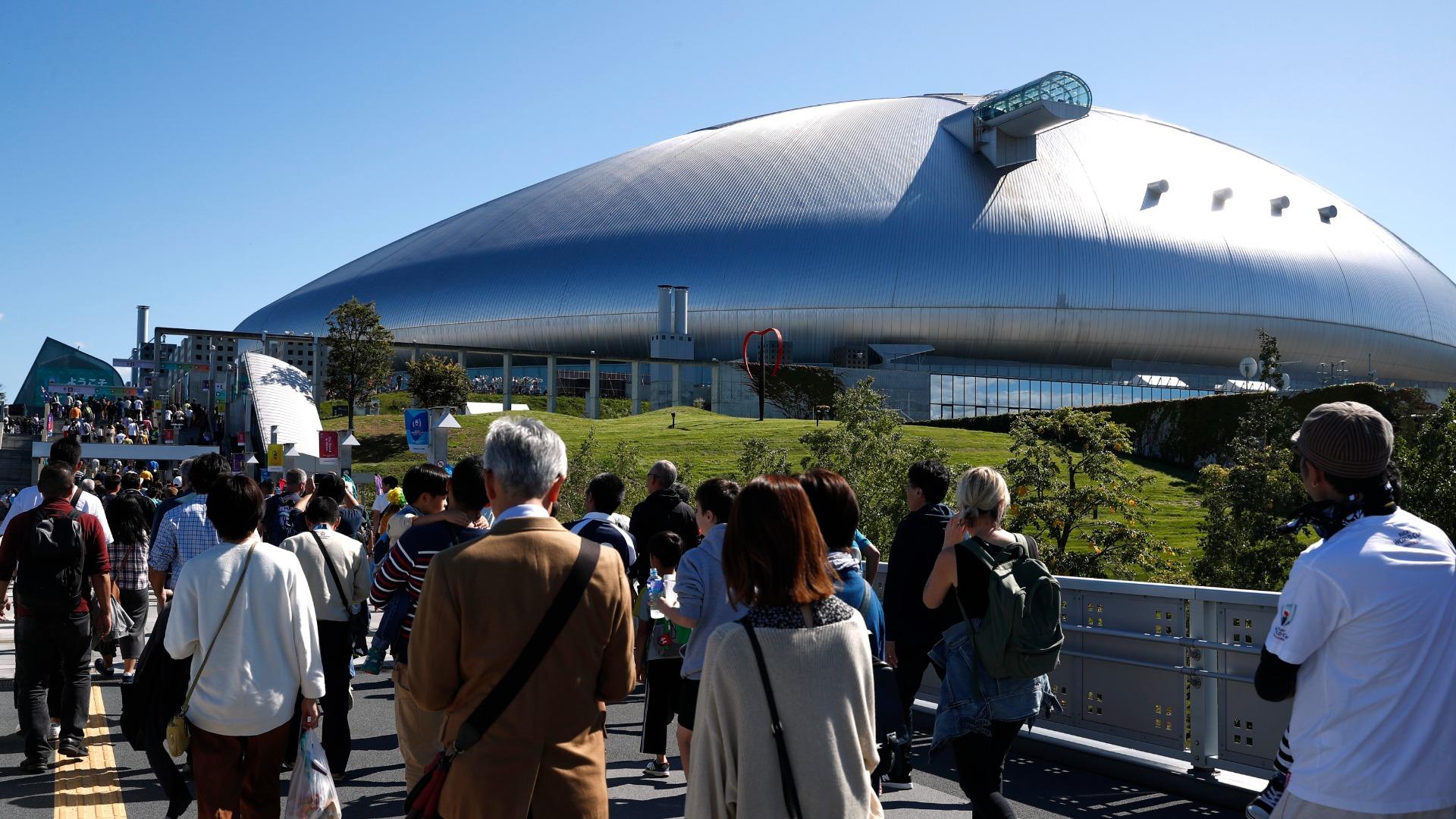数百メートル先まで歩いて外出、シニアにとってどれほど困難だろうか
2割近くは「難しいかも」な数百メートルの歩行
個人差はあるものの歳を経ることによる身体の劣化は誰もが避けることはできない。若者には他愛もない散歩距離でしかない歩行も、ハードルは高く、難儀するものかもしれない。その実態を内閣府調査「平成26年度 高齢者の日常生活に関する意識調査」(60歳以上対象、郵送配送・回収形式)の結果から探る。
次に示すのは日常行動における困難の度合いに関して、自身の実情を回答してもらった結果。対象事象は「数百メートルぐらい歩く」。距離の明示は無いが、数十メートルでは無く数キロの範囲でもない。若年層ならば徒歩と自転車、どちらで行くか判断に迷う範囲の距離。
困難さを覚える人は全体で2割近く、7割は「問題ない」、そして1割は判断留保。男性よりは女性の方が困難率が高いのは、より歳が上な人が多いからだと考えられる。そして年齢階層別では、きれいな形で高齢ほど困難率が上昇していく。同時に判断留保率も増加していくのは、単なる距離だけでは仕切り分け出来ない状況との自覚が増えていくからと考えれば道理は通る。
60代前半では困難率は1割にも満たない。それが70代前半では1割を超え、80代になると3割を超えていく。さまざまな事情はあるが数百メートルの移動に困難さを覚えるとなると、通院や普段の買い物にも苦労をすることは容易に想像できる。
世帯構成別で見ると……
これを同居している状態別に仕切り分けしたのが次のグラフ。
本人と親の世帯では困難度が一番低いが、回答者本人にとっても困難な状態ならば、親を支える日常生活が非常に難儀してしまう。親は当然回答者よりも年上のため、歩行に難儀している可能性は高いからだ。また見方を変えれば、回答者自身は高齢層の中でも比較的歳が若い可能性が高く、最初のグラフの通り、歩行移動に困難さを覚えない人が多いのは道理ではある。
他方子供や子供・孫と同居している世帯では、本人の困難度は高め。しかしこの場合、子供や孫が移動の用件を代行している、あるいは自動車などに同乗させてもらっている可能性はある。
気になるのは単身世帯。同居人がいない以上、基本的には日常生活は自身でやりくりをしているはずで、その状況下で2割が数百メートルの歩行を困難だとしている。自転車やバイクでの移動は想定しがたく、自動車、あるいはいわゆるシニアカーの類を用いているか、タクシーなどの交通機関を用いているのだろう。当然自由度、あるいはコストパフォーマンスは自身の歩行よりも低いものとなる。
歩行による外出の目的は買い物に限ったことではない。今後高齢化と地域の過疎化が進むに連れ、中距離以上の歩行が困難な高齢者にどのような対応をしていくべきかも、例えば代替手段となり得るインターネット通販の活用も合わせ、今まで以上の検証が求められよう。
■関連記事: