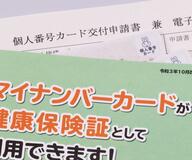「政治とカネ」問題― 本当の解決策はこれだ!

政治資金規正法の国会審議が始まりましたが、与野党のどの案も的をはずれて(はずして?)いて、解決策にはなりません!
問題の本質は、資金の受け手である政治家、政治団体、政党の管理のずさんさにあるのに、どの党の改革案も資金の出し手や金額の制限が中心だからです。
地震でヒビが入った壁や落ちた天井だけ補強しても、また同じことが起こります。建物の骨格や基礎の耐震強化が必要なのに、小手先の補修だけをしているようなものです。別の言い方をすると、資金の種類や金額など“人のせい”にせず、まず自分のことをきちんとすべきなのです。
(1)問題はどこに
多くの政治家が後援会など政治団体をたくさん持っています。政党の支部も実質的には議員個人の政治団体と同じです。
そして、これらの団体間の資金の移動は自由にできる。つまり、政治家はサイフをたくさん持ち、サイフどうしのカネのやり取りを自由にできるのです。
例えば企業は後援会には寄付できませんが、政党(支部を含む)にはできます。ですから、支部で受け取った資金を後援会に移せば「企業献金禁止」と言っても何の意味もありません。つまり、会社で言う連結決算をしていないので、政治資金の全体像と動きが外からは見えないのです。
もう一つ、政治資金の収支報告書では、「資産」の全体も見えません。例えば普通預金は含まれていないのです。民間ではあり得ないことです。会社、公益法人、NPOなどすべてに義務付けられている賃借対照表(B/S)を、政治団体はなぜか作らなくてよいことになっているのです。
さらに、収支報告に対する監査は「外形的、定型的」なものに限られていて、「政治資金の使途の妥当性を評価するものではない」と総務省の監査マニュアルは言っています。しかも、監査を受けて公表した収支報告書が後から手書きで修正されることも珍しくありません。企業なら大問題です。監査とは本来、お金の使い方の妥当性をチェックすることです。各党の改正案には「監査の強化」といった言葉も見られますが、自分を縛りたくないわけですから、民間並みに「強化」することはないでしょう。
私たちは、会社からも税務署からも、そして会社であれば銀行からも証券取引所からも世間からも、お金に関して限りなく「白」であることを求められています。
ところが、毎年1,200億円もの税金と非課税のお金を使い、会社よりも公益法人よりも公共性が高い政党や政治家の資金が「ブラックボックス」の中にあるのです。そして、各党の改正案では、お金の出し手や金額について「もっと白くしよう」「オレたちはこんなに白くする案を出している」と言うばかりで、自分の中の「ブラック」については全くと言っていいほどメスを入れていません。
(2)本当の解決策は(構想日本の提言)
ここまで読んでいただければ、読者の皆さんは何をしないといけないかお分かりだと思います。
以下、ポイントだけ書きます。
① 資金管理団体を一つにする
今でも、一つの政治団体で政治活動も選挙運動も十分行っている議員はいます。議員を長くやっていると、いろんな事情で議員の政治団体が増えていくということはあるでしょうが、少なくとも資金管理団体は一つにして、連結決算をきちんと公表するのは民間では当たり前のことです。サイフを一つにまとめるだけなのですから。
② 資金の出入りと財産状況をすべて公表し、会社と同様の監査をする
現在の収支報告書に書かれているのは、お金の出入りと不動産、証券など一部の資産です。しかも、支出については「組織活動費」といった漠然とした記載で、添付する領収書についても金額や書き方にいろいろ抜け穴があります。
すべての資産を含む賃借対照表と具体的な使途を公表し、それらに対する本来の監査を義務付ける。これも民間なら当然のことでしょう。
(3)メディアはどこを追求すべきか
冒頭にどの党の案も的をはずれていると書きましたが、新聞やテレビなど報道、解説も同じです。
例えば、自民党の「政策活動費」が問題になっています。党から幹部議員に支給されるお金で、令和4年では茂木幹事長への10億円近くを筆頭に、総額約14億円が支出されています。
国会やメディアではこの政策活動費は廃止すべきだという声が強いのですが、政策活動費とは何かが法令で決められているわけではありません。ですので、仮にこれを廃止しても、例えば「調査研究費」といった名前に変えて同じような支出が行われるだけでしょう。要は、「政策活動費」と呼ばれているお金が何に使われ、最終的にどこに行き渡っているかが問題なのです。
このお金はおそらく全国の地方議員経由で日常の選挙活動に多くが使われているのでしょう。もちろん、金のかからない選挙を目指すことは大事ですが、どこの国を見ても選挙にある程度のお金がかかるのも現実です。大事なことは、選挙を含めて「政治」といういろんなことがごちゃまぜに行われているブラックボックスの中で、お金の流れ、使われ方が国民に見えるようにすることなのです。そして、(2)で述べたことはそのために不可欠のことなのです。
一見鋭い追求のように聞こえる「○○禁止」は○○を他の言葉に変えて逃げられることが多いのです。メディアで鋭そうな発言をしている人には、そのあたりのことをきちんと整理してもらいたいと思います。
以上は、政治資金規正法に限定したことですが、本当はもっと基本的なところで「締めるべきこと」がまだまだあります。それは政党という組織の「ガバナンス」です。それについては近いうちに続編でお伝えします。
(参考)
- 国民と政治家。こんなに違うのか!お金の扱い方。(2023年12月29日投稿)
- 「<政治とカネ>を問う」(8) (2024年5月13日日本記者クラブ会見)