専門用語のはなし―「アウフヘーベン」ってなに?―

何気なく使っている言葉でも、意外と歴史が浅かったりします。明治の小説家、坪内逍遥が翻訳したとされる「文化」「批判」「運命」「標準」「男性・女性」、福沢諭吉の手になる「自由」「演説」「討論」「為替」など、今ではすっかり日常用語として定着している言葉もせいぜい100年ちょっとの歴史しかありません。
私は法律家ですが、「権利」や「義務」といった基本的な法律用語も、明治になって西洋法を輸入してから急遽考案されたものです。明治6年に、当時の司法省に法学校が設立され、フランスから招聘した有名な民法の教授がフランス語で法律学の授業を行っていました。学生たちもフランス語で法律学を議論していました。
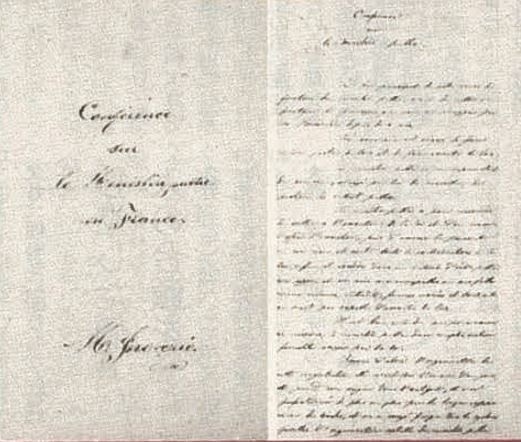
「誤訳も妨げず、ただ速訳せよ」とは、初代司法卿(しほうきょう、今の法務大臣)江藤新平の言葉です。東洋の貧しく小さな島国が文明開化の大号令のもと、西欧の国々からバカにされないように、彼らに追いつこうと必死になって外国の法律を日本語に直してきました。法律学に限らす、他の西洋の学問すべてがそうでした。今では普通に使っている「哲学」「論理学」「心理学」「現象」「客観・主観」「実体」「観察」など、基本的な学問用語の多くがそうです。
こうして急に造語された言葉は、使っているうちに徐々に自然に日常の世界に着地していきました。法律学でいえば、日本語で法律の議論ができるようになったのは、ようやく明治の20年代以降のことだったといわれています。しかし、新しく創られた言葉が、人びとになかなか消化されず、専門の狭い領域でだけで使われ、世間から浮いたままになっているケースも少なくありません。
欧米の専門用語は、よく言われることですが、日常用語の広い裾野をバックに、学問的な検討の中で余分な意味がそぎ落とされていき、特別な意味を持たされています。日常用語の下地があるので、学問的議論の中で洗練されていっても、元の意味を引きずっていることが多いと思われます。これに対して、日本の場合は、そのような日常用語の裾野がない専門用語が多く、言葉がいわば宙に浮いた形になっていて、議論が特殊でとても難解なものとなりやすい傾向があります。
ここで話題にしている、「アウフヘーベン」(aufheben)という言葉がその典型例でしょう。ドイツの偉大な哲学者ヘーゲルは、この言葉を自分の思想を説明するための重要な道具として使いました。ある主張が出される。するとそれに反対の主張が出てくる。議論が始まり、議論が上手く噛み合うと新たな次の次元に移行する。それをヘーゲルは〈アウフヘーベン〉と表現しました。
とくに難しいことが言われているわけではありません。しかし、日本語ではこれに難解な「止揚」という言葉が当てられました(「揚棄」(ようき)と訳す人もいます)。日本人が日常生活で「止揚」という言葉を口にすることはほとんどありません。しかし、ドイツでは普通のおばさんが 〈アウフヘーベン〉と言ったりします。
たとえば、週末のお茶に呼ばれたとします。ドイツ人は甘いケーキが大好きだから、大きなケーキをたくさん用意して招待してくれます。しかも、ケーキの上に生クリームをたっぷりとかけて食べます。1つ食べるとお腹がいっぱいになって、「もう結構です」と断ることになります。そこで、「じゃあ、アウフヘーベンしなさい」と言われることがあるのです(実際、ドイツに留学していたときに体験しました)。何のことはない。「アウフヘーベン」とは、要するに「お持ち帰り」なのです。
言葉のキャッチボールをしていて気持ちの良いコミュニケーションが続くと、受けたボール(言葉)の感触を残しながら、それぞれが気づかぬ間に全く別の新たな次元に進んでいることがあります。相手の言い分を否定して、自分の意見をゴリ押しする。論争で相手を負かす。あるいは、足して2で割ったり、異なるもの単に積み上げる。これらは、「アウフヘーベン」とはまったく異ります。 いろいろな人がいろんな意見を持ち寄り、そしてみんなで揉んで、そこからそれまでの考え方とは違った新しい考え方にみんなの心を統合させていくこと。
「議論の『お持ち帰り』」。
私は、「アウフヘーベン」をこのように理解しています。(了)










