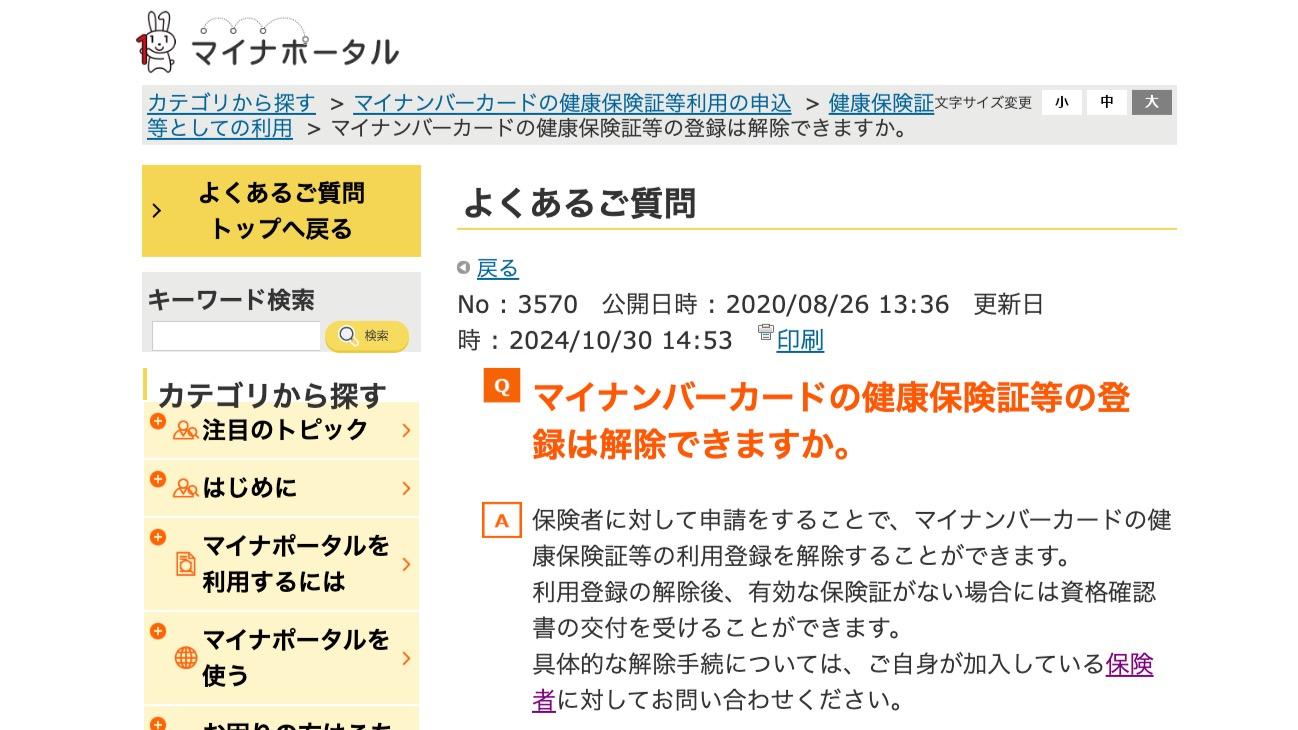爪真菌症の難敵、難治性爪白癬(デルマトファイトーマ) - 見逃さないために知っておくべきこと

【難治性爪白癬(デルマトファイトーマ)とは?その臨床的特徴】
難治性爪白癬(デルマトファイトーマ)は、爪真菌症の一亜型で、1998年にRobertsとEvansによって初めて報告されました。臨床的には、爪甲に黄色や白色の線状、あるいはパッチ状の病変として現れます。好発部位は爪の大部分を占める爪母(そうぼ)ですが、どの爪にも発症する可能性があります。
皮膚科医でない方にとっては聞き慣れない名称かもしれませんが、爪白癬などの爪真菌症の5~10%を占める、比較的頻度の高い病型と考えられています。本症の診断には、臨床所見だけでなく、水酸化カリウム(KOH)直接鏡検やPAS染色による病理組織学的検査が必要です。
【難治性爪白癬(デルマトファイトーマ)の診断の重要性】
難治性爪白癬(デルマトファイトーマ)は、依然として認知度が低く、見逃されやすい疾患です。しかし、爪真菌症の他の病型とは臨床像が異なるため、皮膚科医が本症の臨床的特徴を理解し、的確に診断することが極めて重要です。
難治性爪白癬(デルマトファイトーマ)の治療法は、他の爪真菌症とは大きく異なります。そのため、適切な診断なくして、患者さんに最良の治療を提供することはできません。診断の遅れは、治療の遅れにつながり、患者さんのQOL低下を招くことになります。
【難治性爪白癬(デルマトファイトーマ)の最新治療】
かつて難治性爪白癬(デルマトファイトーマ)の治療は、外科的な爪甲切除が主体でしたが、近年は外用抗真菌薬の有効性が複数報告されています。代表的なものは、エフィナコナゾール10%溶液とタバボロール溶液です。
エフィナコナゾール10%溶液を用いた223例の爪白癬患者の臨床試験のサブ解析では、本剤の縦走スパイク(錯角化)に対する有効性が示されました。また、タバボロール溶液については、第II相試験の102例の事後解析で、180日目までに24.4%の患者で病変が完全に消失したと報告されています。
一方、難治性爪白癬(デルマトファイトーマ)を伴う爪白癬では、複数の爪に病変を認めることも多く、そのような場合は、外用薬に加えて内服抗真菌薬の併用が推奨されます。
爪は、皮膚の一部であり、爪の病変は皮膚疾患の一種と捉えることができます。最近の研究によれば、爪真菌症は、単なる美容上の問題だけでなく、患者さんの日常生活に大きな影響を及ぼすことが明らかになっています。皮膚科医として、難治性爪白癬(デルマトファイトーマ)をはじめとする爪真菌症の患者さんに、適切な診断と治療を提供していくことが求められています。
参考文献:
1. Roberts DT, Evans EGV. Subungual dermatophytoma complicating dermatophyte onychomycosis. Br J Dermatol. 1998;138(1):189-190.
2. Watanabe S, et al. J Dermatol. 2021;48(10):1474-1481.
3. Aly R, et al. J Drugs Dermatol. 2018;17(3):347-354.