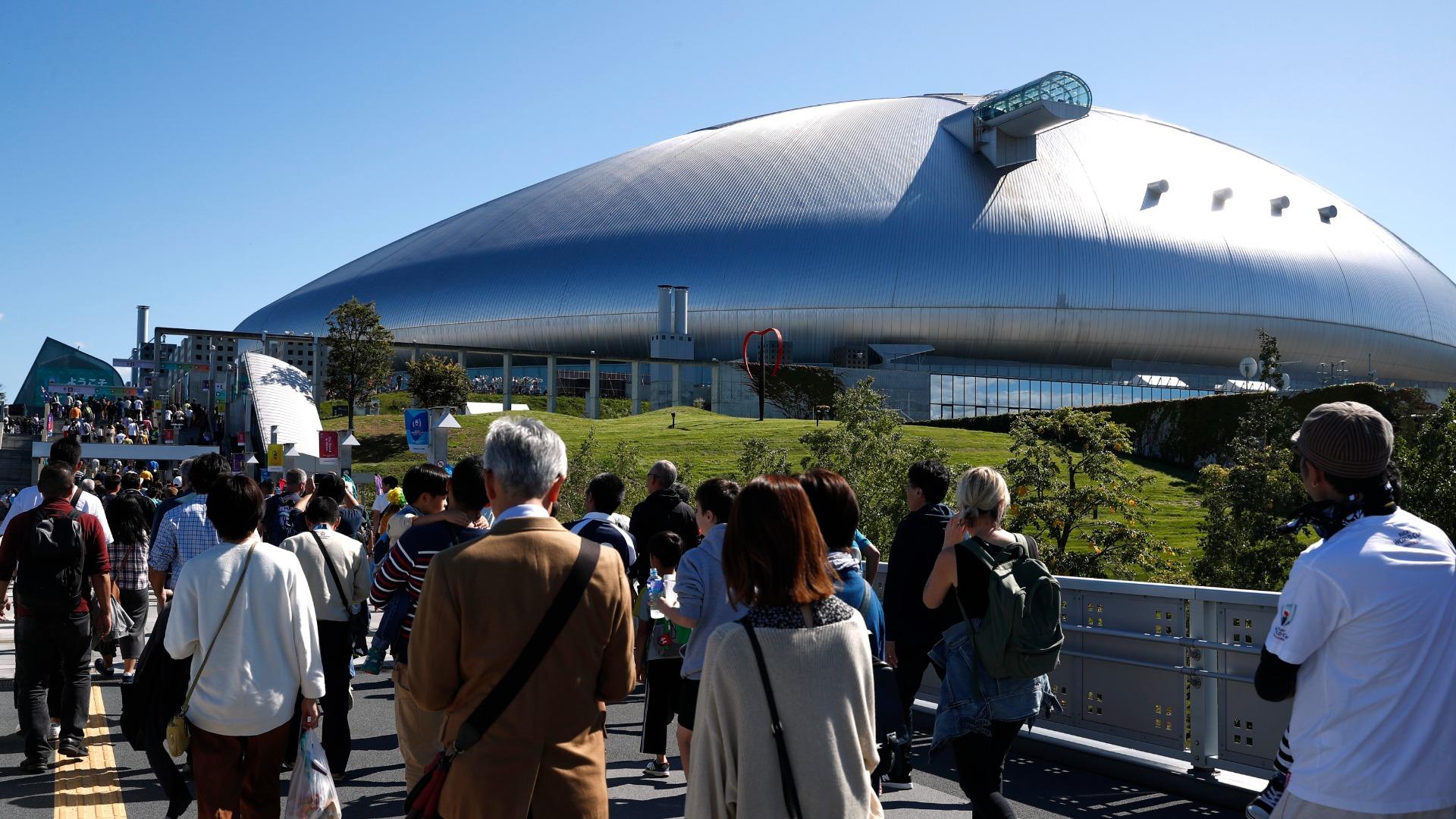米国以外で防衛協力や交流相手として役立つ国はどこだろうか(2023年公開版)
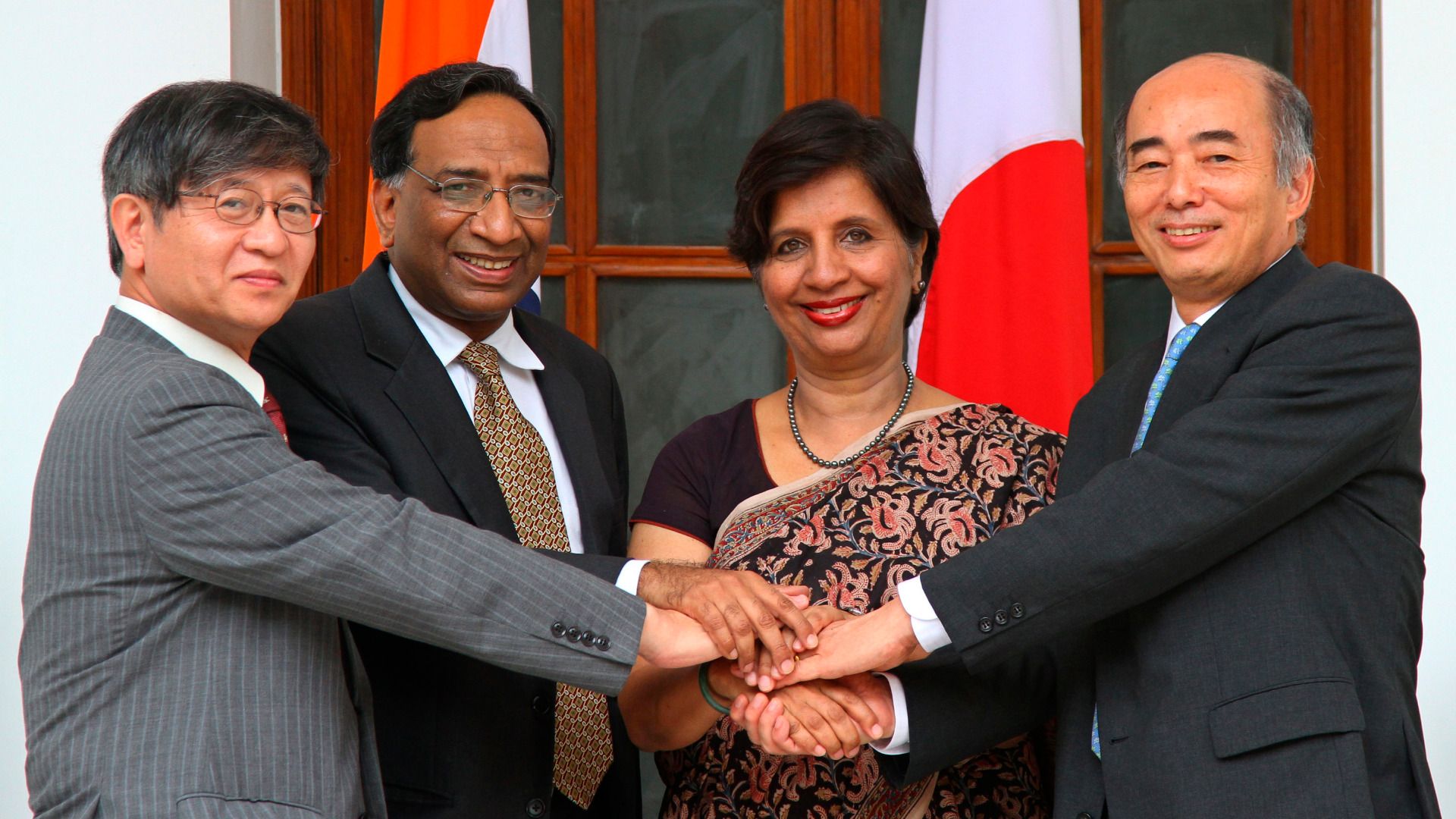
日本と米国(アメリカ合衆国)との間の日米安保条約は、日本の安全と平和に大いに貢献している。しかし日本が防衛面で協力・交流をしている国や地域は、米国だけに限らない。いかなる国との関係が役立つと評価されているのだろうか。内閣府が2023年3月に発表した自衛隊・防衛問題に関する定期世論調査(※)の結果報告書の内容から、米国以外の国などとの間における防衛協力・交流が、日本にとって安全・平和面で貢献しているか否かに関する評価を確認する。
日本は米国以外の国との間にも個々の関係に応じた協力体制を築き、交流を実施している。これらの行為に関して、「回答者が」日本の安全と平和に役立っているか否かの観点でどのように思っているかを尋ねた結果が次のグラフ。国を特定していないこともあるが、6割強の人は肯定している。

役立っていないとの意見は5%にも満たない。「どちらともいえない」が27.7%は単純に判断をするのに足る情報が不足しているのだろう。
それでは具体的にどの国や地域との関係が、日本の安全と平和に貢献していると思われているのか。(どちらかというと)役立っていると回答した人(役立っている派)に複数回答で答えてもらった結果が次のグラフ。具体的名称を挙げている選択肢のみを抽出している。

トップは東南アジア諸国(具体的国名の表記は無し)、次いで韓国、オーストラリア、さらには欧州諸国(除く露。英仏などの主要国)が続く。欧州諸国は日本との直接的距離は離れているものの、何かと協力体制にあった方がよいことが多いとの判断からだろう。あるいは元西側諸国としての馴染みからだろうか。
さらに中国、インド、そしてロシア。領土問題で日本と対立が続く中国が3割強の値を示していることに驚きを覚える人もいるかもしれないが、設問の「防衛協力・交流」を偶発的な問題を防ぐための連絡手段の確保として認識している人もいるのかもしれない。むしろロシアによるウクライナへの侵略戦争で大いに国際的イメージを損なっているロシアに対しても、1割強の人が回答している方が驚きだろうか。
「防衛協力・交流が日本の安全と平和に役立っている」とする対象国・地域だが、属性による違いが見受けられる。男女別では男性が東南アジア諸国やオーストラリア、インドに好意的なのに対し、女性は韓国や中国、ロシアへ好意的。

男女別で順位を見ると、男性は東南アジア諸国、オーストラリア、韓国、欧州諸国、インド、中国、ロシア。女性は韓国、東南アジア諸国、欧州諸国、オーストラリア、中国、インド、ロシア。価値観の違いや個々の国に対して抱いている基本部分となるイメージの違いが表れているのだろうか。特に女性では韓国の値が伸びて東南アジア諸国以上を示しているのが興味深い。
続いて年齢階層別。

年齢階層別では東南アジア諸国や韓国、オーストラリア、インドへの回答値はおおむね高齢層ほど高く、欧州諸国、中国、ロシアは若年層ほど高い値が出ている。西洋は若年層・東洋は高齢層との区分けができるだろうか。興味深い傾向ではある。
■関連記事:
【アメリカ合衆国にとって現在、そして今後重要なパートナー国は? 一般の人に聞いてみました(最新)】
【日本が1番中国2番…アメリカ合衆国の有識者におけるアジア地域諸国に対するパートナー意識の重要度推移(最新)】
※自衛隊・防衛問題に関する定期世論調査
2022年11月17日から12月25日にかけて、層化二段無作為抽出法によって選ばれた18歳以上の日本国内に在住する日本国籍を持つ人に対し、郵送法で行われたもので、標本数は3000人、有効回答数は1602人。有効回答者の男女構成比は757対845。年齢階層別構成比は18~29歳が170人、30代が162人、40代が240人、50代が276人、60代が306人、70歳以上が448人。
(注)本文中のグラフや図表は特記事項の無い限り、記述されている資料からの引用、または資料を基に筆者が作成したものです。
(注)本文中の写真は特記事項の無い限り、本文で記述されている資料を基に筆者が作成の上で撮影したもの、あるいは筆者が取材で撮影したものです。
(注)記事題名、本文、グラフ中などで使われている数字は、その場において最適と思われる表示となるよう、小数点以下任意の桁を四捨五入した上で表記している場合があります。そのため、表示上の数字の合計値が完全には一致しないことがあります。
(注)グラフの体裁を整える、数字の動きを見やすくするためにグラフの軸の端の値をゼロではないプラスの値にした場合、注意をうながすためにその値を丸などで囲む場合があります。
(注)グラフ中では体裁を整えるために項目などの表記(送り仮名など)を一部省略、変更している場合があります。また「~」を「-」と表現する場合があります。
(注)グラフ中の「ppt」とは%ポイントを意味します。
(注)「(大)震災」は特記や詳細表記のない限り、東日本大震災を意味します。
(注)今記事は【ガベージニュース】に掲載した記事に一部加筆・変更をしたものです。