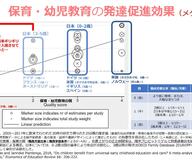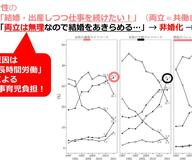コロナ後の社会――長期的にどう変わっていくのか(3)「リスク社会論」(後編)

前回は、ベックの「リスク社会論」の背景を紹介した。
今回は、その「リスク社会論」の内容を紹介する[※1]。
参照するのは、『リスク社会』(原著1986年)、『グローバル化の社会学』(1997年)、『世界リスク社会論』(1997、2002年)、『ナショナリズムの超克』(2002年)、『〈私〉だけの神』(2008年)、『リスク化する日本社会』(共編著、2011年)である。
あくまで要点を紹介するにとどめるため、それ以上の詳細は上記の書籍を直接参照されたい。
※1:以降の記述の多くは、拙稿「リスク社会と福島原発事故後の希望」(大澤真幸編『3・11後の思想家25』左右社、2012年)に負っている。
第二近代社会としての「リスク社会」
まず、彼の「リスク社会論」を一言でまとめれば、こうである。すなわち、社会の近代化の必然的帰結として、「空間的・時間的に無境界・無限界なリスク」が、社会的に生産され、近代社会そのものへの脅威となる。これを彼は「(世界)リスク社会化」と呼ぶ。
無境界・無限界なリスクの代表例として、彼がこれまで挙げてきたものは、「(近代以前から存在していようといまいと)近代の科学技術によってその危険が増幅または生産された有害物質(放射性物質など)」「遺伝子工学による危険」「情報技術による危険」「科学技術による環境破壊や気候変動」「金融危機」「テロ攻撃」「人工知能による危険」「生殖医学による危険」などである。
それらは分野横断的に多岐にわたっているが、しかしいずれも、「人間の行為(科学)によってもたらされる危険(リスク)であり、かつ、その危険の範囲は、空間的にも時間的にも、境界がなく限界もない」という意味で、空間的・時間的に無境界・無限界なリスクである。
しかし、これらのリスクは、あくまでも人間の行為に起因しているがゆえに、人間の反省的決断(たとえば原発を廃止するという決断)によって、その生産を(少なくともある程度は)未然に防ぐことができる、というのが彼の主張である。
ここで、彼の「リスク社会論」で用いられる基本的な用語の意味を、確認しておこう。
「社会」は、人間たちの行為とそれから影響を受けるものによって構成されているものである。また「社会の外部」は、人間の行為から影響を受けないものによって構成されているものである。「社会の外部」のうち、空間的外部は、人々によって「自然」と呼ばれ、また時間的外部は「伝統」と呼ばれてきた。
さて、社会の「近代化」は、2つの段階(「第一の近代化」と「第二の近代化」)に分けられる。
第一の近代化(主に19世紀から20世紀前半)は、人間が、科学を発達させていくことで、社会の外部(自然と伝統)を支配し、社会の内部に組み込んでいく段階である。この段階では、人々の生き方は、階級などの伝統から解放される(「脱埋め込み」される)。その上で人々は、彼らを「自己決定権をもつ個人」として扱う福祉国家へと、新たに組み込まれる(「再埋め込み」される)。それによって人々は、すべての場面において、個人としての自己決定を(それを望んでいるかどうかとは関係なく)強いられるようになる。
このように、生活の中のより多くの場面で、個人としての自己決定が強いられていくことを、ベックは「個人化」と呼ぶ。そこでは、福祉国家が形成されていくため、ナショナルな富の分配が争点となり、階級の解消による貧困解消と平等が求められる。よってこの段階にある社会(第一近代社会)を、ベックは「貧困社会」と呼ぶ。
つぎに、第二の近代化(主に20世紀後半以降)は、科学が自然と伝統を(人間の認識上では〔以下同様〕)完全に支配し、それらを社会の内部に完全に組み込んだ後の段階である。この段階では、社会の外部(自然と伝統)は完全に失われてしまっている(つまり、自然は「敢えて社会的に想定された自然と、敢えて社会的に想定から外された自然」、伝統は「敢えて社会的に選択された伝統と、敢えて社会的に破棄された伝統」になっている)。
そのため、科学の視線は、社会の内部へと向けられることになる。すると、社会の内部において、科学そのものが生み出している危険が、新たに発見される。そしてその危険は、(以前から使われていた)「リスク」という用語によって、名指されるようになった。
かつて自然が存在していたとき(前近代および第一近代)、「人間の生命を脅かすもの」(危険 Gefahr, danger)の中には、「人間の行為とは無関係に、社会の空間的外部(自然)で発生し、人間の生命を脅かすもの」(リスクではない危険)と、「人間の行為によって、社会の内部で生産され、人間の生命を脅かすもの」(リスク Risiko, risk)が存在していた。
しかし、その(前近代と第一近代での)リスクは、あくまで個人的なリスクであった。たとえば大航海時代には、「リスク」という語は、「個人の勇気・冒険」を意味しており、今日的な「人類全体への危険」という含意を持っていなかった。
他方で、第二近代で発見された「科学が生み出すリスク」は、個人・階級・国境を超えて拡散し、将来にわたってもその影響の範囲を限定できないため、無境界・無限界なリスク(人類全体への危険)である[※2]。このリスクは、階級・国境を超えて作用するため、社会では「富の分配」に加えて「リスクの分配」もまた争点となる。
つまり第二の近代化によって、社会は、国内での「階級・貧困の解消と平等」を求める第一近代社会(貧困社会)から、グローバルな「リスクの統御と安全」を求める第二近代社会へと変容する。後者の第二近代社会を、ベックは「リスク社会」(近年の著書ではグローバルな側面を強調して「世界リスク社会」)と呼ぶ。富の分配は、相対的貧困や不平等を縮小することはできるものの、「科学が生み出すリスク」を縮小することはできない。
※2:さらに、「科学が生み出すリスク」は、放射性物質に代表されるように、人間には基本的に知覚できず、科学によってしか識別できない。よって、科学の視線が社会の内部に向かい、科学(の副産物)が科学の対象となる「第二近代」に入って初めて、「科学が生み出すリスク」は発見されたのである。
なお、「金融危機」「テロ攻撃」のリスクも射程に入れた『世界リスク社会論』(2002年)においては、「リスクの知覚不可能性」という条件は、議論の前面には出ていないように思われる。しかし、「金融危機」の発生源や「テロ攻撃」の犯行者を、あらかじめ識別し特定することは難しい。これもまた、情報技術の発達に起因する金融システムの複雑性の増大や、科学技術の発達に起因する隠蔽技術の高度化に、由来している。そういう意味では、「リスクの知覚不可能性」は、「金融危機」や「テロ攻撃」についても当てはまるといってよいと思われる。
もちろん、リスクの分配は、富の分配と重なるところが多い。つまり、低所得者はより多くのリスクに曝されている傾向がある。
しかしながら、科学が生み出すリスクは、低所得者と高所得者が共有せざるをえない「環境」の全体に、無境界・無限界に拡散する。そのため、たとえ富の再分配によって所得が完全に平等になったとしても、人々は、科学が生み出すリスクから逃れることはできない。
このようなリスク社会においては、階級・国境を超えたリスクへの不安を、階級・国境を超えて「コスモポリタン」的に共有することを通じて、階級・国境を超えた政治的連帯が、生まれる可能性がある。
ここで、「コスモポリタン」とは、「個人がグローバル化(文化的に異質な他者との出会い)を自らの生活のなかで体験すること」を意味する。第一近代ではナショナルな連帯によって福祉国家化と個人化が進んだが、第二近代ではそれに加えて、リスクのコスモポリタンな共有によって、グローバルな政治的連帯が進みうると予想されるのだ。
反省、倫理的問題、信仰の衝突、そして政治的実践
さて、第二近代では、近代(の実践である科学)がリスクを生んでいることが人々によって認識されるため、人々において近代への反省が生じる。
よって、近代への反省のない第一近代化を、ベックは「素朴な(片道の)近代化 einfacher Modernisierung, simple modernization」と呼び、近代への反省のある第二近代化を「反省的(再帰的)近代化 reflexiver Modernisierung, reflexive modernization」と呼ぶ。
反省的(再帰的)近代になると、科学は、自らを反省することにより、「自らが人的被害を生む確率」を――よって「自らが生む人的被害の期待値」としてのリスクを――、減らすことができる。
しかし、その確率(およびリスク)を完全なゼロにはできない。なぜなら、科学は常に、不確実な確率論の枠内にあるからである。ここから、「不確実性」という概念が生まれる。
科学は、確率論的な議論しかできない(たとえば原発が重大事故を起こす確率はゼロにはならない)。そのため、リスクへの事前対処のしかた(原発設置の是非や原発設計の方針など)については、科学では完全には決定できず、最終的には倫理的判断(どのように生きたいのかの決断)が必要になる。
こうして、反省的近代においては、倫理的問題が前景化する。
ただし、その倫理的問題は、あくまでも、個人化されコスモポリタン化された倫理的問題である。すなわち、個人が主体的に問題化した問題であるとともに、コスモポリタンな問題共有と解決実践が可能な倫理的問題である。さらに、「どのように生きたいのか」の決断を迫る倫理的問題は、「このように生きたい」という(非科学的な)信仰を必要とする。
よって、個人化されコスモポリタン化された倫理的問題は、個人化されコスモポリタン化された信仰を、人々の中で発生させると予測できる。
なお、現在のところは、個人化された信仰(個人が古今東西の宗教的要素を取捨選択し組み合わせて自分自身の神を作り上げること)しか、まだ発生していない。コスモポリタンな状況は、むしろアンチ・コスモポリタンな信仰(文化的他者を認めない原理主義)を引き起こしてしまっている。それゆえに、個人化されたアンチ・コスモポリタンな信仰同士のあいだで、衝突が生じている。
さて、倫理的問題や、それに起因する信仰同士の衝突は、議会政治に限定されない広義の政治的実践によってしか、解決されえない。ではその政治的実践とは何か。
たとえば科学(を用いた企業活動)は、リスクを生み、人々の生命を脅かすため、人々の社会的生活に対して直接的な影響力を持つ。同様に、市民運動や経済活動もまた、人々の社会的生活に対して直接的な影響力をもつ。
人々の社会的生活に対して直接的な影響力を持つということは、政治性をもつということである。このように、代議制民主主義の外部で行われている政治を、ベックは「サブ政治」と呼ぶ。それに対して、代議制民主主義に則った議会内での政治を、彼は「政治」と呼ぶ。つまり、上記の政治的実践とは、サブ政治と政治を合わせたものである。
3つの可能なシナリオ
では、「科学がもたらすリスク」についての倫理的問題は、政治とサブ政治によって、どのように解決されうるのだろうか。ベックは、『リスク社会』の中で、互いに同時進行しうる3つのシナリオを、予想している。
第1のシナリオは、リスクが経済活動の新たな資源(ビジネス・チャンス)になるというシナリオ(産業社会への回帰)である。
その際、人々がリスクを認識すれば、責任の所在についての議論が起こり、代議制民主主義(政治)が活発化するだろう。逆に、人々がリスクを否認した場合には、リスクが放置されて拡大し、さまざまな社会的領域において、不確実性が増す。すると、不確実性を恐れて、独裁や原理主義を求める声が高まるだろう。
第2のシナリオは、科学技術の発展過程を、民主主義的決定の対象に含めていくというシナリオ(技術‐経済的発展の民主主義化)である。
たとえば、専門家や市民を交えた議会と関係官庁組織が、科学研究や技術産業を統制する。しかし、企業の合理化と科学的研究は、議会と官僚制によって阻害されるだろう。また、科学の権威主義と官僚制の肥大化が生じる危険性がある。しかし他方で、市民運動や反対運動などが形成され、議会への権力の集中を避けられることもありうる。それらの運動は、直接的な同意と統制(直接的な民主主義)にもとづいており、代議制という政治的限界を乗り越えることができるかもしれない。
第3のシナリオは、リスクを生む「科学的研究」というサブ政治を、代議制民主主義によらずに、別のサブ政治(他の専門家や市民運動など)によって統制していく、というシナリオ(政治の分化)である。
このためには、サブ政治の影響力を、一定範囲で育てて法的に保障する必要がある。また、サブ政治間(専門家間、専門家と市民の間)の自由な議論と、それぞれの自己批判の機会を、制度化しなければならない。すると、たとえば企業は、科学的研究を始める前に、その研究がもたらすリスクについて他分野の専門家や市民も参加した場で自由に議論する法的義務を負う。
第3のシナリオのなかで、政治(代議制民主主義)に対しては、サブ政治間の紛争を調停したり、サブ政治を保護監督したりする役割が、ますます求められるようになるだろう。その際、社会的権利と民主主義的権利は、守られ発展されねばならない。また政治とは対照的に、技術革新は権力を失っていくだろう。それにより、個人化の過程において新しい生活様式が発展し、専門職の内部で多元主義と批判的精神が広まるだろう。
さらに『世界リスク社会論』においては、ベックは、リスクの超国家性に着目し、超国家的な制度やネットワーク、複数国家間の協力体制、そしてサブ政治と政治(市民と政府)のグローバルな連携、の必要性を説いている。
そのグローバルな連携においては、個人が直接、政治的な決定に参加できるため、個人の集合的参加(不買運動など)が決定的になる。多国籍企業と各国政府の行為は、グローバルな公共性の圧力にさらされるようになる。グローバルなリスクを意識化し、自己批判と反省を行い、サブ政治をグローバルに用いること。それが、世界リスク社会における政治的実践のわずかな可能性であるとする。
「リスク社会論」の先へ
以上がベックの「リスク社会論」の要点である。私としては、新型コロナウイルスをめぐる私たちの経験をふまえて、この「リスク社会論」を、さらに前に進めたい。
どのように進めることができるか? それを次回は考えたいと思う。(つづく)