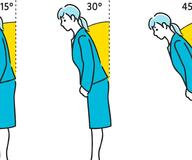事実と表現、記録と記憶:『Fukushima 50』とそれへの批判について考える
東日本大震災から9年たった。新型コロナウィルス感染症のため大がかりな式典は行われないが、多くの人たちがそれぞれの場所であのときを思い出し、犠牲者を悼み、今なお苦しんでいる人たちに心を寄せたりするのだろう。このタイミングに合わせてか、福島第一原発事故の際、多くの職員が避難した中、原発にとどまった人々を描いた映画『FUKUSHIMA 50』が公開されている。
震災もそれに続いた原発事故もまだ記憶に新しいこのタイミングで、実際のできごとを映画化したとなれば、映画を語りながら現実の人々や組織、状況を語ることになってしまうのはある程度はやむを得ない。事故自体についてもいろいろな意見がある以上、本作への評価も割れるのは自然なことだろう。実際、みる限り反応は賛否が真っ二つに分かれているようだ。
原作者の政治的方向性に近い考え方をする人には比較的支持されやすい作品なのだろうが、糸井重里氏のように、そうした方向性とはやや異なる人々にも支持者は少なからずいるようだ。賞賛する意見の中には、絶望的な状況での一部の人々の英雄的な行動について、あるいは極限状況下での人間ドラマとして、作品を高く評価しているケースが少なからずみられる。
震災の日、福島第一原発の現場では何が起きていたのか? 感動の実話『Fukushima50』
(紀平照幸- Yahoo!ニュース個人2020年3月5日)
戦争映画や、時代劇だと「いのちを捧げて」やらねばならないことがでてくる。いまの時代は「いのち」は無条件に守られるべきものとされるから、「いのちを捧げる覚悟」は描きにくい。映画『Fukushima50』は、事実としてそういう場面があったので、それを描いている。約2時間ぼくは泣きっぱなしだった。
一方、これを批判する人は、この作品をすべて実際にあったことととらえることへの懸念や反発を表明している。そしてそれは、現政権への批判的な態度と重なる部分が少なからずあるようだ。たとえば編集者の中川右介氏は、この作品で悪者として描かれている首相が現実と異なると批判している。当時は民主党政権下であったことを考えると、その首相を悪者として描くことは、結果的に民主党(現在は分裂しているが)への批判となる(裏返せばその後現在まで続く現政権を擁護することになる)ということだろうか。
映画『Fukushima 50』はなぜこんな「事実の加工」をしたのか?
(現代ビジネス2020年3月6日)
糸井重里氏のツイートに対しても強い批判が寄せられている。作品自体より糸井氏本人に向けたものとみえなくもないが、少し引いてみれば、これは現政権を概ね支持する社会の空気、現代日本の国のあり方全般への批判ということになろう。
糸井重里さんが原発を守るために命を捧げた映画を絶賛して泣いている。糸井さんは、忌野清志郎ボスが原発や戦争を恐れた歌を「くだらない」と批判した人だ。原発を恐れるのはくだらなくて、命を捧げるのは素晴らしいのか。
福島の原発事故を描写する際に、現場で戦った人間を英雄視することで、東電という組織ならびに原発というシステム自体が内包していた根本的な問題点を看過させてしまう手法は、先の大戦を語るに当たって英霊を称揚することで、国の戦争責任から目を逸らさせる手口とまったく同じだと思う。
ざっと見渡した限りでは、よい評価をしている言説も批判している言説も、映画を現実と結びつけてとらえる傾向があるようにみえる。危機に陥った日本を救った人々の実話とみる人が肯定的に評価している一方で、過剰に美化された虚構とみる人は否定的に評価しているわけだ。
確かに、『Fukushima 50』は「真実の物語」と銘打っているわけで、事実を糊塗するものだ、歴史改変だといった批判を呼びやすいのはわかる。とはいえこれは、ハリウッド映画でもよくある「based on a true story」というキャッチフレーズと同様、映画が事実だけを描いていることを意味しないと考えるべきだろう。娯楽作品である以上、そこに物語を盛り上げるため、わかりやすくするための創作や改変が混じることはむしろ当然だ。その意味で「真実の物語」は「全米が泣いた」とそう変わるものではない(まさか米国民が1人残らず泣いたなどと思う人はいないだろう)。
もっといえば、事実ですら、その伝え方によってある特定の方向へ印象を操作することはできる。実際、ドキュメンタリー作品ではそうした作品が珍しくはない。報道も同様だ。いかにもハリウッド映画のタイトルにありそうなこの「Fukushima 50」という呼び方自体、朝日新聞の下掲記事によれば米国の報道が最初であるらしいが、事故直後の原発で作業した人々を英雄視する視点が色濃く表れている。
「英雄フクシマ50」欧米メディア、原発の作業員ら称賛(朝日新聞2011年3月18日)
米紙ニューヨーク・タイムズ電子版が15日、「顔の見えない無名の作業員が50人残っている」とする記事を東京発で載せた。米ABCテレビも「福島の英雄50人――自発的に多大な危険を冒して残った原発作業員」と報道。オバマ米大統領は17日の声明で「日本の作業員らの英雄的な努力」とたたえた。
彼らが本当に「自発的」に残ったのかどうかはわからない。戦争中の特攻隊でも「志願スル者ハ一歩前ヘ!」と上官に言われて嫌々志願した人もいれば、自発的に志願した人もいただろう。それぞれの個人がそのときどのように考えていたか知るすべはないし(本人たちもわかっているとは限らない)、あえていえば知る必要もない。この作品に対する批判者が最も問題視しているのは、この作品に描かれた内容が事実か(彼らは本当に英雄なのか)という点より、彼らを英雄化することが、それが現状の追認や政権批判の封じ込め、あるいは国民に犠牲を強いる政策の推進に利用されようとしているのではないか、という点であるからだ。批判する言説の多くは、作品の内容を事実としてとらえてしまうこと、及びそれがもたらすかもしれない政治的影響への危惧や憤りが強く感じられる。
しかし、そうだろうか。
いうまでもないが、大きなできごとであればあるほど、事実は複雑な様相を持つ。事故が起きた直接的な原因は福島第一原発の津波対策の不十分さであるわけだが、そこには原発があの場所に作られることになった経緯から設計、建設、その後の運用に至るまで、東電やその関係者、政治家や学者など、関わってきた数多くの人々の大小さまざまな誤りや不作為、あるいは慎重さを欠いた判断が積み重なっている。それらは必ずしも、当時の民主党政権や東京電力だけに帰すべきものではない。
日本の原子力政策を推進してきた自民党や原発を誘致した福島県の政治家を含む多くの人々の作為・不作為が積み重なったうえに巨大地震が最後の引き金を引いたのだ。その意味で作中悪者にされた首相の姿は、自民党を含む日本の政治家全般、さらに大きくいえば日本の社会そのものの問題点を凝縮したものとみることもできる。
この作品の最大の意義は、誰を悪者として描いたかにあるのではない。これが作られ、多くの人のさまざまな反応を呼び起こしたこと自体にあるのだと思う。現代日本において最大級のインパクトをもったできごとであった福島第一原発事故については、当時日本にいた人は誰でも、当時の緊迫した状況を見聞きしていたはずだ。しかし事故後9年を経過(わずか9年だ)した今、それらの多くが急速に人々の記憶の中から消えつつある。これは福島(そして東北を始めとする多くの被災地)の復興にとっても、また次の大地震に向けた備えを進めるためにも、深く憂慮すべき状況だ。
そのことは、作中、福島第一原発の吉田所長を演じた渡辺謙氏もインタビューで語っている。
あの事故がなかったことになるよりは… 渡辺謙は「賛否を巻き起こしたい」
(BuzzFeed 2020/03/08)
「ポジティブすぎる言い方に聞こえてしまうかもしれません。でも、僕はこのタイミングで改めてあの時、福島で何が起きていたのかを伝え、賛否を巻き起こすことに意味がある、そう考えました」
「僕たちは原発そのものの是非を問うているわけではない」と前置きした上で、「この事故によって得たはずの教訓がなかったことになるくらいならば、賛否を巻き起こした方が良いと思うんです」とその理由を口にする。
「色々な課題にまだまだ直面されている方もいる。そうしたことを含めて、あったことや今あること、事実が消えていってしまうことが一番の問題だと思うんですよ」
映画は記録ではない。しかし記憶を呼び起こし、記録をひもとき、考え、議論するきっかけを作ることはできる。
福島第一原発事故は、これまで多くの人々の手によってさまざまな角度から検証や評価が行われ、それらの記録は残されている。しかしそれらが忘れ去られてしまえば、記録の価値はなくなってしまう。東北地方には、以前の大地震で発生した津波が到達した地点を記録し、後世の人々に警告する石碑がいくつも建てられていた。しかし時間の経過によってそれらが忘れ去られたため、石碑より海寄りに建てられた家々が東日本大震災で津波の被害に遭ったりしている。記録だけでは災害を防げない。記憶していくための努力が必要なのだ。
映画などの娯楽作品は、記憶をつないでいくための大きな力になりうる。作品を成立させ、商業性を追求するために、表現のうえで事実を一部省略したり改変したりすることもあるだろう。しかしそれは、記録と照らし合わせて検証することができる。事実と違えばこれは事実ではないと主張し、今後の改善につなげていくことができる。そのために、記録と記憶の双方が必要なのだ。
『Fukushima 50』を、事実と異なると批判することはおおいにあってよい。主張はさまざまあろう。どんどん議論したらよい。しかしそれができるのは、『Fukushima 50』が作られたからだ。それまで原発事故のことは、多くの人の頭の中からほとんど消え去っていただろう。もちろん、歪曲された歴史が記憶されるのはよくない。海外だと「based on a true story」と銘打った数々の映画のどの部分が事実かを検証したサイトなどもある。重箱の隅をつつくような話もなくはないが、少なくとも『Fukushima 50』のような作品の場合、こうした努力は無駄ではないだろう。
BASED ON A TRUE TRUE STORY? SCENE-BY-SCENE BREAKDOWN OF HOLLYWOOD FILMS
(information is beautiful)
記憶に残れば、似たテーマでまた作品が作られることもあろう。歴史上の重要な事件などは繰り返し娯楽作品として描かれている。たとえば太平洋戦争を描いた映画は数多く、その描き方もさまざまだ。それぞれの作品に対して賛否はあっても、そうした作品が作られ続けることによって、戦争の記憶は次の世代に引き継がれていく。福島第一原発事故も、東日本大震災やその他の大災害と並んで、私たちが記憶にとどめておくべきものだろう。その初期の取り組みの1つとして、その存在意義を前向きに評価したい。