日本型雇用の課題とこれからの雇用社会①~ジョブ型雇用の誤解とメンバーシップ型雇用の矛盾~

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
悪い円安やウクライナ危機など、日本経済を取り巻く環境は不確実である中、日本型雇用の変革を求める声も大きくなっています。そこで、昨年末に開催され筆者も登壇した「日本型雇用の課題とこれからの雇用社会 ~昭和的働き方から脱却せよ」のイベントレポートを4回に分けてお届けします。
同イベントの第1部から3部までは、濱口桂一郎氏、倉重公太朗、白石鉱一弁護士が登壇し、それぞれの視点から日本の雇用社会の問題点について報告し、第4部はパネルディスカッションという構成です。
第1部は、労働政策研究・研修機構労働政策研究所の濱口桂一郎研究所長が登壇。昨今流行している「ジョブ型」論の誤解を暴き、日本的なメンバーシップ型雇用が様々な労働法分野で矛盾をもたらしている姿を描き出します。
<ポイント>
・世間で使われている「ジョブ型」の多くは一知半解
・採用差別禁止が理解できない理由
・「忠誠心の不足」は正当な解雇理由になるか?
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ジョブ型は古くさい?
濱口:私からは「ジョブ型雇用の誤解とメンバーシップ型雇用の矛盾」というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。
まず初めに申し上げたいのは、「ジョブ型は古くさいぞ」ということです。昨年来、ジョブ型という言葉が毎日のように出ていました。その出発点は、おそらく経団連の経営労働委員会報告でしょう。その内容を基に新聞社が「これからはジョブ型だ」と報道したのです。
2020年の初めにコロナが世界中に広がり、テレワークが急増しました。その中で「日本でテレワークがうまくいかないのは、ジョブ型になっていないからだ」という論調になり、新聞やネット上でジョブ型という言葉が氾濫をしました。
この言葉を十数年前にでっち上げた身からすると、昨今世間で使われているジョブ型という言葉の多くは一知半解なのです。

私はこの言葉を現実に存在する雇用システムと、欧米やアジア諸国の雇用システムを分類するための学術的概念として作ったつもりでした。
ところが昨年来のマスコミやメディアに氾濫する「ジョブ型」という言葉の使われ方を見ると、新商品を売り込むネタとして使っている気配が大変強いのです。ジョブ型はちっとも新しくありません。それどころか古くさいのです。
産業革命以来、約200年の近代社会における企業組織の基本構造はジョブ型ですし、日本以外では今日に至るまでずっとそうでした。日本も本当はジョブ型なのです。
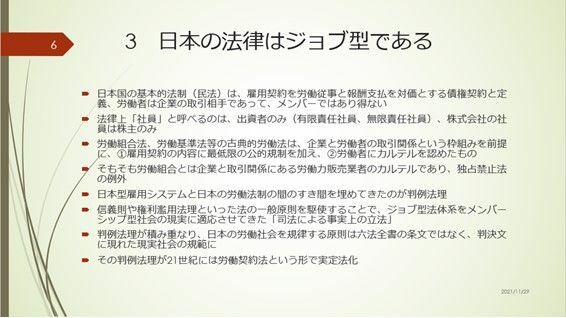
正確に言うと、六法全書に書いてある法律はジョブ型を基本にしています。例えば民法の債権各論に雇用という契約がありますが、これはまさにジョブ型です。終戦直後に労働組合法、労働基準法、職業安定法等という労働法制ができましたが、全部ジョブ型がベースになっています。しかし、現実の社会はジョブ型ではありません。その隙間を裁判所が埋めてきたわけです。その積み重ねがいわゆる判例法理というものです。日本の労働法の教科書では、条文よりも判例のほうがはるかに大事だということになっています。
今から半世紀前ぐらいまで、高度成長期の労働政策は、基本的にはジョブ型を志向していました。池田勇人内閣の国民所得倍増計画とはそういうものです。
ただ1970年代半ばのオイルショックから1990年代半ばの金融危機までの20年間には、今から振り返ると非常に皮肉なのですが、まさに新商品としてのメンバーシップ型でした。当時は日本型雇用に対する礼賛論があふれましたが、90年代半ば以降はもう古びてしまいました。
その時代の雰囲気を、過去の文章や発言で確認してみましょう。
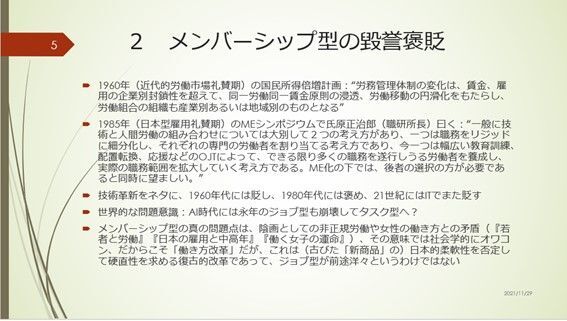
1960年、池田勇人内閣の時代に、国民所得倍増計画というものができました。誰もがその名前を知っていますが、実際に読んだ人はほとんどいないと思います。図書館の奥のほうでほこりを被っている『国民所得倍増計画』を開いてみると、まさしく日本的な雇用の在り方に対する否定的な表現がたくさん出てきます。
今から30年ぐらいまでは大変褒め称えられてきたメンバーシップ型の真の問題はどこにあるかについて説明します。
雇用システムが技術革新にとってプラスかマイナスかというのは、一概には言えません。ただメンバーシップ型は、非正規労働や女性など、周辺的なところに非常に無理がかかる働き方であるため、社会学的にいろいろ問題があります。だからこそ、安倍前々首相の下で働き方改革が行われたわけです。
働き方改革というと何か新しいものを導入しようという話に聞こえます。私に言わせれば、実は古びた「新商品」として日本的な柔軟性を否定して、復古的な、硬直的なジョブ型を持ってこようという話だったのです。
先ほど言った「日本の法律はそもそもジョブ型でできている」ということを少し詳しくお話をしておきます。ご承知のとおり、日本国の基本的法制である民法は、雇用契約を「労働に従事すること。報酬を支払うことを対価とする債権契約」と定義しています。労働者というのは企業の取引相手であって、そもそも会社のメンバーではあり得ません。
労働基準法や労働組合法も、労働者を企業の取引相手というふうに捉えています。こういったことを少し頭に置いた上で、各論に入っていきたいと思います。
■採用とは何か?
1つ目は、「就職と採用」です。
昨年来の2年ぐらいジョブ型論が氾濫しています。実はジョブ型かメンバーシップ型かの違いが一番よく表れるのは、入り口の話です。そもそも募集、採用とは何かというと、全て具体的なポストの欠員募集なのです。
採用とは、ジョブ型であれば「特定のジョブに最適な労働者を当てはめること」という定義になります。当該ジョブに最も高いスキルを有する労働者であるにもかかわらず、「この人は黒人だから」「女であるから」といった属性に対する差別感情から採用を拒否するというのは、ジョブ型社会の基本原理からして非合理ということになります。「かわいそうだから」という話ではありません。
日本だと全部情緒的な話になりますが、少なくとも法律学的な意味での採用差別の問題はまさにジョブ型社会における採用の定義から来ます。
ところが、採用差別禁止の一丁目一番地が日本で理解されません。普通のサラリーマンの世界においては、特定のジョブへの応募者の中から最適な者を選択するというシチュエーションがほとんどないからです。なぜ採用差別がいけないのか、日本社会にどっぷり漬かっていると全く理解できなくなります。

そのために他の国と違って日本では市場社会の大原則がそのまま維持されているのです。ジョブ型社会では既に大修正されている原理が、日本では一見維持されているように見えます。実はメンバーシップ型社会特有の採用の在り方がもたらしている採用法理なのです。
下のほうに書いてあるのが、労働法の教科書に必ず出てくる三菱樹脂事件最高裁判決です。有名な最高裁の判決において、企業は「ジョブが一番できる人」を募集しているのではなく、「新卒採用から定年退職までの40年にわたる長いお付き合いの仲間を選抜する」という思想信条が明らかになりました。
ジョブのスキルなどという枝葉末節よりも、はるかに大事な人間性、人間味というものでもって判断するということが認められるわけです。
■試用期間とは何か
この三菱樹脂事件というのは、労働法の教科書には「採用差別の事案だ」と書いてあるのですが、本当は採用差別ではありません。この人は試用期間満了時の本採用拒否だったのです。
問題はこの試用期間は何かということです。

日本の企業はだいたいどこにも試用期間がありますが、これは何ですかと聞くと、「うっかり採用してしまった不適格者を排除するためのものだよ」と言います。世界中どこに行っても、ジョブ型社会ではまさにそうです。
このジョブ型社会における試用期間の説明を日本に持ってきたらどうなるでしょうか。新卒採用で採用した人間はみんなど素人で、彼らが仕事をできるように鍛えるのが上司の務めです。だから仕事ができないというのは理由になりません。それなのになぜ試用期間があるかというと、「やる気のない者はクビにする」ために使っているということです。
■正当な「能力不足解雇」とは?
次が出口の話です。まず「ジョブ型は解雇が自由だ」という話を吹聴している新聞もありますが、そんなばかな話はありません。アメリカ以外の全てのジョブ型社会には解雇規制があります。実は規定も日本とほぼ一緒です。日本は「客観的に合理的な理由」が必要ですが、ヨーロッパ諸国も似たような規定になっています。問題は「何が正当な理由か」どうかです。
ジョブ型社会というのは初めにジョブがあって、そこにできる人を当てはめるという形ですから、「ジョブがなくなる」というのが一番正当な解雇理由です。
しかし日本では「解雇の中で一番極悪非道なのはリストラだ」という全く逆の話になります。
皆さんの頭がさらに混乱するのは、能力不足解雇というものです。「日本以外のジョブ型社会ではスキル不足で解雇するのは正当な理由なのに、日本ではなかなか認められないのはけしからん」という話をしたがる人がいます。一見もっともらしいけれども、全く見当はずれなのです。
なぜかというと、日本語の「能力」とジョブ型社会の「スキル」は似たような言葉でありながら違う概念なのです。世界中どこへ行っても「ジョブを遂行する能力」を「スキル」と言います。
ところが日本の「能力」は、具体的なジョブのスキルとは関係のない一種独特の概念です。素人を採用してOJTで鍛えて仕事ができるように育てるのが上司の任務です。だから、若者にスキルがないからといって解雇することなどはありません。日本で能力不足解雇ということで問題になった判例を見ると、だいたい中高年のおじさんです。「働かないおじさん」という言葉もありますが、長年勤続してきた中高年を能力不足と称して追い出したがるのです。
職能給というのは「能力」に応じた賃金と称しています。その「能力」は、ジョブのスキルとは関係なく、若いころから積み重ねてきたものです。そういう意味では会社がその人に「能力がある」と認めているから高い職能給を払っているわけです。その人を「能力不足」と言って解雇できるのでしょうか? これ以上ない自己矛盾です。
■忠誠心不足が正当な解雇になるのか
もう1つ問題になるのが懲戒解雇です。
日本の懲戒解雇の例をヨーロッパの方々に話すと、「そうか、日本はアメリカ並みに解雇が自由な国なのか」とみんなが思います。先ほどの三菱樹脂事件もそうですが、会社の言うことを聞かないような者は懲戒解雇していいと日本の最高裁はお墨付きを出しているからです。

解雇の全体像を見ると、日本とヨーロッパではどこで厳しくてどこで緩いかというのが、非常に対極的ですが、それは全て「正当な理由」の違いによるものです。何が解雇の正当な理由かというのは、それぞれの社会の雇用システムの在り方によって形作られているわけです。
現実の中小零細企業では現実には金銭解決はあまりなく、あっても10万円ぐらいだという話を『日本の雇用終了』という本に書きました。法律上は金銭解決制度がなく、解雇無効による地位確認請求しかありません。ジョブ型社会であれば、解雇無効というのならば当然原職復帰です。それが困難なら金銭解決になります。日本では地位確認請求によってメンバーシップが認められるだけで、ジョブには戻れません。結果的に金銭を受け取るしかないという二重、三重、四重ぐらいにねじれた話になっています。

こういう構造に対して、労働法学者や弁護士はまともに突っ込んでいません。解雇については山のように議論がされているように見えますが、私に言わせればほとんど表層的な議論ばかりです。
■ジョブ型社会における賃金とは?
ジョブ型のける賃金とは職務評価による固定価格制です。「この椅子はいくらか」ということを評価して、椅子に値札をぺたっと貼るわけです。その椅子に座る人間が誰であれ、その値札通りの値段が払われます。人を評価してその背中に値札を貼るのではないのです。

1969年の『能力主義管理』という報告書で、経営側は職務給という主張を放棄するとともに、能力を査定して賃金を決めるというスタンスに変わりました。それ以後の日本型賃金制度の基本型である職能給です。
会社のために一生懸命残業したり、配転に応じたりするような「愛い奴」は高い査定でどんどん上がっていきます。そうでない者は低い査定であまり上がらないということで、競争を駆り立てるわけです。半世紀前に労使の利害が一致したのだと思います。
しかし、この「能力」は下がりません。結果中高年層で人件費とその貢献が乖離(かいり)をしてきます。企業は基本給の上昇を抑制するために、小手先の手段として成果主義と称する得体の知れないものを導入しました。
日本は職務の限定はありませんから、何の成果を測るのかが問題となります。それで「目標管理」と称して、むりやり達成困難な目標を押し付けて、「達成していないだろう」と言って中高年の賃金を引き下げたわけです。
そういう意味では効果がありましたが、反発も大きくなり、21世紀に入ってから成果主義とは廃れていきました。もう一度リベンジするために持ち出してきたのが、「ジョブ型」ではないかと私はにらんでいます。
■日本版同一労働同一賃金について
2016年1月に、当時の安倍首相は国会で、同一労働同一賃金に踏み込むと言いました。昨年日本郵便やメトロコマースなどの、いわゆる最高裁5判決が出たときに、全てのマスコミが「同一労働同一賃金の判決が出た」と報じました。
でも考えてみてください。これらの事件は全部、安倍前々首相が同一労働同一賃金に踏み込むという前に起こった事件です。ということは、踏み込む前から日本は同一労働同一賃金だったとしか解釈できませんね。政治家も官僚も労働法学者もマスコミも、そろいもそろって誰もこれに突っ込まないという面白い世界です。
定年退職もおかしな話がたくさんあります。定年とは何でしょう。日本政府は一応日本の法律の主だったものを英訳しています。定年は「mandatory retirement age」と訳しています。再度日本語に訳すと強制退職年齢ですね。けれども、今60歳で強制的に退職させられる人がいたら違法です。65歳まで継続雇用を義務付けられているので、mandatoryにリタイアする歳は65歳のはずなのです。

ではみんなが定年と称している60歳の正体は何かというと、実は処遇の清算年齢です。年功で高くなり過ぎた中高年の賃金を、本来あるべき水準に引き戻して、なおかつ引き続き雇い続けるためのつなぎ目です。経済的実体をいえば、60歳で年齢に基づく労働条件の不利益変更をしているわけです。
企業側は「60歳後は嘱託という別の雇用契約だから不利益変更ではない」と言って、異議申し立てを封じようとしました。しかし長澤運輸事件でも見たように、異議申し立ては完全には封じられませんでした。だからといってわざと低レベルな仕事を当てがおうとすると、トヨタ自動車事件のようなトラブルが起きます。日本の雇用社会は、こちらを叩くとあちらに矛盾が出てくるという世界なのです。
(つづく)
2021年11月29日開催
「日本型雇用の課題とこれからの雇用社会~昭和的働き方から脱却せよ~」
より抜粋編集の上掲載。
【登壇者】
■倉重 公太朗(KKM法律事務所)
■白石 紘一(東京八丁堀法律事務所)
■濱口 桂一郎(独立行政法人労働政策研究・研修機構)
■芦原 一郎(弁護士法人キャストグローバル)










