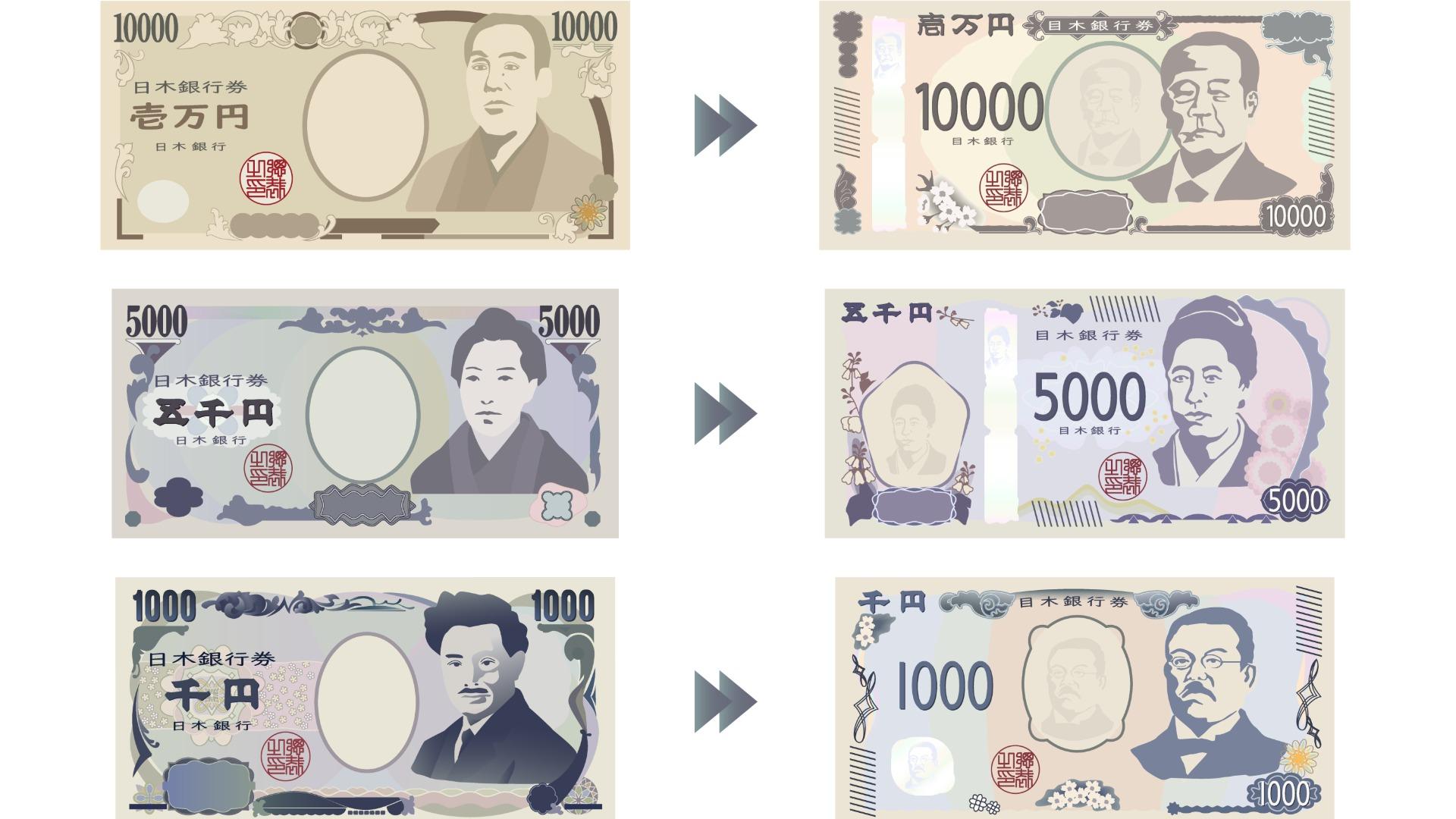自己目的化する日銀の金融政策

31日の夕刻に発表された「長期国債買入れ(利回り・価格入札方式)の四半期予定(2022年4~6月)」、通称「オペ紙」によると、利付国債についてはすべての年限で増額されることになった。
1年以下は変化なし。1年超3年以下については月4回で一回あたりのオファー金額は4500億円から、4回で同4750億円に増額。3年超5年以下は月4回で同一回あたりのオファー金額は4500億円から、4回で同4750億円に増額。5年超10年以下は月4回で一回あたりのオファー金額は4250億円から、4回で同5000億円に増額。10年超25年以下は月1回で一回あたりのオファー金額1500億円から、2回で同1250億円となり月あたりで増額。25年超も月1回で一回あたりのオファー金額500億円から、2回で同500億円となり、こちらも月あたりで増額する。
増額が大きいのは5年超10年以下となったのは、10年債利回りの0.25%の上限を死守するためとみられるが、超長期債の増額については疑問が生じるところとなる。
すでに30日の通常の国債買い入れで、予定になかった超長期債も対象とし、オファー額もそれまでのものから増額した。
10年国債の利回りよりも超長期ゾーンの国債利回りが急騰していたことで、それを押さえ付けるのが今回の日銀の目的であったのかもしれない。
しかし、これはYCCと呼ばれるイールドカーブコントロールが導入された経緯をみると疑問が生じる。
2016年1月に日銀はマイナス金利付き量的・質的緩和の導入を決定した。しかし、これに対して金融界から批判が出た。このため日銀は同年9月に長短金利操作付き量的・質的金融緩和を決定した。
これは10年までの利回りを抑え込む半面、10年を超える国債利回りを上昇させることによってイールドカーブをスティープ化させることも目的であった。
これを日銀は特に示してはいなかったが、金融機関からの批判を抑えるには少しでも利回りを得られる政策が必要とされたためと、少なくとも市場参加者は認識していたはずである。
ところが日銀は10年国債の利回りを0.25%で抑えたいがために、超長期ゾーンの利回りをも抑え込もうという手段に出てきたのである。
日銀は果たして何をしたいのか。2%の物価目標達成のために、超長期ゾーンの利回り形成まで操作する必要性はあるのか。
物価目標達成目的のために立てた、達成のための手段としての10年の0.25%が、いつの間にか目的にすり代わり、日銀の金融政策が自己目的化しているようにもみえる。