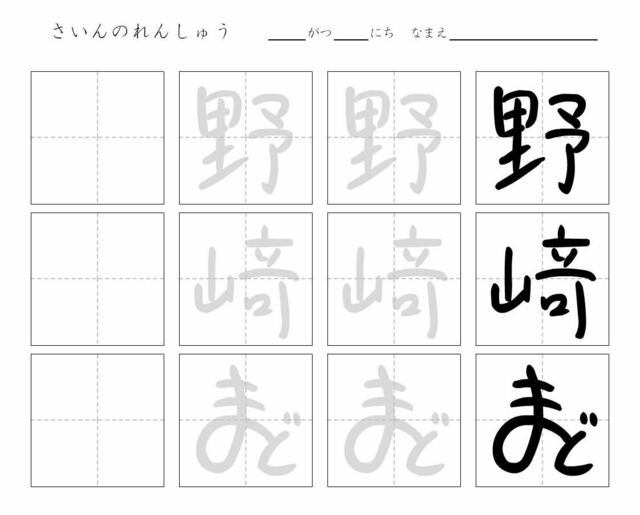「変わってるふり」では敵わない、同期の「頭のネジ」の飛び具合……デビューから「15年」が経ってもかわらない「絆」
ライバルではない「同期」の関係
──その後、野﨑さんは『2』に収束していく一連の作品、綾崎さんは「花鳥風月」シリーズをメディアワークス文庫から刊行されていきます。お互いライバル意識はあったのでしょうか。 野﨑:最初は綾崎さんのほうが刊行ペースが早かったので、「負けないようにしなければ!」と意識していました。でも三作目あたりで、これは追いつくのは無理だなと。すっかり諦めて、そのときライバル意識はなくなりましたね。 綾崎:僕の場合はライバルというよりも尊敬の念が強くて……。まどさんは当時、隔月刊だった『電撃文庫MAGAZINE』に「野﨑まど劇場」を連載されていましたよね。デビュー直後から連載できる体力はもちろん、内容が奇想天外すぎて衝撃を受けていました。 野﨑:ほら、真面目な雑誌には一個ギャグがほしいじゃないですか。「野﨑まど劇場」は当時の担当編集だった(KADOKAWAの)湯浅さん・土屋さん両名とギャグセンスをそろえるのが難しく、その隙間をなんとか通すかたちで採用されていました。没になった原稿の一部は『野﨑まど劇場』として刊行されたときに収録されていますが、世に出なかったものはそれ以上に多いです。 綾崎:没にされたから読んでほしいと言われて、まどさんから原稿を見せられたこともありましたが、あれは……すごかったです(苦笑)。 ──お互いに交流を続けながら小説を書かれていくなかで、メディアワークス文庫以外の版元から原稿を依頼される機会も増えていったのではないかと思います。多くの人に読まれるようになった実感はありましたか? 野﨑:あまりありません。もちろん十五年のあいだで少しずつ読まれていくようになったとは思うのですが、特定の作品で爆発的にファンが増えたという印象は特別にはありませんでした。元々癖の強い作風なので、百人が読んで一人でも好きになってくれたらありがたいです。 綾崎:僕も長いあいだ代表作と呼べるものがなかったのですが、『死にたがりの君に贈る物語』は多くのひとに読んでいただけて、応援してくださるひとがとても増えたと実感しています。昔から現在に至るまで読み続けてくれているひとも多く、とてもうれしいです。 野﨑:おそらく僕よりも、綾崎さんのファンのほうがお手紙を書いてくれるタイプのファンなのだと思います。愛の伝え方が真摯というか、ストレートというか……。 綾崎:それは確かに。 野﨑:僕のファンはきっと読み終わったあと、ニヤリとして本を閉じるタイプなのかなと。ファンレターが送られてきたときは額に入れて飾るようにしています。