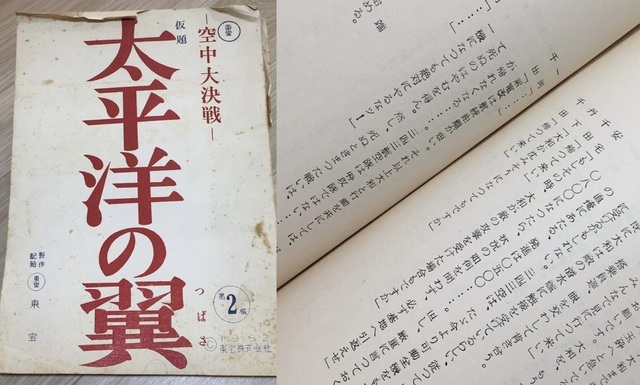「俺は死ぬ係じゃないから」…「特攻隊」立案編成に深く関わった「男たち」が戦後にとった「あまりにも違う態度」
源田の「経歴ロンダリング」
――こうして源田は、「戦局が悪化したのちも、特攻という理不尽な作戦に真っ向から反対した名参謀・名指揮官だった」という、実像とは正反対の世評を得た。みごとな経歴ロンダリング(洗浄)と言えるだろう。 昭和57年には、統一教会と国際勝共連合により設立された「世界日報社」が刊行する日刊紙「世界日報」に、「風鳴り止まず」と題する回想記を329回にわたり連載したが、ここでも源田は特攻について、 〈これらの若人は、決して強制によって組織せられたものではない。それは疑いもなく祖国の急を救うべく、自発的意志によって募集に応じたものである。〉(第322回) 〈「特攻」によっても戦局の挽回はできなかった。だが、日本民族が特攻隊の精神を受け継いでいく限り、長い歴史の流れの中に、大東亜戦争は真の敗戦ではなかったことを必ずや見出すであろう。〉(第327回) などと述べながらも、自身が航空特攻を推し進め、深く関与したことにはやはりひと言も触れていない。 大西瀧治郎中将は、太平洋戦争開戦時には、台湾・高雄の第十一航空艦隊参謀長として、東南アジアにおける日本海軍航空隊の緒戦の快進撃を仕掛けた。 ただし、大西は、日米開戦には反対、ないしは慎重な立場だった。
「美談のある戦争はいけない」
山本五十六連合艦隊司令長官から、真珠湾攻撃についての意見を求められたとき、大西ははじめ反対意見を述べている。 大西はその後、航空本部総務部長、軍需省航空兵器総局総務局長を歴任したが、草柳大蔵著『特攻の思想』によると、軍需省にいた昭和19年夏、東京・有楽町の朝日講堂で行った「血闘の前線に応えん」と題した講演で、「美談のある戦争はいけない」という歴史観を披露している。 「非常に勇ましい挿話がたくさんあるようなのはけっして戦いがうまくいっていないことを証明しているようなものなのである。たとえば南北朝時代、足利、北条が楠木正成に対して、事実は勝っていた場合の如きがそれである。あの場合、足利や北条のほうにはめざましい武勇伝なり、挿話なりというものはなくて、かえって楠木方に後世に伝わる数多い悲壮な武勇伝がある。 だから、勇ましい新聞種がたくさんできるということは、戦局からいってけっして喜ぶべきことではない。この大東亜戦争(太平洋戦争)でも、はじめ戦いが非常にうまくいっていたときには、個人個人を採り上げて武勇伝にするようなことは現在に比べるとずっと数は少なかった。いまはそれだけ戦いが順調でない証拠だともいえるのである。状況かくのごとくなった原因は、航空兵力が残念ながら量においてはなはだしい劣勢にあり、制空権が多くの場合、敵の手にあるからである」 ――歴史と照らして当時の戦況を冷静に分析し、悲観的な見通しを一般聴衆に対し率直に吐露しているのがわかる。 ではなぜ大西は自ら「統率の外道」とも評した特攻を命じたのか。これについて私は2011年、門司親徳副官と、大西に直接特攻を命じられた歴戦の零戦搭乗員・角田和男中尉の証言を軸に検証、『特攻の真意』(文藝春秋/現在は光人社NF文庫)という本を書いた。 角田は特攻待機中、かつて計器飛行を習った教官である小田原参謀長から、大西中将の「特攻の真意」を聞かされている。それは要約すれば、 「敵に本土上陸を許せば、未来永劫日本は滅びる。特攻は、フィリピンを最後の戦場にし、天皇陛下に戦争終結のご聖断を仰ぎ、講和を結ぶための最後の手段である」 というものだった。しかもこのことは、海軍砲術学校教頭で、昭和天皇の弟宮として大きな影響力を持つ海軍大佐・高松宮宣仁親王、米内光政海軍大臣の内諾を得ていたという。つまりこれは、表に出さざる「海軍の総意」だったとみて差し支えない。 フィリピンを最後の戦場にすることは叶わなかったが、その後も特攻は、 「敵に恐怖を与え続けて日本本土上陸を思いとどまらせると同時に、天皇に終戦の聖断を仰ぐための最終手段」 として続けられた。だとすれば、終戦を促す「ポツダム宣言」が日本本土決戦を待たずに連合国側から出されたこと、そしてその受諾が天皇の聖断によって決定されたことを思えば、特攻隊員たちの死はけっして「無駄死に」ではなかったことになる。 終戦がもし、陸海軍や政治による多数決で決まったならば、国内の「抗戦派」の不満がくすぶり、「和平派」とのあいだで内戦も起こりかねなかった。「天皇の聖断」であったからこそ、日本陸海軍は整然と矛をおさめることができたのだ。