#話題のタグ
検索結果
11件
 多くの氷河湖「危険な状態」 第3部「未来が見える場所」(7)〔66°33′N 北極が教えるみらい〕インド国立極地海洋研究センターのタンバン・メロス所長の話 ヒマラヤの氷河は、ほとんどの地域で解けている。 減少ペースは過去20年で加速している。時事通信アジア・オセアニア
多くの氷河湖「危険な状態」 第3部「未来が見える場所」(7)〔66°33′N 北極が教えるみらい〕インド国立極地海洋研究センターのタンバン・メロス所長の話 ヒマラヤの氷河は、ほとんどの地域で解けている。 減少ペースは過去20年で加速している。時事通信アジア・オセアニア 2023年の温室効果ガス排出量、過去最多 今世紀中に「気温3.1度上昇も」とUNEP警告2023年の世界の温室効果ガスの排出量は571億トン(二酸化炭素換算)に及び、前年から1.3%増加して過去最多になったとする報告書を国連環境計画(…Science Portal科学
2023年の温室効果ガス排出量、過去最多 今世紀中に「気温3.1度上昇も」とUNEP警告2023年の世界の温室効果ガスの排出量は571億トン(二酸化炭素換算)に及び、前年から1.3%増加して過去最多になったとする報告書を国連環境計画(…Science Portal科学 南極観測に初の女性越冬隊長 極地研・江尻省准教授、来年出発…大低温科学研究所の青木茂教授(58)に決めた。副隊長(兼越冬隊長)は国立極地研究所の江尻省准教授(51)で、女性が越冬隊長に選ばれるのは初。 青木氏…共同通信社会
南極観測に初の女性越冬隊長 極地研・江尻省准教授、来年出発…大低温科学研究所の青木茂教授(58)に決めた。副隊長(兼越冬隊長)は国立極地研究所の江尻省准教授(51)で、女性が越冬隊長に選ばれるのは初。 青木氏…共同通信社会 極地の光環境が育む生物多様性の秘密...フィンランド研究チームの新説…と、地球の極地で見られる白夜や極夜のような極端な光環境が、長期にわたり生物多様性を維持する重要な役割を果たしている可能性がある>地球の極地で極端な光…ニューズウィーク日本版国際総合
極地の光環境が育む生物多様性の秘密...フィンランド研究チームの新説…と、地球の極地で見られる白夜や極夜のような極端な光環境が、長期にわたり生物多様性を維持する重要な役割を果たしている可能性がある>地球の極地で極端な光…ニューズウィーク日本版国際総合 「火星の石」大阪万博で初展示 日本観測隊が南極で発見政府は17日、2025年大阪・関西万博で、国立極地研究所(東京都立川市)が保管している「火星の石」を目玉の一つとして展示すると発表した。00年に日…共同通信社会
「火星の石」大阪万博で初展示 日本観測隊が南極で発見政府は17日、2025年大阪・関西万博で、国立極地研究所(東京都立川市)が保管している「火星の石」を目玉の一つとして展示すると発表した。00年に日…共同通信社会 中国、海洋調査用の国産新型砕氷船引き渡し…【東方新報】海洋調査と災害対応能力を強化した中国国産の新型砕氷調査船「極地(Ji Di)」が6月24日、広東省(Guangdong)広州市(Guan…東方新報中国・台湾
中国、海洋調査用の国産新型砕氷船引き渡し…【東方新報】海洋調査と災害対応能力を強化した中国国産の新型砕氷調査船「極地(Ji Di)」が6月24日、広東省(Guangdong)広州市(Guan…東方新報中国・台湾 南極から「地球や宇宙をのぞく」 50年前の“南極点到達”が開いた観測の扉提供:国立極地研究所Yahoo!ニュース 特集社会
南極から「地球や宇宙をのぞく」 50年前の“南極点到達”が開いた観測の扉提供:国立極地研究所Yahoo!ニュース 特集社会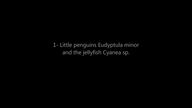 「ペンギンはクラゲを食べる」従来の見方覆す研究結果 国立極地研など発表国立極地研究所を含む国際共同研究グループは22日、南極海などのペンギンがクラゲを頻繁に食べている事実が確認されたと発表した。従来、クラゲは栄養価が…THE PAGE科学
「ペンギンはクラゲを食べる」従来の見方覆す研究結果 国立極地研など発表国立極地研究所を含む国際共同研究グループは22日、南極海などのペンギンがクラゲを頻繁に食べている事実が確認されたと発表した。従来、クラゲは栄養価が…THE PAGE科学 「千葉」が地質時代の名前になる?「チバニアン」から考える地磁気の変化…国際標準として申請 認定されれば地質時代のひとつが「チバニアン」に(国立極地研究所)…THE PAGE科学
「千葉」が地質時代の名前になる?「チバニアン」から考える地磁気の変化…国際標準として申請 認定されれば地質時代のひとつが「チバニアン」に(国立極地研究所)…THE PAGE科学 日本の南極観測60年、世界で初めてオゾンホールを観測した日本隊…年。過去、世界初のオゾンホール発見など、数々の研究成果をあげてきた。国立極地研究所の白石和行所長(68)は、取り組むべきテーマはまだまだ多くあり、地球…THE PAGE科学
日本の南極観測60年、世界で初めてオゾンホールを観測した日本隊…年。過去、世界初のオゾンホール発見など、数々の研究成果をあげてきた。国立極地研究所の白石和行所長(68)は、取り組むべきテーマはまだまだ多くあり、地球…THE PAGE科学 凍結後30年経っても蘇生・繁殖 「最強生物」クマムシの秘密とは?…結されていたクマムシが蘇生した」という驚くべきニュースが駆け巡った。国立極地研究所が発表した成果で、蘇生したクマムシはその後、繁殖も行ったという。人間…THE PAGE科学
凍結後30年経っても蘇生・繁殖 「最強生物」クマムシの秘密とは?…結されていたクマムシが蘇生した」という驚くべきニュースが駆け巡った。国立極地研究所が発表した成果で、蘇生したクマムシはその後、繁殖も行ったという。人間…THE PAGE科学
トピックス(主要)
アクセスランキング
- 1
顔よりデカい“特大バーガー”が目当ての客も…ナゼ?「スーパーのバーガー」が大人気【THE TIME,】
TBS NEWS DIG Powered by JNN
- 2
小学生の空手大会で危険行為 反則選手の所属会が謝罪 セコンドの処分を発表「無期限の謹慎」治療費も対応
スポニチアネックス
- 3
国民・玉木代表の不倫相手は元グラドル 現在は「ムチムチボディー」 観光大使委嘱の高松市は「確認中」
スポニチアネックス
- 4
アレン様、バラエティー番組「相席食堂」制作サイドから届いたとするメールに苦言 「偉そうな口調で外して等と連絡してきて、」「二度とオファーしてこないで下さぃませ」
ねとらぼ
- 5
玉木氏は代表続投なのに 不倫相手は大使解任の可能性 橋下徹氏「これはアカン」
デイリースポーツ




