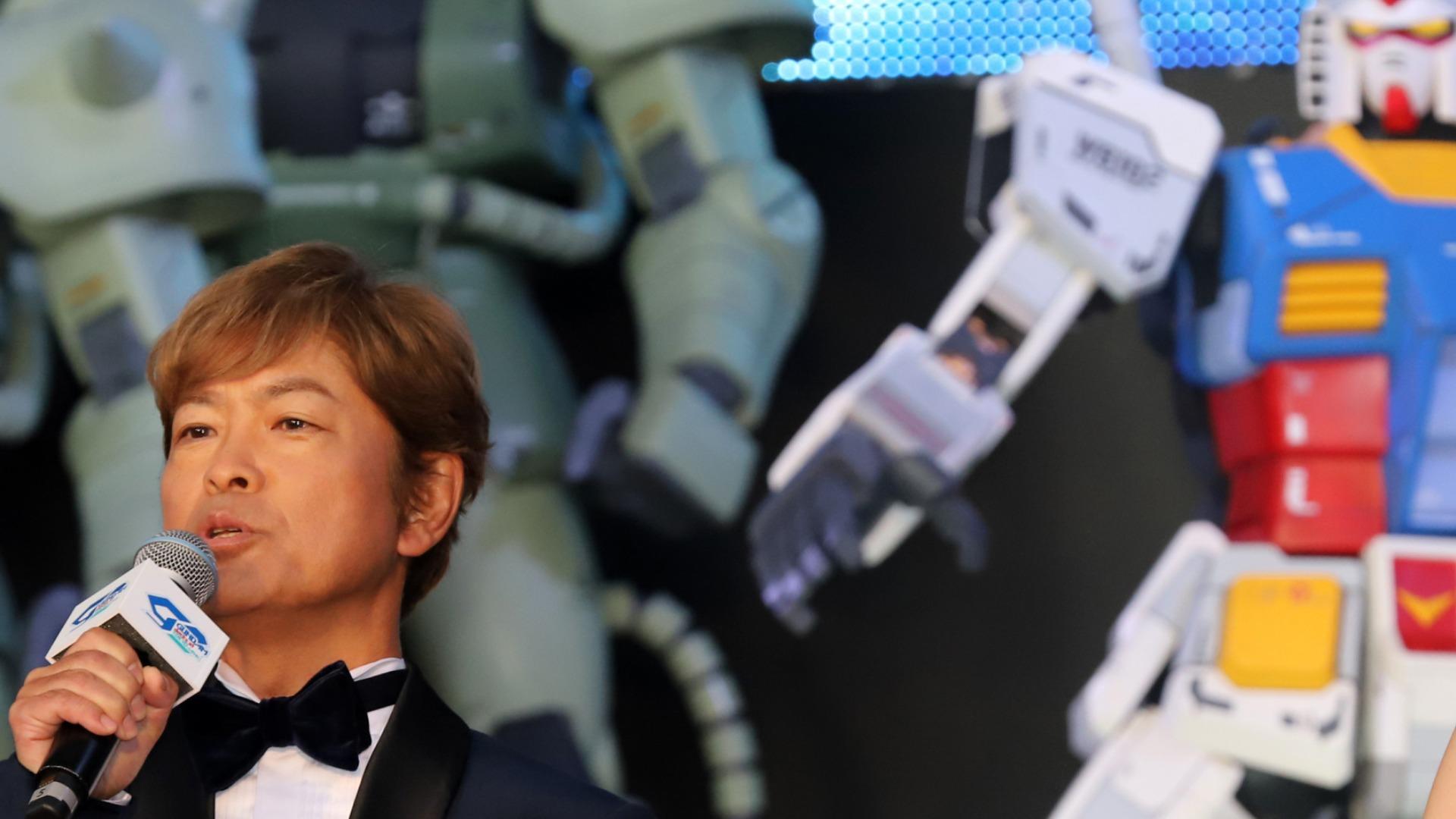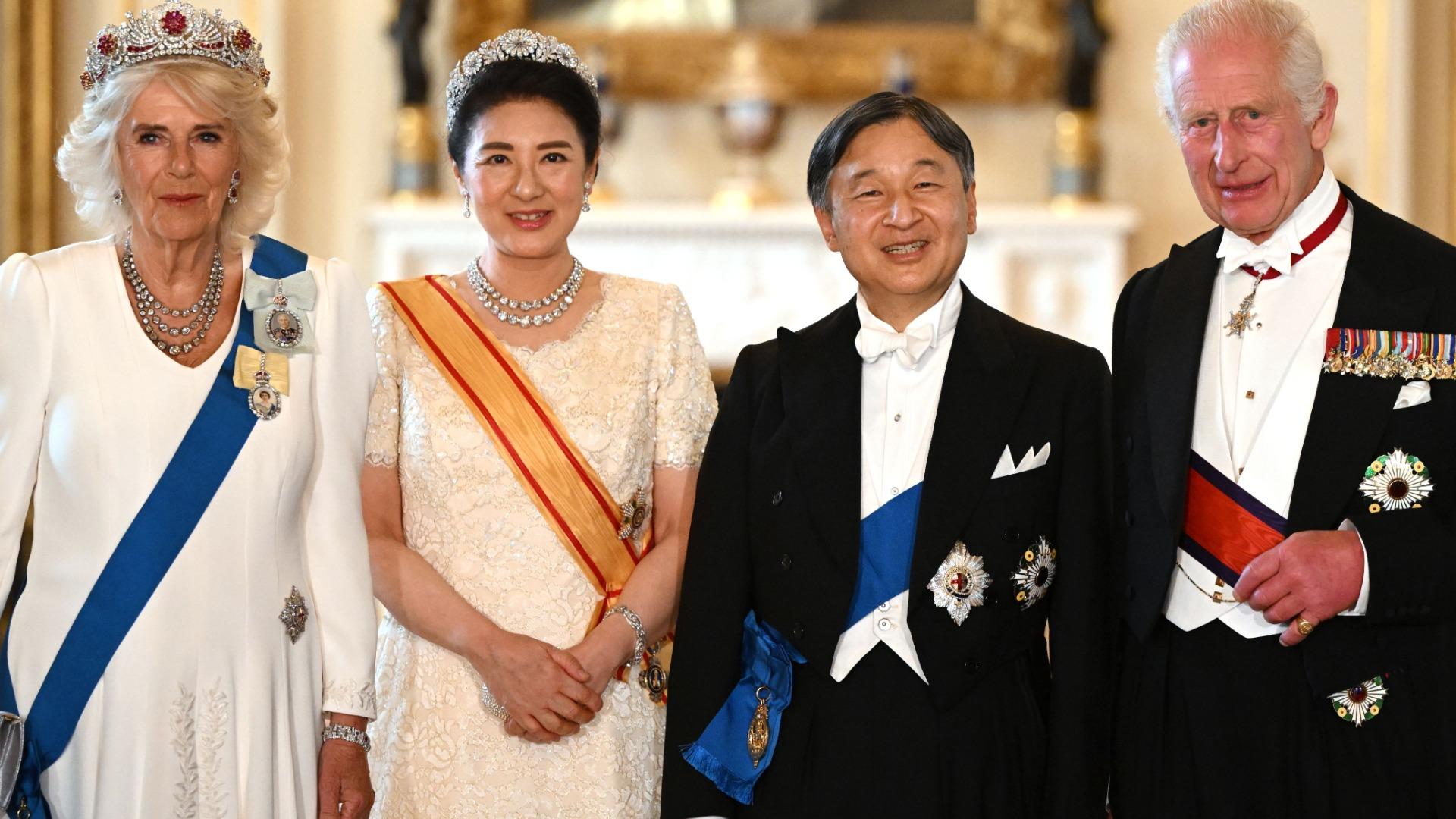ダウ平均が800ドル安と今年最大の下げ幅となった理由

14日の米国株式市場では、ダウ平均は800ドル安となり年最大の下げ幅となった。このきっかけはいくつかあるが、最も大きかったものは米国と中国の通商交渉への懸念とそれによる米国経済への影響、さらには世界経済への悪影響が意識されたためであろう。
米通商代表部(USTR)は13日、ほぼすべての中国製品に制裁関税を広げる「第4弾」について、スマートフォンやノートパソコン、玩具など特定品目の発動を12月15日に先送りすると発表した。これによって13日の米国株式市場は反発し372ドル高となっていた。しかし、クリスマス商戦の仕入れなどに配慮した米国側の都合によるものであり、時間稼ぎに過ぎず、交渉の行方について楽観的な見方が出てきたわけではない。
市場は現在、長期にわたる景気の回復が、米中の貿易戦争によって悪化してくるとの懸念を抱いている。米中の交渉の進展に期待が持てないところに、経済指標の悪化も意識されはじめた。13日に発表された8月のドイツZEW景気期待指数がマイナス44.1と、7月のマイナス24.5から大幅に悪化していた。14日に発表されたドイツの第2四半期GDPは輸出の落ち込みが影響しマイナス成長となった。これらを受けて欧州の国債の利回りは低下し、ドイツの10年債利回りは過去最低を更新している。
また、14日に発表された中国の7月の鉱工業生産は17年超ぶりの弱い伸びにとどまったことも嫌気された。
14日の米国債は長いところ主体に買い進まれた。米30年債利回りは過去最低利回りを更新。10年債利回りも低下し、2年債利回りを下回った。2007年以来の2年債と10年債利回りの逆転も米株下落の要因とされたが、米国の長短金利は3月にすでに逆転していたことで、後講釈にも思える。
トランプ大統領は今回の株価下落の犯人を自分ではなくFRBとしたいようだが、トランプ大統領だけでなく、市場もFRBの利下げを要求しているかにも思える。それが長期金利の一層の低下に繋がった可能性がある。
しかし、中央銀行の金融緩和策への過度な期待もどうかと思う。利下げなどによる金融緩和策による景気への影響は限定的とみられ、市場もトランプ大統領も金融政策に対する幻想を抱いているかにも思える。中央銀行の金融政策はそもそも万能薬ではない。
今回の米国株式市場の急落をどうみるか。ダウ平均のチャートからは何ともいえないが、もしダウ平均が25000ドルを割り込んでくると、再びダウントレンド入りしてくる可能性はある。リスク回避の動きから再び円高も進行し、ドル円は105円台となっている。15日の東京株式市場も売りが先行しているが、いったん下げ渋りともなっている。ここからの動きをどうみるか。もう少し様子を見る必要がある。