【光る君へ】藤原道長の実像。意外と病弱で、よく寝込んでいたのは本当か?(家系図/相関図)
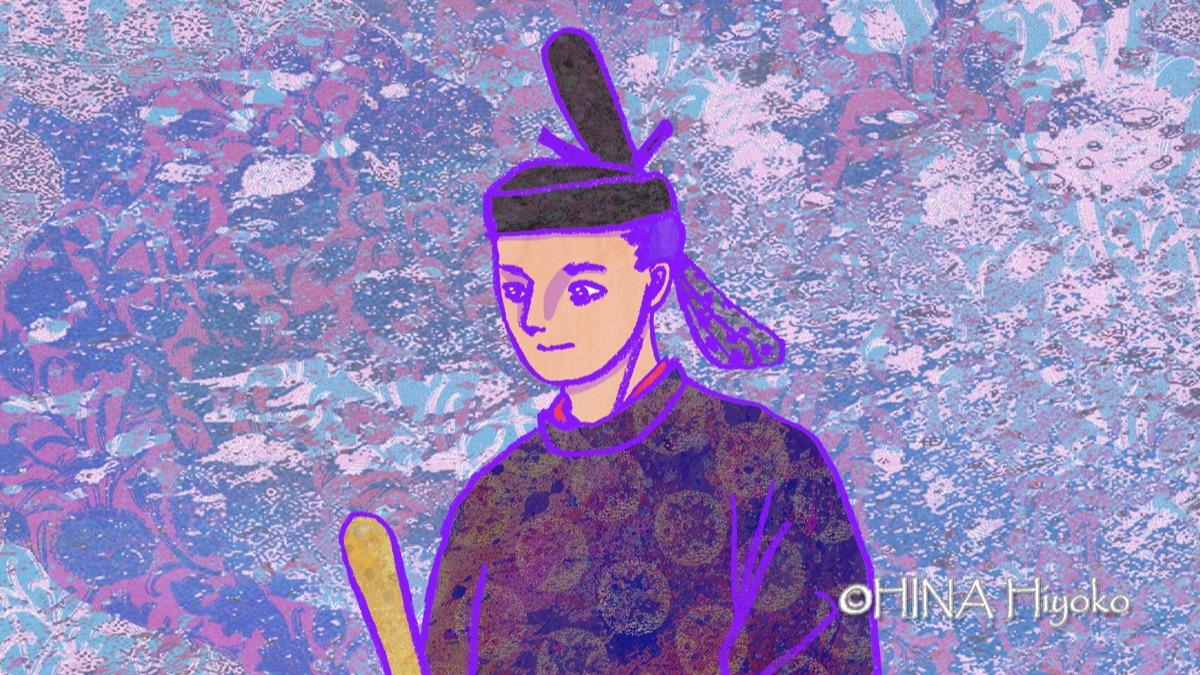
NHK大河ドラマ『光る君へ』。世界最古の小説『源氏物語』の作者・紫式部(演:吉高由里子)と、平安時代に藤原氏全盛を築いた藤原道長(演:柄本佑)とのラブストーリー。
少しだけ前回(6/23放送)のおさらい。
不実な女・まひろ(紫式部)とさらに不実な男・藤原宣孝(演:佐々木蔵之介)がついに結婚。あろうことか、宣孝は道長に結婚の報告に行く。
(つまり、宣孝は妻の元カレが道長だと知っていたのだ)
そして道長の反応をまひろに伝える宣孝。道長からは祝いの品が届くが、手紙は代筆だった。
まひろは傷つくが、ある意味吹っ切れたのだから、宣孝は女心がよくわかっているのだろう。
たしかに表面上は道長の態度はあっさりしていたけれど、ここは職場、しかも左大臣という身分ならば当然のこと。よもや泣き崩れるわけにもいくまい。
ショックのあまりその日は家にも帰らずに道長が仕事に没頭したことを、まひろは知らない。
◆史実の道長は、権力欲の強いギラギラしたイメージ通りの人なのか?
ここからは、いつものようにドラマと史実を比べてみる。今回の主役は道長である。
平安時代、そして藤原氏を代表する権力者。さぞかしやり手で権力欲の強い御仁というイメージが強そうだが、史実として考えられている道長は、どのような人物だったのだろうか?
◎道長が天皇に数回辞表を出したのは本当?
安倍晴明(演:ユースケ・サンタマリア)の予言通り、川の決壊により都は水害にみまわれた。道長や藤原行成(演:渡辺大知)の再三の対策要求を無視した一条天皇(演:塩野瑛久)。
天皇はその後も中宮定子(演:高畑充希)やその兄・藤原伊周(演:三浦翔平)と一緒に、藤原公任(演:町田啓太)の笛の音をのんびりと楽しんでいる。
そこへ乗り込んできた道長は、この度の災害の責任を取って左大臣の職を辞すると告げる。
あわてて引き留める天皇。今の朝廷には道長に代わる人材など誰もいないということなのだろう。
その後道長は3度辞表を提出するが、いずれも受理されることはなかったという。
権力への執着が強く、のちに権力者として専横を極めたといわれる道長は、本当に辞表を提出したりしたのだろうか?
◎辞表を出した理由:不手際のせいではなかった?
実際に道長は辞表を出したと伝わる。しかし、理由は水害の引責辞任ではない。このころの道長はかなり健康を害していたといわれるのだ。
ドラマの中では姉の女院・詮子(演:吉田羊)が物の怪を恐れるシーンがあった。伊周が部屋の隅で睨んでいたと恐れ、胸の痛みを訴えた。そのため、997年(長徳3年)一条天皇は大赦をおこない、伊周や弟の隆家(演:竜星涼)は帰京。
史実によれば、翌998年(長徳4年)には女院だけでなく道長も寝込みがちになり、左大臣を辞して出家を願うようになったと伝わる。何度も辞表を出したのはこのときだと考えられる。
998年といえば、紫式部が結婚したころだといわれている(正確な時期は不明)ので、ドラマの時期とも重なるのだ。
まだ道長は32歳。ドラマでは数年前に夜通し疫病にかかったまひろを看病してもピンピンしていたが、実際は意外と虚弱だったのである。
◎物の怪を恐れ、出家を望む、それが貴族のスタンダード?
この時代は病になると物の怪のしわざとされた。通常であれば、自分を恨む人などそれほど多くはないものだが、道長の場合、兄たちの死の結果得た権力の座である。
道長の目には長兄の道隆(演:井浦新)やその妻の高内侍(演:板谷由夏)、次兄の道兼(演:玉置玲央)などが物の怪となって見えたと考えられる。
よくよく考えれば、自分に恨みを持つ者がみな兄弟など近しい間柄なのである。ついすべてに嫌気がさして出家したくなるのも、無理はないかもしれない。
この時代、疫病で多くの人が死んだり、権力の座からあっという間に転落したりして、貴族でも無常感を持つ人が多かった。
そのような俗世の無常感から救済を願い、出家したがる若い貴公子や貴婦人が多かったのである。道長の三男・顕信も18歳で出家している。

◆兄と同じ病に苦しんだ晩年
◎「飲水病」でいつものどが渇いていた道長
道長の兄・道隆と道兼はいずれも疫病が流行った年(995年)に亡くなっている。道兼の死因は疫病だが、道隆は持病の「飲水病」が悪化したと伝わる。
飲水病とは、現代の糖尿病のこと。ほがらかで酒好き・宴会好きだったといわれる道隆。そういえばドラマでも道隆はかなりの登場シーンで酒を飲んでいたような気がする。
道長も中年以降は飲水病におかされ、のどの渇きに苦しんだといわれる。晩年にはかなり視力も衰えていたそうだ。
道長は1028年(万寿4年)薨去。享年62。
兄道隆を反面教師として相当生活に注意を払っていたという道長。そのおかげで享年43歳の道隆より20年も長生きし、後一条天皇の外祖父となり栄華を極めた。

しかし、家庭人としては、4人もの子に先立たれるという不幸にもみまわれている。彼は泣き上戸で、うれしくても悲しくてもよく泣いたという。
政治家としての道長は、実資(演:ロバート秋山)とともに社会政策に取り組み、業績も残している。
ドラマの道長はかなり美化しているといえなくもないだろうが、権力者としての道長とは違う人間的な一面も当然、彼にはあったのである。
(イラスト・文 / 陽菜ひよ子)
◆主要参考文献
フェミニスト紫式部の生活と意見 ~現代用語で読み解く「源氏物語」~(奥山景布子)(集英社)
ワケあり式部とおつかれ道長(奥山景布子)(中央公論新社)
紫式部日記(山本淳子編)(角川文庫)
藤原道長「御堂関白記」(訳:倉本一宏)(講談社)










