【抜毛症・皮膚むしり症・爪噛み症の最新治療】薬物療法の効果と限界とは?
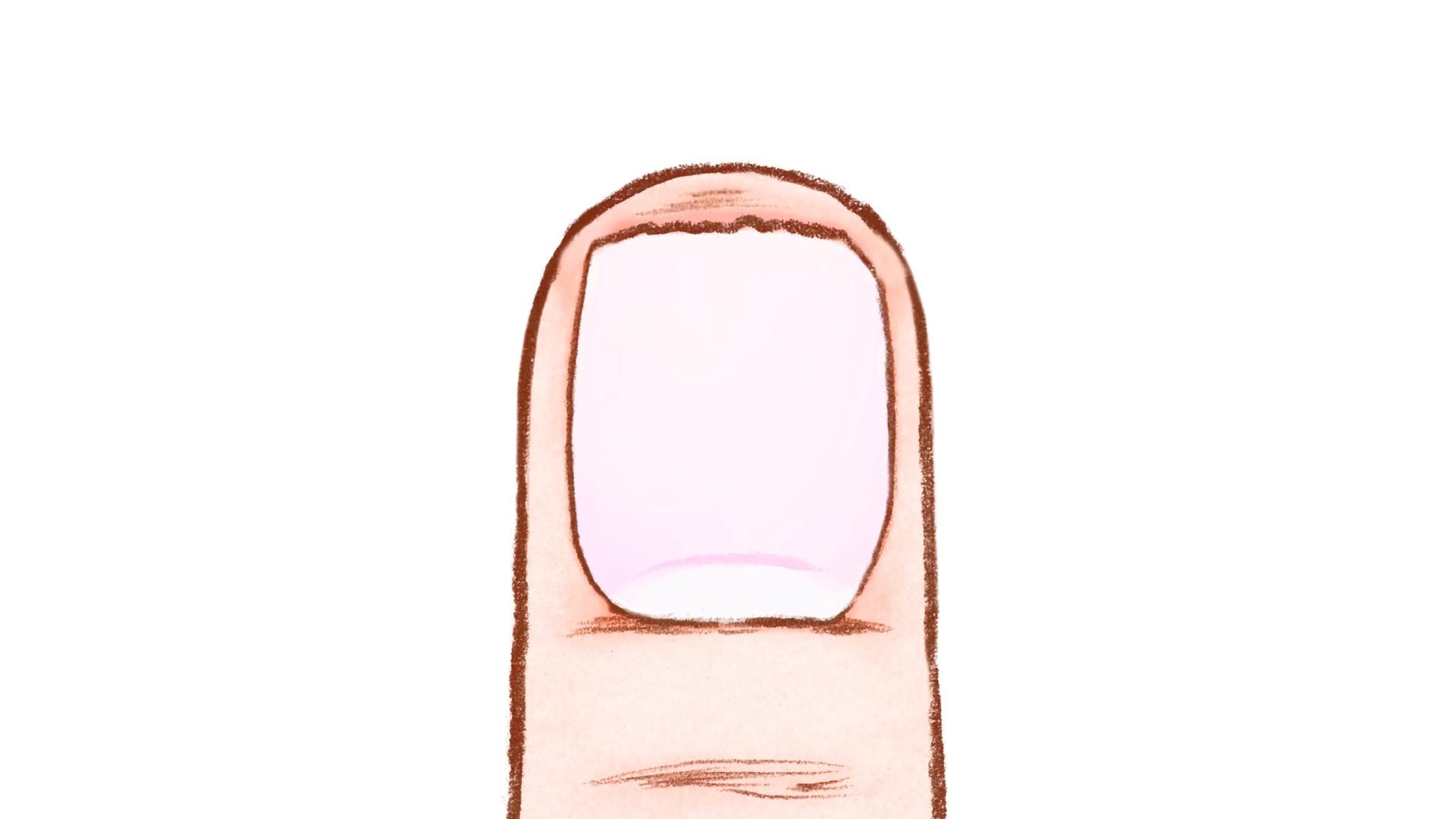
今回は、抜毛症、皮膚むしり症、爪噛み症などの強迫性障害に対する薬物療法について、最新の研究をまとめてみました。
強迫性障害の一種である抜毛症、皮膚むしり症、爪噛み症は、自分の髪の毛を抜いたり、皮膚をむしったり、爪を噛んだりする衝動を抑えられない状態を指します。これらの行動は自傷行為の一種とも考えられ、心理的な苦痛を伴うだけでなく、外見上の問題も引き起こします。
これらの障害に対しては、認知行動療法などの心理療法に加えて、薬物療法が試みられています。ここでは、各種の薬剤の効果と限界について解説します。
【抗うつ薬による治療とその限界】
抜毛症や皮膚むしり症の治療には、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)などの抗うつ薬がよく用いられます。しかし、フルオキセチンなどのSSRIについては、プラセボ(偽薬)との比較で明確な効果は認められていません。一方、三環系抗うつ薬のクロミプラミンには一定の効果が示唆されていますが、副作用の問題もあり注意が必要です。
【抗精神病薬・抗てんかん薬・その他の薬剤】
非定型抗精神病薬のオランザピンは、抜毛症に対する小規模な試験で効果が認められました。一方、抗てんかん薬のラモトリギンや、大量のイノシトールを用いた治療については、有効性は確認されていません。
オピオイド拮抗薬のナルトレキソンについても、抜毛症に対する効果は見られませんでした。グルタミン酸調整薬のN-アセチルシステインは、皮膚むしり症に一定の効果を示しましたが、抜毛症や爪噛み症に対する有効性は限定的でした。
【皮膚疾患との関連と治療における注意点】
抜毛症や皮膚むしり症は、皮膚に直接的な損傷を与える疾患です。繰り返されるこれらの行為は、脱毛や皮膚の炎症、痒みを引き起こし、最悪の場合は瘢痕を残すこともあります。したがって、治療に際しては精神科と皮膚科との連携も重要になります。
抜毛症、皮膚むしり症、爪噛み症に対する薬物療法は、いまだ発展途上の段階にあると言えるでしょう。現時点では決定打となる治療薬はなく、個々の患者の状態に応じて、心理療法と組み合わせながら慎重に薬剤を選択していく必要があります。今後のさらなる研究の進展が期待されます。
以上、抜毛症、皮膚むしり症、爪噛み症に対する薬物療法の現状についてお伝えしました。自分や周囲の人がこれらの症状で悩んでいる場合は、専門家への相談をおすすめします。
参考文献:
Sani, G., et al. (2019). Drug Treatment of Trichotillomania (Hair-Pulling Disorder), Excoriation (Skin-picking) Disorder, and Nail-biting (Onychophagia). Current Neuropharmacology, 17(8), 775-786.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7059900/










