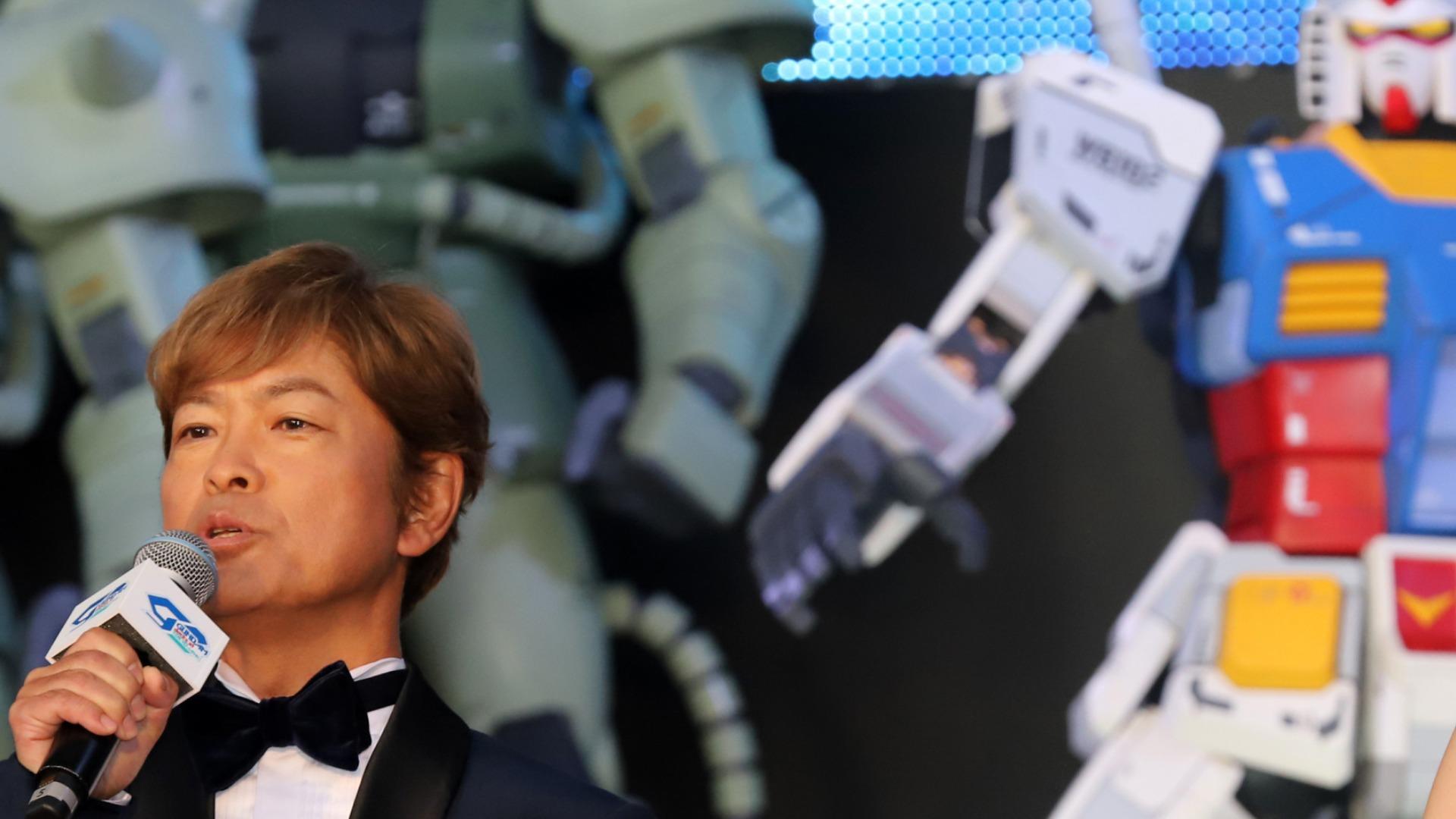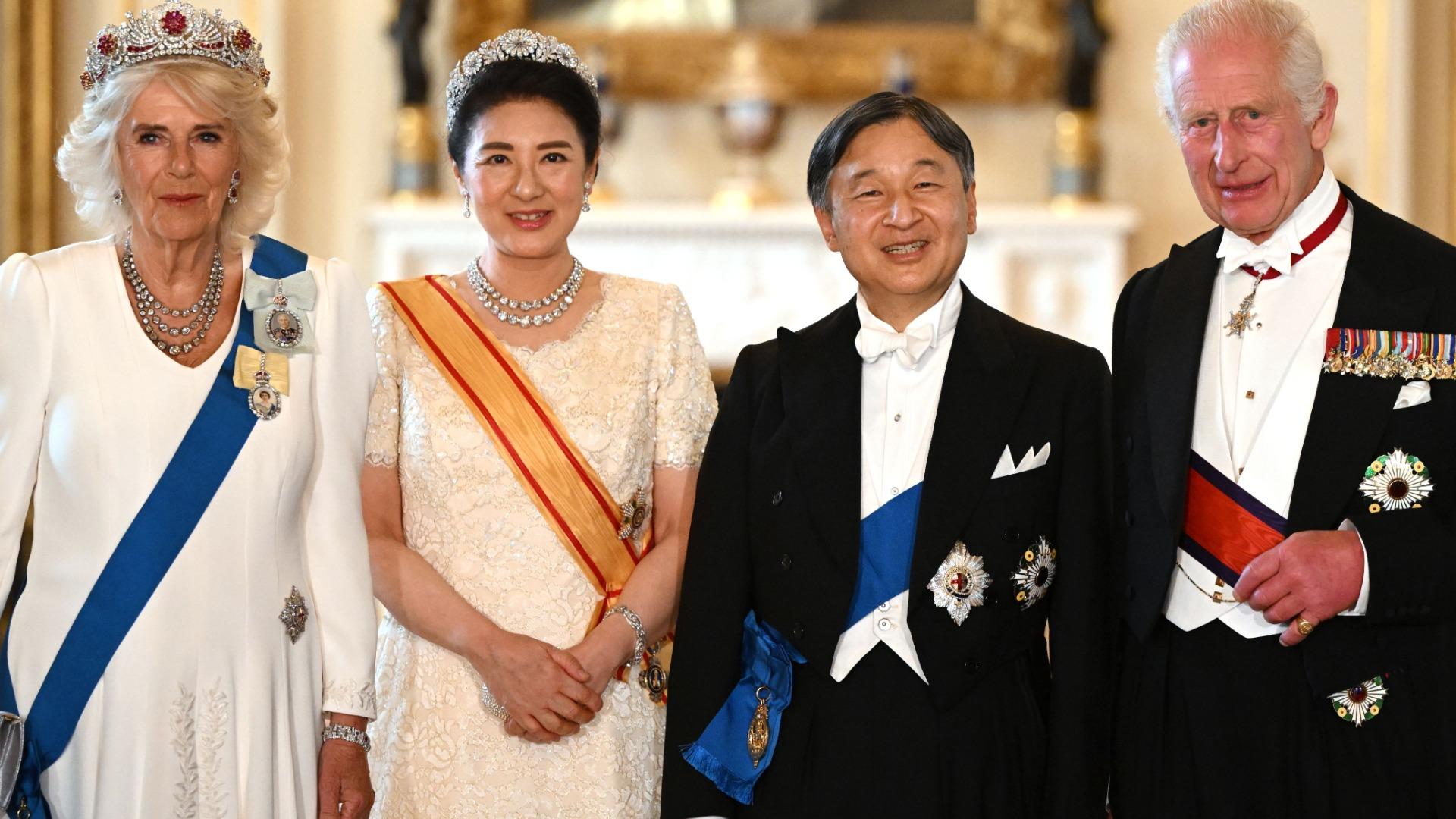日銀がやるべきことはYCCをどう続けるかではなく動揺を与えずどう停止させるか。無理な工夫は市場を壊す

3月20日から日銀の副総裁が交代し、元日銀理事の内田氏と元金融庁長官の氷見野氏が就任した。元日銀理事の内田氏はいかに異次元緩和を継続させるかに力を注いでいたとみられる。金融政策の企画立案を担ってきた内田理事が副総裁に昇格したことに伴い、日銀は清水誠一理事を企画局担当にすると発表した。清水氏は2020年7月まで金融市場局長を務め、イールドカーブ・コントロールの実務に精通するとされている。
2021年まではイールドカーブ・コントロールの欠点が見えていなかった。そもそも日銀は長期金利は市場で形成されるものと認識していた。それをコントロールするということがいかに困難であるのかが、わかってきたのが2022年に入ってからのことであった。
長期金利コントロールを導入したのが2016年9月。同年4月に決定したマイナス金利政策の批判に対応するためでもあった。10年よりも長い期間の国債利回りを引き上げ、金融機関の収益チャンスを拡げようとしたものである。
この際に日銀は政策目標を両から再び金利に戻していた。問題となったのは、黒田総裁を中心として、日銀には金融緩和を拡大する方向ばかりみており、それを後退させることは言語道断といった認識を持っていたことにある。
あたりまえのことであるが、中央銀行の金融政策は状況に応じて金融緩和を行ったり、金融引き締めを行う。それは柔軟かつ機動的に行われるものである。しかし、黒田日銀にとって引き締めは禁句となってしまっていた。
ただし、2021年までは物価が上昇してこなかったことで、金利そのものも低位安定していた。これによって日銀の長期金利コントロールがさも可能であったかのように見えた。
物価が上昇し、それに応じた金利が形成されるとなれば、状況が異なってくる。新型コロナウイルスの感染拡大によるサプライチェーンへの問題が発生し、ロシアによるウクライナ侵攻などをきっかとして世界的な物価の急騰が起きた。これに当然ながら日本も巻き込まれた。
欧米の中央銀行はそれに対して機動的かつ柔軟な対応をみせた。それに対して日銀は断固として大胆な緩和姿勢を緩めることはせず、長期金利コントロールに無理が掛かり、10年債カレントを発行額以上日銀が吸い上げるなど異常な事態が発生した。はっきり言えば市場機能が失われ、日本の債券市場が壊れ掛かっている。10年債など国債の利回りの居所がめちゃくちゃになってきている。
今後は日銀の金融政策に必要な柔軟性、機動性を取り戻すとともに、長期金利の形成を戻す作業が必要とされる。しかも市場に大きな動揺を与えずに行うことが、新体制の日銀に求められている。ミスターイールドカーブ・コントロールがやるべきことは、イールドカーブ・コントロールを止めることである。