デジタル・ゴールドラッシュを狙え!深センに集まる若者たち

デジタル・ゴールドラッシュ。黄金に引き寄せられて野心家たちが殺到した、かつてのカリフォルニアのように、「ハードウェアの聖地」深センは野心あふれる若者たちを引きつけている。
ファーウェイの任正非、テンセントの馬化騰を筆頭に、深センの歴史はそうそうたる起業家たちの名によって飾られている。経済特区として資本主義を取り入れる窓となった深センは、中国でもっとも早く市場経済、民間企業が発展した街だ。加えてIoT(モノのインターネット)時代を迎えたことで、自慢のエレクトロニクス産業の重要性がさらに高まった。
IoT時代にはインターネットにつながるさまざまなデバイスが必要とされる。きわめて多様なニーズが存在するだけに、大企業のみならず、一発屋が成功する余地も大きい。多くのベンチャー企業がIoTに参入しているが、彼らにとって深センこそが最良の製造拠点となる。この街ならば自分でも一発あてられるのではないかと夢見る若者たちが、深センにはあふれている。
深センのスピード感のとりこに

鈴木陽介さん(35)もその一人。彼は深センに魅せられたと話す。前職は自動車関連の設備機器メーカーの社員だった。2011年に駐在員として広東省に赴任した。
「2010年に中国の日系自動車メーカーの工場で賃上げストがありましたよね。あのニュースを見て社長が中国でも今後、工場の自動化が進むはずだからチャンスだとビビっと来て。それで中国事業立ち上げに派遣されたんですよ」
中国に赴任すると、その勢いに驚いた。
「荒々しい発展とでも言うんでしょうか。近未来的なビルがどんどん建つかと思えば、そのすぐ近くにスラムが残っている。とり残された人や場所があってもおかまいなし、ともかくものすごい勢いで社会が変わっていくんです。スピード感が日本とはまるで違います。それと人の眼ですね。輝いているっていうか。社会の勢いが一人一人に乗り移っているような気がしました」
赴任から約2年で帰国を命じられたが、「中国に残ったほうが絶対に面白い」と判断し、独立を決めた。越境EC(電子商取引)の事業から始まり、香港・深セン情報サイトの運営、日本企業向けの翻訳サービスや深セン視察ツアーの企画、IoT製品の開発支援などさまざまなビジネスを手がけてきた。成功ばかりではない。むしろ失敗したビジネス、なかなか芽が出ないビジネスのほうが多いかもしれない。だが、スピード感と熱狂が漂う、この地で戦い抜く覚悟は変わらない。
夢追い人の熱気にあてられた
日中ハーフの荒井健一さん(29)は、中国各地を旅した末に深センでの起業を決めた。中国の大学を卒業後、この街にやってきた。学生時代から起業を決めていたが、どの街を舞台とするのかは決めあぐねていた。故郷・河北省から遠く離れた深センを選んだ理由は、その空気感に引かれたからだという。旅行で訪れた時、衝撃を受けた。住んでいるのは若者ばかりで、起業の夢を追っている人が多い。大企業重視の傾向が強い中国北部とは別世界だった。その熱気にあてられたかのように、荒井さんもスーツケース一つでこの街にやってきた。
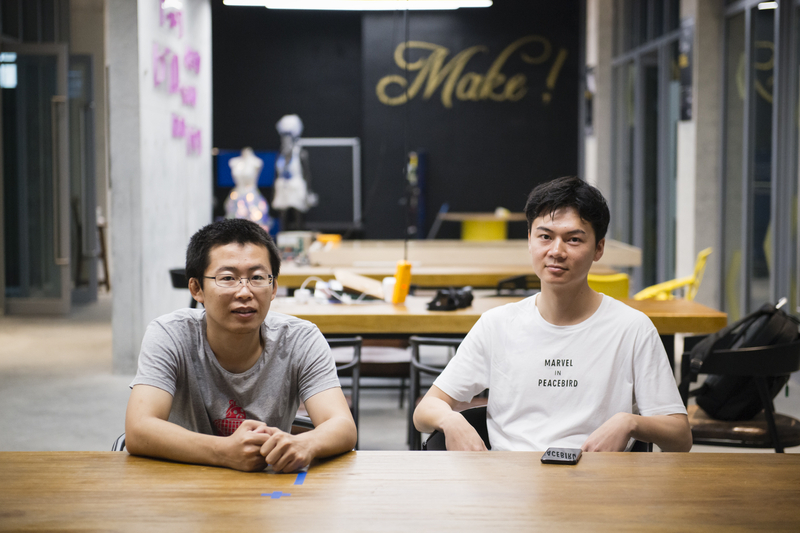
荒井さんと一緒に起業した塩入孔章さん(35)も、深センの“熱”に魅入られたという。
「深センが面白いから見に行こうと誘われて、旅行したんです。そうしたら確かに活気があってすごいなと思いました。一回住んでみようと思って留学したんですが、留学した翌月には荒井さんと出会って、気づいたら起業することになってました」
荒井さんと塩入さん、それに中国人の胡さんの3人で深セン市丑角科技有限公司が創設された。起業当初は独自のハードウェア開発にチャレンジしたが、想像以上の厳しさに直面したという。
「ハードウェアの開発はお金も時間も必要で、ハードルが高いな、と。しかも深センにはその方面が得意な人材がごろごろしているわけで、彼らに勝つのは簡単じゃないとわかりました」
そこでハードウェアからは一時撤退。深セン視察ツアーのアテンドやイベント開催の協力、工場探しなど「できることはなんでも引き受ける」方針に転換したという。まずは経験を積み、その中から次のチャンスを見つけたいという。今、次の勝負の場として狙っているのは日中人材のマッチングサイト。アテンドなどで得た人脈を生かし、日中の架け橋となるビジネスを構想している。
包摂力、他の中国都市にはない深センの魅力
成功を目指す若者たちを受け入れる深セン。ただ活気があるだけではなく、他の中国の都市にはない包容力もあるという。「この街は外地人に優しい」と流暢な日本語で話したのは阿徳さん(41)だ。内モンゴル自治区の出身。日本の千葉大学で人間工学を学び、会社勤めも経験するなど、日本滞在歴は17年間に及ぶ。2014年に日本を離れ、深センでの起業を決意した。人間工学を生かしたデザイナーになるとの夢を実現するためだった。

「深セン市の起業ブームを聞いてですね、夢を実現しようとこの街に来ました」
ただしさまざまなトラブルが続いた。阿徳さんの武器とも言える人間工学は中国での知名度が低く、企業からはあまり興味を持たれなかった。ならば自分で人間工学に基づいた製品を開発しようと考えたが、最初の製品である「薬の飲み忘れ防止タイマー」は基盤の試作まで進めたにもかかわらず、量産までいたらなかったのだという。
「処方薬の袋に貼っておくタイマーで、薬を飲むタイミングになると教えてくれるという製品でした。アイディアは良かったと思うんですが、バッテリーがネックとなりました。せめて数カ月は電池が持たないと製品としては使いものになりませんから」
こうしてアイディアはボツに。基盤の試作料も無駄になってしまった。とはいえ、基盤の設計に支払った料金は1万4000元(約23万円)。低予算で気軽にアイディアを試せるという深センの魅力もわかった。
次に手がけたのがお昼寝枕の「O-Pillow」。この枕は中国、日本でのクラウドファンディングに成功するなど一定の成果を収めた。くまモン・モデルを出すなど、バリエーションもそろえている。

まだ大きな利益が出るような段階ではないというが、「年間の売り上げ15万個を目指します」と阿徳さんの目標は高い。たんに枕を売るだけではなく、この製品を通じて人間工学の価値を中国に広めるのが最終目標だ。
来たら誰でも深セン人、包摂力が街の魅力に
内モンゴル自治区出身の阿徳さんにとって、深センは日本以上に遠い場所だ。だがそれでも住みやすさを感じるという。
「中国には本地人、外地人という言葉があります。本地人とは先祖代々この街に住んでいる人のことです。中国では地域主義が強いので、別の場所から来た外地人が街になじんで、ビジネスをするのは大変なんです。でも、深センは違う。歴史がない街ですから、本地人がほとんど存在しないんです」
深センの人口は現在1250万人。40年前に深セン市が創設される前の人口は約30万人だったという。つまり今住んでいる人々はほとんどが外から来た人々だ。
「老北京(北京の本地人)、老上海(上海の本地人)という言葉があります。江戸っ子みたいなものですね。でも老深セン(深センの本地人)はいませんね。逆に「来了就是深セン人」(来たら誰でも深セン人)という言葉があるほど。外地人でも外国人でも、引け目を感じることなく住める街なんです」
外から働きに来た人々。その多くは老いたら地元に帰っていく。その繰り返しが続くため、街は若さを保っている。平均年齢は32.5歳。高齢化が進む中国だが、深センはその若さを保ち続けている。
深セン住みの深セン知らず
多くの中国人、外国人が夢を追って集まる深セン。だが、日本人の動きは鈍い。在広州日本国総領事館によると、深セン市に住む日本人は1万9244人(2016年10月)と決して少ない数ではないが、その多くが日本企業の駐在員や家族だ。
「いまだに古い深センのまま生きている人たちが多いのです。本社から与えられた仕事を、下請けに投げてこなすだけ。中国語も話せないし、中国人との付き合いがないので、深センの変化にも気づいていない。深セン住みの深セン知らず、ですよ」

深センでEMS(電子機器受託製造)企業を経営する藤岡淳一さんは嘆いた。この街に住んでいながらも、昔ながらの「アジアで働く」のままでいる日本人のほうが大多数なのだという。
キャリアを積んだ日本人ビジネスマンに中国企業は敬遠される。ならば、若き日本人が夢を追って深センに飛び込むことはできるのだろうか。仕事を未経験の若者でも言葉さえ身に付ければ十分戦力になると、藤岡さんは言う。
「死ぬ気で勉強すれば、1年もあれば使える中国語は身に付きます。日本の大学を出た人が中国に留学して言葉を覚えたら即戦力だと思いますよ。ただね、最初の給料は安い。日本は初任給からある程度もらえますけど、中国の給料は市場原理ですからね、ペーペーの給料はひたすら安いんです。それでもいい、修行させてくださいという野心ある子は雇ってあげたいんだけど、そういう子ってすぐに独立しちゃうんですよね。かといって、まったく野心がない子は使えないし。経営者の立場からすると、ちょうどいい塩梅の若者がなかなかいないですね」
新卒で正社員になれば、一定以上の暮らしが約束されている日本社会。市場原理むき出しの中国は違う。高度な専門技術を持っていれば別だが、普通の新人は安く買いたたかれる。その代わり経験を積めば給料は一気に上がる。取材中、ある企業の賃金体系を聞いた。同社の新人社員の月給は初年度5000元(約8万5000円)だが、3年後には1万元(約17万円)と倍増するという。新人はごまんといるため価値はないが、キャリアを積めば一気に価値が上がるというわけだ。

深センには激しい競争が待ち構えている。その勢いは魅力的だが、反面リスクがあることも事実だ。「それでもぜひ日本人に来て欲しい」と阿徳さんは語る。「生き馬の目を抜く中国社会ではみんなトゲトゲしているというか、常に隙を見せないような緊張感で生きているんです。日本人ならではの温和な感性や協調性は武器になると思いますよ。もちろんリスクはあります。でも深センは南国ですから凍死する心配はないし、お腹が減ってもそこらに果物がなっていますから」と笑った。
厳しい競争社会で成功は約束されていない。それでも飛び込む勇気が持てるかどうかがカギとなる。
*本稿と同様のテーマで記事「猛スピードで変わる巨大都市――中国「深セン」に賭ける日本人たち」(Yahoo!ニュース特集)を発表した。ご興味を持たれた方はぜひそちらもご覧ください。










