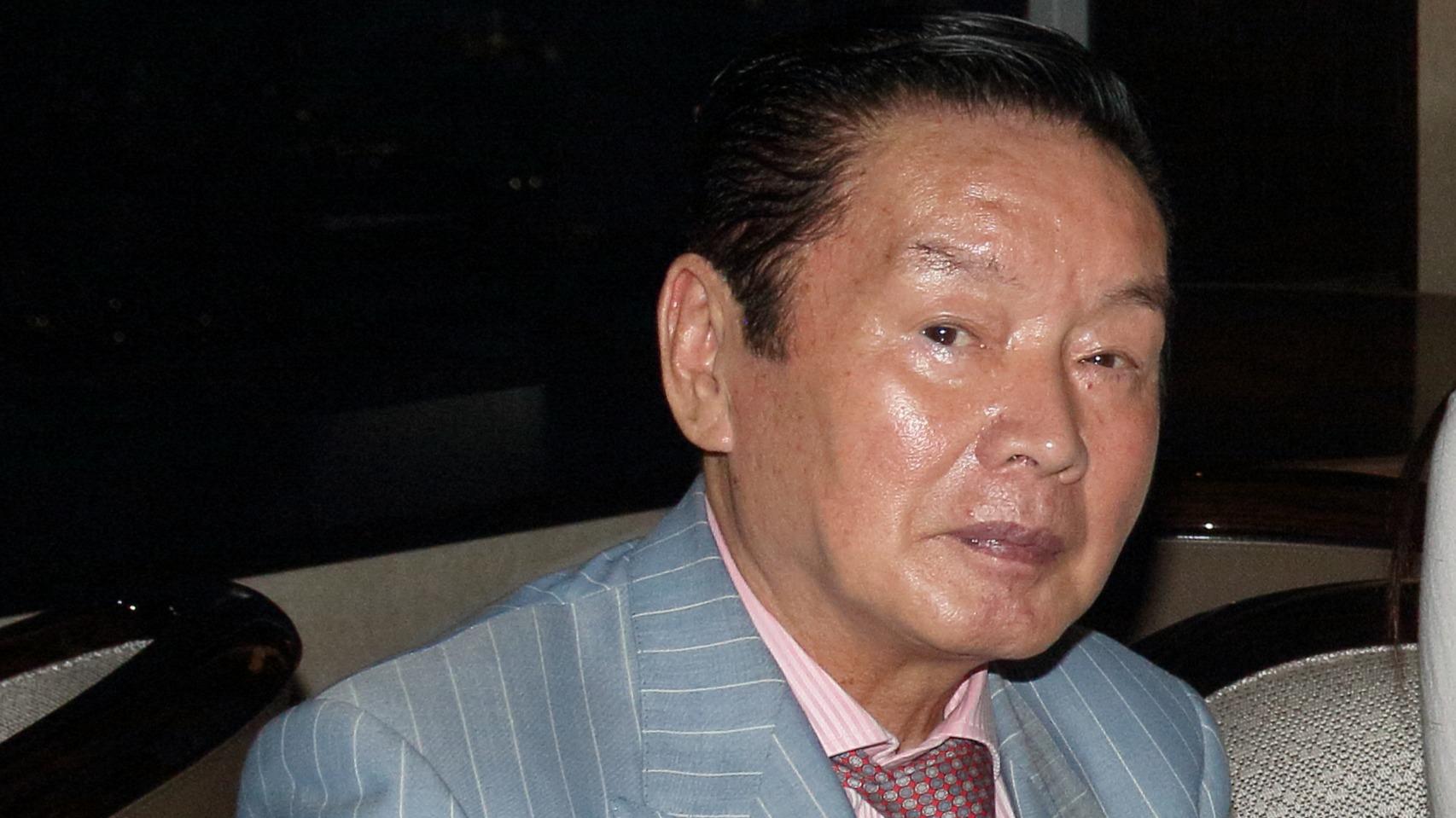原発の街、富岡町の相続税の倍率の特徴と、街を歩いてみて感じた課題とは? #知り続ける

■はじめに
今年も3.11が来ます。
「Yahoo!ニュース個人」編集部さんでは、「これからも、できること」とのテーマで課題を伝えることで、復興支援、風化防止、防災啓発を目指しておられます。
たまたま、私個人も、昨年3月に原発のある福島県富岡町で不動産鑑定をしたことがあり、立会をいただいたお客様に「せっかくだから」と鑑定業務と無関係な範囲で色々と復興の現場をご案内いただきました。
また、土地に課せられる固定資産税の路線価や相続税の分析についても、通常の都市では見られない特徴的な動きがあります。
前回の記事では固定資産税路線価の爆上がりから感じたことを述べましたが、今回は「Yahoo!ニュース個人」編集部さんの方向性に賛同しつつ、土地の相続税評価から感じた課題について述べたいと思います。
※前回の記事はこちら。
https://news.yahoo.co.jp/byline/tomitaken/20220310-00285171
なお、写真はすべて筆者が令和3年3月3~4日に撮影したものです。
■地方の過疎地では、土地の固定資産評価額が相続税にも影響する。
主要都市の中心部で、土地をお持ちの方が亡くなった場合、原則として「国税庁の提示する相続税路線価に基づき『市場価格とは異なる相続税計算用の土地の便宜的な価値』を算定し、これに基づき相続税を課す」こととなります。
しかし、相続税路線価は過疎地では定められていません。このような場合、原則として、「毎年、市町村が定めるその土地の固定資産税評価額」に、「国税庁が予め定める倍率」を乗じて「相続税計算用の土地の便宜的な価値」を算定することとなります。
この評価方式を倍率方式というのですが、この倍率は、宅地の場合は通常は1.0~1.3倍程度であることが一般的です。
実際、固定資産税路線価が爆上がりした富岡町中央も、固定資産税路線価が爆上がりする前は1.3倍でした。
ところが、固定資産税路線価が爆上がりした令和3年(例えば、地価公示地「福島富岡5-1」の固定資産税路線価は令和2年に比べて令和3年は1.68倍となった)は、0.8倍となっています。
筆者も数多く、過疎地の案件を不動産鑑定や税務で見てきていますが、倍率が0.8というケースは記憶にありません。
その背景を察すると、令和2年の固定資産税評価額を1とすれば相続税評価額は1.3となっていたところ、令和3年の固定資産税評価額は1.68になっていますから、そのまま1.3倍にすると2.184となり、相続税評価額も爆上がりします。
これはさすがに・・・ということで、1.68×0.8→1.344と、令和3年度の相続税評価額を令和2年から微増程度に調整したものと考えられます。つまり、0.8倍とした意図は、相続税評価の局面において令和2年の1.3から令和3年の1.344と「微増」程度に抑え、急激な相続税上昇を避けた点にあると思われます。
■0.8という数字から感じる税務署の忖度
本来、相続税路線価や固定資産税路線価は「土地に課せられる相続税課税価格算定用の、便宜的な目線」であり、「純粋な市場の適正時価」とは異なります。
ただし、目安として「相続税評価額の目線」は「市場価格(公示価格)」の8割との建前とはされています。全国的に見れば公示価格自体が相場と乖離していることも多々ありますので、実際はともかくとしての話ですが。
細かいことを言いますと、固定資産税路線価そのものが「市場価格(公示価格)」の7割とされるので、更にそこから8割とすると7割×8割は5.6割となりますから、他の土地が8割との点を勘案すると、本当のことを言えば課税の公平の観点からは疑問が残らないでもないのです。
ただし、富岡町の特殊事情は十分に配慮すべきとの点も理解はできます。
固定資産税等を課す富岡町は実態に合わせて固定資産税路線価を上昇させた一方で、富岡町を管轄する相馬税務署は特殊事情に配慮し、相続税に一定の配慮をしている様を感じ取れます。

■実際、街を歩いてみた感想
筆者も、富岡町の実際の土地の価値はどの程度なのだろうとの点も意識をしつつ、実際に歩いてみました。
あくまでも個人的な感想ですが、令和3年3月時点で以下の点を感じました。
- 筆者が歩いたのは日中であるが、道路では自動車に乗っている人以外の人をほとんど見かけない。
- 中には古い建物もあるが、通常の「地価水準が高くても30,000円・平米台」の街と比較して上記の写真の通り、新しい建物がやたらに目立つ印象である。
- 一応は中心部にモールがあるが、町の中心部にもあまり店舗が見られず、あっても銀行とかである。コンビニも国道6号線沿い以外に見られない。
- 気軽に入れるレストランや居酒屋的なものも見かけなかった。
復興の進捗と同時に、これに連動する固定資産税路線価は上昇し、倍率方式とはいえ相続税評価額も倍率で調整こそされているものの概ね微増程度とは思われます。
ただ、その背景は前回の記事で書いた通り、除染や復興等の不動産需要に起因するとのことです。
通常の街との比較で、下記の問題点があるように感じます。
- 街全体に漂うどこか無機質な空気を感じる。避難等の影響かと思われるが、昔からの繋がりが希薄になっているからと推察される。
- つまるところ、復興関連が街を支えている。では、「復興が終わったら」この街はどうなるのであろう。

復興の現場は、現状、復興の現場以上でも以下でもないのが実態と感じています。
個人的な意見ですが、復興の現場であるため、地価や固定資産税路線価等の上昇に見合う「賑わい」の上昇がないと感じています。
それはそうでしょう。復興それ自体は進捗していても、復興関連のものしか進捗がないため、居酒屋や気軽に入れるレストラン等の復活が見られないのですから。
大都市から遠く採算性にも疑問があるなどの理由で、難しい面があるのは理解します。
その一方で、震災の爪痕を残す街に、10年以上経過して求められる要素の一つには、各種のイベントや飲食店舗等に基づく賑わいではないか…とも感じています。
「賑わい」を戻したり、提供することも復興の支援ではないか…と感じていますが、いかがでしょうか。