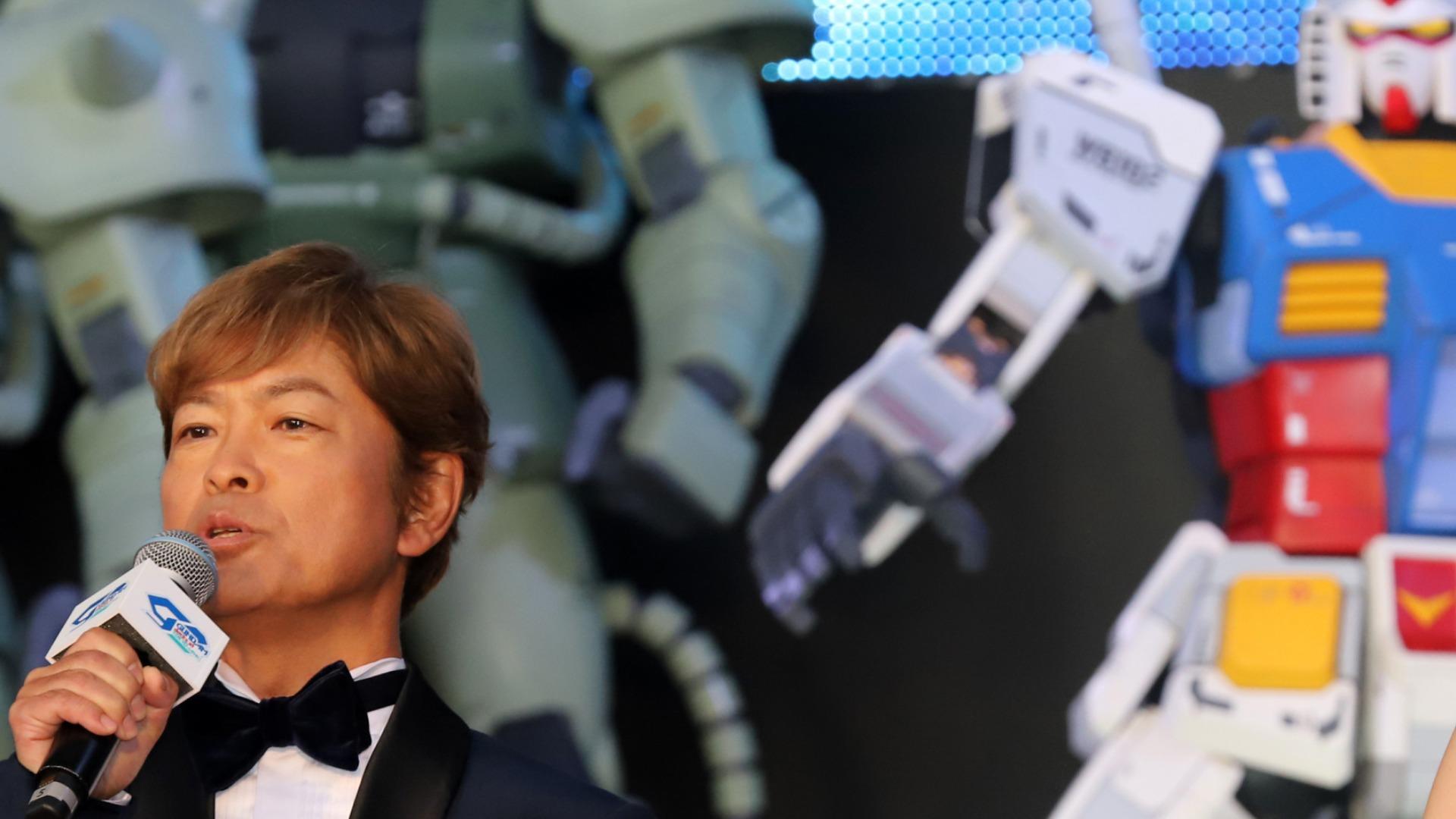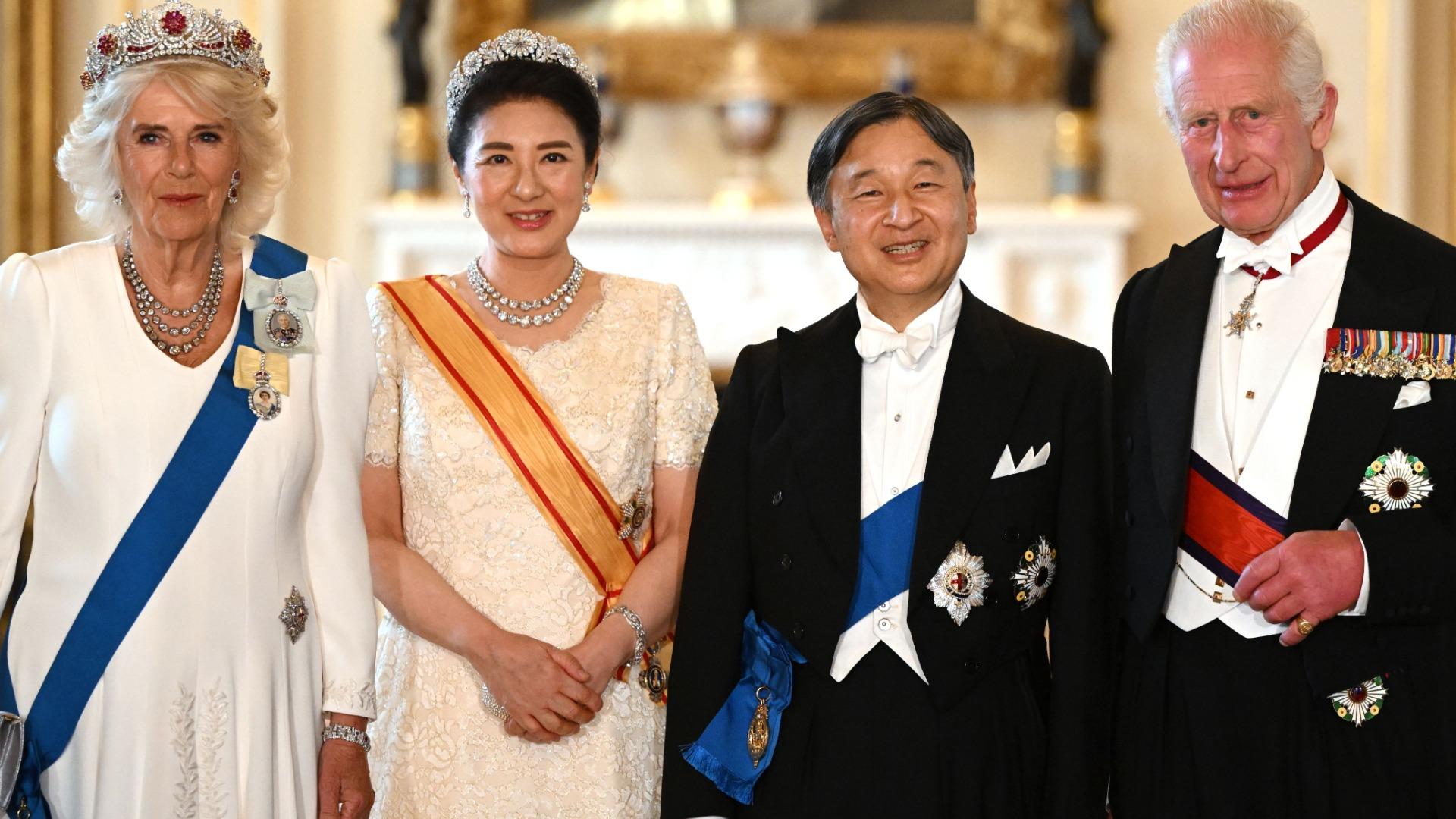日銀によるイールドカーブ・コントロールとは何だったのか

日銀は2016年9月21日の金融政策決定会合において、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」と名付けられた金融政策の新しい枠組みの導入を決めた。これは長短金利の操作を行う「イールドカーブ・コントロール」と消費者物価上昇率の実績値が安定的に2%を超えるまで資金供給拡大を継続する「オーバーシュート型コミットメント」が柱となった。
イールドカーブ・コントロールとは、短期金利と長期金利にそれぞれ目標値を設定し、その目標値に誘導するものとなる。イールドカーブとは、短期の金利と長い期間の金利を結んだ曲線のこと。金利のなかで中心的な役割を果たしているものとして、短期金利は日銀の政策金利となり、長期金利は通常、10年国債の金利となっている。
2016年の1月に決定した日銀のマイナス金利政策は、金融機関のトップからも批判が出るなど評判が良くないものとっていた。これは利ざやの縮小による金融機関への収益への悪影響が懸念されたためである。これを解消する手段としてイールドカーブのスティープ化が意識されたものと思われる。
日銀が何故にこれまで「なるべく市場メカニズムに委ねることが望ましい」としてきた長期金利を「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」によって金融政策の目標に据えたのか。
これにはいろいろと複雑な要因が絡んでいたと思われる。
これまで日銀は大胆な国債買入などにより量の拡大で、人々の物価予想に影響を与えて、物価目標を達成しようとした。しかし、9月21日に発表された「総括的な検証」で示されたように原油安など外部要因によって目標が達成できなかったとした。しかし、現実には金融政策の量によって物価を動かすことにそもそも無理があった。
その量についても限界が見えてきた。金融機関の保有国債を引きはがして日銀が買い入れるにも限界がある。そこで取った手段がマイナス金利政策であったが、その年に長期金利までもがマイナスとなってしまい、国債での資金運用が難しくなった。日銀の金融政策に対する金融機関からの批判的な声が強まった。さらに危惧されたのは国債の流動性の低下であった。これらを解消するために取られた手段が今回の長期金利を政策目標に据えることであったと思われる。
この一番の目的は日銀の金融政策の目標を「量」から「金利」に変えることにあった。これにより、量、つまりマネタリーベース目標による制約を受けることがなくなり、国債の買い入れについて柔軟な対応が可能となった。さらに日銀が長期金利をも政策目標に置くとの思惑だけで長期金利を上昇させることとなり、それ以上に超長期と呼ばれる20年を超える国債の利回りが大きく上昇することとなった。
これは国内物価が低位で安定し、海外の特に欧米の長期金利も落ち着いていれば、操作が可能なようにもみえた。しかし、その前提が崩れると日本の長期金利にも当然、上昇圧力が加わることとなり、実際に市場で形成されるべき長期金利と、日銀が想定して抑え込む長期金利の目標値との乖離が生じることとなる。