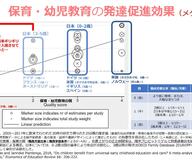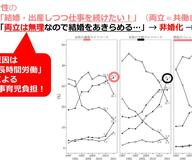自民党の「こども庁」、立憲民主党の「子ども省」について考えるための基本情報

「すべての子どもが安全に育ち、健康的に能力を発揮できる社会」へ
今年の衆院総選挙とも関連しながら、子ども支援政策を統括する新省庁として、自民党は「こども庁」を、立憲民主党は「子ども省」を検討しています。
新省庁については、コロナ対応で逼迫している子ども支援現場を混乱させないように、もし創設するとしてもコロナ流行の収束後にすべきと私は考えます。
他方で、子ども支援について、新省庁創設も選択肢の一つに入れて「積極的に議論する」ことそのものは、基本的に歓迎したいと思います。
新省庁創設の是非の議論では、新省庁の担う子ども支援政策が「すべての子どもが安全に育ち、健康的に能力を発揮できる社会」の実現にどう寄与するか、の検討が最も重要です。
それを前提に、本記事では、いくつかの基本的な情報を共有したいと思います。
「子ども支援」の内訳と支出規模は?
新省庁が統括することが期待される「子ども支援」(減税を除く)は、
「現物」給付としての
- 「就学前教育・保育(保育所・幼稚園・認定こども園等)」(2020年支出額の対GDP比:0.7%)
- 「ホームヘルプ・施設(児童福祉施設等)」(0.1%)
- 「その他の現物給付(児童相談所等)」(0.5%)
と、
「現金」給付としての
- 「家族手当(児童手当等)」(0.5%)
- 「出産・育児休業給付」(0.1%)
- 「その他の現金給付(給付型奨学金等)」(0.1%未満)
から構成されます(下図)。
(なお、新省庁がこれら以外の政策も担当する可能性もあります。)

子ども支援への公的支出は、いまだ先進諸国の「並み」レベル
日本では、コロナ禍以前から、子どもの自殺率が上昇していました (2010年から急増した10~14歳の自殺の動機は「家族関係・学業不振」が最多でした)。
また、少子化も加速していました(下図のように少子化の主要因は「20~34歳女性の非婚化」です。なお34歳以下非婚者の8割以上は結婚を望んでいます)。

このように子どもが生きづらく、家族形成がしづらくなってきたにもかかわらず、子ども支援への公的支出額は、いまだ先進諸国の「並み」レベルにとどまっています。
たとえば、2020年の公的支出額(減税分を除く)は、対GDP比で見ると1.9%で、2017年のスウェーデンの3.4%、フランスの2.9%に遠く及ばず、OECD平均の2.1%にさえ届いていないのが現状です。
逼迫する子ども支援現場(児童相談所や保育所など)の処遇改善・人手増員には、速やかな予算増額が必要です。
子ども支援の「予算」と「人員」を増やそう
こども庁創設を提唱した「Children First の子ども行政のあり方勉強会」の提言書では、「2040年までに対GDP比3%台半ばまで引き上げる」との旨の目標が書いてあります。
いずれにせよ、まずは、「新省庁創設によって、子ども支援の予算と人員が実際に増えるかどうか」が一つの重要な論点となるでしょう。
なお、予算増額のための財源としては、「国債発行」以外の方法も考えるならば、「資産税増税」が、国内経済へのダメージが最小という分析結果(※)があり、資産格差(=子ども世代の人生機会の不平等)の拡大を抑制する上でも、望ましいように思われます。
※:OECDシニアエコノミストJens Arnoldによる国際比較時系列分析によれば、増税(税収中立)による国内経済(一人当たりGDP)へのダメージは、「法人税>個人所得税・社会保険料>消費税>資産税」の順に小さくなると推定されました。つまり、国内経済へのダメージが最も小さかった増税は、「資産税」の増税でした。