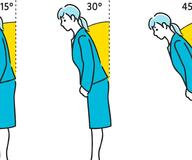「就職戦線」から「就活」へ:就活の大衆化と個人化

「就活」ということば
いま、就職活動に言及するとき、「就活」と略すことが多い。このことばがいつごろ生まれたのかは定かではない(おそらく「就職活動」とそう変らない時期にその略語として生まれたのだろう)が、メディアで多くみられるようになったのはそれほど古いことではない。
朝日新聞の記事データベースでみる限り、「就活」ということばが初めて登場するのは1999(平成11)年4月27日付記事「就職情報掲示板に川柳」で紹介されている投稿作品の川柳「空爆も就活もいつ終わるやら」だ。読売新聞では2001(平成13)年1月21日付大阪版「就職氷河期こそ結束 関西の大学生NGOがイベント開く」という記事で、学生による学生のための就職活動支援イベント「ナイスな就活2002」の紹介、毎日新聞だと2001(平成13)年2月22日付コラム「[憂楽帳]最近の若いモン」で、「「就活」(就職活動)」とわざわざ注釈をつけている。国会図書館収蔵書タイトルで検索するともう少し古く、1994(平成6)年刊行の『エラベル. 優良企業ガイド : 四国4県「就活データ集」 四国版』(東京商工リサーチ高松支社)が最も古いようだ。いずれにせよ、1990年代~2000年代初頭の時期である。
この時代は概ねバブル崩壊後の景気低迷期であり、特に90年代末は金融危機など、日本経済が危機的状況に陥った。就活の領域では「就職氷河期」と呼ばれた時代である。より頻繁に口にする機会ができたために「就活」と略されるようになったと考えれば、不景気で就職がより困難になっていく中で、就職のための「活動」がより重要になったことを反映したものであろう。
「就職」の歴史
これに対し、「就職」ということばの歴史は古い。記録に残るものとして最も古いのは、官吏登用に際して科挙が行われていた古代中国において、受験者が詩文の制作の模範とした詩文集『文選』に収録された、李密『陳情表』中の「臣具以表聞辭不就職」というくだりだ。これは267(泰始3)年、西晋の初代皇帝(武帝)となった司馬炎によって招聘された李密が、老いた祖母の世話をしたいとしてそれを断るために書かれたもので、いわば現存最古の内定辞退メールである。
とはいえ、日本で就職ということばが一般に使われるようになったのは明治以降だ。明治維新による政治体制の変化は社会に大きな変化をもたらしたが、その中の1つに人の地理的移動及び階層移動の増加がある。封建体制から中央集権体制への変化、及びその後の産業化の進展により、地方から東京を始めとする都市部への人の移動が進んだ。封建的な身分制が廃止されたことで、学歴の獲得によって社会階層の上位へと移動できる可能性が大きく開かれた。それまでの支配階級であり、主に世襲でその職が引き継がれた武士がなくなり、それに代わって高等教育を受け、試験を突破することが、官職にせよ企業人にせよ、社会のリーダー層となるために求められるようになったのである。「就職」ということばの普及はこうした変化を背景にもつものだった。
尾崎盛光(1967)『就職―商品としての学生』(中公新書)はこのような「就職」を、(i)単に雇われて給料をもらうだけのことではなくむしろ支配階級の一端にはいりこみやがて管理職・経営者のポストを得るための手段であること、(ii)潜在的支配階級としての身分を有するものがこの潜在的身分を顕在化するために名のある「地位」を手に入れることであると表現している。
実際、「就職」ということばが朝日新聞の紙面に初めて登場した1881(明治14)年7月10日付大阪版朝刊記事「官令 甲第四号」では、「府縣會規則第廿一條に拠り議員改選の上其就職交替の手續ハ豫じめ府縣會に於て議定せしめ府知事縣令認可の上施行致すべし此旨布達候事」として、府県会における改選による新議員の就任を「就職」と表記している。同様に、1885(明治18)年3月12日付大阪版記事「米国新大統領就職の節演説(支那人駆逐を述ぶ)」では、現在なら大統領「就任」と書くところを「就職」と書いている。
就職の「大衆化」
明治に始まった「就職」は、封建制社会の終わりとともに消滅した武士というエリート階層に代わるエリート選抜のしくみであり、生まれではなく能力によって活躍の機会を得ることができるという意味で、文明社会への一歩でもあった。同時にこの流れは、「就職」の主体が民間に拡大し、次第に大衆化していったことをも意味している。民間における新卒一括採用は1895(明治28)年の三菱(当時の日本郵船)や三井銀行などから始まったとされる。この時代は試験や学歴を基準とする選考より縁故採用が多かったという。採用試験が行われるようになったのは1910年代、第一次大戦が始まった後の好景気による採用難がきっかけであった。1918(大正7)年の大学令公布により、それまで官立の帝国大学に限られていた大学が公立、私立の設置も認められるようになり、大学生の数が急増したという事情もある。
しかし「就職」の時代は、ほどなく「就職難」の時代へと転ずる。第一次世界大戦終結後の1920年代に入ると戦争中の好景気の反動で戦後不況に見舞われ、その後1923(大正12)年の関東大震災でさらに打撃を受けた日本経済は、1927(昭和2)年に至って昭和金融恐慌、さらに1929(昭和4)年に始まった世界恐慌、1930(昭和5)年の金解禁による円高からくる輸出不振、1931(昭和6)年、1934(昭和9)年の凶作、1933(昭和8)年の昭和三陸津波など、内外のさまざまな困難に直面することとなり、就職難が社会問題となった。1929(昭和4)年の映画『大学は出たけれど』はこうした社会情勢を背景に作られた作品である。
1920年代から30年代にかけて悪化の一途をたどる就職難はやがて「就職戦線」ということばを生んだ。厳しい就職状況を戦場にたとえるもので、朝日新聞の記事では1931(昭和6)年3月2日の「刀折れ矢は尽きた 各大学就職戦線 昨年に比し半減、3分の1減 無残、打砕かるる若人」が初出のようだ。当時は世界恐慌の真っただ中にあり、それまで紙面に多く登場していた「就職難」を上回る厳しい状況を戦争になぞらえたものだろう。また、この記事の約半年後となる1931(昭和6)年9月には柳条湖事件をきっかけに満州事変が勃発するなど、当時の情勢を反映したものでもあった。以後このことばは就職を語る際の常套句となり、それは21世紀にまで続くこととなる。
個人化と自己責任化
Googleトレンドで検索動向をみると、就職を語る際に多く使われてきた「就職戦線」ということばは2010年ごろを境に次第に使われなくなり、90年代以降に登場した「就活」が代わりに使われるようになった(グラフ参照。この2つのことばの実際の検索数には大きなちがいがあるが、比較のためその最大検索数を100として描いている)。これはいうまでもなく、リーマンショックから東日本大震災という、日本経済にとって激動の時期にあたり、就活の領域では「第2氷河期」と呼ばれる時期にあたるが、この逆転にはどのような意味があるのだろうか。

就職を戦争にたとえる「就職戦線」は、そこに参加する学生たちを兵隊の集団のようにとらえ、大勢の学生が就職というひとつの「目的」に向かって一斉に取り組むという意味で一種の共同作業的に、あるいはある種のマクロな社会現象としてみているのに対し、「就活」において就職は、各自が独自の工夫と努力をもって取り組む個人としての「活動」であるという意味合いが濃い。実際、独立行政法人労働政策研究・研修機構の「高校・大学における未就職卒業者支援に関する調査」(2010)では、未就職卒業者の比率が30%以上と高い大学(43.1%)の方が10%未満とそうでない大学(29.5%)と比べて、調査時点の2~3年前より「就職活動への取り組み状況の個人差が大きくなった」と答えている 。
すなわち、「就職戦線」から「就活」への移行は、就職が社会の情勢を語ることばから、自己責任で取り組むべき活動をさすことばと考えられるようになっていく流れの中にあったとみることができる。「個人化」はまた「自己責任化」でもあり、全体の動向にかかわりなく、自らの就活への取り組みによって内定を複数獲得する勝者と1つも獲得できない敗者のどちらになるかが決まると考えられるようになったのである。
就活とメディアの発達
明治時代からの就活の変化の背景には、そこに用いられるメディアの発達と普及がある。こうしたメディアを仮に「就活メディア」と呼ぶことにしよう。その主要な機能は就活に関する情報提供、就職をかちとるための指南、そして自らに適した就職先とのマッチングである。
かつて個人間のネットワークを通じ、対面もしくは手紙などによって行われていた就活がより幅広い層に開かれていった時代はまた、マスメディアが本格的に発達する時代でもあった。明治初期に発刊された新聞にはその早い時期から人材採用広告が掲載され、官職などの採用試験が始まると試験情報を掲載した書籍が登場した。就職難の時代には就職をかちとるためのテクニックを解説した就活本が数多く出版され、戦後の高度成長期には就職情報誌が発刊された。個人的な縁故による採用や、大学からの紹介による採用は次第に自由応募方式にとってかわられ、1990年代以降はエントリーシート方式が普及した。
キャリア教育が大学でも行われるようになった現代と異なり、以前の大学において就活のための知識は自ら集めるしかなかった。就活の大衆化は、その際のマスメディアの活用を必然的に促したのだろう。とはいえこうした就活メディアの機能は概ね、就活に関する情報の伝達と、就職成就のための指南であり、実際に就活生がどの企業を選ぶかというマッチングの機能は本人の努力に委ねられていた。個人ごとにカスタマイズされた情報の発信はマスメディアには不得意だったからだ。
大きな変化が生じたのは1990年代後半以降だった。この時期以降普及が進んだインターネットは早くから就活の情報発信の場となったが、このことは情報流通における双方向性を劇的に高めるものであると同時に、個人別に最適化された情報をやりとりできる情報の多様化をも推し進めることとなった。就活においては、就活生が希望の条件を示して検索し、より幅広い選択肢の中から主体的に志望先企業を選ぶことができるようになったということだ。
さらに1997(平成9)年の職業安定法施行規則改正、及び1999(平成11)年の職業安定法改正で民間の有料職業紹介事業が原則自由化されたことにより、就活生に対して就職先の紹介を行うことができるようになった。こうした、就活生と企業のマッチングは、もう1つの就活メディアの重要な機能であり、これを備えたことで、現代の就活メディアはウェブを中心にさまざまなメディアを活用し、情報提供、指南、そしてマッチングの3つすべての機能を持つこととなった。現代の就活生はかつてないほどにこうした就活メディアのサービスに依存するようになり、よしあしは別として「お客様化」が進んでいる。
すなわち、就職氷河期に一般化した「就活」ということばは第2氷河期に至って「就職戦線」と入れ替わって就職を語る際の一般的な用語となったが、この変化の背景には、情報流通の多くがマスメディアからネットメディアにシフトしつつあるのと同様の変化が就活メディアにおいても起きたことがある。就活生はマスメディアを通じた限られた情報を受け取るだけの存在から、主体的に情報を検索し就活を行う存在となったことで就活は「個人化」し、必然的に「自己責任化」することとなった。それが就活サービスの高度化を促し、現代はそれらに強く依存する「お客様化」が進んでいる。技術と社会の変化に応じて変っていくメディアのあり方は、今後も就活のあり方を変えていくことになるだろう。