「食欲」が止まらない?それ食品に添加された「増粘剤」や「安定剤」のせいかも【最新論文】
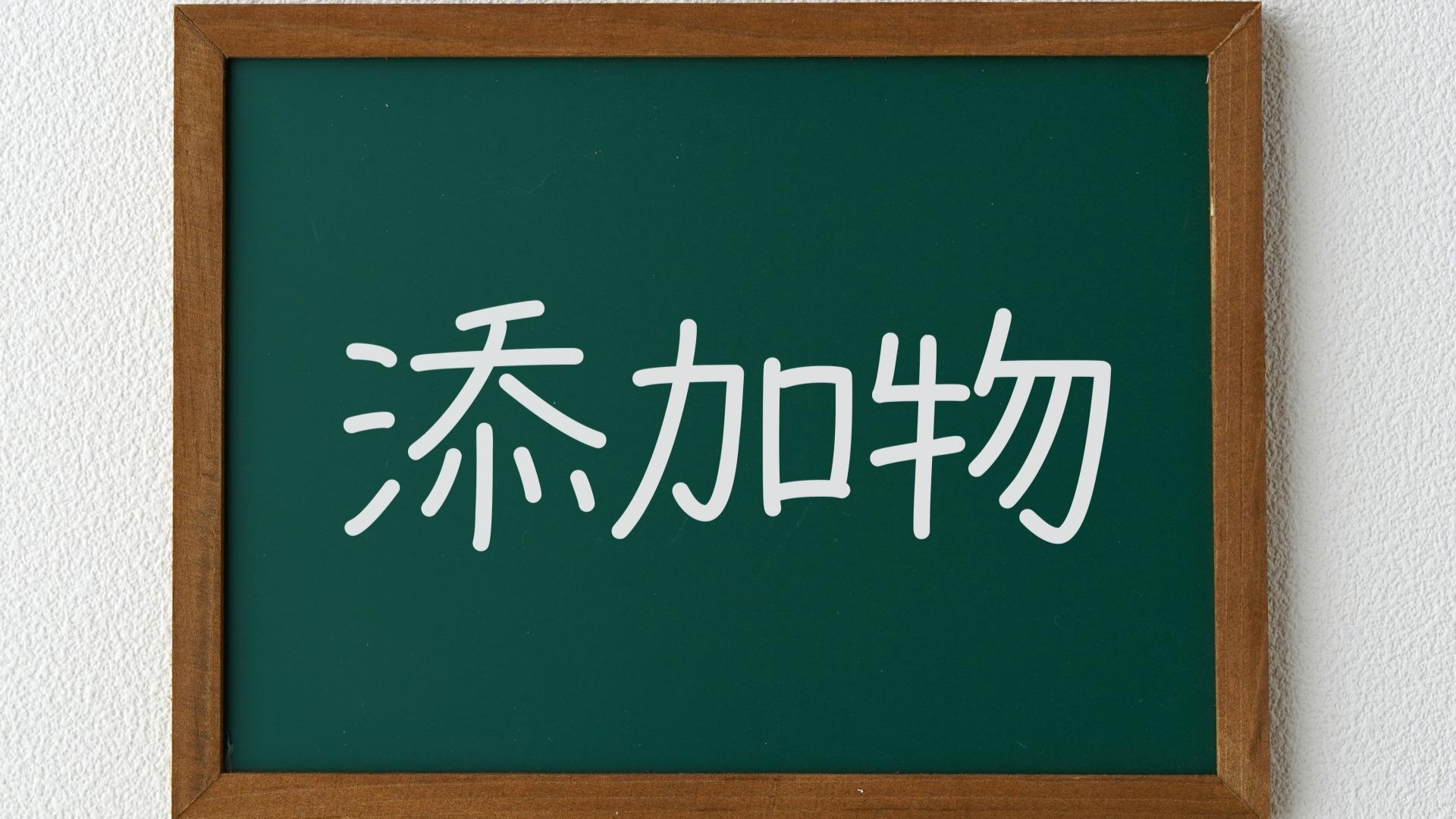
春も終わり、季節は夏へ。薄着に備えて体の線が気になり始める頃ではありませんか?
スタイリッシュな体の維持には適度な量の食事と十分な運動が大切。でも「食べ過ぎてしまう」。そんな悩みを抱えている方も多いでしょう。
意志が弱い?いやいや食品添加物、それもある種の「増粘剤」が、食欲にストップをかける邪魔をしているかもしれないのです。あくまでも「可能性」ですが、米国イリノイ大学のスミト・バタチャリヤ氏たちが明らかにしました。ネイチャーが発行する国際学術誌「栄養と糖尿病」に5月16日、掲載された論文をご紹介します [文末文献1] 。
増粘剤に広く使われている「カラギナン」が「満腹ホルモン」の分泌を抑制?
今回バタチャリヤ氏たちが実験した物質は、「カラギナン」と呼ばれる糖類です。
食品添加物としては「加工ユーケマ藻類(別名:ユーケマ)、精製カラギナン(別名:紅藻抽出物)、ユーケマ藻末(別名:ユーケマ)」という名称で書かれるのが原則ですが、「増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料、増粘多糖類」と表示されることもあるようです [福岡県薬剤師会] 。
この「カラギナン」を「腸」の細胞にかけると、細胞からの「満腹ホルモン」の分泌が減った——。これが今回バタチャリヤ氏たちが報告した事実です。
ただしこれはあくまでもシャーレの中の実験なので、実際にカラギナンを食べると「満腹ホルモン」分泌が減るかどうかは確認されていません。
しかしバタチャリヤ氏たちは、「カラギナン」をたくさん摂ると「満腹ホルモン」が出にくくなるため、なかなか満腹を感じず、ついつい食べ過ぎてしまう可能性があると、論文の中で推論しています。
ではこの「満腹ホルモン」とは何でしょう?最近ダイエット方面で話題の「GLP-1」です。
簡単に説明させてください。
お腹と頭に働きかけて「満腹」を感じさせる「GLP-1」
「GLP-1」は腸管から分泌されるホルモンです。食事が腸に届くと分泌され、さまざまな働きをします。そしてその1つが「満腹感増進」です。つまり「もう食べなくていいや」という気持ちにしてくれるのです。
その仕組みは2つ。
1つは「胃袋から腸への食べ物移動遅延」です。
そうすると胃袋に食べ物が溜まりやすくなるので当然、満腹感を感じやすくなります。
もう1つは「脳満腹中枢の直接刺激」だと言われています。「もう十分な食事が届きましたよ」と腸から脳に連絡するわけです。
この2つの仕組みで「GLP-1」は「食べ過ぎ」を抑えると考えられています。その結果、最近では「痩せホルモン」などとも呼ばれるようになりました。
さきにご説明した通り、「カラギナン」は「GLP-1」分泌を抑制します。ですから「GLP-1による食べ過ぎ抑制」が作動しなくなる可能性があります。食べ過ぎでしまうかもしれない、ということです。
「カラギナン」が使われている可能性の高い食品は?
というわけで「食欲が収まらないな」とお悩みの方は、ダメもとでカラナギンを取り過ぎていないか気をつけてみてはいかがでしょう?専門商社さんによれば、以下の加工食品ではカラナギンが使われている可能性が高いということです。
デザートゼリー
プリン
タレ、ソース、ケチャップ
ココア飲料
アイスクリーム
ハム、ソーセージ
これらの食品を購入する時は「食品表示」をよく見て、「ユーケマ」や「カラギナン」などが添加されていないか、さらにそれらが材料となっている増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料、増粘多糖類の添加も確認した方が良いかもしれません。
先述の通り、あなたの体には「食べ過ぎないためのシステム」がきちんとインストールされています。そのシステムを阻害する要因さえ取り除けば、食べ過ぎなくなるはず。自分の体を信じて、少しだけ食べるものに気をつけませんか?
最後に
いかがでしたか?身近にある思いもかけない食品添加物が、あなたの食欲コントロールを妨げている「可能性」をご紹介しました(誤解なきようもう一度書きますが、増粘剤を食べると食欲抑制が効かなくなると直接示されたわけではありません)。
加工食品を買うときに少し注意するだけで、「痩せホルモン」の分泌を増やせるかもしれません。高いお金を出して「GLP-1ダイエット」に走る前に、ぜひ、試してみてください。
食事については次のような論文紹介記事も書いています。こちらもぜひ、ご覧ください。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた!
今回ご紹介した論文
【注意】本記事は医学論文の紹介です。研究結果の文責は「論文筆者」にあります。また論文の解釈は論者により異なる場合もあります。さらにこの論文の内容を否定する論文が存在する可能性もゼロではありません。あくまでも「参考」としてご覧ください。










