Huaweiの任正非とアリババの馬雲の運命:中共一党支配下で生き残る術は?
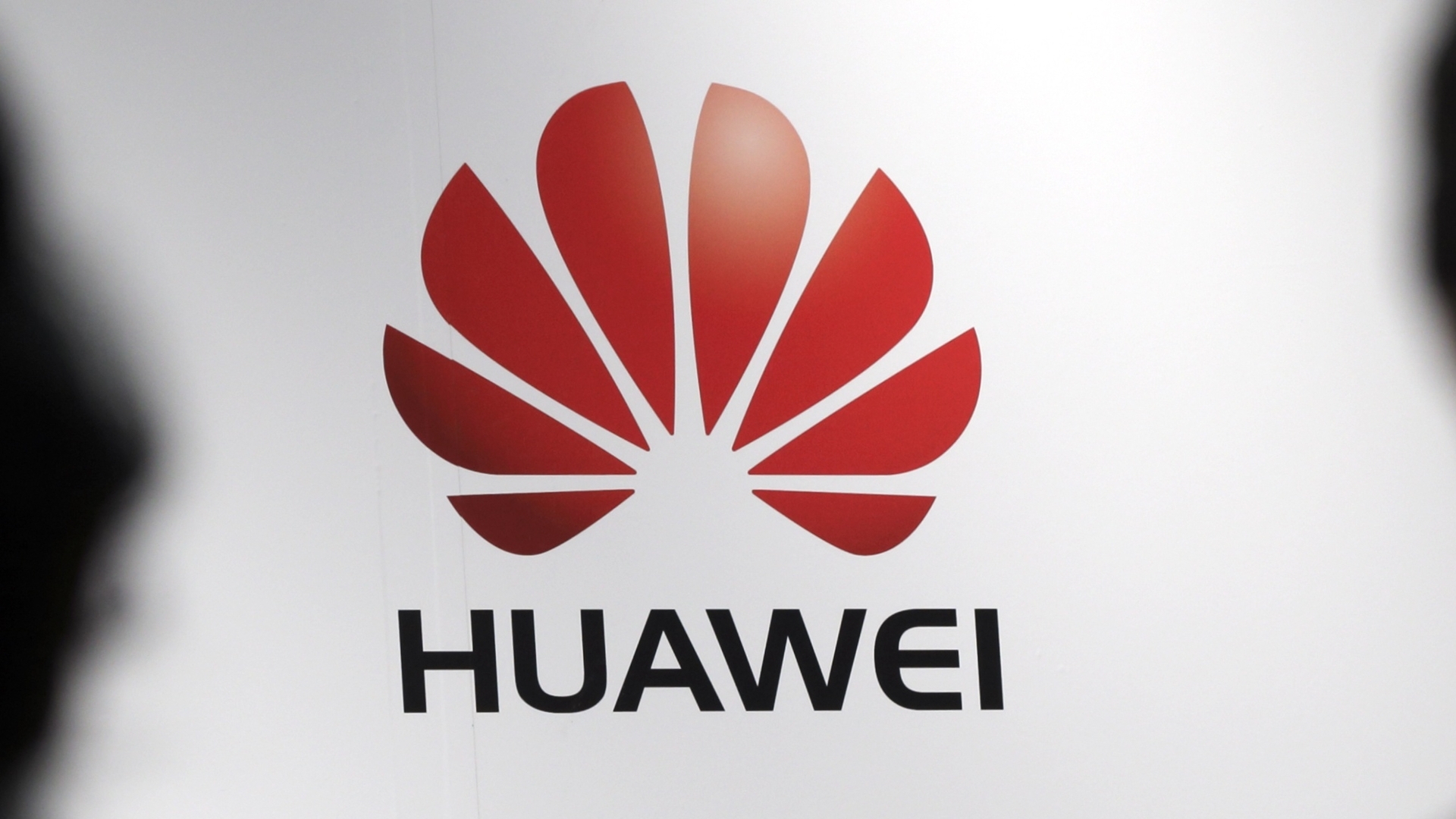
民間企業Huaweiが追い込まれている運命は、アリババの馬雲の突然引退宣言と共通している。Huawei叩きを喜んでいるのは、実は習近平だ。それが見えないと中共一党支配体制の怖さは見えてこない。
◆アリババの馬雲とHuaweiの任正非との共通点と違い:「民進国退」か「国進民退」か
昨年12月30日付けのコラム「Huawei総裁はなぜ100人リストから排除されたのか?」では、Huaweiの創業者である任正非がなぜ表彰者100人リストから削除されたのかを、「中国政府との近さ」の違いに基づいて分析した。
今回は、もう少し違った角度から斬り込みたい。
アリババの創業者、馬雲(ジャック・マー)が昨年9月10日に引退表明を正式にしたことは世界の注目を集めた。なぜなのか、その理由に関しても多くの見解が出されていたように思う。
ひとことで言えば、「民間企業として成功し過ぎたから」だ。
一党支配体制を貫く中国は、改革開放に当たって「民進国退」(民間企業が前進し、国有企業が控え目になり後退する)をスローガンに掲げながら、結局はその逆の「国進民退」を実行している。
しかし人民は国有企業の製品を購入せず、民間企業の製品を購入する。一つには人民の税金の上に胡坐をかき、のうのうと生きている国有企業の物など買いたくないからだ。もう一つの理由は、国有企業は即ち中国政府そのものなのだから、中国政府が崩壊しない限り倒産しない。そのため国有企業の従業員は庶民のニーズに必死で合わせてイノベーションを展開しようと死にもの狂いにならなくとも企業が倒産することはないと、高(たか)をくくっているから良い製品が生まれて来ないからだ。
対して民間企業は生き残りをかけて、必死で庶民のニーズを探り当て、その中から「これは成功しそうだ」という方策を練り出して売り出していく。ニーズの調査に余念がないので、当然商売繁盛につながっていくわけだ。
こうして馬雲は次から次へとヒットを飛ばし、アリババはe-コマース(電子商取引)において未曽有の成功を収めた。結果、「インターネット+(プラス)」戦略を進める中国政府を喜ばせたはずだが、そこが一党支配体制のややこしいところ。
政府や党を凌ぐほどの成功を収めてはならないのである。
浙江省にいたときから習近平と仲良くやってきたはずの馬雲でさえ、「身の危険」を感じ始めたのだろう。身を引いたので、100人リストには残った。
中国の大手IT企業テンセントの馬化騰CEOも100人リストに残り表彰されているが、彼も大きな犠牲を払って、習近平政権の方針に屈服している。昨年8月にテンセントは当局の命令によりWeGame「モンスタハンター・ワールド」の販売を停止されたのだ。直後の8月30日、教育部など8つの中央行政省庁は「児童青少年の近視を防ぐ実施法案」なる通知を発布し、国家新聞出版署がオンラインゲームの新作やゲーム全体の本数を規制することとなった。
拙著『中国動漫新人類 日本の漫画とアニメが中国を動かす』(2008年)で詳述したように、1980年以降生まれの若者、いわゆる「80后(バーリンホウ)」で日本のアニメや漫画を見ずに育った者はいないと言っていいほど、日本の動漫(アニメと漫画)が中国を席巻していた。中国政府は中国の青少年が「民主や自由」といった日本の精神文化に染まることを恐れ、同じく国家新聞出版総署を使って日本のアニメの放映時間を制限した。
そんな中、ゲームに関してだけは中国産の作品が非常に栄えており、若者たちはテンセント・ワールドに夢中になったものだ。
中国製ならいいではないかと思うだろうが、テンセントは民間企業だ。民間企業が国有企業よりも歓迎されて繁昌すること自体が問題なのである。
今般、テンセントはおとなしく中国政府の規制に従い、販売停止を受け入れた。だからテンセントの馬化騰は100人リストに残って表彰された。
さて、問題はHuaweiの任正非だ。
習近平は「俺の言うことを聞いてハイシリコン社の半導体チップを外販し、中国政府に開放しろ」と迫っているが、任正非は応じていない。
そこで習近平はHuaweiの孟晩舟CFOがアメリカの要求によりカナダで逮捕されたのを「チャンス!」とばかりに受け止めて、Huaweiのために「中国政府として」カナダやアメリカに抗議している。こうすれば、いくらHuaweiでも、中国政府の軍門に下るだろうと計算しているのである。
昨年12月12日のコラム<華為Huaweiを米国に売ったのはZTEか?――中国ハイテク「30年内紛」>で、もしかしたら、孟晩舟をアメリカに売ったのは、Huaweiを苛め抜いてきた国有企業ZTEではないかと書いたが、これはかなりの現実性を持っていることになる。
これを機会に、習近平は任正非をねじ伏せて、屈服させようとしている。民間企業が国有企業を凌ぐということは、一党支配体制ではあってはならないし、習近平にとっては非常に怖い。人民の方が強いことになるからだ。それは一党支配体制を脅かす。習近平が最も恐れているのは人民の声なのだから。
しかしHuaweiは「中国製造2025」の半導体領域におけるトップランナーだ。これを潰すわけにはいかない。それでもハイシリコン社製の半導体チップを外販させ、国有企業の方が優勢である状況を創りたいと、習近平は思っている。
その意味でアメリカのHuawei叩きは、習近平に絶好のチャンスを与えたということができる。
◆初めて現れたHuaweiの真相を語れる日本の中国研究者
1月17日のNews Socraで配信された「トランプ政権のファーウェイ叩きのパラドックス」を読んで驚いた。ここまで正しくHuaweiの真相を知っている中国研究者を発見したのは初めてのことだ。執筆者は元日本経済新聞論説委員兼編集委員で亜細亜大学教授の後藤康浩氏。
日本語なのでリンク先をご覧くださればお分かりいただける通り、後藤氏は冒頭で「米中経済戦争のなかで、トランプ政権から集中砲火を浴び、米国だけでなく日本を含む同盟国の市場から排除されつつある中国の通信機器メーカー、華為技術(ファーウェイ)についてほとんどの報道は先入観に支配され、本質を見誤っている。ファーウェイは中国企業のなかで共産党の支配を巧みに回避してきた民間企業の代表だからだ」と書いておられる。
その証拠の一つとして、『下一个倒下的会不会是華為(次に倒れるのはファーウェイか)』(リンクは筆者)(邦訳『冬は必ずやって来る』)という本を挙げている。
この本は「如何にして生き残るか」がテーマとなっており、言外に「どんなに中国政府に虐められても」を暗示している。後藤氏が書いている通り、「中国共産党に優遇されてきた国有企業なら絶対に出てくる言葉ではない」のである。後藤氏はHuaweiがどれだけ中国政府に冷遇されたかを述べ、最後に「今回の事件で中国政府・共産党は全力を挙げてファーウェイ擁護に乗り出しているが、それはこの機に乗じてファーウェイなど成功した民間企業への影響力を高めようとしているだけだ。国有企業優先の習政権にとって米国のファーウェイ叩きは民間企業支配の千載一遇のチャンスなのである」と結んでいる。
全くその通りで、拍手喝采を送りたい。
日本にこのような研究者がおられることを知らなかったことを恥じるとともに、ここまで正しく中国の真相を捉えておられる後藤氏に心からの敬意を表する。筆者が尊敬できる中国研究者が現れるということは滅多になく、こんなに嬉しいことはない。
後藤氏の分析が如何に正しいかを、客観的事実に基づいて証明するために、2009年8月17日に中国共産党の機関紙「人民日報」の電子版「人民網」に掲載された「中国金融60年大事記之1993年」をご紹介しよう。
このページの4月のところをご覧いただきたい。
国務院弁公庁は、国家体改委、国家経貿委、国務院証券委による「内部職工による持ち株制度という、規範に沿わないやり方を直ちに禁止することに関する意見」を発布したとある。
これこそが、<Huawei総裁はなぜ100人リストから排除されたのか?>に書いた、ZTEの内部告発によって中国政府がHuaweiを潰そうとした何よりの証拠なのである。
つまりHuaweiは中国政府に虐められ、潰されそうになりながらも「生き残ってきた」。それが本のタイトルに現れている。本を貫いている精神は「顧客第一主義」だ。
◆各国支社の状況に関して
一方、まったく正反対の視点かもしれないが、今年1月6日の深田萌絵という方が書かれた<遠藤誉氏の「このままHuaweiを排除すると日米にとって嫌な事態が:一刻も早く解明を」記事に異論(100)>という記事にも興味を持った。見解は筆者と異なるものの、彼女は非常に素直で、正直に自分の経験したことを書いておられる。人を反中か親中かなどで分けずに、事実で分けている。たとえば<遠藤誉著『毛沢東』日本軍と共謀した男(99)>では、事実だと分かれば、素直にその事実を認めている。その真っ直ぐさが気に入った。こういう人も多くない。
Huaweiの本社あるいは創設者の信念および中国政府との関係は上述した通りだが、170ヵ国もの支社を持っていれば、その末端では「産業スパイ」を行なっていないという保証はない。むしろ各国の支社が競争しているので、より大きな功績を上げるために「産業スパイ」はやっているだろうと筆者も思っている。そこに見解の乖離はない。
先般、ポーランドで逮捕された産業スパイとされるHuaweiの社員に関して、任正非は「本社とは関係がない」として直ちに解雇したようだが、なんと言っても逮捕された中国人は駐ポーランドの中国大使館に長年にわたり勤務していた人物だ。こういう人間が、170ヵ国の支社の中にはいくらでもいるだろう。それはHuaweiに潜伏してHuaweiを潰すために中国政府から派遣された(二重)スパイかもしれないという複雑な側面さえ持っている。
世界各国の支社の隅々まで、任正非も把握はできていないだろう。
だから、深田氏がHuawei日本支社の社員に騙されたというのも理解できる。
ただ、深田氏はQualcomm (クァルコム)とHuaweiとの関係をご存じないのではないか思う。できたら、昨年12月8日のコラム<Huaweiの頭脳ハイシリコンはクァルコムの愛弟子?>を読んでほしい。ハイシリコン社総裁の卒業大学(北京郵電大学)はクァルコムが特に力を入れて共同研究所を設立し、半導体技術を積極的に伝授した大学なのである。クァルコムのCEOは昨年まで、習近平の母校である清華大学経済管理学院顧問委員会のメンバーだった。習近平のお膝元にいた人物だ。
もう少し見識を深めて下さると、非常に優秀な分析者になるだろうと深田氏には期待している。










