「日本の生産性は先進7カ国で最下位!」に惑わされないために知っておきたいこと

昨年12月、日本生産性本部が「労働生産性の国際比較」の2017年版を発表しました。それによれば、日本は1990年代前半から、先進7カ国で最下位を更新し続けています。
このニュースを受けて、「日本の企業はムダが多い」とか、「もっと業務の効率化をしなければ」といった声が聞かれました。しかし、この国際比較の結果をもって「日本人の働き方は効率が悪い」と言うのは早計です。本記事では、この結果をどう受け止めればよいのか、そこから見いだせる個々の職場における生産性向上のヒントとは何かを解説します。
労働生産性の国際比較は、何を比較しているのか?
まず、今回発表された「労働生産性」は、どのような計算で出てくるのでしょうか? 日本生産性本部が計測しているのは、以下の2つの労働生産性です。
(1)1人当たり労働生産性=GDP/就業者数
(2)時間当たり労働生産性=GDP/総労働時間(就業者数×労働時間)
分かりやすくするために、国ではなくひとつのお店という単位で、このふたつの労働生産性について考えてみましょう。

(1)1人当たり労働生産性は、パートタイマーが増えると低くなる
例えば、常時スタッフがひとりで営業するコーヒースタンドがあるとして、同一人物がずっと働く場合と、何人かの人が交代で働く場合とでは、この店の1人当たり労働生産性は異なります(どちらのケースでも売上高は変わらず、時給の差もないものとします)。分母となる就業者数が少ない方が、労働生産性が高い、という結果になるのです。
今、日本では労働人口の減少に備え、子育て中の女性や高齢世代でも働きやすいしくみの整備が進められようとしています。実際、サービス業を中心に「1日1〜3時間」というような短時間の求人も増えています。結果としてパートタイム労働者が増え、以前はひとりでやっていた仕事量を複数の人でシェアするという方向にあります。これは1人当たり労働生産性を押し下げることになりますが、それが必ずしも悪いことだとは言えないでしょう。
(2)時間当たり労働生産性は、同じ仕事をしても売れなければ下がる
労働生産性の分子はGDPなので、同じ労働時間で得られる利益が大きいほど、時間当たり労働生産性が高くなります。先ほどのコーヒースタンドの例では、同じ時間内により多く、より利益の大きい商品を売る方が、時間当たり労働生産性が高いのです。
逆に、お客さんが来なくても必ずひとりの店員がいなければいけないコーヒースタンドの場合、景気が悪くなったりして売上が落ちたときは営業時間を短くしない限り、時間当たり労働生産性が落ちます(時給を下げることはしない前提で)。
モノを作れば売れた高度成長期と異なり、今は闇雲に仕事をしてもダメ。成果(=利益)につながる仕事をしなければ――、というのはこの時間当たり労働生産性を重視する考え方なのです。
効率よく働けば生産性ランキング上位国になれる、は間違い

発言しない人がたくさん出席する会議、たくさんの承認印を集めて回らなければいけない決裁書類など、読者の皆さんは「日本の働き方は無駄が多い」と感じる場面が多いことでしょう。でも、こういった“無駄”を省いていけば、生産性で上位の国になれるのか? そう簡単な話ではないことは、上の労働生産性の定義の説明からも、なんとなく感じられたのではないでしょうか。
ここでは、国際ランキングで上位の国がなぜ労働生産性が高いのか、その要因を考えてみます。
例えば、比較されている35カ国中、1人当たり労働生産性と時間当たり労働生産性の両方で1位に位置するのはアイルランドです。アイルランドの労働生産性は1980年代頃までは日本とさほど変わらない水準でしたが、近年になって急に浮上してきました。これは、極めて低い法人税率でグーグルやアップルといった国外の大企業を誘致し、その売上がアイルランドで計上されていることが大きいようです。
2位のルクセンブルクも、アイルランド同様に海外企業の誘致に成功していることなどに加え、労働人口が少ない小国で、隣国から国境を越えて働きに来る労働者が非常に多いという特徴があります。他国からの労働者は分母となる就労者にカウントされないため、それが労働生産性を押し上げるのです。
このような事情を知ると、アイルランドやルクセンブルクの人たちが効率よく働いているから労働生産性が高い、というわけではないことがよく分かるでしょう。
日本企業が目指すべき「生産性向上」とは
ここまでは国際比較における労働生産性の定義について解説しましたが、“生産性”そのものは、もっと色々な捉え方が可能な概念です。辞書を引けば、生産性とは「アウトプット(生産量)をインプット(資本や労働などの生産要素の投入量)で割った値」といった説明がされていますが、そのアウトプットを作りだす主体が誰かは決められていません。
国際比較の場合、問題になるのは国の生産性なので、アウトプットはGDPで考えるわけです。しかし、企業やひとつの部署にとっての生産性を考えるならば、アウトプットは売上や利益ということになるでしょう。また、個人にとっての生産性となると、仕事においては収入や業績、人生全体を考えれば、家族との時間や社会貢献活動などもアウトプットとして捉えて良いかもしれません。

今、人手不足が深刻な日本の企業が目指すべき「生産性向上」とは、従業員の労働時間を減らしつつ十分な利益を生む、という方向でしょう。単にコストと利益の関係だけで生産性向上を目指せば、従業員を低賃金で長時間労働させて使い潰してしまったり、「サービス残業」のような隠れたコストの存在を見落としてしまったりといった方向に進みかねません。従業員がスキルを上げつつ長く働ける組織を目指すならば、真の労働時間を計算に入れ、健康状態や生活の充実など社員個人にとっての生産性向上とも両立するような生産性向上を目指すべきでしょう。
ランキングに惑わされず、それぞれの職場単位での生産性向上を目指そう
今回は労働生産性の国際ランキングをあまり気にしても仕方ないということをお伝えしたかったわけですが、発表されているデータには企業にとって参考になるものもあります。それは、産業別の比較データです。
レポートには、産業別に主要先進7カ国の労働生産性の上昇率を比較したデータが掲載されています。それを見ると、製造業や情報通信業はリーマンショック以降、各国で右肩上がりの傾向であるのに対し、卸小売・飲食宿泊業や教育・社会福祉サービスは全体的に伸び率が低いなど、産業による差が大きいことが分かります。日本と他国を比較してみると、製造業の伸び率は他国と遜色ありません。情報通信業は、ドイツ、フランス、米国と比べると伸び率が低めです。
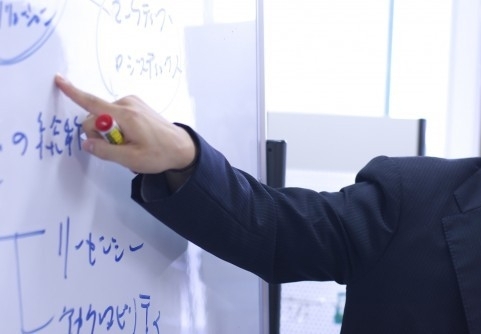
他国より時間当たり労働生産性が低い産業については、他国のビジネスモデルや業務プロセスを分析してみると、生産性向上につながるヒントが見えてくるかもしれません。
企業にとって重要なのは、それぞれの職場において生産性を上げるということです。他国や他企業との比較も参考にはなりますが、一番注目すべきなのは自分たちの職場における時系列での変化ではないでしょうか。いろいろな方法を試してみて、自分たちが目指す生産性向上が実現できたかを確かめながら次の施策を打つという、PDCAを続けていくことが、企業の体力強化につながるはずです。
(本記事は、2018年3月に『Work × IT』に掲載した内容を、一部編集の上で投稿しています)










