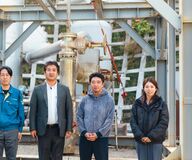「ガソリンスタンドも自分たちで」住民=株主という会社を立ち上げた過疎集落の挑戦

人口の減る地方から、民間企業は次々に撤退している。行政も市町村合併や財政悪化により、いつどういう形でサービスが低下するかわからない。今、小さな地区単位で、住民同士がつながり、生活をコンパクトに、かつ継続的に維持できるしくみが必要になっている。
全国でもそのしくみづくりの最先端をいくのが、高知県の梼原(ゆすはら)町だ。8割が中山間地の県下でも山奥の北部に位置する。
梼原ではこれまでにも、さまざまな新しい試みが行われてきた。自然エネルギーの導入、電柱を地中化した美しい町並み、小中一貫校の充実した教育制度など、この町独自の暮らしやすい環境や制度が充実している。隈研吾氏の設計による先進的な図書館が完成したのは2年前のことだ。ところが、同じ町内でもより山間部や、小さな集落では商店がなくなり、交通の便も悪く…と、生活は厳しい状況に置かれている。
そこで、今町がもっとも力を入れているのが、「小さな拠点」を基とした地域社会づくりである。
高知県独自の政策として始まった「集落活動センター」の取り組みを、町内の全6地区に率先して導入し、地区主体で事業を始めている。法人格を取得し、利益を生み出す団体も生まれ、地域のエンジンとして機能し始めている。
全国的に、人口そのものが減るこれから、都会であっても、行政サービスの行き届かない範囲が広がる可能性は高い。梼原で見てきたことをレポートしたい。

■地域住民が株主。ガソリンスタンドがなくなるなら自分たちで
ガソリンスタンドで立ち働く空岡則明さんは、次々に訪れるお客さん相手に忙しそうだった。電話もひっきりなしにかかってくる。「ちょい待っちょって。すぐ行くけん」「おう、給油やろ」、従業員に「入れてやって〜」と叫ぶ。
梼原町のなかでもっとも北に位置する人口499人の四万川(しまがわ)地区。このガソリンスタンド、じつは地区住民でつくられた地域法人で運営されている。空岡さんはこの株式会社四万川の代表であり、集落活動センター四万川推進委員会の会長、地区の区長も兼ねる。

「もともとあった民間のガソリンスタンドがね、数年前に廃業することになったんですよ。ガソリンスタンドがなくなったら困るでしょう、そら自分たちでやらにゃいかんと」
柔らかい物言いにはっきりした意思をにじませて、空岡さんは言った。
株式会社四万川は、住民175人が株主であり、地区が筆頭株主。ガソリンスタンドのみでなく、生活に必要な物資の販売、たばこの販売、葬祭事業など民間が撤退した事業や、配食サービスなどの福祉事業、生活に欠かせないサービスを提供している。民間のガソリンスタンド時代に比べて、地域法人になってから給油だけでも売上が3倍になったという。

「そりゃあ、1リットルでも外で入れればよそへお金が出ていくわけやから、ここ(地区内)で入れようってなるわね。みんなに自分たちの会社って意識を持ってもらうために、あえて株券を発行したんです。特に配当金が出るわけではないんだけども」
現在、雇用しているのは地区の若手従業員一人に、アルバイト一人。さらに町の「集落支援員」制度で助成を受けて働いてもらっている一人。空岡さん自身は、じつは地元の建設会社の役員でもある。朝晩この店に立ち、日中は本業である建設会社に勤めに出る。
■高知県独自の「集落活動センター」とは何か?
高知県が「集落活動センター」(以下、集活)と呼ばれる、中山間地域支援の事業を始めたのは2012年のことだ。集活とは、高知県独自の政策で、旧小学校単位ほどの地区ごとに必要な活動を住民主体で進める取り組み。県により初期投資として各所3000万円ほどが助成される。
2018年8月に高知県庁を訪れた際、中山間地域対策課の職員はこう話していた。
「集落活動センターの特徴は、地域ごとにやっていることがまったく違う、オーダーメイドという点にあります。国や県で決めた型に地区をはめるのではく、地域住民を主役として、集落の維持存続に必要な事業をそれぞれが計画して実行するまでをサポートしています(*1)」
確かに、各所の活動を見ると福祉をはじめ、特産品の販売や獣害対策など、事業内容はじつにさまざまである。
6年間で県内52ヵ所に開設され(2019年12月時点)、四万川地区のような生活支援や売上を上げる経営団体も出始めており、他県からの視察も絶えない。

梼原町はすぐに導入を決め、5年かけて全6地区に設置してきた。株式会社四万川も、集落活動センターとして始まった経営団体である。
■収益を原資として、地域内でまわす地域法人
集活の一つの大きな目的に「自走をめざす」という点がある。はじめの3〜4年は県や市町村からの初期費用や運営費が助成されるが、その後は自活しなければならない。
たとえば前述の四万川地区も、ガソリンスタンドを新設するのに7500万円近くの初期投資がかかっている。3000万円を集活の費用として県が助成し、3000万円を町が、残りを地区の積立金と地区住民による株主の出資でまかなった。梼原町では県の助成とは別に、年200万円の運営費を各センターに出しているが、四万川では設立5年目にして、そろそろ自走できる域に達している。
空岡さんはこう話す。
「投資してもらったからには売上を出して、地域に還元できてナンボ。そのために給油事業や物販だけじゃなく、色々やっています。せっかく地域法人ができたんやから、町の委託事業もよその業者に頼むんじゃなく、できるだけ地区内でやろうって、役場にも営業して。配食サービスを月に2回、年寄りの見守りも兼ねてやったり。
経営努力もします。たとえば配食でいうと、地元の年寄りからの注文だけではせいぜい20食程度。それでは利益が出んので、地元の企業やら社協に声かけて、60食分くらいの注文を取ってね。そしたらわずかやけどスタッフの時給も払えるわけです」

同じく梼原町の初瀬(はつせ)地区では、有志の女性グループが行っていた鷹取キムチの加工生産を、集活の設立を機に、大きく飛躍させた。高知の民間スーパー「サニーマート」と提携し、キムチの新商品やドレッシングも開発。
さらに、韓国料理レストランと韓国式サウナ「チムジルバン」をつくり、町外からの人の呼び込みにも成功しているという。

この施設へ足を運んでみて驚いた。道中は、どこまで続くのだろう…と思うような細い山中の一本道。町内でも人口128人ともっとも小さな地区である。けして立地がいいとは言えないこの場所に、平日の昼間から高知市内や県下のほか地域から女性客が次々と訪れる。サウナに入る人、韓国料理を満喫して帰る人。
韓国人から直に教わったという本格キムチは、確かにおいしかった。

季節によってバラつきはあるものの、利用者数は年間1200人程度、売上は、キムチなどの物販や町外での売上も合わせると、2017年度で約1126万円、2018年度1500万円と、年々伸びている。
ところが地域発で始まった事業だけに、難しい面もある。
たとえばキムチの製造は地元の女性数名でまわしているが、年齢が66歳から84歳。サニーマートとの取り組みが始まってすぐは、月に1000のキムチを手で生産しなければならず、身体的に負担も大きかった。

さらには味にこだわり、売値も上げたくない女性たちの思いから、原価率がきわめて高い。営利企業であれば、原価を下げるか、売値を上げるかするところだが、利益に走りすぎれば「何のためにやっているのか」わからなくなる。
働き手の幸福度を損ねずに儲けも出す。
この葛藤が、今後、地域法人の舵取りをする難しさになるのではないかと思えた。
■稼ぐだけではない、幸福度を追求した循環型社会のモデルに
しかし、さらに町内いくつかの地区を見せてもらっているうちに、集活の役割が稼ぐことだけではないとわかってくる。地域住民の生活支援、住民の生き甲斐、活力創出の面も大きい。
越知面(おちめん)地区では、高知新聞の販売店が廃止を決めた際、集活センターが委託販売先となり、住民自らが配達を行っている。早朝に届く新聞に、地域のスタッフの一人が広告を折り込み、別のスタッフが配達する。この事業については集活センターの取り分はゼロで、働いた人に利益の100%が還元される。
越知面区長で、NPO法人おちめんの理事長をつとめる上田未喜さんによれば、越知面ではこのほか、主に3つの事業が進んでいるという。一つは集落営農。一つは女性有志グループによる製菓・加工食の販売事業。そして三つめが廃校になった旧小学校を活用した宿泊事業である。
田畑の荒れは、高齢化の進む中山間地域の抱える課題の一つ。60〜70代はまだ力があっても、10年、20年先には田畑の管理が難しくなる。そうした未来を見据えて、住民同士で共同組織をもち支え合おうというしくみだ。

具体的には農作業を請け負う営農組織を立ち上げ、田植えや稲刈りなどの作業を有償で個人から請け負う。現在は作業代行のみで、まだ農産物の販売までに至っていないが、ゆくゆくはそうした営利活動を積極的に行うことを見込んでいる。宿泊事業は、梼原高校の野球部の対戦相手を招致するための合宿所として始まった。今では一般の宿泊客も増えている。

こうした集落の生活支援や外貨(町外からの収入)を稼ぐ事業とはまた違った役割を果たしているのが、女性グループ「チームシルク」。
ピザやシフォンケーキ、焼き肉のタレなどの加工品の製造販売と、週に一度土曜日にカフェ「くわの実」を営んでいる。シフォンケーキは店に卸す分もあるが、ピザなどは焼いたその日のうちに町内へ販売に出かけ、50〜60枚を売り切る。
シルク代表の瀬戸口登貴恵さんは、とても60代には見えない若々しい笑顔でこう話した。
「メンバーは7名、週1回の活動です。それぞれ生活もありますからね、負担になりすぎんように。ずっとお百姓さんやってきた方もいますし、営業なんてしたことのない女性たちが、ピザやお菓子をもって販売に行くんですよ。町中や役場に出かけて、知らない人にも声かけて。全部売れるまで帰らないって方針で頑張った時期もありました」
そもそもそれほど儲かる商いではない。毎回時給が出せるかどうかぎりぎりで、それでも活動を維持するために、次回の材料費を確保した上で、残った額をメンバーで山分けするようなやり方で続けてきた。
「売上のためと思ったらやれないです。でも、みんなでワイワイやることが楽しいから続けられる。続けることが目的です。次の世代とも接点をもちたいと思って、お母さんとお子さんを呼んでピザ焼きのワークショップをしたりもしています」

現在こうした集活の取り組みを率いているのは、ほとんどが定年退職後の60代。若い現役世代がこれほどの地域活動に携わるのは、難しいだろう。だが子育て世代にとっては何かあった時に頼れる場にもなる。新しく定年退職した人たちが参加できる組織があることが、大事なのかもしれない。
以前、東京都世田谷区の調査で、65歳以上の男性単身者のうち2週間の間に会話が1回以下の人が16%という結果があった。あるインターネット調査では、60代以上の38.4%が、一週間に他人と会話する頻度が1回以下、と答えている(*2)。梼原町で起きていることは、都会に暮らす者にとってもけして他人事ではない。
■人材支援も、町独自の視点で
こうした集活の取り組みを「町の総合戦略の中で、今もっとも重要な施策と言っていいと思います」と教えてくれたのは、町役場のまち・ひと・しごと創生総合戦略推進室主事の松本裕子さん。

「いま集活で行われていることをすべて行政が行ったとしたら、もっと人もお金もかかります。地域の人たちの努力で、何とかまわしてくれている。ほかの市区町村より梼原での進みが早いのは、もともと地区長さんをはじめ地域の組織がしっかりしていたことです。
集活を始める時、ほかの市区町村では組織をゼロからつくることもあると聞きますが、うちの町ではその必要がない。もちろん地域には経営の知識がある方ばかりではないので、法人格を取得する際など、行政の担当職員が勉強して伴走してきました。今では決算書をつくるのも、税理士さんに渡す書類を用意するのもすべて地区の側でやってくださっています」
松本さんから見てこれから先の課題は何か、聞いてみた。
「何より、担い手不足です。梼原はおかげさまで、空き家の対策や子育て支援の制度も充実していて移住者も多く、平成27年度からは社会増が続いています。でもやっぱり集活の取り組みを広げていくには、事業を率先して担う人が足りません」
人材支援にも、町独自の視点がある。通常、こうした地域づくりの活動で担い手がほしい場合、総務省の「地域おこし協力隊」があてがわれることが多い。ところが、前述の四万川地区の空岡さんはこう話していた。

「初期の頃は、やっぱりゆすはら応援隊(*3)といって、よそから来た人が手伝いに来てくれよったがよ。でもね、時々来るくらいでは本格的な戦力にはならんわね。地域に慣れとる人でもないしね。しっかりお金のことも任せられる人が欲しいから、地元の若い子らを支援してもらう方がええんじゃないかと。そう僕らから提案して、集落支援員の制度を利用することになったんです」
集落支援員とは「地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有した人材が地方自治体からの委嘱を受け、市町村職員と連携し集落への目配りとして集落の巡回、状況把握等を実施」(*4)する役割の人で、総務省からも自治体に対して、財源手当が行われる。
役場が一般募集をかけるのではなく、地区の側から推薦した人材に対して、役場がその任務を委嘱する形で、3年間、月々18万円強の支援が行われる。結果的には、応援隊を卒業した人がこの制度を生かして、集活センターの運営に当たるケースもあるが、従来との違いは、よそから移住してきたばかりの地域に不慣れな若者が就くのではなく、同じ移住者でも、地域にある程度慣れた上で、この町に根をおろして働きたいと希望する若手が就任しやすい制度になったことだ。
「やっぱりそう簡単なことじゃないですからね。普通の民間と違って、儲かることをやるわけじゃなし、それでも地域に必要なことを、地域の存続のためにやるわけやから。そうした思いが根底に必要よね。ここ(四万川)だって売上的には厳しい時もあったんよ。今はだいぶ落ち着いて、何とかこのままいけば利益も少しずつ増やしていけると思いますけどね」
■いま、ここにいる人たちで集落を維持存続させていくために
集活を導入し、町をあげて地域自治を促進してきたのは、矢野富夫・前町長である。矢野さんにも話を伺うことができた。地域法人の収益を追う側面と、福祉や生活支援を促進する面が相反することはないだろうかと聞いてみた。

「私はね、こうした地域活動の目的は、最終的には売上とは思っていないんです。発展をめざす会社経営にするつもりはなくて、あくまで地域の人たちが長く楽しく生きていけるしくみをつくりたいということ。地域を維持するためのサービスやお金は必要やけど、それ以上は儲けなくてもいいんじゃないかと。
たとえば、働く住民の側からしても、自分たちでつくる野菜や加工品を他の人たちにも食べてもらうことで、小銭が稼げるならいいことですよね。それで介護保険料を賄うことができたり、生活の楽しみになったり。そうやって始めたことで、結果的に月2万円とか、多い人だと月7万円稼いだりってことが起きている。
どんどん稼いで地域を発展させて…ということではないんです。それなら大きな企業や工場をつくるやろうけど、工場入れてここに何十人分もの雇用が生まれても、工場が駄目になったり、急に株価が下がったりという外部要因で一気に人がおらんようになったら梼原はたちまち潰れてしまう。大きくは儲からんけど、いま住んでいる人たちが楽しみながらまわしていける循環型の地域社会をつくろうとしているわけです。今梼原を支えている人たちが幸せと思う生き方ができたら、それが核になる。地域で稼ぐというのも、ゆすはらを未来に引き継いでいくための経営ってことです」
各集落を見せてもらって感じたのは、従来の地域活動に比べて、よりリーダーに求められる能力や資質が増すのではないかということだ。地域のリーダーが必ずしも経営感覚の持ち主ばかりとは限らない。一方で、利益主義に偏りすぎると、働き手の幸福度や“地域のために”という面が損なわれる。そのバランスをどうとっていくのかが一つの課題だろう。
しかし、梼原がこうした住民主体の地域づくりを進めている状況は、全国のなかでも先をいっている。この先、生き残る地域とそうでない地域があるとしたら、こうした自走できる循環型の地域社会を築くことができるかにかかっているのではないだろうか。
高知の山奥で、多くの市町村がこれから参考にするであろう、まちづくりのモデルを見た気がした。

(*1)県による支援には大きく2つの側面がある。一つは財政支援、もう一つはアドバイザー派遣や支援チームなどの人材支援。平成30年度の県の予算規模は1億9678万円。ハードソフト両面の初期費用や、最長4年間の人件費および活動費(年125万円/1人)が助成される。
「集落活動センターポータルサイト」によれば、集落活動センターとは「旧小学校や集会所などを拠点として、次のような活動を行う仕組み」として、以下3つが挙げられている。
(1)日々の助け合いの活動(例:高齢者などの見守り活動、健康づくり)
(2)地域の資源を活用した経済活動(例:特産品づくり、民泊)
(3)地域の暮らしを守る取り組み(例:自主防災組織、ヘリポートの整備)など
(*2) @niftyニュースのアンケート結果。日常生活で会話(電話やメールでのやり取りも含む)の頻度を調査。実施日時:2018年11月02日~2018年11月08日/有効回答数:2,177/年代別にみると「1週間に1回以下」の割合は30代以下は23.5%、40代は27.2%、50代は28.8%、60代以上は38.4%と、上の世代ほど割合が高くなっている。
(*3)高知県の「ふるさと応援隊」と同義。総務省の「地域おこし協力隊」とは別に人材支援の制度として県が行っているもの。
(*4)総務省の「集落支援員について」(総務省 地域力創造グループ 過疎対策室)より
※この記事は「一般財団法人澄和」による「ジャーナリスト支援プログラム」の採択を受けて取材しました。