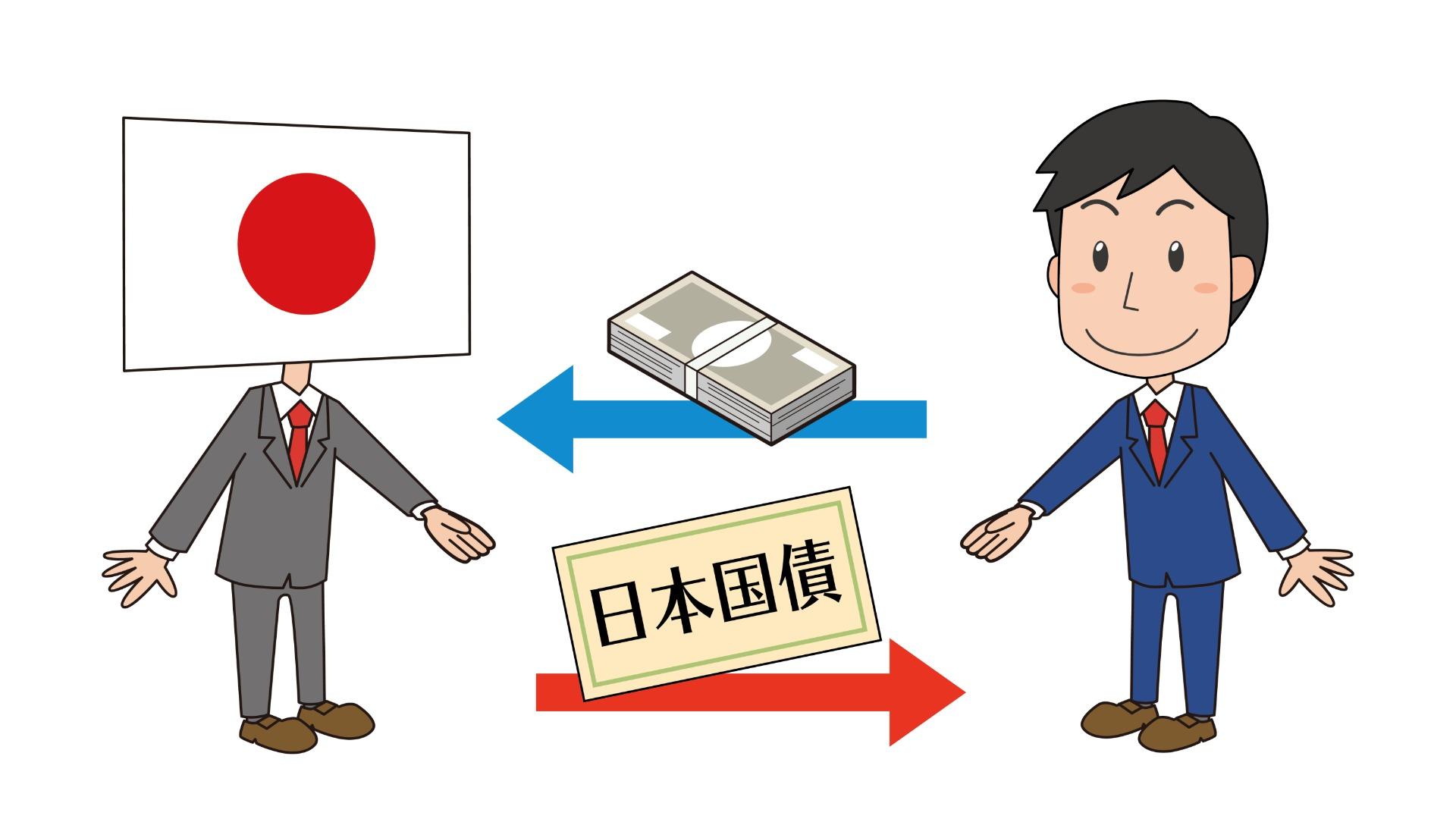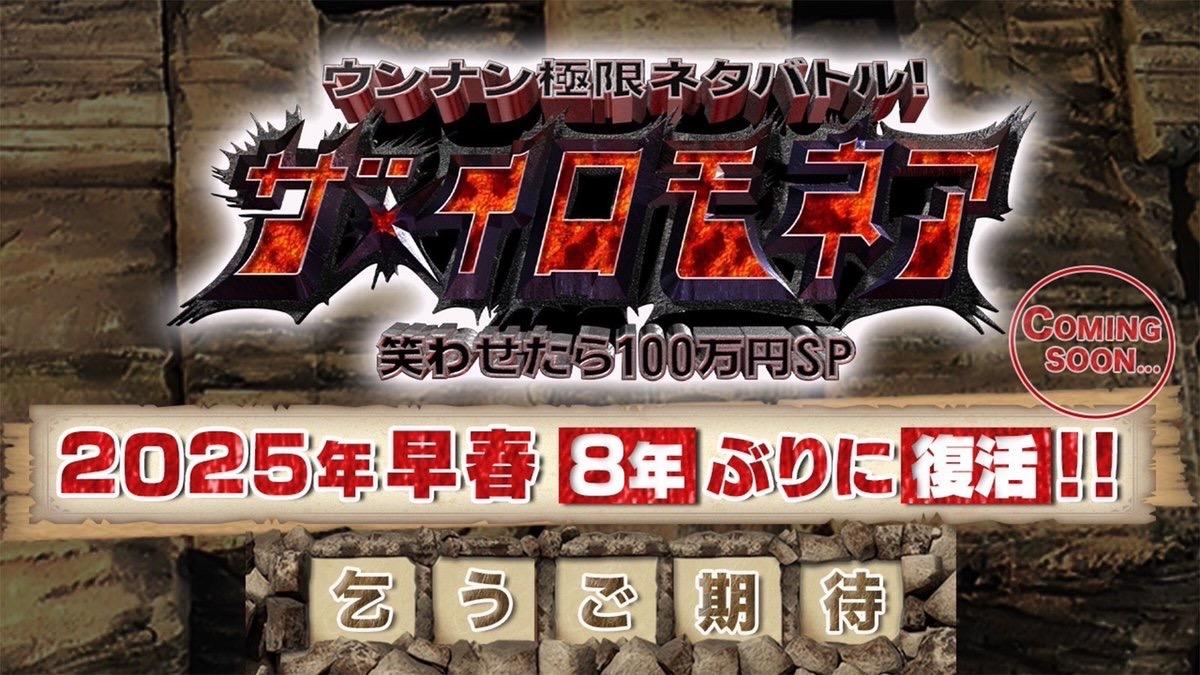尾道の観光客を魅了する元駅長 ガイドで培ったまなざし

坂や寺の多い港町、広島県尾道市。ラーメンやレトロな街並み、猫、サイクリストの聖地しまなみ海道などが注目され、近年観光人気が高い。その玄関口となるJR尾道駅前に、20年間立ち続けるのが小林仁(しのぶ)さん(81)だ。市民ボランティア団体「観光パートナー尾道の会」の会長として、観光客のガイドをしている。
小林さんは元国鉄、JR職員で、平成初期には尾道駅長を務めていた。新型コロナウイルス禍で活動を中断した時期もあったが、80歳を越えても意欲は衰えない。その原動力は、駅から町へと歩み出すことで培った「まなざし」にあった。
「血の通った会話ができる町」
3年ぶりのゴールデンウイークの賑わいが落ち着いた5月末。尾道水道を見渡す斜面地の路地に小林さんがいた。東京から訪れた観光客を連れての市街地ガイド。腰を曲げ、痛めている足の動きは慎重だが、語り口はとても柔らかい。

「北前船が寄港した尾道の交通は、船が軸でした。お寺の参道が、大体海を向いとるでしょう。参道が海岸まで繋がっていた名残です。明治の鉄道敷設で参道が寸断され、斜面地にも家が立ち並び、現在の姿になったんです」
寺の境内ではゆかりの人物の物語を、道端の井戸の前では平地の少なさゆえに深刻だった水不足の歴史を語る。偶然の出会いも多い。通りすがりの近所のおばあさんに声を掛けられたり、移住者が古民家を改装して営む店に立ち寄ったり。「血の通った会話ができる町だと、喜んでくれる人が多いんです」。週末には会の仲間と駅前に立ち、マップを手に観光案内を続ける。
形だけの観光都市に感じた駅長時代
そんな小林さんだが、「地元だけど、退職するまで尾道のことはそんなに知らなかった」という。尾道郊外の農家で生まれ育ち、高校卒業後国鉄へ。岡山鉄道管理局では広報畑を歩み、新幹線岡山延伸、JRへの民営化、瀬戸大橋開通と、山陽路の節目に立ち会った。尾道駅長として赴任したのは1989年のことだ。


「観光都市をうたっていましたが、公衆トイレは汚いし、案内板もまともになくてね‥。どうかと思いました」。世はバブルの真っ只中。本四架橋と共にリゾート開発の波が押し寄せる瀬戸内地域にあって、尾道はやや取り残された感があった。かつての商都の活気はなく、基幹の造船業は不況。再開発も遅れていた。
2年間の駅長時代は、民営化によるイメージアップのため、広報経験を生かして駅の旅行案内の充実や、地域向けのイベント企画に奔走した。当時の観光の目玉は、地元出身の故大林宣彦監督が撮影した映画「転校生」「時をかける少女」「さびしんぼう」のロケ地巡り。大林監督も、帰省時には下駄履きで駅にふらりと現れたという。あくまで駅の中からではあったが、飾らず、自然体でいられる町の空気を小林さんは感じ取っていた。
ガイドとして地元と自分に向き合う
そんな尾道に90年代後半から新たな風が吹き始める。3本目の本四架橋としてしまなみ海道が開通し、駅前再開発で海を見渡す緑地帯が整備された。定年退職で帰郷した小林さんはその光景に刺激される。町を知り、観光客を出迎えられないか。仕事や子育てがひと段落した中高年を誘い、観光パートナー尾道の会を結成したのは2001年のことだ。
毎週末駅前に立って観光客と話す日々。合間に町を歩き、歴史の勉強会や住民からの聞き取りを重ね、ガイドの技を磨いた。次第に団体客や個人のガイドを頼まれるようになり、しまなみ海道を渡って愛媛県側まで出向くことも増えた。尾道を舞台にしたNHK朝ドラ「てっぱん」(2010~11年)の放映後は、年100件を超えた。特定のハコモノではなく、町の日常そのものが観光の舞台となっていく時代。尾道は結果的にその流れにはまり、市内の観光客はコロナ禍直前の19年に推計682万人を数えた(中国新聞、20年6月16日付)。


しかし小林さんは、単に観光の売り込みをしていたのではない。ガイドは過去の自分とも対話しながら町の多様な魅力を発見し、共有していく過程だった。
「町を歩いていると、幼い頃の記憶が蘇るんです。千光寺の坂道では、足を失った傷痍軍人さんが花見客の前でアコーディオンを弾いておった。階段式の船着き場のことを『雁木』と呼ぶんですが、昔祖父と海岸で雁の群れを見て、祖父が『階段じゃ』と言っていたんですね。それが雁木の由来だとガイドを始めてから知って、記憶が繋がったんです。暮らしの中で見聞きしてきたエピソードを交えて風景を紹介すると、お客さんも喜んでくれます。やりがいがありますね」
「路地の壁に自筆の色紙を貼るおじいさんがいたり、線路沿いの花壇を欠かさず誰かが手入れしていたり。歩かないと分からないところに、尾道の人のぬくもりを感じます。そうした魅力を伝えたいんです」

観光のまなざし
「観光のまなざし」という、イギリスの社会学者ジョン・アーリが唱えた概念がある。人はそれぞれの価値観や場所のイメージに基づく「まなざし」によって、風景や建物、人、文化などに非日常性を感じ、観光の魅力を見出すという。まなざしはしばしば、ステレオタイプな地域像に偏る。
一方で、体験や出会いによってまなざしは容易に変化する。小林さんは地域を細かく歩き、人と接することで、独自のまなざしを磨いていった。ある意味観光客だったのだ。

「僕は鉄道員というより、やっぱり広報マンなんですよ」と小林さんは言う。内と外のまなざしを併せ持ち、駅長時代もどんな言葉で伝えればいいかを相手目線で考えてきた。単なる「わがまち自慢」にならなかったのは、組織人としての経験が大きい。
「ガイドで大切なのはおもてなしじゃなくて思いやりですね。お土産はないけど人情を感じて、また行きたいと思ってもらえたらええんです」
琴線に触れた場所の写真をSNSで共有し、誰しもまなざしを拡散できる時代。その反面、他者のまなざしにも囚われがちになる。生の体験を大切にする小林さんの姿勢は、身近な町に自分なりの魅力を見出すヒントを与えてくれる。