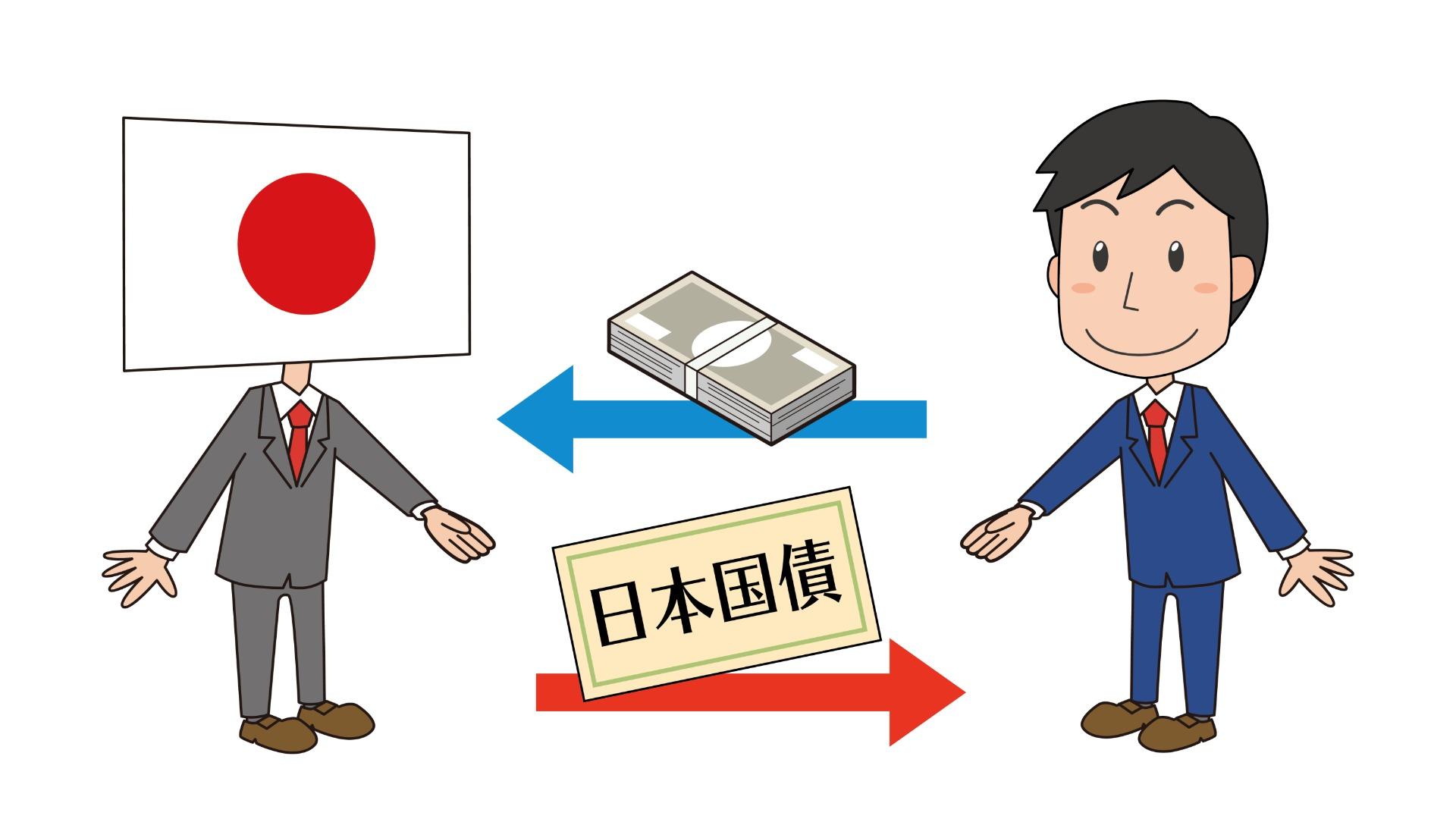映画『逆光』を支えた尾道の人々と、町の未来

昨年7月、広島県尾道市を舞台にした映画『逆光』が、同市で先行上映された。俳優須藤蓮さんが初監督と主演、NHK朝ドラ『カーネーション』などで知られる渡辺あやさんが脚本の自主映画だ。公開から1年、波は全国に広がる。これまで地方を中心に14都市で流れ、現在は岐阜、7月下旬以降は高岡や高崎での上映が続く。
何事も東京中心の映画業界で、地方発の自主配給である『逆光』は異彩を放つ。実現を後押ししたのは、作り手の熱意をくみ取った地元の人々だ。
勢いでスタートした自主映画
尾道は戦前から数多くの映画の舞台となり、尾道水道や斜面地、路地など独特の景観が映える。『逆光』もそんな舞台装置を生かし、政治の季節の余韻が残る1970年代の若者の情愛を描いた。先月あった「尾道映画祭」では久々の地元上映。映画館シネマ尾道の客席は若者が目立ち、高校生の姿もあった。

舞台あいさつで須藤さんは「尾道に育ててもらった」と感謝した。いまも上映が決まった都市に滞在し、市民に直接訴えて協力を願い、訪れた観客との対話を欠かさない。須藤さんにとって、こうしたコミュニケーションも作品の一部だ。
企画は新型コロナウイルスが蔓延した2020年春、突如決まった。渡辺さんの脚本作品『ワンダーウォール』に須藤さんが出演し、同作の上映で2人で尾道を訪れたのがきっかけ。「作品のすべてに自分の思いをぶつけたい」と考える須藤さんに、渡辺さんがシナリオを提供し、勢いのまま尾道で撮ることになった。しかし地方ロケは場所探しから難航するし、予算もほぼない。まして配給も地方発となれば、業界では通常「無謀」と一蹴される。
有志が顔の見える関係で支える
そこで地元側のキーパーソンとなったのが北村眞悟さんだ。シネマ尾道の元スタッフで、現在はロケ協力や映画関連のイベントを企画する市民団体「尾道フィルムラボ」の代表を務める。小さな町だからこそ生かせると考えたのが、顔の見える関係だ。北村さんはかねがね「東京の部隊が町を一方的に撮るだけで終わるロケは残念」と感じてきた。地域と交流しながら映画を作るように仕掛けようと思ったのだ。

観光地で移住先としても人気な尾道には、飲食やゲストハウス、雑貨など小商いに関わる人が集い、若い世代のネットワークがある。北村さんはそこに須藤さんたち制作チームをつなげた。普段から映画を見ている人ばかりではないが、何かをしようとする若者を面白がり、助けようとする気持ちは強い。当時24歳だった須藤さんの熱い思いに応え、自然と協力してくれた。
町の素人たちは多才で、フットワークが軽い。エキストラや小道具はすぐ集まる。美術セットを作ったり、制作資金のクラウドファンディングを助言したりする人もいた。コロナ禍で大都会ではいっそう薄れた対面のつながり。須藤さんはその力強さを初めて思い知った。
須藤さんは「面倒くさいコミュニケーションもあるからこそ、鍛えられた」と振り返る。例えば試写会では、東京では業界人に表現手法を絶賛されたが、尾道では「町のことを分かってない」「面白くない」と正直な批判を浴びた。そのショックがむしろばねになり、本気の配給活動に駆り立てた。制作チームで尾道や広島市に1か月以上滞在。ポスターを手に島の小さな店まで泥臭く回り、「劇場に足を運んで」と宣伝した。作品の好みは別でも、須藤さんの熱意は通じる。人々はSNSよりも拡散力のある口コミで広めてくれた。

その甲斐あって、広島県内4館でのおよそ1か月半の上映には計1500人以上が来場。大都市を含まない地方での自主配給としては十分成功だった。シネマ尾道の河本清順支配人は「インディーズの作品が映画ファン以外にも見られることはなかなかない。須藤君たちが足で稼いだからこそ、成長を見守るかのようにみんなが惹かれていった」とたたえる。
「組織より人」は大林映画から
有機的につながった市民と共に、映画を完成に導く。作品の知名度や事情は違うが、尾道には先例がある。地元出身の故大林宣彦監督のロケだ。『転校生』(1982年)から遺作『海辺の映画館-キネマの玉手箱』(2020年)まで、実に38年間の積み重ねがある。
特にスポンサーが降板し製作のピンチだった『転校生』は、大林監督の父が地元で有名な医者だったこともあり、同級生や建築事務所の社長、市職員たちが組織の枠を越えて協力。撮影交渉から道具作り、機材の運搬まで担ってロケを成功させ、ヒットにつなげた。食事や洗濯など現場の世話を一手にこなす妻の大林恭子プロデューサーを慕い、ロケのたびに集う市民は「大林組」と呼ばれた。

大林映画はロケ地巡りの観光客を尾道に呼び込み、開発が遅れ不便な町だと嘆く市民に元気を与えた。撮影を支援し地域振興につなげたのは、現代の「フィルムコミッション」のモデルとも言える。しかし尾道は今でも、あくまで組織ではなく個人が主体で映画制作を支えている。
「映画に携わるのは、人と人の関係性あってこそ」。『転校生』で撮影された喫茶「こもん」を経営し、大林組の中核だった大谷治さんは強調する。「観光振興のため組織的にロケを誘致しても、経済効果は一瞬ですよ」。個々の市民が映画や表現者と触れ合って味わう、喜びや充実感の方が大切で、一生残るものだという。
ボランティア依存と映画の町の未来
大林組の考えは、組織や数字でなく人を相手にモノづくりをする『逆光』のチームとも通じる部分がある。脚本の渡辺さんは「今の映画業界はスポンサーや宣伝会社に依存した作り方で、システマチックになりすぎている。それでは限界がある」とみる。尾道を出発点にした草の根の全国行脚は、作り手と受け手の距離を縮め、共に文化を育んでいく試みだった。
もちろん、組織がないことにも大きな問題がある。市民が映画に関わるといっても、結局一部の熱意あるボランティアに依存する体質になっているからだ。北村さんたちも映画で生計を立てているわけではない。さらに大林組の人々も高齢化し、地元での記憶は薄れつつある。ノウハウが受け継がれず、意欲やゆとりのある人がいなくなれば、有志が映画制作を支える営み自体が消えてしまう。今年で6回目を数えた「尾道映画祭」の継続にも関わる。
危機感を抱くからこそ、北村さんは「尾道フィルムラボ」というゆるやかな組織で、映画に親しんだり、ロケ支援に関わったりする人を増やそうとしている。大林監督の功績を伝えることはもちろん、映画音楽を手掛けたミュージシャンのライブや、若者が映画について語るイベントなどを企画する。「映画は自分の町の魅力を見つめ直すコンテンツでもある。もっと町全体に広がってほしいんです」
映画の町の文化を次世代につないでいく。『逆光』の成功は、その小さな一歩になるだろう。
<参照>
映画『逆光』公式サイト
https://gyakkofilm.com/
大林宣彦「大林宣彦の映画談議大全 ≪転校生≫読本 ―ジョン・ウェインも、阪東妻三郎も、…」角川学芸出版