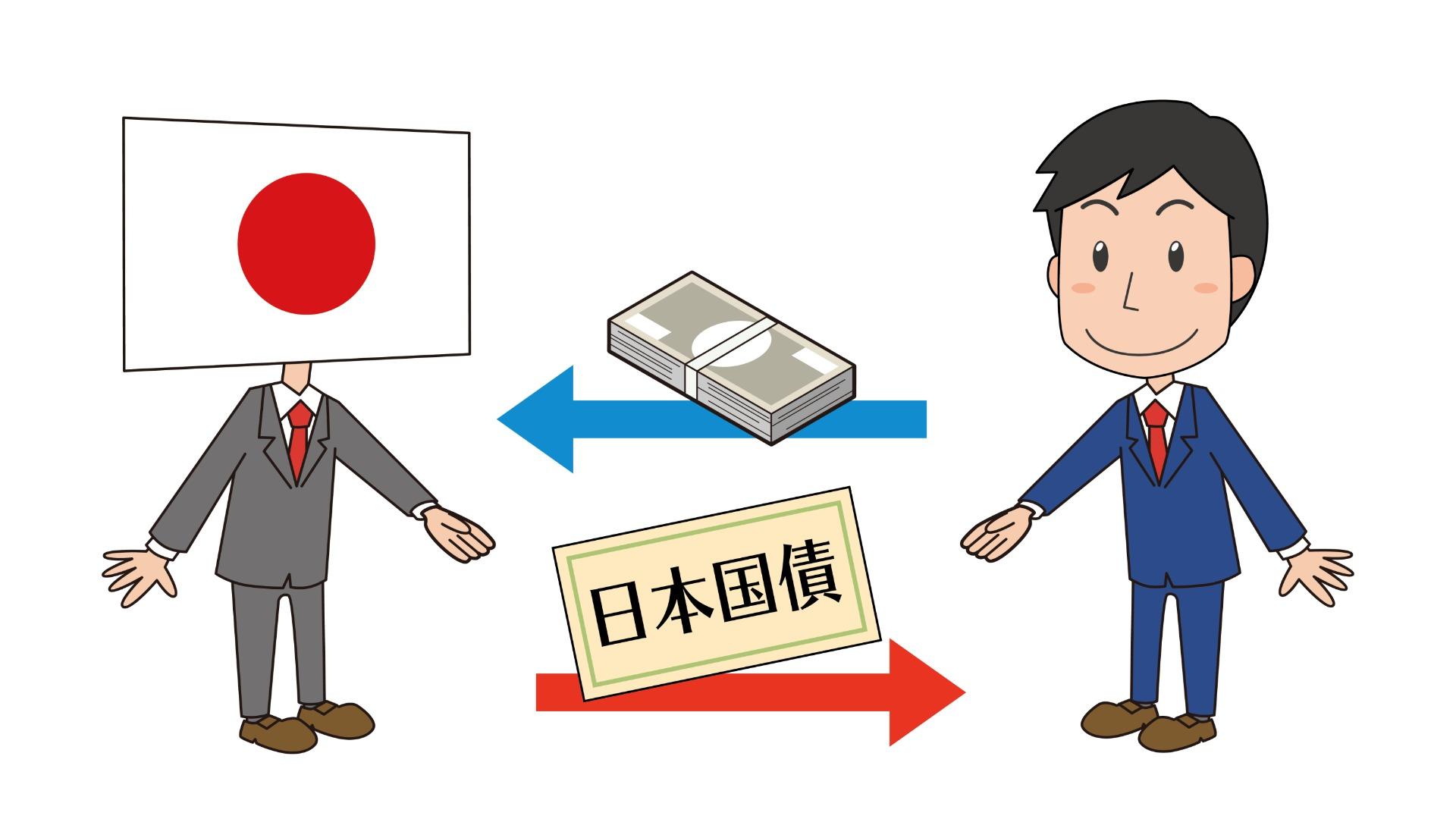ボクシングの力とは何か──元日本ランキング1位、村松竜二さんが取り組む社会貢献

ボクシングは社会に対してどんな貢献ができるのか─。そんな難題を真剣に考え、実行に移している元プロボクサーがいる。元日本ライト・フライ級1位の村松竜二さんだ。現在45歳。東京都昭島市でD&D BOXING GYMを営む村松さんは障害者の自立支援や、視覚障害者たちが楽しむブラインドボクシングを通じ、社会に貢献しようと模索する日々を送っている。
8月下旬の土曜日。東京都は西部にある昭島市はうだるような暑さに包まれていた。JR昭島駅に向かうTシャツ、短パンのグループはD&D BOXING GYMの面々。この日、同ジムで開かれるブラインドボクシングの練習会に集まるメンバーを駅まで迎えにいくところだった。

「迎えにいくときが一番心が躍りますね」と笑顔の村松さん。スタッフ一同は、次々に集まったメンバーたちとあいさつを交わすと、白杖を片手に会話を交わしながらジムまでのおよそ5分を歩いた。
村松さんは日本ライト・フライ級王者でのちに世界王者となった戸高秀樹さんを皮切りに、日本タイトルに4度挑戦してベルトを巻くことができなかった元プロボクサーである。プロ選手を育てようと考えた時期もあったが、いまはボクシングを通じた社会貢献活動に全力投球している。
スタートは6年前だ。村松さんが所属していたジムに、星島一太さんという臨床心理士、精神保健福祉士の資格を持つ後輩がいる。言葉でうまく表現できない障害者に対するボクシング療法に早くから取り組み、当時は青梅市内にある障害者の自立支援施設でボクシングを教えていた。人手が足りなくて困っていた星島さんの手伝いをしたのが、福祉活動に足を踏み入れるきっかけとなった。
「私の子どもが学校に通うようになってから、ボクシングを通じた青少年育成に興味を持ち、昭島市内の小学校でいじめ撲滅のボクシング教室を開いたりしていました。自分はボクシングで自信をつけましたから、子どもたちにも同じようにボクシングで自信をつけることを伝えることができるのではないかと思いました。自信がつけば、人をいじめたり、いじめられたりすることも少なくなるのかなと思うんです。相手が障害者であっても自信をつけることの大切さは同じではないのか。そう考えました」

自立支援施設には、精神障害を患った人たちもいた。声をかけても反応がない人、ずっと床に座っているだけの人…。そうした環境で教え始めた1回目か、2回目だったか、手首から肩の近くまでリストカットの痕が生々しい人を教えているとき、交わした会話に衝撃が走った。
「『パンチを打つときにどんな顔をすればいいんですか?』と聞かれたんです。そんなことを聞かれたことは一度もありません。必死に考えて『パンチを打ってミットがいい音をたてたらいいパンチだから笑えばいい。納得いかないパンチだったらそういう表情をすればいいんじゃないかな』と言ったんです。そうしたらその人が懸命にパンチを打って、ぎこちないながらも笑顔を見せました。それを見たときですね。これは続けないといけないなと。ボクシングを通じて社会に役に立てることがあると感じました」
実は村松さん自身も障害を持っている。選手時代のキャリア序盤に交通事故にあい、左手首が曲がらなくなったのだ。ここからほぼ右手一本で日本ランキングの1位まで上り詰めた。こうした背景もあったからか、「村松さんはどんどん活動にのめり込んでいった」(星島さん)。ついに2年前、整備士として24年勤めた自動車会社を退社、18年9月にD&D BOXING GYMを立ち上げたのである。

ジムを開いてからは、社会福祉法人きょうされんに勤務し、障害者が瓶を洗ってリサイクルする仕事のサポートをしている。平日はこれに加えて朝と夕、健常者のパーソナルトレーニングをジムで受け持ち、週末は自立支援活動とジム開設からほどなく始めたブラインドボクシングと休みはない。それでも村松さんは「ギブ・アンド・テイクという言葉が好きなんです。こちらが与えるだけでなく、元気をもらうこともたくさんある。充実していますよ」と明るい。
ブラインドボクシングとは、対面する2人が打ち合うのではなく、アイマスクをした選手が、首に鈴をつけたパートナーにパンチを打ち込んだり、パンチを防御したりして、その動きをジャッジが採点して競い合う日本発祥のスポーツ(競技)だ。
実際の練習はといえば、健常者のボクシングと何ら変わりはない。いかに体重の乗った鋭いパンチを打つか、パンチを打ったらすぐにディフェンスの姿勢を作るとか、といったオーソドックスな内容である。村松さんに言わせると「視覚障害の方は目が見えないだけなので、そこをサポートしてあげればいい」ということになる。

実際に打ち合わないとはいえ、鈴の音を頼りに見えない“敵”を追いかける作業ははたから見ている印象よりもはるかに難しい。すくみそうな足を前に出し、懸命にパンチを打ち込んでいると、心地よい疲労とともに1ラウンドの2分間はあっという間にすぎていく。
練習の参加者に話を聞いてみた。濱田圭司郎さんは全盲の51歳。打撃系の格闘技が好きで若いころに空手をしたこともあったそうだが、目が見えないという理由で試合は許されなかった。そんな経験を持つ濱田さんは「ボクシングができる時代になってうれしいですね。競技の名前はブラインドボクシングですけど、自分はボクシングという感覚しかないんです。もう楽しくてしょうがないです」と完全にのめりこんだ様子。葛飾区から東京を横断し、往復5時間かけて月2度の練習会に通っている。
近隣の福生市から通う45歳、関章芳さんは「以前はゴールボールをやっていたんですけど、家から遠いし、欠席するとみんなに迷惑をかけてしまうんですよね。ボクシングは個人戦なんでいいかなと。高校生の子どももボクシングに興味を持っていて、健常者のボクシングに通う予定なんです」。こうした話を聞くと、ブラインドボクシングもまだまだ普及の余地はありそうだ。

村松さんはこれからも、社会貢献活動を軸にしたボクシングジム運営をしていくつもりでいる。その原動力となっているのは「ボクシングは健常者であっても、障害者であっても、最高のコミュニケーションツール」という信念である。
人を殴るという暴力的な要素を含むボクシングは、自分が傷つくがゆえに、相手の痛みを知ることに敏感だ。それはつまり相手を思いやる大切さを理解し、伝えることにもつながる。「ボクシングならではの力は絶対にあると思います。あとは使い方です」。村松さんの挑戦は続く。(写真はすべて筆者撮影)
(取材協力:ブラインドボクシング協会関東支部、一般社団法人B-box)