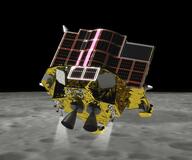まもなく帰還!「はやぶさ2」プロジェクトマネージャが語る真の挑戦とは

宇宙科学ミッションの歴史においても、真の科学的欲求に忠実に応えられることはそうそうない。何かしら妥協が入る。だから、着陸のような大変な難局で、制約を打破し、真の科学的欲求を引き出し、ディスカウントなしで「未知への挑戦」を完遂したことの価値はとても大きいのだ。
あと1週間に迫ったJAXAの小惑星探査機はやぶさ2の地球帰還。2020年12月6日に地球に届くはやぶさ2のサンプルコンテナ入りカプセルには、小惑星リュウグウ上で2回のタッチダウン(着陸)を行った際に採取した、太陽系の歴史を映す物質が入っている。『はやぶさ2 最強ミッションの真実』(津田雄一著、NHK出版)は、世界で初めて小惑星に2回着陸し、地下の物質へのアクセスを成功させたはやぶさ2プロジェクトで2015年以来プロジェクトマネージャを務めている当事者中の当事者、JAXA 宇宙科学研究所の津田雄一教授自身によるはやぶさ2ミッションの記録だ。
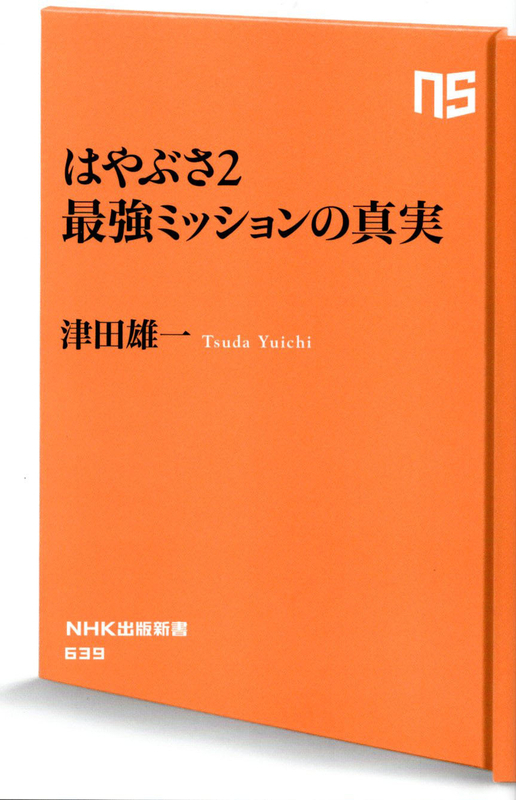
はやぶさ2は、2018年6月27日に小惑星リュウグウに到着し、翌2019年2月22日にリュウグウ表面で第1回タッチダウンと小惑星表面サンプル採取を実施。2019年4月5日には衝突装置(インパクター/SCI)によるリュウグウ表面での人工クレーター生成に成功した。2019年7月11日には、衝突装置が穿ったクレーター周辺に飛散したリュウグウの地下物質めがけて第2回タッチダウンを行い、これも成功させている。
直径900メートルほどの小惑星リュウグウのような比較的小さな小惑星は、45億年の太陽系初期の物質をとどめ、科学者からすれば歴史がそのまま保存されているような存在だとされている。特に、地下にあって太陽光にさらされていない物質は天然のストレージに入れられていたようなもので、科学的価値が高い。

はやぶさ2はこのフレッシュな地下の物質を採取することを目指して計画された探査機だが、地球からは光の点にしか見えない小惑星リュウグウは、実際に行ってみると恐ろしいほどゴツゴツの岩だらけで、津田プロマネ自身が「牙を剥いてきた」と表現した厳しい世界だった。計画時には直径100メートルの平坦な場所を探してタッチダウンする予定が、実際に探すことができたのは直径6メートル。はやぶさ2は、機体側面に羽根のように広がる太陽電池パドルがようやく収まる程度の、とてつもなく厳しい条件をクリアしてのタッチダウンを強いられた。
1回でも厳しいリュウグウでのサンプル採取だが、本書の白眉となっているのは2回目のタッチダウンを巡る攻防だ。1回目のタッチダウンを成功させ、その時点で小惑星リュウグウの表面(太陽光にさらされていた場所)のサンプルは入手している可能性が高い。複数回予定していたタッチダウンを1回とし、後は上空からの観測にとどめて地球に帰還すれば、2回目のタッチダウンではやぶさ2の機体を損傷、最悪の場合は探査機を失って何一つ得られないというリスクは低減できる。本書終盤には、そうした「安全に、60点でミッションを終えよ」というJAXA内部のプレッシャーも強かったことが語られている。
だが、工学実証機としての初代「はやぶさ」から小惑星探査に関わってきた津田プロマネを始めプロジェクトチームは決してあきらめたくはない。運用中にはやぶさ2が計画外の事態を検知して動作を中断した「アボート」時にさえ、タッチダウン実施に向けた情報収集を仕込んでいたエピソードが、なんとしてでも未知への挑戦をやり遂げるのだという姿勢を語っている。
津田プロマネは、はやぶさ2プロジェクトで機体の設計開発にあたったエンジニアリング側の代表だが、プロジェクトのもう一方の代表は、小惑星探査の科学を主導するプロジェクトサイエンティストの渡邊誠一郎教授だ。著者の津田プロマネにとっては、同じプロジェクトの仲間でもあり、サイエンスチームという外部の視点を代表する立場でもある渡邊教授が「自ら作ったできたてのクレーターを目の前に着陸地点を吟味するようなことを、人類がこの50年や100年のうちに実現するとは全く思っていませんでした。今私たちはそれをやっているのです。この状況を実現した工学メンバーのチーム力、士気の高さは本当に感動的です。そういったものに支えられたディシジョンは信頼するし、サイエンスチームは全面的に支持します」と第2回タッチダウンを後押しする場面は圧倒的だ。
1年5カ月にわたるリュウグウ近傍運用の中で、「ディスカウントなしでの『未知への挑戦』」がひとつひとつ積み上げられていくエピソードを追うのは実に楽しい。もちろん、初代はやぶさ帰還前から始まる長いはやぶさ2計画が常に、眉間にシワを寄せたような厳しいやり取りだけで占められているわけではない。「探査を嗜む」と津田プロマネが評する宇宙探査の技術を愛する人々、楽しげにぼやきまくるプロジェクトエンジニア、正確無比なメールを常に書き続けロボット説が噂されたNEC技術者、まさかの出荷時サンプラホーン後送事件など当事者でなければ出てこない記述が数え切れないほどある。
そして12月6日のカプセル帰還時の報に接したとき、1グラムに満たないリュウグウのサンプルに太陽系45億年の重みを乗せて感じたい。本書はそのガイドとなってくれるだろう。