ウェイン・クランツというギタリストのライヴがボクの興味を著しくひいたので
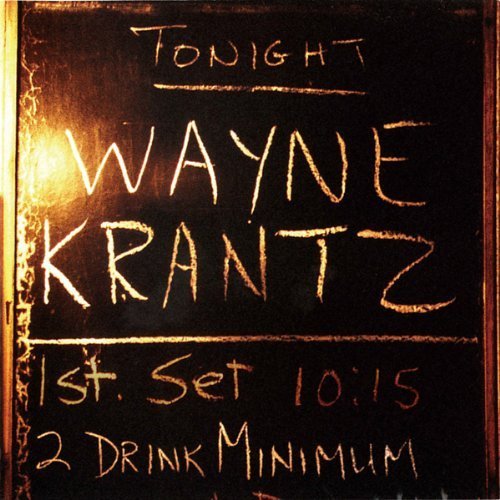
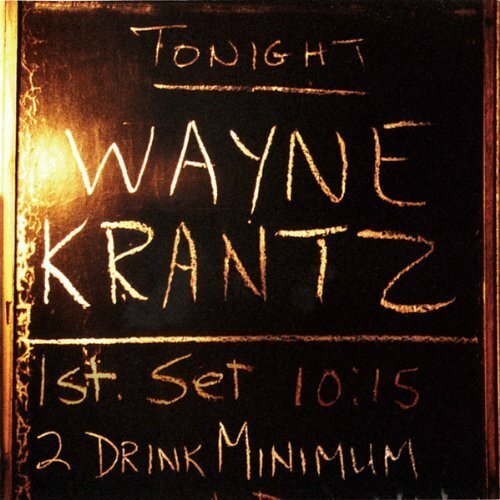
ウェイン・クランツが来日して、10月28日から30日に丸の内コットンクラブでライヴを行なった。
彼の来日はこれが初というわけではなかったようだが、これまでボクは観る機会がなかった。
今回、日本を含めたツアーにあたって、ソニック・ユース・ナイン・インチ・ネイルズ、プリンス、トーマス・ドルビーといった、“さすが還暦”と思わせる縦に長い時間軸のセレクションを予定しているとアナウンスがあった。
会場となった丸の内コットンクラブのサイトに掲載されているコメントによれば、スターダスト・レビューの根本要三はスティーリー・ダンの1996年の来日でウェイン・クランツの勇姿を目の当たりにして衝撃を受けた、とある。
ボクもそのころにスティーリー・ダンのライヴを取材した記憶はあるのだけれど、残念ながらウェイン・クランツの印象は残っていない。きっと、クランツではないギタリストのときのステージだったんじゃないかな。
ブレッカー・ブラザーズにしても、マイク・スターンやディーン・ブラウンという個性的な(ある意味でウェイン・クランツと“同類”の)ギタリストが強烈なオーラを放っていた記憶があるけれど、やっぱりウェイン・クランツの印象は残っていない。たぶんボクは彼が参加したステージを観ていなかったに違いない。
ハード・ディスクに保存してあるデータを検索しても、まったくウェイン・クランツの名前は出てこなかった。
しかし、観てみたいという欲求が出不精を上回ってしまった。なぜだかはわからない。ウェイン・クランツに“呼ばれた”といか言いようがない。
ライヴの感想を書く前に、彼の経歴をかいつまんで紹介しておこう。
ウェイン・クランツ(Wayne Krantz)は1956年生まれの60歳、米オレゴン州出身だ。
14歳でギターを始め、1985年からニューヨークの第一線で活動を始める。ブレッカー・ブラザーズ、スティーリー・ダン、クリス・ポッターなど、多くの著名ミュージシャンから声がかかるスタジオ・ミュージシャンとしての活動の一方で、自己の活動も展開。
2014年にリリースした『Good Piranha / Bad Pkranha』では、レディオヘッドのトム・ヨーク、N.W.Aのメンバーだったアイス・キューブ、MCハマーといったヒップホップやオルタナティブ・ロックのカヴァーを披露――。
といったところがウェイン・クランツの主な経歴で、要は“知る人ぞ知る”といった言い方しか紹介すべき言葉が見当たらないという、ちょっとライター泣かせのアーティストだったりする。
――と、その経歴に疑問を呈しておきながら、立場を翻すようで申し訳ないのだが、ミュージシャンズ・ミュージシャンとはそういうものであり、逆に言えば、ポピュラリティに欠けていても“逸材”は存在する。
そんなこともあって、ボクのなかでのウェイン・クランツへの期待度は、アマノジャクにもグンッと膨らむことになってしまった。
さらに、ネットをフラフラしていたら引っかかってきた「このGuitarを聴け![Wayne Krantz]|Out of JAZZ」の小金丸彗氏の記事を読んで、俄然このギタリストがボクの愛してやまない、“限りなく灰色”なゾーンで暗躍しているミュージシャンであるとの確信を深めてしまった次第なのである。
そして、ライヴを観終わると、その確信は正しかったことがはっきりした。
ニューヨークで変態系と認識されているギタリストの筆頭は、ジョン・スコかビル・フリゼルあたりがろうか。そのあとに、マイク・スターンやハイラム・ブロックが出てくるんじゃないかと思うのがけれど、マイク・スターンやハイラム・ブロックといえばジャコ・パストリアスとトリオを組んで、フリー・ジャズとは異なるハーモニックなインプロヴィゼーションのできる演奏を模索していたギタリストたちだ。もっともストレートな状態で模索していたとは言えないのが残念なのだが……。
ハーモニックという目標を持つかどうかは別にして、1970年代で途切れたフリー・ジャズとは異なるインプロヴィゼーションへの欲求は、やがてジャム・バンドというかたちでスタイル化されていく。1990年代の話だ。
ウェイン・クランツがシーンに出てくる1980年代後半はその黎明期で、インプロヴィゼーションに関するいろいろな模索が行なわれていたことがうかがえる。実はその90年代初頭、ジョン・ゾーンから「おっそろしく速いフレーズを弾きまくってあっという間に終わってしまうようなパフォーマンスが流行っている」というような話を聞いた覚えがある。当時はまだクラブ・ジャズともジャムとも名の付かない時代だったが、彼はそれがウエスト・コーストから伝播し、スラッシュとかスピードとか呼ばれていると言っていたと思う。
おそらくこうしたムーヴメントのなかにウェイン・クランツはいたにちがいない。いや、彼こそがその牽引役であったとも言える。
実際に観た彼のライヴは、曲であって曲でないような、どこまでが決まっているのかわからない緊張感と濃縮感に溢れていた。明らかに途中でウェイン・クランツがなにかに閃き、そこから違う方向性へと発展していった場面も何度かあった。
要するに、とても自由なのだけれど、考える余地をもたせないという、矛盾した状況を作り出すことで、瞬発的な音楽の完成度を競うゲームのようなジャズをめざそうとしたと言えばいいだろうか。言葉にしてみると、ビバップのコンセプションに近い気がする。だから、こうした指向性をもつ演奏家たちは自分をジャズに近いと認識しているのかもしれない。
ウェイン・クランツのようなミュージシャンは、ジャズにモヤモヤとしたものを感じているヒトにはぜひチェックしたもらいたいタイプではないかと思ったので、なんとなくモヤモヤした書き方しか出来なかったけれど、書いてみた次第です。










