「自動車会社が消える日」はやって来るのか 100年ぶりのパラダイムシフトの中で

このままでは、伝統的な自動車メーカーは存在感を失ってしまうのではないか。この2、3年、そう感じることが多くなった。下手をすれば、消えてなくなる会社も出てくるかもしれない。そうした問題意識から拙著『自動車会社が消える日』を執筆した。
筆者の経歴を少し説明すると、1995年から自動車産業を取材してきた。現在はフリージャーナリストだが、一時期は大手紙の経済部員兼豊田支局員としてトヨタ自動車の本社がある愛知県豊田市に居を構え、自動車産業の取材にどっぷりと浸かってきた。
自動車産業は20世紀最大の産業、産業の中の「王様」だった。雇用、税収などの面で地域に与える影響は大きい。これは世界各国共通で、今でも自動車工場の誘致合戦がある。そして、自動車は、機械、電気・電子、化学、鉄鋼などのあらゆる産業を融合させて成り立つので、自前でクルマを造ることができて、初めて先進国に仲間入りできた。
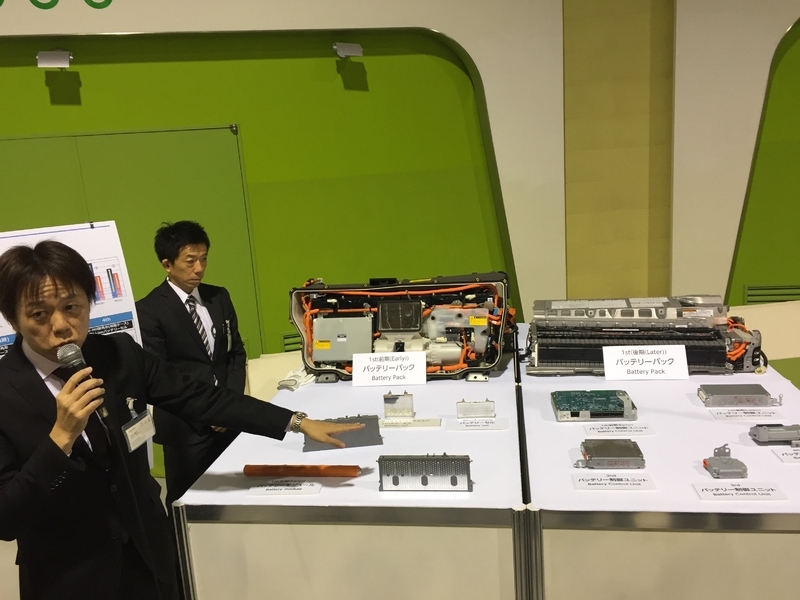
志賀会長の大胆予測
しかし、こうした筆者の認識が崩れ始めている。その動きは「CASE」というキーワードで端的に象徴される。これは、ドイツのダイムラーが使い始めたタームだと業界では言われている。Connected(つながるクルマ)、Autonomous(自動運転車)、Shared(配車サービスなど)、Eelectric(電気自動車)の頭文字を取ったものだ。ここに自動車産業以外の分野からの新規参入が相次ぎ、自動車メーカーは守勢に回っている感もある。
産業革新機構の志賀俊之会長は個人的な見解と断ったうえで、「ガソリンスタンド、運転免許証、信号機、自宅の駐車場が2050年には消えているのではないか」と言う。
志賀氏は日産自動車で最高執行責任者(COO)を歴任、現在も日産取締役を兼任しており、40年近く自動車業界を見てきた経営者が、こうした大胆な予測をしているのだ。
志賀氏によると、電気自動車の普及によってガソリンスタンドは不要になる。自家用車を使わない時間はシェアカーとして貸し出す。インターネットに常時繋がっているので指示を受けて無人の完全自動運転によって借りたいお客のところに勝手に動いていけば、自宅の駐車場は要らなくなる。優れた予知機能を持つAIが搭載された完全自動運転車であれば信号の指示に従わなくても事故は起こらない。そして人間が運転しないので、免許証も要らなくなる、といった具合だ。
自動車メーカーは「恐竜」になるのか
自動車産業界ではいま、大きなパラダイムシフトが進んでいる。1908年に米フォード・モーター自動車の大量生産を始めて近代のモビリティ産業が確立されて以来の地殻変動的な変化が起きているのだ。こうした時代は、恐竜が気候の変化についていけず、絶滅したように、ビジネス環境の変化に対応できなければ、いくらリソースが豊富な巨大企業でも滅び去ってしまうだろう。
トヨタは12月13日にパナソニックと次世代の車載電池での提携、19日には2025年までに世界で販売する全車種を電動専用車や電動グレード設定車にして、エンジンのみのクルマはゼロにすると、立て続けに新戦略を発表している。トヨタに限らず、日産も12月8日、カーシェアサービス「NISSAN e―シェアモビ」を18年1月15日から開始すると発表。前述した「CASE」に関してのニュースが目に入らない日はないと言っても過言ではない。

バーチャルエンジニアリングの台頭
こうした「CASE」の進行と相まって、実は自動車の開発手法も大きく変化している。今回のコラムはこの点を強調したい。
「IPGオートモーティブ」と聞いても、一部の自動車エンジニア以外に知っている人はほとんどいないだろう。この会社にいま、トヨタやホンダなどのエンジニアが押しかけている。
なぜなら、この会社の製品なくして自動運転車の開発はできないと言っても過言ではないからだ。本社はドイツ。ドイツのカールスルーエ工科大学発のベンチャーとして1984年に創業された若い企業で、2014年には日本法人が設立された。
このIPGは自動車の開発ツールを作る会社だ。代表的な商品は「Car Maker(カーメーカー)」。自動運転車の開発において、路面、天候、スピード、運転者の力量など様々な条件を設定すると、実際に動く自動車を試作することになしに、バーチャル(仮想現実)・エンジアリング技術を使い、パソコンの画面上で開発できるソフトウェアだ。実際に運転手が乗った状態でのシミュレーションもできる。
億単位のシーンを想定
IPGは、自動運転に関するバーチャル・エンジニアリングでは最も進んでいる企業の一つで、ある自動車メーカーのエンジニアはこう語る。
「レベル1(自動ブレーキなどの単一機能の自動化)や、レベル2(加速・減速やハンドル操作など2つ以上の機能の自動化)の自動運転では、600万シーンを想定してプログラムを作って開発していますが、レベル4(人が関与しない完全自動運転)の段階になると、億単位のシーンの想定が必要になる」
ここでいう「シーン」とは、「映画の場面」と同じ意味だ。どのような場面でクルマが自動走行するのか、あらゆる状況を想定して、それに対処できるよう自動運転のクルマの頭脳に、その「シーン」をインプットしていくということである。
そのエンジニアは「実物で億単位のシーンをインプットしていくことは不可能。そんなことをしていたら40代の私が定年退職するまでに開発は終わらない」と言う。
宇宙開発の手法がクルマにも
今のクルマはソフトウェアの固まりになっている。それが自動運転になるとさらにソフトウェアの比重は高まる。ソフトウェア同士が相互にどのように協調・干渉するのか、それを実物の自動車で確認しながら開発する体制は限界が近づきつつあるのだ。
IPG日本法人の小林祐範社長がバーチャル・エンジニアリングを取り巻く潮流について説明してくれた。
「自動運転に限らず、EV(電気自動車)でもバーチャル・エンジニアリングを使った技術が重要になります。EVは、部品点数が減ることなどによってハードとしての構造はシンプルになりますが、ソフトウェアは内燃機関(エンジン)のクルマに比べて煩雑になる傾向にあります。開発期間を短縮させるためにもバーチャル・エンジニアリングは欠かせなくなっています」
IPGが得意なバーチャル・エンジニアリングを採り入れた開発手法を「モデルベース開発(MBD)」ともいう。
これはソフトウェアや宇宙探査機などの開発で用いられてきた手法だ。遠く離れた宇宙空間で使われる技術は、実際に使用される場面を直接確認することはできない。だから条件を想定してシミュレーションしながら開発される。
ここでいう「モデル」とは、実物の試作機を作成せずに設計の仕様を作成するための数式モデルやデータ・モデルを指している。コンピューター上(バーチャル=仮想)で動作をシミュレーションできるモデルを作り、それを使って開発する手法だ。
重要な2つの試作
このバーチャル・エンジニアリングが、自動車産業にどのような変革をもたらしているのか。それを述べる前に従来の自動車開発のプロセスについて大まかに説明しよう。
クルマの開発は、まず商品企画から始まる。
「買い物に行く主婦が使いやすい」 といったコンセプト作りから始まり、「燃費効率をこれくらい」「時速50キロで曲がる場合に、搭乗者にかかる加速度をこれくらいまでに抑える」と、徐々に商品のイメージを固めていく。そのプロセスの中で試作エンジンや試作車など実物を作る。その実物をつかって性能などの仕様を決めて、設計図に落とし込んでいく。これを「開発試作」と呼ぶ。
設計図が完成すると、ここでもう一つの試作がある。それが「量産化試作」だ。生産ラインに乗せたら、設計図通りに大量生産できるかを確認するプロセスだ。
これら二つの試作は、自動車メーカーが単独で行うわけではなく、下請けの部品メーカーなども加わる。この量産化試作の段階で、設計図に不具合があることや、生産設備の制約で図面通りでは対応できない、といったことが判明することがある。そうなると開発部門と工場との間でキャッチボールを繰り返しながら最終的な仕様を固めていく。

開発思想の転換
仕様が確定するといよいよ量産である。実は自動運転の研究が進み、ソフトウェアの量が膨大に増えた今の時代になっても、この流れは大きく変わっていない。
では、バーチャル・エンジニアリングの導入で何が変わったのか。それは商品企画の段階で仕様を定める方法だ。これまでは、ざっくりとしたイメージをもとに試作品を実際に制作して、そのイメージに少し具体性をもたせた程度で仕様が決まっていた。それがバーチャル・エンジニアリングを導入したことで、実物なしで仕様(モデル)が決り、「開発試作」が完了するようになったのだ。
自動車産業では、70年代から80年代にかけて、紙の図面がCAD(コンピューター支援設計)に置き換えられてきた。90年代半ばからは三次元CADも普及したが、バーチャル・エンジニアリングがもたらした変革は、これまでのハイテク化、デジタル化とは異なる次元だといっていい。大胆にいえば、CADは手作業をデジタル化したもので、「業務の効率化」の範疇に入る。しかし、バーチャル・エンジニアリングの導入は効率化という枠におさまらず、自動車産業の開発思想を抜本的に変えてしまった。
ドイツが標準化で先行
そして、このバーチャル・エンジアリングはドイツが圧倒的に進んでいる。関係する企業が集まるコンソーシアム「ペガサス」にはドイツ政府からの補助金も入っている。すでに欧州ではバーチャルで試験したデータが認証試験で認められているが、日本はこの点でも遅れている。ドイツは、バーチャル・エンジアリングの世界でデファクトスタンダードを握ろうとしているのだ。
さらに、欧州ではフォルクスワーゲンやダイムラーなどの完成車メーカーだけがクルマを開発するわけではない。量産部門を持たない開発会社(エンジニアリング会社)が台頭して、完成車メーカーと分業する形で担当して開発のスピードを高めている。このエンジニア会社は「頭脳集団」であり、完成車メーカーへのコンサルティングも行っている。
最近は日本メーカーも欧州のエンジニアリング会社を活用し始めており、ホンダが国内で復活させた「シビック」のエンジンはオーストリアのAVL社、車体はドイツのEDAG社が開発を一部請け負ったと言われている。
こうした動きはクルマの外観からは見えない「クルマの内側」で進んでいる話だが、そこでも大きなパラダイムシフトが起ころうとしているのだ。










