1979年東京生まれ。東京大学経済学部卒、同大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学。一般財団法人知的財産研究所特別研究員を経て、現在駿河台大学経済経営学部教授。専攻は経営組織論、経営情報論。Debian公式開発者、GNUプロジェクトメンバ、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)理事。Open Knowledge Japan発起人。共著に『日本人が知らないウィキリークス』(洋泉社)、『ソフトウェアの匠』(日経BP社)、共訳書に『海賊のジレンマ』(フィルムアート社)がある。
関連リンク(外部サイト)
記事一覧
1〜13件/13件(新着順)
 エンド・ツー・エンド暗号化に関する京都声明
エンド・ツー・エンド暗号化に関する京都声明 見えない巨象としての Sci-Hub
見えない巨象としての Sci-Hub 本気で匿名性を保つために留意すべきこと
本気で匿名性を保つために留意すべきこと ウェブで社会を動かす?
ウェブで社会を動かす? インターネットからスプリンターネットへ
インターネットからスプリンターネットへ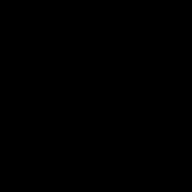 Facebookとファクトチェックという難問
Facebookとファクトチェックという難問 ベネズエラのネット検閲、日本のジャーナリズムの危機
ベネズエラのネット検閲、日本のジャーナリズムの危機 闘う図書館と情報の自由―ライブラリー・フリーダム・プロジェクト
闘う図書館と情報の自由―ライブラリー・フリーダム・プロジェクト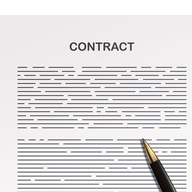 オンライン・プラットフォームを利用規約で手なずける
オンライン・プラットフォームを利用規約で手なずける 公開なくして公費なしーパブリック・マネー、パブリック・データ、パブリック・コード
公開なくして公費なしーパブリック・マネー、パブリック・データ、パブリック・コード 言論の自由とインターネットの中央集権化
言論の自由とインターネットの中央集権化- やましくなければプライバシーは要らない? nothing to hideを巡って
- 開始にあたりごあいさつ
- 前へ
- 1
- 次へ
1〜13件/13件





