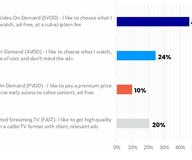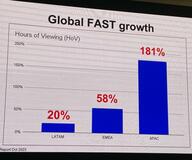ラーメンは宇宙だったけど、作っている人はもっと宇宙だった

誰でも映像が撮れ、発信できる時代に、テレビ屋にとってモノを作るベースとはいったい何なのか、、、。シリーズ4回目となる今回、そんな疑問に答えてくれたのは現在、公開中のドキュメンタリー映画「ラーメンヘッズ」のプロデューサー、大島新(オオシマ・アラタ)氏だ。テレビの世界で生きるひとりのテレビ屋であるが、映画監督・大島渚氏を父に持つ顔もある。最新作に込める想いはそう単純なものではなかった。
ラーメンは日本のアレンジャー文化の最たるもの

大島新氏の最新作である映画「ラーメンヘッズ」を知ったのは昨年、同作がトロントの北米最大ドキュメンタリー映画祭「Hot Docs(ホットドックス)」でワールドプレミア上映されたことからだった。現地でラーメンを振舞うPRイベントも行われ、評判上々という話を聞いた。何より、当初から海外展開を狙って企画されたという話に惹かれた。今年1月から日本で映画公開が始まり、プロデューサーの大島氏に直接お会いする機会を探ると、同シリーズ初回から登場するTBSビジョンの演出家、天野裕士氏が偶然にも長年の付き合いがあるという。天野氏のお膳立てでお会いできることになった。
いろいろと伺いたいことがある気持ちを抑えつつ、まずは「海外展開を狙って、何故、ラーメンをテーマにしたのか?」そんな質問から始めた。なお、「ラーメンヘッズ」をまだご覧になっていない方のために簡単に説明すると、千葉県松戸市にあるラーメン屋「中華蕎麦とみ田」の店主、富田治氏を追いながら、言葉を選ばずに一言で表すと、“ラーメンバカ”の世界が描かれているものだ。

大島氏はこう答えた。「ラーメンは日本的なんですよ。外来のものを取り入れ、異常なこだわりによって発展させていくのがいかにも日本人的。誰も頼んでいないのにそこまでやるかと思わせるほど、店主も頑張り、熱狂的なお客さんもいるから、受け手のこだわりが強まります。」
これを受けて、同席していた天野氏が「日本はアレンジャー文化ですね」と。
透かさず大島氏が続けた。「アレンジャー文化。まさにそうですね。寿司や天ぷらはどれも美味しくてどれもそう変わらないけれど、ラーメンはアレンジャー文化の最たるもの。『とみ田』のようなつけ麺や『飯田商店』を代表とするしょうゆ系、他にもとんこつ、煮干し系もあります。同じラーメンとは言えないほど、アレンジしまくってますよね。そして、それぞれにお客さんがついています。」
海外ではそれが他のどこにもないユニークなものとして、興味を抱かせる。それが日本人を象徴するものにもなり、同作ではラーメンをテーマにしたということだ。

狙い通り、3月16日のニューヨークとロサンゼルスでの公開を皮切りに、米国内では20都市近くで公開が決定している。ヨーロッパからも引き合いがあり、「今後も増えていきそうな勢い」という。アメリカでヒットした日本を題材にした映画には伊丹十三監督の『タンポポ』やNY出身の若い映像ディレクターによる『二郎は鮨の夢を見る』がある。『タンポポ』は約40館、『二郎~』は約80館で公開されており(米「Box Office Mojo」公表数字を参考)、「目指せ、タンポポ、二郎です」と期待を込めて大島氏が口に出して言った。
うまく転がり始めている背景には、海外と契約交渉ができる共同プロデューサーを立てたことも大きく、その結果、条件が合うNYのエージェントとの直接契約に繋がり、海外配給が広がっている。一方、自分たちでハンドリングできる体制のデメリットとして、映画祭のエントリーから何から何まで自分たちの手で進める作業などが増えるが、展開先の全てのライツを保有し、Netflixなど世界配信も柔軟に仕掛けることができるメリットは大きい。聞くと、実際にそんな展開も見据えている。海外展開を狙うひとつのノウハウがここにはある。
テレビ局に感じるストレスを解消するために作った
さてここら辺で、大島氏が考えるモノ作りの哲学にも触れていきたい。けれども、大島氏は寡黙で冷静といった印象を受ける。なかなか聞き出せないままにいると、天野氏が大島氏について話し出した。
「テレビの世界では基本的に視聴率二桁超えが求められますが、ある時、大島さんは『二桁を超えるために、視聴者に媚びるような番組を作る仕事はやりたくない。それができないテレビ屋は嫌ですね』とおっしゃったんです。えらく共感し、面白い方だなと改めて思いました。」
それを聞いた大島氏は一度笑い、真顔に戻って話し始めた。「『ラーメンヘッズ』はある意味、テレビ局と付き合っているなかで感じるストレスを解消したいと思って作りました。自分と同様にテレビマンでもある重乃康紀監督も同じ想いを抱えています。テレビ企画の場合、どうしたって常にストレスがあります。企画を世の中に出すためには局のプロデューサーがいるので、フリーハンドで作ることはなかなかできないのです。視聴率のこともあるし、ナレーションから落としどころまで、決められたフォーマットの中で作る必要性にかられ、作り方の幅が狭くなります。時にはモノ作りがわかっていない局のプロデューサーに頭を下げなくてはいけない。もちろん、お世話になっている優れたプロデューサーもいますが、最近はそういう方になかなか出会うことができない。だから、『ラーメンヘッズ』は面白がって作ることにしました。自分が面白いと思うものを大事にしたい。その延長線上の先に視聴者がいると信じています。」

例えば、語りのプロではない監督の重乃氏がナレーションを担当している演出などが、テレビの企画では成立しない。だからそれを敢えてやっている。映画の中で2度も出てくる「松戸というこれといって特徴のない街に」というフレーズなんかがまさにそうだ。ドキュメンタリーを放送する番組では通りにくい表現だが、松戸出身の私は失笑しながらも妙に納得してしまった。映画に協力する松戸市からも理解を得たという。
こうした演出につい天野氏も独自に解釈する。「舞台が京都であり過ぎる京都では文学にならないけれど、『これといって特徴がない』と表現できる松戸にこそ文学を感じます。ラーメンを題材に海外展開されていることにもミクロとマクロの互換性がありますよ。ラーメンを題材にすることによって、自分たちが演出する手法そのものが宇宙のような存在であるラーメン化していくと、そんな感覚を覚えました。一見、相反するようにみえるものが実は互換的なんですよ。」
目立って自分の価値を上げることで、モノ作りの幅が広がる
しかし、厳しい現実もある。海外展開は走り出しているはいるものの、日本における興行成績だけでは現在のところ回収のメドは立っていない。「腹ペコ男子映画ですからね。今の日本のドキュメンタリー市場には合わない。お客さん事情はリタイアしたご夫婦が求めるものか、沖縄や原発、LGBTなど社会問題に興味がある層がメイン。敢えて辛口に言うと、映画を観て、やっぱり問題だよねと確認させる循環でビジネスが回っています。そういうものを突破していきたいんです。」

そう熱く語る一方で、こんな本音も漏らしてくれた。「ただね、代表を務める会社の経理を妻が担っているので、妻から『道楽ばかりやっていないで、テレビで稼いできて』と言われていますがね。」これを聞いて、たまらずに天野氏も続けて言う。「いい話ですね。何もない松戸に繋がっていく話です。」
これは大島氏が抱える立場を表した言葉なのかもしれない。大島氏が「妻に言われながらも、変なことをやって、僕が目立つことに意味があるのですよ」と言うので、「はじめから目立つ存在にはありますよね」と返すと、「父のことですか?それはどうしようもないので、そこで目立っても仕方がない。今できるなかで、自分と会社の価値を上げることによって、モノ作りの幅が広がると思っています。例えば天野さんはディレクターとしての天野ブランドがありますから、現場を実際にみているわけではないですが、通りがいいはず。僕は人物ドキュメンタリーにこだわって、自分にしか撮れないもの、自分にしかできないものをテーマによって演出方法を変えながら、毎回、何がいいのか探りながら、作っていきたいです。」
『ラーメンヘッズ』も売り方としてラーメンも取り上げながら、「とみ田」の店主である富田治氏の生き様をいろいろな角度から伝えている映画だ。大島氏は「人の持つ面白さを見つめています。人間は真面目にやっていればいるほど、面白い」とも語っていた。こだわるテーマは、作り手の置かれてきた環境や生き方が自ずと影響するもの。そこから目をそらさずに突き詰めて作り続ける作品は、面白さも無限大に広がる。だから、作り手と一緒になって、ラーメンを食べる客のように私も面白がり続けたい。
画像Copyright:大島氏と天野氏写真は筆者撮影。ほか、映画「ラーメンヘッズ」場面写真より。
【大島新(オオシマ・アラタ)氏】フジテレビでキャリアをスタートした後、フリーのディレクターとしての活動を経て、制作会社ネツゲンを設立。現在、同社代表取締役を務める。代表番組にMBS『情熱大陸』の寺島しのぶ、秋元康、見城徹、田中慎弥、磯田道史などの演出。監督を務めた映画作品は『シアトリカル 唐十郎と劇団唐組の記録』と『園子温という生きもの』、最新プロデュース作品は『ラーメンヘッズ』。