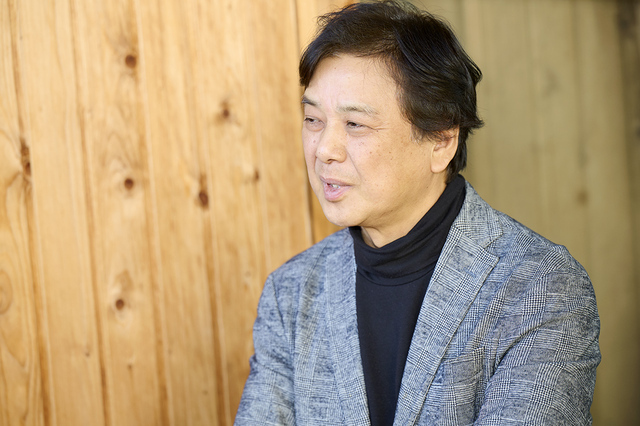なぜ理不尽な冤罪事件は起きるのか。「もうひとつの袴田事件」が伝える「境界線上」で起こる問題【鈴木おさむ×阿武野勝彦】
「名張ぶどう酒事件」は近代と現代の間で起こった
鈴木:正直言うと、僕はその根本のところを理解できていないんです。なぜ奥西勝さんは一審判決で無罪になっているにもかかわらず、二審で死刑判決が出てしまったんでしょうか? シリーズの過去の作品で、再審請求を棄却した裁判官の顔写真まで出してるのは、ドキュメンタリーの作り手側の強烈なメッセージだと思うんですが。 阿武野:「袴田事件」もそうですが、1960年代は冤罪が起こりやすい捜査環境があったように思います。強烈な自白偏重で、一度「クロ」にしたものを「シロ」にしたくない。警察と検察の間違ったプライドですね。「冤罪」は、裁判所がある意味でそこに加担してしまっている。そもそも検察が起訴した以上、有罪立証できていると思う裁判官は多いですし、先輩の判決をひっくり返す裁判官は出世コースを外れるというムードもあります。 鈴木:時代、ですか。そのときに作ってしまった「事実」を曲げたくないという。 阿武野:東海テレビ製作の『死刑弁護人』(12)で取材した安田好弘弁護士が、「事件は境界線上で起きる」と言っていました。「境界線」とは、山の手と下町、貧困と富裕などで、事件はその境目で起きるんだと。私はそれを聞いて、「名張毒ぶどう酒事件」は「近代と現代の狭間」で起こったのではないかと思いました。 鈴木:なるほど。 阿武野:非常におおらかな時代から急速に近代化していく日本の、時代の軋轢みたいなものの中で起きたのではないかと。激しく進む都市化と変わらないムラ社会の中での、突発的な出来事として。
奥西さんは「シロ」だと確信している
――取材チームはかなり長期にわたって奥西さんの弁護団や支援者、家族を追いかけていますから、当然ながら情も湧いてくると思います。意地悪な見方をするなら、奥西さん側への肩入れにつながる「偏った目線」に陥る危険性はないのでしょうか。長く密着している歴代ディレクターの事件に対する入れ込みようは相当のものだと思いますが、阿武野さんはプロデューサーとして、どんな立ち位置なのでしょう。 阿武野:この事件は、強要された自白以外に奥西さんを「クロ」と言える材料はないんです。それなのに検察は証拠物を60年たった今も全面的に開示しないし、裁判官はそれを出しなさいと言わない。ここまで論争が続いている裁判ですから、証拠物を全て出して事件を洗い直すべきです。私自身はこの事件を曖昧な「中立な視線」で見ることはできませんし、奥西さんは「シロ」だと確信しています。 もうひとつ言いたいのは、私たちは現場の村に取材に行っていて、毒入りぶどう酒の被害に遭った方の家族も含め、口の重い村人からも話を聞いています。彼らの中には、奥西さんが犯人だとはっきり断定する人もいる。でも、そう思わざるを得ない村の事情を慮っても真実はそこにはなく、事件の見方は揺るがないですね。 鈴木:「シロ」だというのは、阿武野さんはじめディレクターやスタッフの統一見解なんですか? 阿武野:スタッフは、みな「シロ」だと確信していると思います。しかし、東海テレビという大きな組織で言うなら、冤罪だと思っていない人間もいます。そんな考え方、そんな放送内容はおかしいと、過去にはかなり感情的になじられたこともありました。報道原理主義者のように凝り固まっていないので、話は聞きますが、そういう局員はだいたい「客観中立論」を持ち出してくる。「大事なのは事実なのに、くだらない立場を持ち出すんだな」と思いますが(笑)、「こちらは途方もない時間と労力を費やして取材を積み上げている。あなたは何を調べ、何を読み込んでそれを言うのか?」と反論します。 鈴木:ドキュメンタリーって、公共性の高いテレビで放映されることで、映画とはまた違った大きな責任を問われますよね。映画よりずっと多くの人の目に触れるわけですから。危ない綱を渡りたくないという人もいるでしょうし。それだけに、阿武野さんはテレビで放映することに意義があると思ってやってこられたんですよね。 ◇続く後編〔被写体に「お金貸して」と土下座されたら?「ドキュメンタリー」という表現の面白さ【鈴木おさむ×阿武野勝彦】〕では、そもそも「ドキュメンタリー」とな何なのか、またドキュメンタリー的な作品における「撮り手」と「被写体」の関係性の面白さについて語り合ってもらった。 『いもうとの時間』は2025年1月4日(土)よりポレポレ東中野、ヒューマントラストシネマ有楽町にてロードショー!
稲田 豊史(ライター、コラムニスト、編集者)