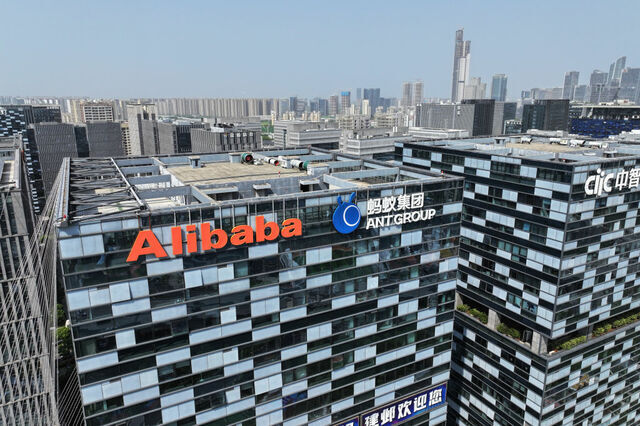6000人の応募から、残ったのは18人だけ…アリババで日本事業のトップに上り詰めた日本人が明かす「グローバルに生き残るための思考法」
すさまじいスピード感
アジアの片隅から生まれたのち、世界に名だたる企業となったアリババでは、社内でも猛烈な競争が繰り広げられ、ついていけないものは容赦なく振り落とされていった。 「AGLAで入社した18人の同期社員のうち半数は1年以内にアリババをやめていきました。とにかく競争が激しく、評価も厳密で厳しい。そのため、早期退社する人間は後を絶ちません。その厳しさを物語るのが社内表彰制度です。1年勤続しただけで、表彰されるんですよ。私自身、試用期間の3か月が終わった時点で同僚や上司から『すごいね』と言われたくらいです」 人材の新陳代謝が激しいだけでなく、あらゆる決断のスピードもアリババはとにかく早い。 「全ての決断は基本的に『その日のうち』です。日本のように『じゃあ1週間くらい揉んで…』なんてものはない。プロジェクトを進めていて何か問題があったら『責任者はあなたですね、今日か明日までに改善策を出してください』と言われる。 基本的には『できない』とは言えませんから、期限までに全力でできうる限りの対策を考える。ただ、日本のような根回し文化はありませんでしたから、無駄に時間を使うようなことはほぼなかったですけどね」 そんなアリババにはメールやチャットツールで連絡してから返事を待つ、という悠長な文化もない。 「基本は電話です。返事や反応が欲しければ、すぐ電話を使えと言われる。もちろんチャットツールもあるのですが、連絡をしてからしばらく返事がないとAIツールで相手に電話をしてリマインドするという機能が付いていました。アリババではそれくらい電話が大事です。正直に言えば、テック企業なのかよくわからなくなる文化ではありますが、スピード感が違いますからね」 当時を冷静に振り返る大山さんだが、自身も入社して間もなく、あわや退職という危機に瀕していた。 中国語はおぼつかず、すぐに電話をしろと言われても、日本で培った習慣はなかなか抜けない。『これからお電話をしてもよろしいでしょうか』と、ついメールで先に連絡をしたくなってしまう。 アリババの猛烈なスピード感になかなか慣れなかった大山さん。3か月の試用期間中の評価は「メチャクチャ悪かった」という。しかし、そんな大山さんを救ったのもアリババのスピード感だった。 「ある金曜日のことです。人事担当者に呼ばれ、これからお前はどうしていくつもりだと聞かれました。パフォーマンスの改善を求められたのです。そこで私は『週末、今後1年の改善策を考えてきます』と告げました。すると『それでは遅い、今この場で具体的な改善策を言ってください』、そう返事が返ってきました」 即決の文化がここでも現れた。少したじろいだという大山さんだが、その場で、「これからは一切英語を使わない」「次の〇〇のプロジェクトリーダーに手を挙げる」など具体的な目標を立て、心を入れ替えて行動に移した。郷に入っては郷に従えではないが、何かあれば、すぐに電話をかけるよう心掛け、実践したところ奏功し、社内でめきめきと頭角を現すようになっていったという。