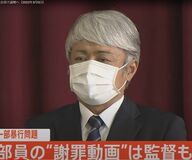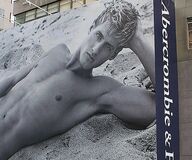もともと新型コロナはCOVID-19というのが国際名称で、2020年2月の段階でWHOが命名している(2019年にWHOに報告されたということで19が使われている)。 通常、ネーミングは「これから使うもの」に付けるもので、何らかの強い意向がなければ、今回のように「これまでのもの」に新たに付けることは少ない。そして、「コロナ2019」という、かなり時間の経過した過去の年号を使うことで、「過去のもの」という印象が生まれることは明らかだ。 COVID-19という名称が命名されたころなら、-19以外の名前が出てくる可能性も考えられたのだろうが、今の時期に「2019」という名前を付けるのは、その可能性を意識したというよりも、ソフトウェアのネーミングのようにあくまでも「最新ではない」という印象を作り、経済活動を重視して世の中を新しいムードにしようと意図していると考えるのが自然だろう。
同じ記事に対する他のコメンテーターコメント
コメンテータープロフィール
シリーズ60万部超のベストセラー「頭のいい説明すぐできるコツ」(三笠書房)などの著者。ビーンスター株式会社 代表取締役。社会構想大学院大学 客員教授。日本広報学会 常任理事。中小企業から国会まで幅広い組織を顧客に持ち、トップや経営者のコミュニケーションアドバイザー/トレーナーとして活動する他、全国規模のPRキャンペーンなどを手掛ける。月刊「広報会議」で「ウェブリスク24時」などを連載。筑波大学(心理学)、米コロンビア大学院(国際広報)卒業。公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会元理事。防災士。
鶴野充茂の最近の記事
アクセスランキング
- 1
鷹・柳田悠岐は「右半腱様筋損傷」で全治4か月 球団発表…今季絶望の可能性も
Full-Count
- 2
中途採用の3割が経歴詐称? 「部長職10年」ではなく「アルバイトを転々」…それでも簡単に解雇できない企業の防衛策は
ABEMA TIMES
- 3
日本ハム・新庄監督 2戦連続被弾の守護神・田中正義の配置転換を明言「良いときの正義くんに戻るまでは」3戦連続失点で決断 代役抑えは日替わり起用に
デイリースポーツ
- 4
ロッテ 2試合連続サヨナラで19年ぶり11連勝!15戦負けなし 愛斗がサヨナラ打
スポニチアネックス
- 5
【訃報】俳優・本橋由香さん死去 原発不明がんで闘病中「水曜日に体調が急変して帰らぬ人となりました」
TBS NEWS DIG Powered by JNN