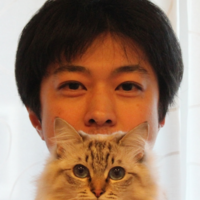補足冷凍食品の本格的普及は、1964年の東京オリンピックから始まりました。選手村で提供する食事に冷凍肉・魚介・野菜が活用され、生鮮食品を使った料理と遜色のない出来映えで各国の選手から大好評だったことから、それまでの「冷凍食品は不味い」というイメージが払拭されていきました。 家庭での普及は、冷蔵庫と冷凍庫が分かれた2ドア式冷凍冷蔵庫が一般化した1970年代以降。それまでは冷蔵庫の庫内に小さなフリーザーがついた1ドア式が主流で、冷蔵庫の普及率も1965年でやっと50%と低かったのです。 1980年代後半から電子レンジ普及率が伸び、90年代からはレンチンで食べられる商品が登場。冷凍惣菜のバリエーションは急増していきました。 それでも冷凍食品に偏見を持つ層は一定数いましたが、コロナ禍で買物回数が減って試してみたことをきっかけに、とりわけ冷凍野菜の便利さ、優秀さに気づいた人が多いようです。
コメンテータープロフィール
『シェフ・シリーズ』と『暮しの設計』(ともに中央公論社)の編集長をつとめるなど、プロ向きから超初心者向きまで約300冊の料理書を手がけ、流行食を中心に近現代の食文化を研究・執筆。第3回「食生活ジャーナリスト大賞」ジャーナリズム部門大賞受賞。著書に『熱狂と欲望のヘルシーフード−「体にいいもの」にハマる日本人』(ウェッジ)、『ファッションフード、あります。−はやりの食べ物クロニクル』(ちくま文庫)、『〈メイド・イン・ジャパン〉の食文化史』『カリスマフード−肉・乳・米と日本人』(ともに春秋社)などがある。編集プロダクション「オフィスSNOW」代表。
畑中三応子の最近の記事
畑中三応子の最近のコメント
中身はチーズだけ 農協系スーパーの「中華まん」が売れ続ける理由
十勝毎日新聞 電子版
アクセスランキング
- 1
裁判の傍聴席が満員「この人たちはどこから来たのか?」違和感から重ねた取材 地裁に通い続け、尾行、質問状、記者会見。粘り強く不祥事を明らかにした2か月半
47NEWS
- 2
巨人移籍で15戦連続無失点「なんで放出した」 トレードで無双する27歳は「想像を超えた」
Full-Count
- 3
橋下徹氏「眞鍋さんが正しい」都知事選、蓮舫氏発言「ウンザリ」指摘の眞鍋かをりに同意「意味不明になる」
よろず~ニュース
- 4
『ぽかぽか』生出演の57歳女優、驚きの最新ショートカット姿「美魔女って言葉の最上級」「若い頃より今の方がキレイ」
中日スポーツ
- 5
「家政婦のミタ」長女役・忽那汐里が雰囲気ガラリ!別人のような衝撃姿…「イメージ変わりすぎ」の声も
スポーツ報知