大賞受賞作
目の見えない白鳥さんと
アートを見にいく
川内有緒
「白鳥さんと作品を見るとほんとに楽しいよ!」
友人の一言で「全盲の美術鑑賞者」とアートを巡るというユニークな旅が始まった。視覚や記憶の不思議、アートの意味、生きること、障害を持つこと、一緒にいること。そこに白鳥さんの人生、美術鑑賞をする理由などが織り込まれ、壮大で温かい人間の物語が紡がれていく。
お使いのInternet Explorerは古いバージョンのため、ご利用いただけません。
最新のバージョンにアップデートするか、別のブラウザーからご利用ください。
Yahoo!ニュースは2022年度を持ちまして「Yahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞」の協賛を終了いたしました。長年にわたり本サイトをご利用、ご支援いただき誠にありがとうございました。
目の見えない白鳥さんと
アートを見にいく
川内有緒
「白鳥さんと作品を見るとほんとに楽しいよ!」
友人の一言で「全盲の美術鑑賞者」とアートを巡るというユニークな旅が始まった。視覚や記憶の不思議、アートの意味、生きること、障害を持つこと、一緒にいること。そこに白鳥さんの人生、美術鑑賞をする理由などが織り込まれ、壮大で温かい人間の物語が紡がれていく。
2022年のノミネート作品が決定しました。全国の書店員さんが選んだのは、この6冊です。果たして大賞に輝くのはどの作品でしょうか? みなさんも実際に読んで予想をしてみてください。
作品名は50音順
出版社からのコメント 2014年、朝日新聞を次々と大トラブルが襲う。「慰安婦報道取り消し」が炎上し、福島原発事故の吉田調書を入手・公開したスクープが大バッシングを浴びる。著者は「吉田調書報道」の担当デスクとし、スクープの栄誉から「捏造の当事者」へと転落。保身に走った上司や経営陣は、次々手のひらを返し、著者を責め立て、すべての責任を押し付けた。戦後、日本の政治報道やオピニオンを先導し続けてきた朝日新聞政治部。その最後の栄光と滅びゆく日々が、登場人物すべて実名で生々しく描かれる。
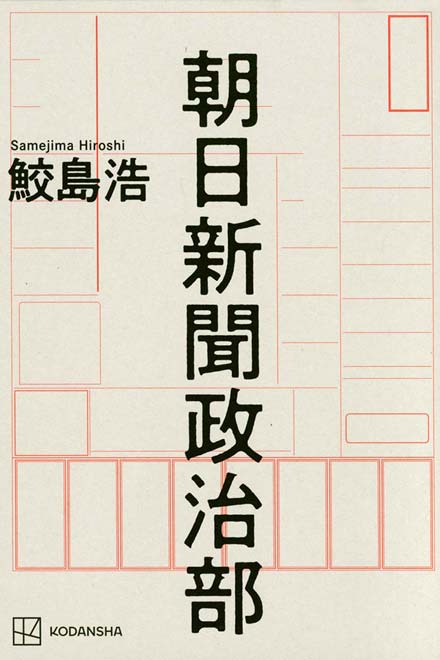
出版社からのコメント いま、球界で名将と呼べる監督はいるのだろうか。いるなら、それはどのような人物なのだろうか。この本はそうした思いから始まっている。善悪や是非、白か黒か。鈴木忠平さんはいずれにも偏らず、取材対象との間合いを保つことに努めた。その結果生まれたこのノンフィクションは、プロ野球選手がレギュラーであり続ける覚悟、ライターがものを書くことの覚悟、そして落合博満監督の、勝つために嫌われる覚悟を鮮烈に描き切っている。それにしてもこの本が持つ力は何であろう。一体、何人の人生を変えるのだろうか。
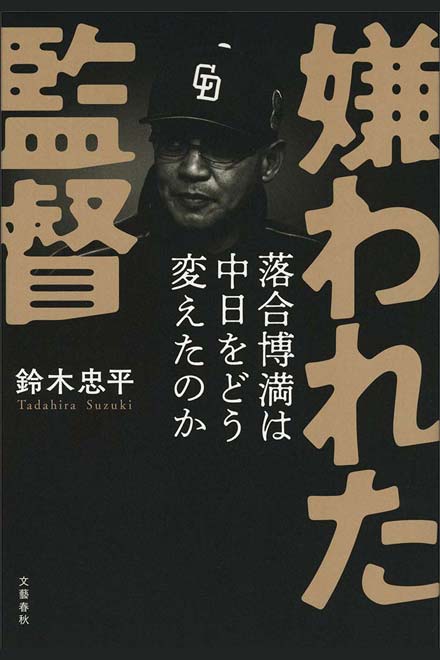
出版社からのコメント 様々な社会活動で知られる「アルピニスト」野口健。著者は作家を志しながらも野口のマネージャーを勤め、18年間で3回、事務所への出入りを繰り返した。「縁切り」を覚悟して書かれた本書では、野口の真実の姿と、その映し鏡のような著者の半生が赤裸々に語られる。野口は登山家としては三・五流なのか。なぜ、橋本龍太郎隊が置いてきた酸素ボンベをエベレストから持ち帰ったのか。なぜ、選挙で小池百合子を応援し続けたのか。そして、野口と著者が別離と和解を繰り返した理由とは。二人の魂の彷徨を綴った、新しいノンフィクションです。

出版社からのコメント 1945年夏――。日本の敗戦は満州開拓団にとって、地獄の日々の始まりだった。崩壊した「満州国」に取り残された黒川開拓団(岐阜県送出)は集団難民生活に入った。しかし、土地を奪われた恨みなどから、現地民の襲撃は日ごとに激しさを増していく。団幹部らは進駐していたソ連軍司令部に助けを求めたが、今度は下っ端のソ連兵が“女漁り”や略奪を繰り返すようになる。頭を悩ました団長たちが取った手段とは……。被害者女性らへの綿密な取材を通して、恐るべき「歴史の闇」の全貌を解き明かします。第19回開高健ノンフィクション賞受賞作。

出版社からのコメント 結婚4年目、29歳のときに異変をきたした妻に寄り添い続けた日々が克明に描かれる、朝日新聞記者によるルポルタージュです。摂食障害、アルコール依存、そして46歳で認知症に。その壮絶な介護体験は、朝日新聞デジタルの連載時から大きな反響がありました。執筆の後押しをしたのは妻の「ぜひ書いてほしい。私みたいに苦しむ人を減らしたいから」という言葉でした。静かな筆致で綴られる二人の姿から、あなたは何を感じとるでしょうか。本書が広く読まれることで、社会のサポート体制が充実し、家族の愛情頼りになるのではなく、誰もが生きやすい社会が実現すればと強く祈らずにはいられません。

出版社からのコメント 「目の見えない人とアートを見る?」タイトルへの素朴な疑問は、やがて驚きとともに解消されます。全盲の白鳥建二さんと現代アートや仏像を前に会話するたびに現れるのは、これまで見えていなかった世界。生と死、障害を持つということ、差別意識、夢について、アートの力……。まるでその場で一緒に鑑賞して、おしゃべりをしているかのような読書体験のなか、常識が気持ちよく覆され、知らなかった自分自身も姿を現します。数多くのアート作品画像や、本に隠された仕掛けもお楽しみください。

『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』の著書、川内有緒さんインタビュー
2022年の「Yahoo!ニュース|本屋大賞ノンフィクション本大賞」は、川内有緒さんの『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』(集英社インターナショナル)が受賞しました。この作品は、川内さんが全盲の白鳥建二さん(53)とアートを巡った旅の記録をつづったもの。白鳥さんは2歳から全盲で、20年以上も前から美術鑑賞を続けています。そんな白鳥さんとの交流を経て、「それまで見えていなかったものが見えてきた」と語る川内さんに話を聞きました。目が見えていても、見えていないことがたくさんある――。
全国の書店員さんが選ぶ「Yahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞」(ノンフィクション本大賞)。その歩みは1年を代表する傑作とともにありました。作家さんはどんな思いを持って書いたのでしょうか?贈賞式スピーチに触れながら、歴代受賞作品をプレイバックします。


(写真:元木みゆき)
事実を調べない、調べられないで明らかにされなかった事実っていうのは、ないのと同じです。(贈賞式スピーチより)
この年、ヤフーと本屋大賞が協力し、ノンフィクション本大賞がスタートしました。専門誌などの減少で、作品発表の機会が減った書き手を応援したい。そんな願いが賞の創設にこめられています。全国の書店員さんが選んだノミネートは10作品で、初年度の大賞に選ばれたのは角幡唯介さんの『極夜行』でした。太陽が昇らない北極圏の「極夜」を4カ月歩いた記録は、巧みな文章表現と構成力で読者を引きこみます。全編に渡って暗闇を描いた物語は豊かそのもので、日本の冒険ノンフィクションという分野に新たな1ページを切り拓きました。角幡さんは贈賞式で力の入ったスピーチも披露。シリアで武装勢力から拘束の後解放された、ジャーナリスト安田純平さんをめぐって、「事実を明らかにすること」の重要性を訴えています。北極圏を舞台にした角幡さんの冒険はいまも続いていて、2022年に『裸の大地 第一部 狩りと漂泊』(集英社)を刊行しています。


(写真:高橋宗正)
「排外主義の大元には『無知』がある。それを恐怖、恐れという火でたきつけると抽出されるのが憎悪であり、ヘイトなんだよ」っていうのがあるんですよ。(贈賞式の対談より)
2年目のノンフィクション本大賞。ノミネート6作品から受賞作に選ばれたのはブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』でした。イギリス在住のブレイディさんには息子さんがいます。彼が進学先に選んだのは、かつて「底辺中学校」と呼ばれた学校でした。ブレイディさんは、経済格差や人種、性的マイノリティなどの問題に向き合う息子さんとのやりとりを通じて、いまという時代の態度・倫理感を読者に提示します。軽やかなタッチで書かれた内容は女性をはじめ幅広い世代に読まれて、累計100万部(文庫版ふくめ)を達成しています。異例の大ヒットは、相手の立場に立って考える「エンパシー」や「誰かの靴を履いてみること」などの言葉が使われるきっかけにもなりました。昨年、続編で完結編にあたる作品も刊行されています。贈賞式では前年受賞者の角幡唯介さんと対談。「排外主義」に飲みこまれないために、他者と関わることの大切さを話してくれました。


(写真:高橋宗正)
一回限りの人生ですが、ノンフィクションを読めば、そこには先を行く人がわたしたちの行く手を照らしてくれています。一回限りの人生ですが、5倍にも10倍にも、100倍にも人生が豊かになる可能性を秘めています。(贈賞式スピーチより)
コロナ禍が世界を襲ったこの年、大賞に選ばれたのは佐々涼子さんの『エンド・オブ・ライフ』でした。病に冒され、人生の最期は自宅で過ごす人々を7年かけて追った作品で、取材対象者のなかには佐々さんの母親がいます。そして友人で、訪問看護師男性の森山さんも描かれます。訪問看護師として数多くの「看取り」を経験してきた森山さんは末期がんを患います。困惑し、取り乱しながら、自らの最期を受けて入れていくまでの過程が透き通るような文章で綴られています。家族や医療従事者らの声も丹念に取材した作品が語りかけるのは、人の看取りとは看取る側にとって「命のレッスン」でもあるということです。作品の終盤、ある病室での描写が続きます。いままさに命を終えていこうとする人に、看取る側がかけていく言葉の数々が胸に迫ります。佐々さんは、贈賞式で亡き友人に対し「自分をこんな場所に連れてきてくれた」ことを何度も感謝していたことが記憶に残っています。


(写真:高橋宗正)
残されたのはただひとつの希望です。それは「私たちはまだ正義や公平、子どもたちに託したい未来を手放さない」ということだと思います。(贈賞式スピーチより)
昨年の大賞は、上間陽子さんの『海をあげる』でした。沖縄出身で、子育てをしながら普天間基地のそばで暮らす上間さんは、こう語ります。「本土への果たし状のつもりで書いた」と。沖縄。かつての太平洋戦争で凄惨な地上戦が行われ、多くの犠牲者が出たこと。その後も米軍基地の問題に翻弄され、反対の民意が示されながらも辺野古への基地移設工事は続いていること。本土との経済格差、DVに晒される若年女性たちのこと。本が訴えるのは沖縄が置かれた過酷な現実です。辺野古の海へのやむことのない土砂投入に対し、幼い娘さんは上間さんにこう問いかけます。「海に土を入れたら、魚は死む?ヤドカリは死む?」......贈賞式での上間さんは、とても穏やかにスピーチをしていたのが印象的でした。そのことがかえって本書の凄みとして伝わってきました。受賞後、『海をあげる』の反響は広がって8万部を超えるヒットを生んでいます。
受賞の言葉 川内有緒さん
小学生の頃、家の前に小さな書店があり、私はほぼ毎日そこで立ち読みして過ごしていました。今年50歳になりましたが、本という存在は、良い時も苦しい時も私を支え、力を与えてくれました。読むこと。書くこと。本がただそこにあること。家の本棚に。そしてポケットに。
このたび、書店員の方々が選ぶ賞を授かるという望外の出来事に心から感謝しています。今回の本を書くことは、他者との出会いや会話を通じて世界の輪郭を捉え直し、自分自身のまなざしが変わっていくような体験でした。書くことは楽しい。楽しいけど、苦しい。その間を行ったりきたりしつつ、これを糧に、また未知の地に向かって歩み、書き続けたいと思います。
撮影:齋藤陽道