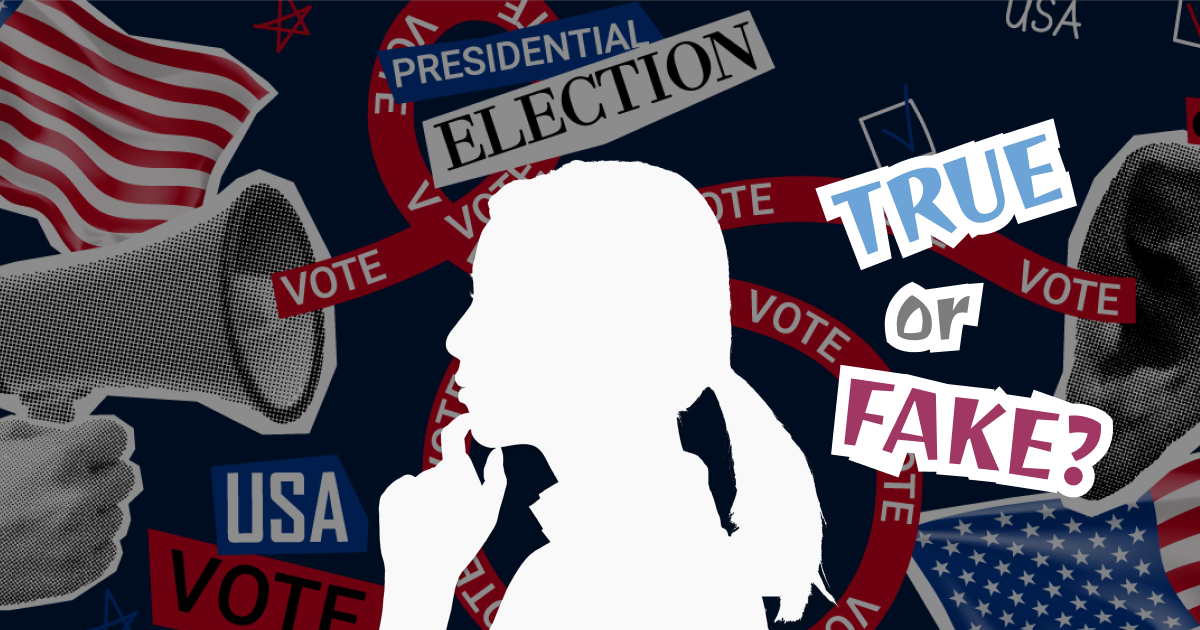「2022年ノンフィクション本大賞」は川内有緒さん『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』に決定――「わかりたいけどわかり合えない。その間をせめぎ合いながら、一緒に生きていく道を」

ノンフィクション本を応援する「Yahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞」が、今年で5回目を迎えました。最終ノミネート6作品のなかから全国の書店員さんによる投票で大賞に選ばれたのは、川内有緒(かわうち・ありお)さんの『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』(集英社インターナショナル)でした。この作品は、川内さんが全盲の白鳥建二さんとさまざまな美術館を訪れ、絵画や仏像、現代美術を前に会話を繰り広げる内容です。話は、美術作品への言及にとどまらず、生と死、障害、差別、生きることそのものにも及んでいきます。白鳥さんとの美術鑑賞が開くのは、これまで見えてこなかった世界そのものです。ここに川内さんの受賞スピーチ全文を公開します。
構成・文:笹川かおり
写真:高橋宗正
川内有緒さん受賞スピーチ
みなさん、こんにちは。ノンフィクションを書いている川内有緒と申します。
この度は「全国の書店員さんが選ぶ」という、とっても光栄で、とってもあたたかい気持ちになる賞を授かって、本当にありがとうございます。すごく大きな喜びもあり、同時にすごく大きな、さらに大きな驚きに、自分はいま包まれています。
というのも、この本は本当にタイトル通りストレートな本でして、全盲の白鳥建二さんという男性と、私と、友人の佐藤麻衣子さんという3人が、バンドメンバーみたいな感じで日本全国の美術館を巡って、作品を前にしていろんなおしゃべりをする。そういう本なんですね。本の8割くらいが、作品を前にして何を考え何をしゃべったか。言ってしまえば、本当にそれだけの本なんです。

書店員さんから川内さんにトロフィーを授与
でも、この本を書店員のみなさんが「推したい」「読んでほしい」と考えてくださった。その理由について私はずっと考えてきたんですけど、きっとそれは本が面白いとか、白鳥さんの生き方がユニークだとか、アートが素敵だとか、そういう個別の理由ではなかったんじゃないかなと考えています。
多分この本をきっかけにして、私たちはどういうふうに生きたいのか。どういうふうにして、他の人と、背景が全然違う生き方をしてきた人たちと、付き合って、友達になって、生きていきたいのか。この社会はどうなっていったらいいのか。そういうことを考えてくださった方がいるんじゃないかなと私は想像しました。
ちょっとだけ、私と白鳥さんがどうやって出会ったのかをお話ししたいと思います。白鳥さんは、共通の友人の、美術館に勤める佐藤麻衣子さんが紹介してくれて。そのときは、本を書こうという気持ちでお会いしたわけではなくて、ただ「白鳥さんっていう人がいて、目が見えない人なんだけど、アートが好きで、一緒に見ると楽しいよ」と言われて。「楽しい」の意味はわからなかったけど「じゃあ行こう行こう」みたいな感じで始まって。
ただ、その日になって、地下鉄の中で初めて「え、目が見えない人が作品を見るってどういうことなんだろう?」と考え始めたんですね。実際、美術館に着いたら、白鳥さんとマイティ――佐藤さんのことを私はマイティと呼んでいるんですけど、マイティがいて。白鳥さんが「じゃあ、では、お願いします」と。そのときに初めて白鳥さんって人は、言葉で、耳で、会話でアートを見る人なんだと理解しました。

左からマイティさん、川内さん、白鳥さん
私たちは作品を前にしていろんな話をするんですけど、初めて見る作品ばっかりなので、合ってるか間違ってるか全然わからないままに、「こういう感じに見える作品で、きっとこの人はこんなことをしてて、私はこんなふうに感じるけど、マイティはどう?」って言うと、マイティは「うーん、私は……」。そんな感じで話が進んでいったんですね。
でも途中で、「この話でよかったのかな? 考えてみたら、私が言ってることって間違いだらけだったりするんじゃないかな?」と、ちょっとだけ心配になったんですけど、白鳥さんは「面白いね」と。「あれ、どういうことなんだろう?」と思ったら、白鳥さんがエンジョイしているのは、作品そのものの解説ではなくて、そこにいる人たちの会話、間違ってるか合ってるかもわからないその会話のライブ感とか、すべてをひっくるめて楽しんでいるんだということが分かりました。
それからすごく楽になって、こんなふうにアートって見ていいんだなと分かって。また、マイティは美術館で働く人でありながら「作品はどういうふうに見ても自由なんだ」と結構強い信念を持っている人で。そこにも影響されて、我々は3人で、「もうちょっと作品を見ていきましょう」ということで美術館をいろいろ巡りました。

以上のことから分かるように、この作品はとくに読み終わった後に、めちゃくちゃ深い感動を覚えるとか、ドラマがあってスペクタクルがあってクライマックスがあって……みたいなものはありません。いろんな会話がただ淡々と流れてく、そんな本だと思うんですね。これを聞くと「え、そんな本なの?」と思うかもしれないけど、そういう本が大きな賞に選ばれることに、私は逆に希望を見出す瞬間があるんです。
というのは、これは別に私が白鳥さんを助けてあげる話でもないし、白鳥さんが何か大きな困難を乗り越えるわけでもない。日常がただくり返されていくような本なんですけど、やっぱりそういうものこそが本当のものというか。
私たちの日常は、ドラマやスペクタクルにあふれているわけではなくて、障害がある人もない人も、同じように毎日淡々と日常を送って、その中で楽しみを見つけている。そういうことを実は描きたかった、というのがありました。
よく障害がある人がメディアで取り上げられるというと、やっぱり何か難しいこと、困難を乗り越えたり、何かを克服したりとか、そういうことが描かれることが非常に多くて、それはそれでもちろん素晴らしいことで、私も心を動かされることも多いけれど、それがあまりにもくり返されたり強調されたりした結果、我々の頭の中に、ある種の「障害は乗り越えるべきなんじゃないか」とか、他の人と同じように、障害がある人だけじゃないですね――例えば困難を抱えている方も、「それを乗り越えるために、努力するべきなんじゃないか」という考え方が、社会の中に蔓延しているんじゃないかという思いを抱えるようになって。

全国の書店員さんから会場に手描きPOPが届きました
でも、実際、果たしてそういうものなのかなって。ちょっと疑ってみてもいいんじゃないか。そういうことを考えながら、この本を書いていました。
私は私で、未熟で、偏見に満ちていて、無知でわからないこともたくさんあって。そういうことを一つひとつ考えていった「自分そのもの」も、きっとこの本に書いていかないといけないのかなって思いました。それによって、他の読んでくださったみなさんも「自分の内なる偏見に気づいた」とか「自分の気づかなかった点に気づきました」みたいにおっしゃってくれる方もたくさんいて、私も勇気づけられます。
白鳥さんを、ありのままに描いていきたいなという気持ちが私の中でありました。白鳥さんはとてもチャーミングな人で、酔っ払うと写真をいっぱい撮っちゃって、それが何十万枚もハードディスクにたまっちゃったりとか、酔っ払って路上で前後不覚になっちゃったりとか。すごくユニークな人物で、そういうところも伝えていきたいなと思いました。
今日まで、いろんな感想をいただきました。「アートの見方が変わった」とか「自分のなかの偏見に気づいた」とか。「誰かと喋りたくなった」「会いたくなった」「美術館に行きたくなりました」、そんな感想をたくさんいただきました。

川内さんとヤフー株式会社メディア統括本部長の小林貴樹
それと同時に、疑問を呈する感想もいくつかいただきました。そのうちのひとつが、「美術館はやっぱり静かな方がいいんじゃないか」。「美術館で会話をする人は迷惑だから、自分は受け入れられない」という方もいらっしゃいました。一見すると、まあそうだな、なるほどなと思う意見ではあるんですけど、そういうことも、実は本当にそうなのかな、それでいいのかなって少し考えてみてもいいのかなと私は思うんですね。
というのも、美術館というとひとつのくくりになってしまうんですけど、やっぱり美術館にはいろんな美術館があって、美術館にも多様性がある。我々が一人ひとり違うように、美術館も違う。「すべての美術館でお話をしましょう」ということではなくて、会話しても問題ない美術館では会話をすればいいし、むしろ積極的に喋りながら見たら面白い作品もたくさんある。

アートといっても、クラシックから現代美術まで本当にいろんなものがあるのですが、「美術館はこう」「これはこうあるべき」って決めつけてしまうと、やっぱりその決めつけが、どんどん窮屈な空気感を生んでしまい、時として社会の選択肢を減らしてしまう。やっぱり私は「こうだから、全部こう」と簡単にひとつのものにまとめ上げない、複雑な社会を受け入れていくことをしていかないといけないんじゃないか、と思うんですね。
これは美術館の中に限ったことではなくて、すべての場所に言えることだと思うんです。電車とか公園とか、大きいところでは国会とか。いろんな人がいろんな場にいられる。一緒にいることができる。
日本の場合は、「他の人に迷惑をかけない」とか「迷惑をかけたくない」という意識がすごく強くて。その空気感が積み重なると、回り回って、我々が生きる場所をどんどん息苦しいものにしてしまうと思うんです。それが積み重なると、いまある選択肢もなくなってしまい、選択肢が1だったものが0になってしまうこともときにある。でも逆に、選択肢を0から1、1から2に変えていく。そういう社会の発展の途上にあるのではないかと思います。
 トークセッションで話す白鳥建二さん
トークセッションで話す白鳥建二さん
とにかく、そんなことを考えながら私は本を書いていたんですけど、当の白鳥さんは「社会を変えよう」とか「枠組みを変えよう」とかは思っていなくて、自分自身が楽しいから美術館に行っているだけ。それがいいところで、私たちはいろんなことを考えてはいたけれども、究極的には楽しくみんなで美術館を巡ってきた。そういうお話です。
私にとってノンフィクションを書くのは、自分自身がこの時代を生きている、いろんな人と関わっていく、一つのやり方、ツールと考えています。
私たちは、一人ひとり違う生き方をしていて、価値観を持っていて、体のあり方、心のあり方も違っていて。私は他の人になれないし、他の人も私になることはできない。だから時として、私たちはなかなか話し合っても、わかり合えない部分がすごく大きいのですが、それでもわかり合えないけどわかりたい。わかりたいけどわかり合えない。その間をせめぎ合いながら、その切なさを抱えながら、私たちはなんとか一緒に生きていく道を探さないといけないと思います。
そんなこともあって時として、自分には自分が生きる社会が、なんというか荒野のような場所に見えてくるんですね。そこには希望もいっぱいあって。同時に絶望もいっぱいあって。希望と絶望が同居しているような感じがしています。
ノンフィクションの書き手はいろんな方がいらっしゃるんですけど、私は自分の性格的に楽しいことが好きなので、私はどちらかというと希望の方を、希望とか夢とか愛情とかをより集めるようにして、いままで本を書いてきました。
ただ、そういう本を書いて、石みたいにして精一杯遠くまで投げたとしても、そんなに遠くには届かないんじゃないかと思っていた瞬間もありました。とくにこの本は「アート」と「会話」をテーマにした一風変わった本なので、そこまで読まれないんじゃないかとずっと思ってきたんですね。でも、現実には大勢の方が読んでくださって。いまこうして遠くの方までその石が届こうとしていることに心から感激しています。
 2022年の最終ノミネート6作品が並びました
2022年の最終ノミネート6作品が並びました
長くなってしまったので、あらためて最後にお礼を言いたいと思います。
まずはずっと一緒に旅をしてくれた、白鳥建二さんと佐藤麻衣子さん、本当にありがとうございました。
あとは、たくさんの人がこの旅に同行してくれて本の中に登場してくれました。今日はここにはいないけれども、その友人たちにもありがとうを伝えたいと思います。そして、たくさんのアート作品が出てくる本です。アーティストや何かを伝えようとして表現してきた人たち、美術や文化を愛してきた人にもあらためてお礼を言いたいです。
またこの本を出すために、本当にたくさんの力を貸してくれた編集者の河井好見(かわい・よしみ)さん、集英社インターナショナルのみなさん、そして最後に、この本をこんなに遠くまで連れてきてくださった全国の書店員のみなさん、読者のみなさん。本当にありがとうございました。
この感謝を胸に、これからも書き続けていきたいと思います。本日はありがとうございました。
授賞式を終えて
ノンフィクションでありながら、同時に“自分そのもの”も描ききった川内さん。スピーチ後、“バンドメンバー”3人のトークセッションでは、「答えは簡単には出ない。一生かかって一つ一つの答えを探し続ける。わかったと思った瞬間に閉じてしまう。いろんなことに常にオープンであり続けたい」とその姿勢を語りました。
今回、川内さんには大賞トロフィーに加えて、取材支援費100万円が贈呈されました。
お問い合わせ先
このブログに関するお問い合わせについてはこちらへお願いいたします。