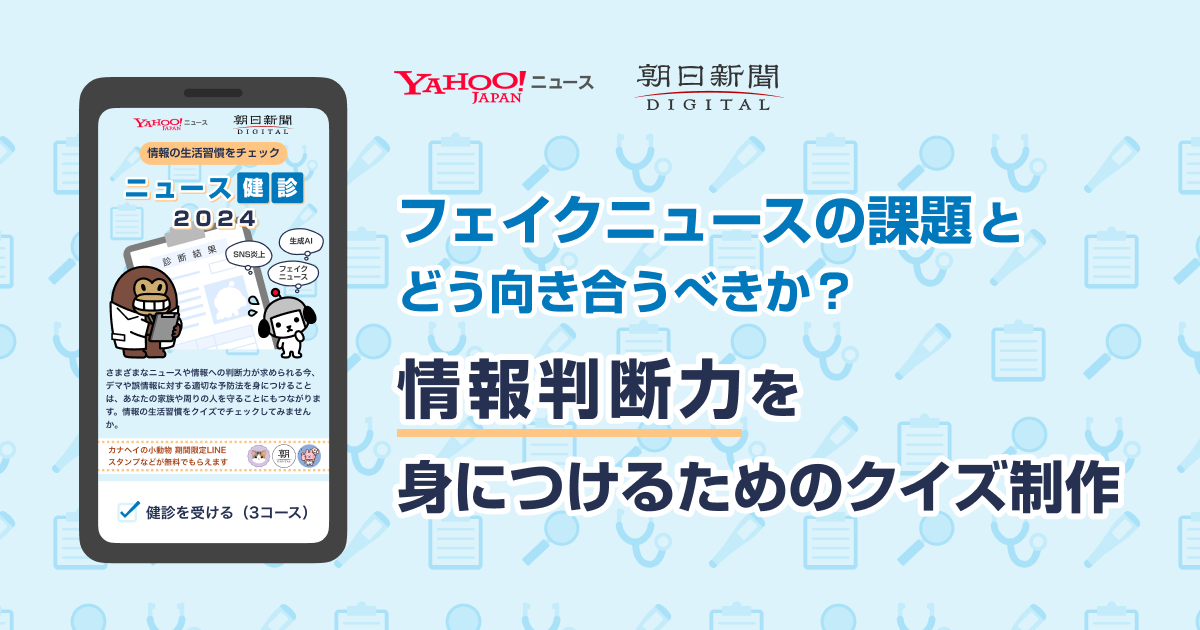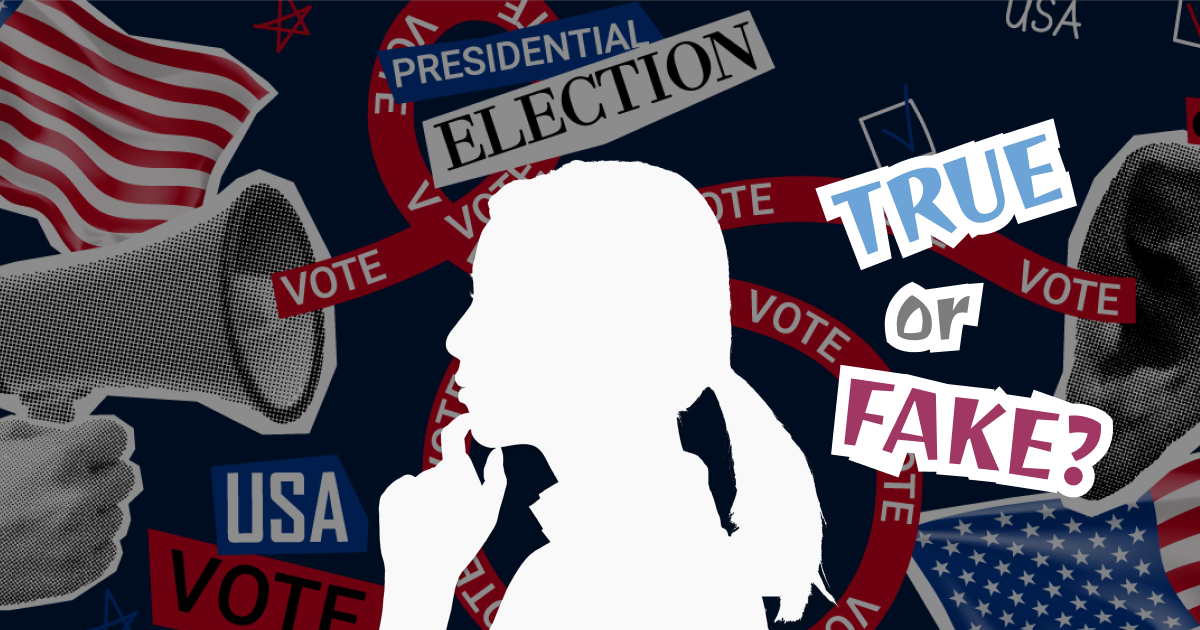「科学ジャーナリスト賞」を受賞した経口中絶薬の特集連載はどう生まれたのか

日本科学技術ジャーナリスト会議が主催する「科学ジャーナリスト賞 2024」で、Yahoo!ニュース オリジナル 特集「経口中絶薬に関する3回連載」が優秀賞に選ばれました。同賞は、選考委員にノーベル化学賞受賞者の白川英樹さんなども名を連ねるもので、ウェブメディア発のテキストが選ばれることは初のことです。したがって今回の受賞は異例ともいえます。連載企画は、どのような取材を経て生まれたのでしょうか。取材を担当したジャーナリストの古川雅子さん、そして担当編集者でジャーナリストの森健さん、LINEヤフーの社員として企画のデスク役を担った塚原沙耶に聞きました。(取材・文:Yahoo!ニュース)
経口中絶薬承認まで35年は長過ぎる、おかしい
3回に及ぶ連載は、こういった序文で始まります。
今年(連載時2023年)4月28日、厚生労働省は「飲む中絶薬」を承認した。妊娠初期に使う薬で、日本で初めて使用可能になった。1988年にフランスで承認され、現在65カ国・地域以上で使われている。だが世界で初めて承認されてから日本での承認までに「35年」もかかった。なぜなのか。製薬企業、現場の医師、厚労省、そして薬を求めてきた女性たちを取材。日本では開発や市場化が検討されるたび、立ち消えになっていたことが新たにわかった。
――取材は28人にも及んだとあります。取材から記事公開に費やした期間はどれぐらいでしたか。
古川:取材を各分野の関係者に「総当たり」することは早い段階から決めていて、結果的に4カ月で28人に取材しました。取材は2カ月ぐらいで、リサーチに1カ月を費やしました。原稿の推敲にも時間がかかって、何回も「峠」はありましたね。

ジャーナリストの古川雅子さん
――この企画を立案した背景には、どんな問題意識があったのでしょうか。
古川:経口中絶薬がフランスで承認されてから日本で導入されるまで「35年」もかかっているんです。ともかく長過ぎる、おかしいという疑問でしたね。WHOによると65カ国・地域以上で承認されています。G7の中で日本の承認が1番遅かった。医会(日本産婦人科医会)や保守系政治家の意向があったのではという声もあったので、どこがどう止めていたのかを探るには「調査報道」的なスタイルが良いだろうと、一つひとつ検証していきました。

日本で承認された経口中絶薬「メフィーゴパック」(写真提供:ラインファーマ)
森:調査報道は「なぜ」を掘り返すことが多いのですが、たとえば、「ないとされている」「あったかどうかわからない」などの事象に対して「なぜ」と問いを掲げ、さまざまな記録を調べ、人物から証言を取ることで浮かび上がらせていきます。調査報道には根拠・裏づけが必要です。古川さんはとても大変だったと思いますね。35年以上も前のことなので、取材先をどうするべきかなどを打ち合わせました。国会図書館や大宅壮一文庫で雑誌記事を調べてもらったんです。新聞データベースは1985年からなので、古い資料は別のところを探しました。
1年あたり100ページ以上ある資料を10年分以上読んだ
――取材から記事制作まで、どんなチームワークで動きましたか?
古川:取材・執筆は私で、編集者の森さんとは綿密に打ち合わせをしています。取材で新しい事実が出ると仮説を修正していき、原稿の構成も念入りに3回ぐらい作りましたし、重要な文書を見つけたあとはYahoo!ニュース オリジナル 特集編集部の皆さんともオンラインで会議をしました。
――記事は3回シリーズで計20ページに及びます。Yahoo!ニュース オリジナル 特集でも異例の長さです。これを掲載に踏み切れたのはなぜでしょうか?
塚原:今回の企画を森さんや古川さんからうかがうなかで、複数の記事で伝えたほうがいいと判断しました。多角的に深く取材し、ファクトを丁寧に積み重ねていく必要があり、それらを簡潔に要約するわけにもいきません。そこで、まずは3~4本で組む構成案を練ってもらったんです。以前にも性教育に関する3回連載を制作するなど、シリーズでうまく届けられた事例があったので、特に迷いはありませんでした。ただ、ネットニュースの記事はなかなかシリーズでは読まれにくい面があり、一つひとつの記事が単独で成立していないといけません。古川さんと森さんにこの点をお伝えし、調整してもらいました。打ち合わせを重ねるなかで、おふたりがこの連載に懸けている情熱を感じました。

担当編集者でジャーナリストの森健さん(左)と古川雅子さん
――政治献金やかつての自民党の動きに関する記述にも息をのみました。医会の前会長への取材交渉も時間がかかったことがうかがわれます。調査報道の過程で困難に直面したことはありましたか?
古川:調べを進めるうちに医会の前会長がキーマンだとわかったんですが、取材を何度も打診しながら、仮説を立てて検証していくために、同時並行で他の方へのインタビューと調査を繰り返していきました。
その過程で重要な文書を見つけたことが、この取材の分岐点だったんです。医会の事業報告書は1年で100ページ以上もあるんですが、それを10年分以上読みました。読み解くなかで、ある議連の発足に伴って政治家と密着して動きを取っていることに気づいたんです。それが国政の場で経口中絶薬の議論が進んできた段階とちょうど時期が重なっていたため、「あれっ」と疑問を感じて、深掘りしていきました。

森:総務省が公表する政治資金収支報告書も参照すると、医会の関連政治団体が国政の議論の時期に政治家に献金を重ねていた。そうした事実に古川さんが気づいていきました。
――いまのケースについて聞きます。取材協力を得るときに心がけたことはありますか?
古川:テクニックではなくて、交渉自体は真正面から丁寧に取り組むことを心がけていました。私たちがいろいろな資料を持っていることが、取材を受けてくれる決め手になったんじゃないかと思います。医会の前会長ご本人への確認もして、了解を得た内容なんです。
こういう記事が重なって世の中は動く
――古川さんは「AERA」のライターとしても活躍されています。今回は長いキャリアの中でどういった位置づけになりますか。
古川:長期間をかけて1本の記事を作ることはこれまでにも行ってきましたが、古い資料や公文書も参照して、これだけ多彩で多くの関係者に直接当たって、聞きにくいことも含めて疑問点をぶつけるような密度の濃い取材が続くことは初めてでした。重要な文書を見つけてからは、「これはちゃんと世に出さなきゃいけない」って思って、とにかく早く記事を届けたいという気持ちでした。結果的にはたくさんの方に読んでいただけた手応えもありましたし、受賞までできて、ありがたいです。
――Yahoo!ニュース オリジナル 特集という取り組みに関して思いつくことがあれば教えてください。また、今後に向けての提言もうかがえると幸いです。
森:ウェブメディアでこういう報道ができて感謝しています。今回の連載を掲載できるYahoo!ニュースの胆力には感謝していますし、やっぱりYahoo!ニュースが1番多くの人に届けられるんですよね。この記事は新聞関係の人にもすごく読まれていて、「おもしろかった」という声を複数聞きました。これまでYahoo!ニュース オリジナル 特集で注力してきた「LGBTQ」、「障害」に関連する記事もさまざま出すことで議論を投げかけてきたと思うんですよ。
今回は、「#性のギモン」(Yahoo!ニュースが届ける「#性のギモン」news HACK 2022.12.19記事)をやってきて、ある種の集大成とまでは言わなくても、大きな力になったかなと。こういうものが重なって世の中は動くんじゃないかなと思うので、続けていって欲しいなと考えています。科学ジャーナリスト賞の受賞者は、新聞やテレビの科学担当の人が多いんですよね。記者クラブに入ってないYahoo!ニュースが選ばれたのは、純粋に記事の力が評価されたと見ています。

塚原:Yahoo!ニュースにとっても、今回の連載は、今後につながる大きな一歩だと思います。多様な書き手や編集者が課題を見つけて深く取材し、広くユーザーに届けられる場をこれからも維持していきたいですね。
古川:私は今も紙媒体にも関わってますし、ウェブの仕事もしていて、特に分け隔てしているわけではないんですけども、特にYahoo!ニュース オリジナル 特集で自分が書いた記事は、読まれたときに反響をすごく感じられるんですよね。自分がフリーランスで活動していく上ではすごく励みになるんです。読者からいただいた反応を踏まえて、次のYahoo!ニュース オリジナル 特集の企画に時代の風をフィードバックしていけるのが、ウェブメディアの特徴だと思っています。
【経口中絶薬に関する3回連載】
・「日本は女性医薬の審査がなかなか通らない」 なぜ経口中絶薬は日本で35年も遅れたのか #性のギモン
・10分の「手術」と8時間待つ「飲み薬」 医会が経口中絶薬の導入に消極的な事情 #性のギモン
・中絶は「女性の罪」か――明治生まれの「堕胎罪」が経口中絶薬の遅れに及ぼした影響 #性のギモン
【性教育記事3回連載】
・「いつもの先生」が教えることに意味がある──性教育を担える教員をどう育成するか
・「性教育はエロいものだと思ってた」──高校生が自分たちで考える「人生の役に立つ授業」
・「きちんと教えてこなかった大人の責任」──性を教え続けた公立中教諭の抱く危機感
お問い合わせ先
このブログに関するお問い合わせについてはこちらへお願いいたします。