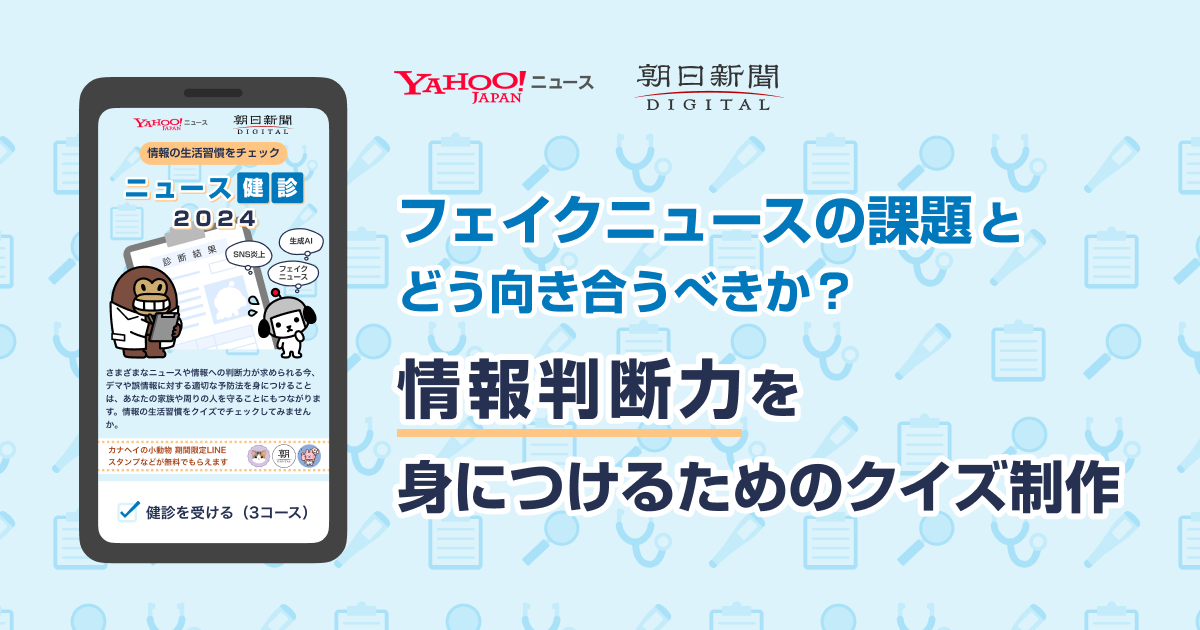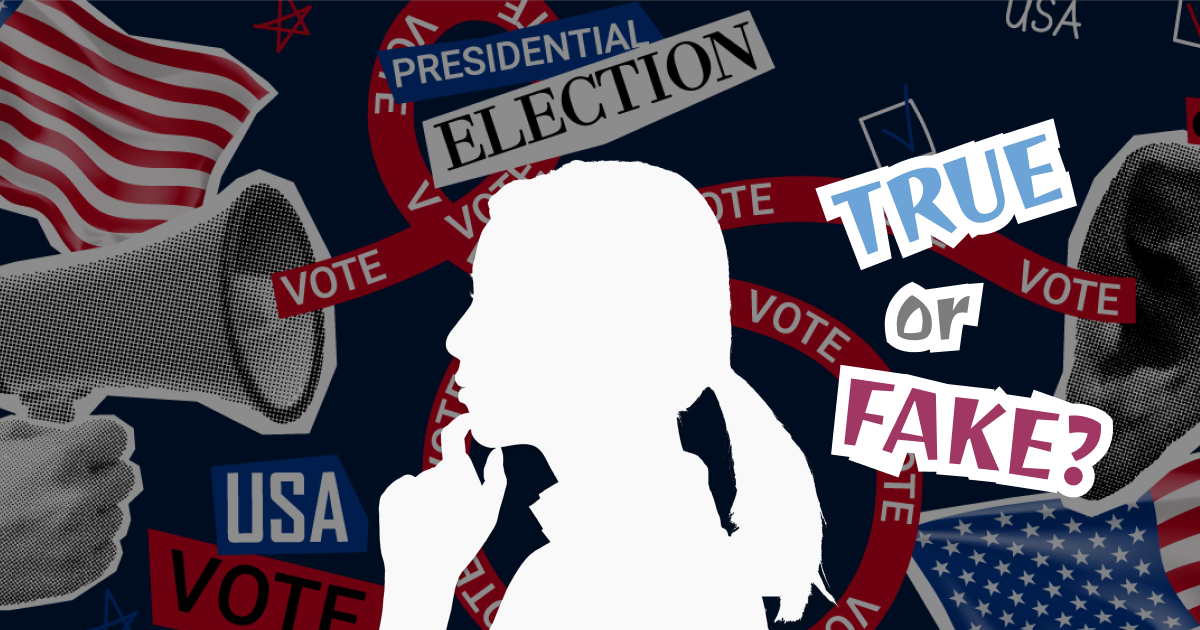「Yahoo!ニュース オリジナル 特集」連載記事が「科学ジャーナリスト賞 2024」優秀賞を受賞

おびただしい情報が行き交う現代社会の中で、埋もれがちなイシューを独自の視点で掘り下げる「Yahoo!ニュース オリジナル 特集」。経口中絶薬の承認がなぜ日本では遅れたのか。その背景を探った連載記事が、日本科学技術ジャーナリスト会議が主催する「科学ジャーナリスト賞 2024」の優秀賞に選出され、6月8日に東京・内幸町の日本プレスセンタービルで授賞式が開かれました。ジャーナリスト・古川雅子さんが4カ月にわたる取材をもとに執筆した連載記事は、調査報道的な手法でこの問題の歴史的な経緯に迫りました。(取材・文・撮影:Yahoo!ニュース)
科学報道で成果を挙げた人を表彰する「科学ジャーナリスト賞」
科学ジャーナリスト賞は、科学技術に関する報道や出版、映像などで優れた成果を挙げた人を顕彰する目的で創設され、2006年に第1回の表彰が行われて以来、今回で19回目を数えます。社会的なインパクトを重視して選考され、これまでに新聞社やテレビ局、出版社で発表された作品を執筆・制作した記者らが受賞してきました。
受賞者に贈呈された盾。ウェブ媒体によるテキスト記事の受賞は初めて
今回の「科学ジャーナリスト賞 2024」は、大賞にはNHKスペシャル関東大震災取材班(代表:木村春奈さん)の「NHKスペシャル 映像記録 関東大震災 帝都壊滅の三日間 前後編」が輝き、優秀賞にはYahoo!ニュース オリジナル 特集記事のほかに、下野新聞「アカガネのこえ」取材班(代表:島野剛さん)の「アカガネのこえ 足尾銅山閉山50年」、そして政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会会長を務めた尾身茂さんの著書「1100日間の葛藤 新型コロナ・パンデミック、専門家たちの記録」が選ばれています。
同賞の19年間の歴史の中で、ウェブ媒体のテキスト記事が受賞したのは初めてのことです。
科学ジャーナリスト賞 2024 受賞作品が決まりました – 日本科学技術ジャーナリスト会議
https://jastj.jp/info/20240422/
経口中絶薬の承認がなぜ日本では「35年」かかったのか?に迫る
優秀賞を受賞したYahoo!ニュース オリジナル 特集の連載記事は、昨年4月に日本でも承認された経口中絶薬がテーマ。
この「飲む中絶薬」は、1988年にフランスで承認され、65カ国・地域以上で使われている(記事公開時点)にもかかわらず、日本では昨年の承認までに「35年」もの年月を要しました。その背景を、製薬企業、現場の医師、厚労省、そして薬を求めてきた女性たちなど28人への取材をもとに、昨年7月末から3回シリーズの連載として記事化しました。
「日本は女性医薬の審査がなかなか通らない」 なぜ経口中絶薬は日本で35年も遅れたのか #性のギモン
10分の「手術」と8時間待つ「飲み薬」 医会が経口中絶薬の導入に消極的な事情 #性のギモン
中絶は「女性の罪」か――明治生まれの「堕胎罪」が経口中絶薬の遅れに及ぼした影響 #性のギモン
 講評では選考委員の一人である小林傳司大阪大学名誉教授が「こうした問題を告発して事態を明らかにしてくれたのは我々の社会にとって大変大きな恩恵」と高く評価した
講評では選考委員の一人である小林傳司大阪大学名誉教授が「こうした問題を告発して事態を明らかにしてくれたのは我々の社会にとって大変大きな恩恵」と高く評価した
日本では長らく、女性の心身に負担の大きい掻爬(そうは)法による中絶が一般的でした。中絶薬自体は、実は日本でも1980年代から論文が発表されたり、研究開発が行われたりするなど注目はされていながら、妊娠初期の中絶薬としては導入に至らず、その後も海外の製薬会社が日本での導入を目指しましたが、日本では女性医薬の審査がなかなか通らないなどの事情もあってうまく進みませんでした。その障壁となったのは何か。それを調査報道的な手法で探ったのが本連載記事です。
取材を続けた古川雅子さん「謎を解きたいという気持ちが原動力に」
授賞式で、執筆者の古川雅子さんは「うれしかったのは、選考の理由に『多くの人に読んでもらいたいと考えて』とあったこと。私自身、女性に限らず広く読んでほしいという思いがありました」と喜びを語りました。
そして、日本で長らく放置されてきたこの問題について続けた4カ月にわたる取材を振り返りました。
 受賞スピーチで古川さんは「女性の性と健康の課題に対してメディアも社会も関心が足りなかったんじゃないか」とも語った
受賞スピーチで古川さんは「女性の性と健康の課題に対してメディアも社会も関心が足りなかったんじゃないか」とも語った
「最初に問いを立てました。なぜ日本では経口中絶薬の導入がフランスでの承認から35年も遅れたのか? その謎を解きたいという気持ちが原動力になった」
「専門家、製薬企業の人に話を聞き、そこからは日本産婦人科医会、学術界、省庁、それから政治家、開業医、女性と取材を広げていきました。専門家たちへのインタビューでは『この薬がなぜ日本で35年出てこなかったのか』の問いに対する明確な答えは誰も持っていませんでした。とても真摯に答えてくれましたが、『なぜ』という問いについては意見や憶測が多かった」
 受賞スピーチの後は質疑応答の時間が設けられた
受賞スピーチの後は質疑応答の時間が設けられた
対象事案が35年も前のことで「最初は苦労した」という今回の取材。過去の資料を徹底的に読み込むことで「日本産婦人科医会の前会長が、古くからこの問題に関わりがあることが見えてきた。その中で2つの重要な文書を見つけた」と明かしました。
「一つは、2013年に前会長の署名入りで厚労省宛てに出されていた要望書で、医療機関の収益性の懸念を訴えていた。前会長に何度も取材を申し込み、何度も断られました。なんとか対面取材にこぎつけ、直接質問をぶつけることで、医会が当初から後ろ向きだったことが証言でも確認できました。もう一つは、医会の事業報告書にあった幹部の活動の記録。毎年100ページを超える文書を10年分以上読んで見つけました。すると、経口中絶薬を医療機関がどう使用するかというルールを議論する時期に、国政の場ではある議連が発足していました。それに伴い、医会の幹部がその議連など特定の政治家に接触し、その年だけで300万円を超える献金が支払われていた。送り先はいずれも保守系の政治家でした」
「医会はそこまでして女性医薬の歯止めに動いていたのかと、そう受けとめられるような動きでした。かつて、この薬を日本に導入しようと試みた製薬会社のリサーチもしていましたが、なぜか日本ではストップしてきた歴史があった。その理由もつながったと思いました」
最後に、困難を極めた取材と記事化にあたって、周囲のサポートに感謝の気持ちを表しました。
「編集者として並走してくださったジャーナリストの森健さんには広い見識から的確なアドバイスをいただきました。そしてLINEヤフーの塚原沙耶さんをはじめ、編集部の皆さんにもサポートをしていただきました。みんなの力を結集していいチームワークを発揮できたんじゃないか」
「振り返ると、証言と事実とつなぎ合わせていく中で、記事づくりがプロジェクト化していったと感じます。私自身は調査報道的なスタイルに熟知していたわけではありませんが、ファクトを積み上げるというプロセスを経たことで、結果として、性と健康と人権の問題を新たに考える種を届けられたんじゃないか。最後まで走り切れてよかったなと思っています」
Yahoo!ニュース オリジナル 特集では、今後もこうした社会に横たわる課題を浮き彫りにし、議論の一端を担える記事を生み出していけるような発信を続けていきます。
 4カ月にわたる粘り強い取材を経た連載記事に「走り切れてよかった」と古川さん
4カ月にわたる粘り強い取材を経た連載記事に「走り切れてよかった」と古川さん
お問い合わせ先
このブログに関するお問い合わせについてはこちらへお願いいたします。