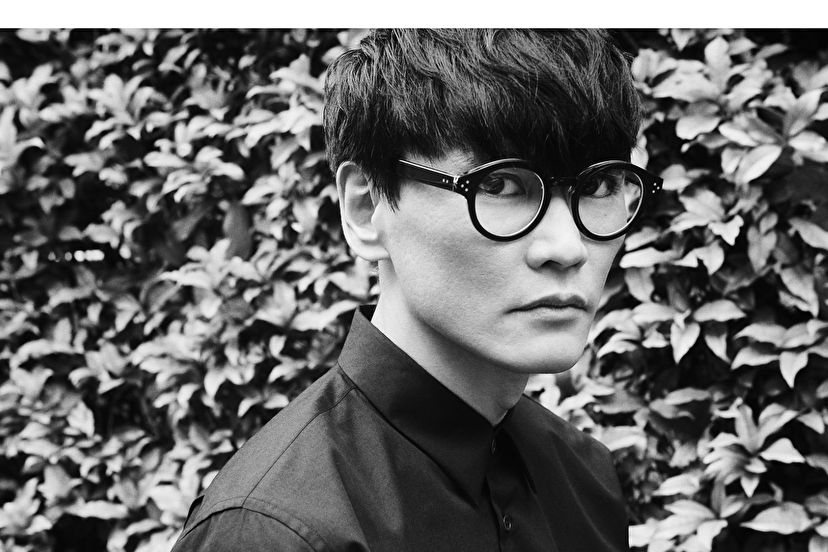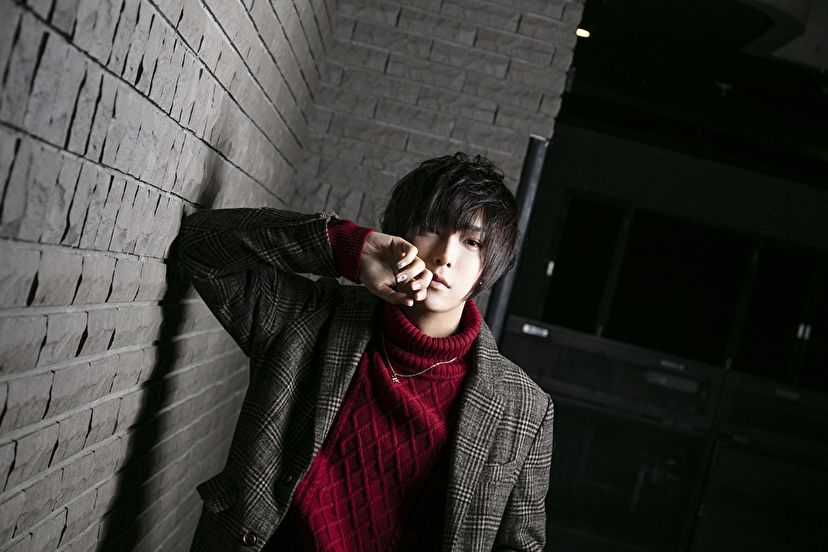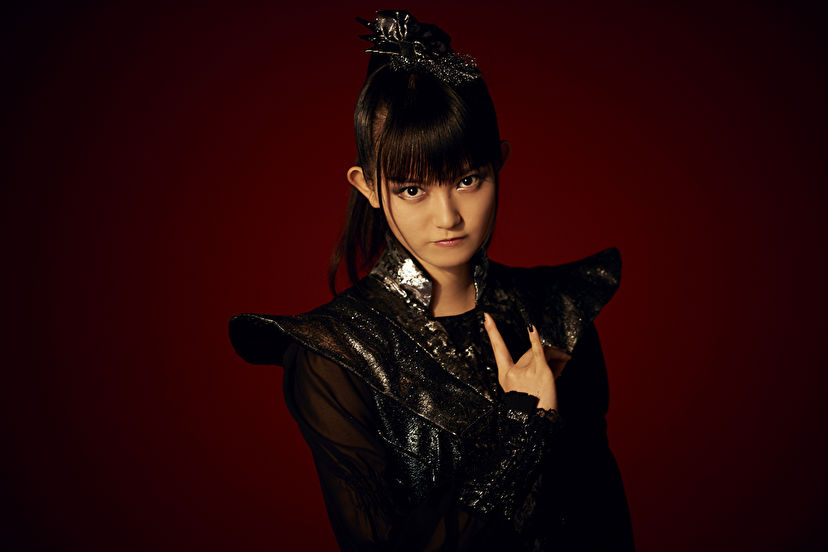「『ベルベット・イースター』という曲はここでつくったんです」。そう言いながら、松任谷由実さん(64)は母校のピアノの前に座った。松任谷さんが高校生の時につくった曲だ。デビューアルバム「ひこうき雲」(1973年)に収録されている。デビュー45周年を迎えたユーミン。「言ってることはブレてないんですよ。世相によって『生意気だ』と批判されたり、『そうだそうだ』と同調されたり。体感温度はいろいろですけど」。今の心境を語ってもらった。(ライター・内田正樹/撮影・太田好治/Yahoo!ニュース 特集編集部)
目標は「詠み人知らず」になること
デビュー45周年を記念したベストアルバム「ユーミンからの、恋のうた。」が発売される。3枚組み全45曲。デビュー40周年記念ベストアルバム「日本の恋と、ユーミンと。」(2012年)と合わせて2部作の完結編という位置づけだ。前回の「日本の恋と、ユーミンと。」は3枚組み全46曲で、「やさしさに包まれたなら」「守ってあげたい」「卒業写真」など名だたるヒット曲が収録された。オリコン初登場で1位を記録した後も売れ続け、2015年には100万枚を突破した。
「日本の恋と〜」に入っていないもので今あらためて聴いてほしい曲がたくさんあったから。前回は私は選曲に関わっていなかったので、今回は全て自分で選びました。そうやってつくったのが今回のベスト盤です。
過去の曲をまとめた作品を出せるのは、「これからも新曲をつくり出せるんだ」という自信があるから。オリジナル作品にブランクがあってベスト盤を出すのは張りぼて感があって気が引けるけど、「宇宙図書館」(2016年)を出して、全80本のツアーも敢行できたから。だから出そうと決めました。

――昨年行われたアルバム「宇宙図書館」の全国ツアー最終日を拝見しましたが、圧倒的な運動量でしたね。
64歳になりましたが、ここ数年で体力は明らかに落ちました。還暦のパーティーの時、宮崎(駿)監督がコメントを寄せてくださったんですね。「60はまだいいんです。62、63歳になると、暗〜いドアがぎぃぃぃっと開きますよ」とブラックなユーモアを込めておっしゃっていたのですが、本当にその通りでした。ただ、そのままにしていては人に分かってしまう。ツアーに向けていろいろてこ入れしましたよ。
――どんなことをされましたか。
筋膜リリースや、初歩的なボイストレーニング。心身の緊張をほどくアレクサンダー・テクニークや、アーユルヴェーダの瞑想法を取り入れたりもしました。短い時間で休息がとれるように。漫然と暮らしてもダメだけど、気にし過ぎるのもよくないので。
「宇宙図書館」ツアーの80ステージは私から言い出したことなんです。2000年に79ステージのツアーを経験しているんですね。でも、もう十数年も前。そこからの変化はものすごい。自分自身もだけど、スタッフも世の中も違う。親友や大切な人を亡くしたりもしました。いつ何があってもおかしくない年齢です。でも、また別の山を、より難しいルートで登りたくなったんですね。

――ツアー最終日、ステージ上のユーミンは感極まっているように見えました。
あのね、感極まるのはいつもなんですよ。3分の1はサービス。
――それは公言しちゃっていいんですか(笑)。
3分の1は本当に感極まっています。残りの3分の1は「感極まっている自分に感極まりたい」っていう感じ?(笑)
(60歳や80ステージといった)数字では測れない地平があるんです。それは決してたどり着くことのない場所。振り返ればデビューの時から(そのイメージは)漠然とあって。(音楽は)自分のためにやっている。それは今も昔も変わりません。いつも言うんですが、私の目標は自分のつくった歌が「詠み人知らず」になることです。そのためにライブもやるし、アルバムもつくる。プロモーションも一生懸命やる。全ては、一曲でも多く人々の記憶に残り、DNAに組み込まれるぐらいのところまでいくためなんです。

ユーミン史上最長、最多本数のロングツアーとなった「宇宙図書館」ツアー。最終公演である東京国際フォーラムのライブの模様がBlu-ray/DVDとなって、45周年記念ベストアルバムと同じ4月11日に発売される(撮影:菊地英二)
闘うべき場所はポップの世界だと自覚した
「ユーミン」のパブリックイメージからは「詠み人知らず」がピンとこないかもしれない。特に「純愛三部作」と呼ばれたアルバム「ダイアモンドダストが消えぬまに」(1987年)「Delight Slight Light KISS」(1988年)「LOVE WARS」(1989年)、そして日本人初の200万枚を突破した「天国のドア」(1990年)などは、時代にくっきりと「ユーミン」を刻印した。それでも常に「ユーミン」という先入観なく「いい歌」だと受け取ってもらいたいという思いで曲づくりを続けてきたのだ。
――アルバム「SURF & SNOW」が発売されたのが1980年。リゾートブームを牽引(けんいん)したと言われました。その後も、女性の社会進出やバブル景気など、アルバムを出すたびに時代を言い当てるようで、予見的とも評されました。
曲をつくっている時はひらめきを追求することに必死で何も考えていなかった。ただアンテナがビキビキに冴えている時は、磁石のように情報が向こうから吸いついてくるんですよ。いわゆる「バブル」の体感は人より早く経験してしまっていました。
――では、実際に世の中がバブルに沸き立っていた80年代後半から90年代初頭にかけては、ユーミンにとってはどんな時間だったのでしょうか。
楽しませる側に徹していました。雑誌の取材に答えることさえもエンターテインメントという感じで。

それには砂漠を訪れた経験が大きくて。1986年にアフリカの砂漠へ行くんです。周りからは「2カ月も休んでなんでそんなところに行っちゃうの!?」と言われましたが。パリ-ダカールラリーに帯同したんですが、そこではモータースポーツというかたちを借りて、大自然の中で本当に闘っている人がいた。その世界から戻ったら、東京が脆弱な箱庭のように見えた。だからこそ、「ここで闘おう」という気持ちになったのね。自分が闘うべき場所はポップの世界だと自覚した。
――では、続く90年代は?
消費されないように必死だったところもあるし……CDが売れない時代をも、先兵として予見していました。
――あれほどヒットを連発していたのに?
一番風圧を受けるところにいるから。「ついにユーミンが売れなくなったぞ」という世の中の反応がもろにくる。あくまで感覚的にですが、エンタメにシフトするぞということは分かっていました。松任谷(正隆)と2人で「興行は不滅だ」と言い合っていました。

――アルバムセールスが好調だったころからすでに革新的なコンサートを行っていました。
そういう時じゃないと贅沢(ぜいたく)できないじゃないですか。ポップアートには才能と時間とお金が必要だから。でも当時、そう考えてやっていたわけではなかった。ただ、その時にやっておくべきことは分かるんです。
「天国のドア」が日本人で初めて200万枚を記録したという、そのニュース性は大事なことで。それがパイロットとなって、ハードが普及し、他のものも売れるようになっていく。ライト兄弟みたいに、そこまで飛べばもっと遠くまで飛ぶものがあとから出てくる。スリップストリームに乗るものがね。
90年代に(アメリカのミュージシャンの)プリンスが新しい音楽ビジネスモデルをつくろうとしたじゃないですか。あれは相当、自分に負担がかかることだったと思う。それに比べたら、日本のマーケットなんてたかがしれている。そのぐらい乗り越えられなくてどうすると思っていますよ。シンガー・ソングライターであり、スターであるという、二兎を追うことは可能だと思っていた。マーケットという考え方も実はしていないんですけどね。いったんマーケットだと思ったら、そこから出られないから。


匂いや湿度を音楽に封じ込めたい
3月17日、東京・調布市で開かれたプレミアムコンサート「SONGS & FRIENDS」。「100年後も聴き続けてほしいアルバム」にユーミンの「ひこうき雲」が選ばれ、複数のアーティストによって「ひこうき雲」収録の楽曲が歌われた。
――MCでは「荒井由実が乗り移ったようで緊張している」と言っていましたね。
めったにあがらないんですけどね。マイクを通した声を自分で聴いて、緊張してるなって。(バックで演奏した)細野(晴臣)さんを見ると、当時からだいぶ変わっているはずなのに、昔の細野さんの姿なんですよ。(鈴木)茂も。そんなはずはないのに。
私の中には今も13歳、14歳の自分がいる。座敷わらしのようなそいつが、「大人ぽい」とか「都会っぽい」と思ったものを採取して、今も曲づくりに役立ってくれているんです。あの日のステージは、彼女が自分の体に乗り移ったようだった。きっと音楽によって不思議と知覚のドアが開かれたんですね。
アルバム「ひこうき雲」は大学1年の終わりごろから約1年かけてレコーディングされた。その演奏に参加していたバンドが、当時キャラメル・ママ名義で活動していた、のちのティン・パン・アレー(細野晴臣さん、鈴木茂さん、林立夫さん、松任谷正隆さん)だった。

豪華アーティストが出演した「PERFECT ONE presents SONGS&FRIENDS 100年後も聴き続けてほしい名アルバム 一夜限りのプレミアムコンサート荒井由実「ひこうき雲」」。シークレットゲストとして井上陽水さんが登場した。コンサートの様子はWOWOWで5月13日夜に放送される(撮影:上飯坂一)
あの人たちじゃないと出ないサウンドがあるんです。手数とか本当に少ないんですよ。松任谷正隆も手数は少ないけれど、そこに情報がすごくある。細野さんのテクスチャーにも、すごい量の情報があるんだと思う。
「SONGS & FRIENDS」をプロデュースする音楽家の武部聡志さんとの対談で、ユーミンはこう語っている。「『ひこうき雲』に入っている曲って、雨とか雲とか霧とかばっかりなんですよね。茫洋とした掴めないものばっかりが歌になってて」「(キャラメル・ママのサウンドに)匂いや、やっぱり質感ですね、そういったものを感じるんです」
私は歌をつくる時に、ストーリーやキャラクターを描きたいのではなく、匂いや湿度、切なさといった目に見えない「クオリア」を描いてきたつもりです。今回のベスト盤は、特にそれが色濃く描かれた曲でできていると思います。
3、4年くらい前かな、石川県の山中温泉(加賀市)というところで、山中節を聴かせてもらう機会があったんですよ。それがすごくて、もう、涙が出ちゃって。


山中節は日本三大民謡のひとつと言われているんですが、恋の歌なんです。昔、日本海を行き来する北前船の船頭さんたちは船を下りると山中温泉を訪れて湯治をしたんですって。彼らはひととき休んではまた出かけていく。その時に芸者さんと恋をする。「ハァー 忘れしゃんすな」と始まるんですが、その心情と旋律とが一体になっていて「うわぁ〜」って。情景が広がる。四次元に伝わってくる。
――それは何人かで歌うものなんですか?
私が見たのは歌い手が1人、三味線が1人、踊り手が1人でした。地元の小さな劇場で、他に誰もいないところで鑑賞させてもらいました。ゆったりとした節回しや、こぶし回し、すべてが伝承されるんでしょうね。
音楽と人間の関係って、そういうものに戻っていくのかもしれない。民謡のような、民族的にしみ込むものと、ショパン以前の教会音楽やサロンミュージックの両極に。一方で、ポップミュージックのパトロンは大衆です。そのことは80年代から松任谷ともよく話していました。「音楽でお金をとるというのは、考えてみたら不自然なことだよね」って。ライブはまたちょっと別ですけどね。
――松任谷正隆さんとの関係は。
よく「おしどり夫婦」とか「二人三脚」とか言われますが、それには非常に抵抗がありますね(笑)。ハサミみたいだなと思うんですよ。刃を向け合うんだけど、お互いのことは絶対に切らない。一部がつながっているけれど、溶け合ってはいない。いつも一緒にいるけれど、0.何ミリか離れている。彼を失うと、私は会話のできる相手がいなくなる。彼も天才だからね。海王星人と冥王星人みたいなものなので、肩を寄せ合って暮らしていかなきゃならないんです。

「SONGS & FRIENDS」のMCでは、ファーストシングル「返事はいらない」(1972年)と、その曲のプロデューサーで、昨年3月に亡くなった親友・ムッシュかまやつさんの思い出にも触れた。
――ユーミンはなぜムッシュにひかれたのでしょうか。
全てが遊びでできている人だったから。音楽もファッションも同じ次元で遊べていた人でした。80年代後半から90年代なかばごろは、私が馬車馬のように働いていたせいで会える時間が少なかった分、なおさらムッシュのあり方がうらやましく思えた。自分ではそれまでと同じように遊んでいるつもりでも、「どこに運ばれていっちゃうんだろう」という不安もあったから。
――若いころと比べて、不安や孤独との付き合い方は変わりましたか。「多少は飼いならせるようになった」と語っていた時期もありましたが。
プラマイゼロかな。孤独は人の一生にずっと付いて回るもの。特にアーティストは男でも女でもなく、男でも女でもある。どちらの孤独からも解放されている反面、どちらの孤独も引き受けなければならない。
老境が近づいてくる孤独もありますよ。ツアー中やアルバムリリースの時はスタッフとかも周りにいっぱいいますが、ひとりになった時にふと、自分の中でパイロットランプを切らざるを得ない時がくるかもしれないな、と思う時もある。

――もしかしたら?
もしかしたらね。でもたとえそうなっても、ファンは問題ないと思う。そのころには繰り返し聴いてもらえるだけの十分な曲がそろっているはずだから。もしかしたらバーチャルなユーミンが存在しているかもしれない。初音ミクより強力な“AIユーミン”とかね(笑)。生身の私はとっくに引退して、どこかの施設で人知れず過ごしているかもしれないし。
――そんなユーミンはとても想像がつきませんが。
でも来(きた)る近未来は、どうなっているかわかりませんよ。環境が変われば身体もオルタナしていくかもしれないし。
――70年代から活躍されてきたアーティストがすごいのは、ロールモデルがいない時代だったということ。情報も限られている中で、楽曲も、セールスも、ライブも、すべて自分の経験と体で答えを出してきたのですから。
その通りです。だから良かったんですね、きっと。当時は「ここに行けばこれがある」という情報はなかった。欲しいものを手に入れるためにはいろんなところに行ってみるしかなかった。でもその回り道にたくさんの宝物があった。それを栄養にして今日までやってこられたんじゃないかな。
今度のツアーは、2つのベスト盤を合わせた90曲を、何日かに分けて全曲やろうかという話もあったんですよ。たとえそれは無理でも、それくらいのボリュームを感じてもらえるものは提供したいし、そうできると思う。人の想像力に勝るものはないですからね。

松任谷由実(まつとうや・ゆみ)
1954年生まれ、東京都出身。1972年、シングル「返事はいらない」でデビュー。「ひこうき雲」「やさしさに包まれたなら」「あの日にかえりたい」「恋人がサンタクロース」「守ってあげたい」「真夏の夜の夢」「Hello, my friend」「リフレインが叫んでる」「春よ、来い」など、数多くのヒットソングを送り出す。1999年から行われた「SHANGRILA」3シリーズでは革新的なステージを生み出した。2018年4月11日、デビュー45周年記念ベストアルバム「ユーミンからの、恋のうた。」をリリース。アリーナツアー「Ghana Presents 松任谷由実 TIME MACHINE TOUR Traveling through 45years」全国14会場29公演の開催が決定している。
内田正樹(うちだ・まさき)
1971年東京都出身。編集者、ライター。雑誌「SWITCH」編集長を経て、2011年からフリーランス。これまでに数々の国内外のアーティストインタビューや、ファッションページのディレクション、コラム執筆などに携わる。
[撮影協力]
学校法人 立教女学院