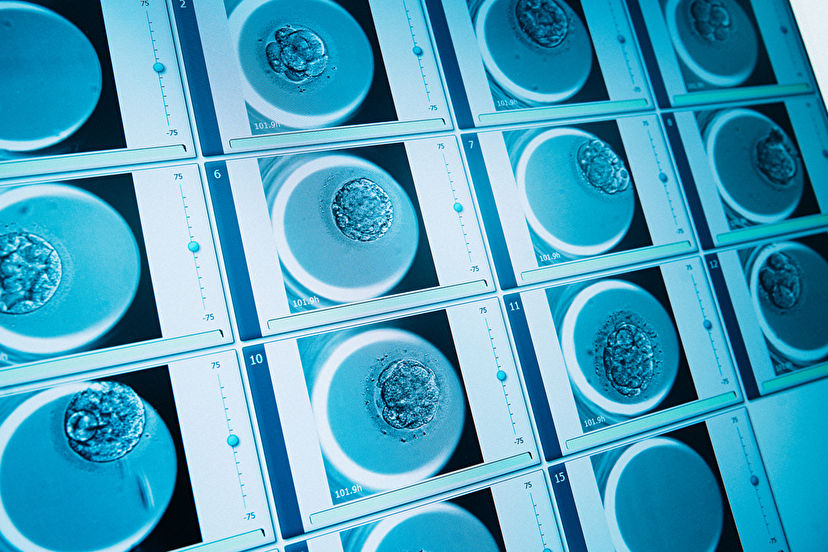妊活中の夫婦が「赤ちゃんが欲しい」と強く願うばかりに、ますます相手を責め、自分を責め、夫婦間の不信感が募る――。いわば夫婦関係の「妊活クライシス(危機)」だ。妊娠をめぐる男女の意識差はなぜ生じるのか。危機を経験した夫婦や不妊治療の現場を訪ね、苦しい心の叫びに、耳を傾ける。
(おおたとしまさ/Yahoo!ニュース編集部)
「いっそ、夫に産んでほしい」
仕事から帰宅した夫に、「今日、排卵日」と告げる。夫は言う。「いいよ」。「なんで私がお願いしたことになってるの?」と言いたくなる気持ちを押し殺す。
そして生理が来るたびに、妻は、絶望を味わう。「できなかった」のではない。おっぱいをたくさん飲んでくれて、ハイハイして、あんよして、「ママ」と呼んでくれて、ランドセルを背負って桜の木の下で写真を撮って……、そうやって一緒に人生を歩むはずだった子供を、毎回、「失う」のだ。
絞り出すように夫にだけ報告する。
「(生理が)来ちゃった……」
ほとんど「私たちの子供が亡くなった」という意味だが、落ち込む妻に、夫は悪気なく言う。
「また次、頑張ればいいじゃないか」
妻は心の中でつぶやく。
「そういう問題じゃない」

妊活中、妻は何度も「失って」いる。夫はどう受け止めるのか(撮影:鬼頭志帆)
佐藤和子さん(39)=仮名、はこんな生活をもう5年以上続けている。単純に計算すれば、約60回の絶望を味わったことになる。しかし夫にとっては「まだ希望を捨てない」状態が継続しているだけ。同じ風景を見ていても、受け取る意味合いがまるで違う。
「生理が来てしまったとき、妊活中の女性は、わが子を失った母親とまったく同じ『喪失感』を味わいますが、男性にはそれがなかなかわからない」と言うのは、不妊治療中のカップルへの心のケアを専門とする生殖心理カウンセラーの平山史朗さん(東京HARTクリニック)。
生理が来るたびに、悲しみに暮れて、泣き続ける女性も多い。
「そこで『泣くな。まだ次がある』は無理。しっかりと悲しむ環境を作ってあげることが、夫の役割です。励まそうと思って外出に誘うのも逆効果になることが多い」

夫婦で同じ風景を見ているようで、実はその受け取り方は同じではない(撮影:鬼頭志帆)
外で子連れの家族を目にすればさらに気持ちが沈む。若い女性を見るだけでもつらくなる。あらゆる刺激がしんどい。そのことへの想像力が必要だ。
和子さんはSNSを見ない。子供がいる暮らしを見せつけられるのはつらいから。独身の若い女性と話をするのも怖い。自分が不妊になるかもなんて想像もしていない彼女たちの何気ない発言に、傷つくことも多いのだ。友達はどんどん減っていった。
不妊について当事者同士で語り合う場はある。「私だけじゃない」と、ほっとできる時間だ。しかしそこでLINEのアドレスを交換する気にはなれない。その人が妊娠するのが怖いから。

妻の複雑な心境を、夫はどこまで想像できているか(撮影:鬼頭志帆)
夫にも不妊検査を受けてもらった。「問題なし」の結果が出ると、夫の表情からは解放感が溢れた。和子さんにとってもうれしい結果であるはずだが、心境は複雑だ。夫が「同士」ではなくなってしまった気がした。
いまはとにかく、年を取るのが怖い。女でいることが苦しい。いっそ夫に産んでほしい。自分が男になって、「応援する側」に立てればどれだけ楽なことだろうか。つい、そんな風に考えてしまう。
まずは男性が検査を受けるべき
千葉商科大学専任講師の常見陽平さん(42)は、自分のためらいが、妻を余計に苦しめたと告白する。
「私が38、妻が37の時に妊活を始めて、1年経ってもできないので、病院に行くことにしました。夫婦で行こうと誘われましたが、仕事が忙しいことを理由にして、私は行きませんでした。正直、そこまでしなければいけないのかという疑問や抵抗感がありました」

常見陽平さん。ここまでしなきゃならないのか。なかには戸惑いを持つ男性もいる(撮影:鬼頭志帆)
「(生理が)来ちゃった……」と言って落ち込む妻を何度も慰めた。一時はあきらめかけた。「2人で愛し合っていればいい」「ペットでも飼おうか」などと話しながら、なんとなく、1年ほど妊活を中断した。
しかし妻からの提案で、もう一度だけ挑戦してみようということになった。ようやく常見さんも覚悟を決めた。病院に行き、精子を調べてもらった。結果は衝撃的だった。精液の中に、ほとんどまともな精子が含まれていなかったのだ。残された選択肢はほぼ顕微授精(※)しかないことがわかった。
(※顕微授精=精子を1つ取り出し、顕微鏡で見ながら、母体から採取した卵子に細いガラス管を使って人工的に注入し、母体に戻す方法)
「あのとき病院に行っていれば、何度も妻を落胆させなくてすんだのに、もっと若い母体で妊娠することが可能だったのに……」
なにより、何年もつらい不妊治療をしてきた妻に申し訳なかった。

検査に抵抗感を持つ男性がいるが、それがのちに火種となることがある(撮影:鬼頭志帆)
男性専門の不妊治療を行う恵比寿つじクリニックの辻祐治院長は、まず男性が不妊検査を受けるべきだと訴える。女性の不妊検査に比べれば、精子検査は簡単。痛みも伴わない。もし異常が見つかっても、早めに治療すればそれだけ早く状況が改善できるかもしれない。男性側が率先して「自分もできる限りの妊活をする」姿勢を示すことで、女性が安心できる効果も大きい。
仮に無精子症と診断されても、子供を授かるチャンスはある。睾丸の中に1個でも健康な精子が見つかれば、顕微授精が可能なのだ。「将来子供を授かりたいと思っている男性は、妊活や結婚に関係なくなるべく若いうちに検査を受けたほうがいい」と辻院長は言う。常見さんも「男性の健康診断の項目の中に、精子検査を入れたほうがいいのではないか」と提案する。
「子づくりも子育ても夫婦共同でするもの。仮にどちらかの体に問題があったとしても、それを2人で乗り越えて行くのが夫婦です。『ふたり』の子供が欲しいと願っているのなら、お互いを思いやりながらお互いにベストを尽くし、2人が納得できる妊活をしてほしいと思います」と辻院長。

妊活は2人で乗り越えていくものだ。互いに歩み寄れるか(撮影:鬼頭志帆)
「不妊でも、気持ちはすでに母なのです」
武田真由美さん(42)=仮名、は24歳で結婚した。20代はあえて子供はつくらず、2人で好きなことをする生活を満喫した。30代になって、「そろそろ……」と思ったが「できない」。
本格的な不妊治療が始まると、仕事を辞めざるを得なかった。突然病院に呼び出されることが多くなるし、心身両面への負担も大きいからだ。毎月何本も筋肉注射を打つ。副作用で気分が悪くなることも多い。膣から針を刺し卵子を採取することもある。激痛を伴う。処置が終わってからも痛みは続く。会社を半休してできるようなものではない。同性の友人にすら話すことができず、真由美さんは殻に閉じこもるようになった。

仮に喪失を経験しても、夫婦の人生は続いていく(撮影:鬼頭志帆)
ようやく妊娠できたときには、すべてが報われたと思った。しかし、おなかの中で、赤ちゃんの心臓は止まってしまった。陣痛誘発剤を打ち、分娩台に上がり、もう産声をあげることのない赤ちゃんを産まなければならない。「死産」である。
夫も立ち会ってくれた。壮絶な「出産」を目の当たりにし、夫は泣き崩れた。「君まで失うんじゃないかと思った。君さえいてくれれば、僕の人生はそれでいい」。夫の優しさが胸に刺さった。そんな優しい夫の子供を産めない私がダメ。夫に先に泣かれてしまい、自分は涙すら流せなかった。仕事も、友達も、そして子供も、すべてを失った。
「悲しみ方には性差がある」
真由美さんはいま、そう感じている。

止まってしまった妻の人生に、夫は気づけるだろうか(撮影:鬼頭志帆)
最近、夫の学生時代の友人宅に招待された。男たちは「オレたち変わらないよな」と笑いながら満足げに飲み交わしていた。その姿があまりにのんきに見えた。
「不妊でも、気持ちはすでに母なのです。それなのに、毎回『喪失』するんです。思い描いていた人生が、いつまでたっても先に進みません。私の人生が止まってしまっていることに、夫は気付いていないのです」
夫はいまでも不妊治療に協力的だ。一緒にクリニックに来てくれて、医師の説明も一緒に聞いてくれる。妊娠の可能性について、毎回シビアな現実を突きつけられるが、夫は自分が納得できるまで、医師に説明を求める。その姿は頼もしくもある。しかし同時に、真由美さんは傷つく。医師に理由を聞くことは、自分が「産めない女」である証拠を求めることに等しいからだ。

妊活は、永遠に続けられるものではない。いつかは「決断」する日がくる(撮影:鬼頭志帆)
夫は毎回のホルモン数値を折れ線グラフにまとめて分析している。正直、それもうざい。自分は身体で痛みを感じ、感情の荒波を抑えるのに必死なのに、夫は数値だけを見て冷静にものを言う。
「私は現実を受け入れる準備もそろそろしなければいけないと考え始めています。でも、夫は、そういう未来を一緒に考えようとはしてくれません。夫の頭の中にはまだきっと、『最後に勝つ』イメージがあるんです」
妊活を始めるまでは、何について語り合ってもフィーリングがぴったり合った。「子供を授かって、家族をもちたい」という想いも同じだ。それなのに、妊娠のことになると、視点のズレや悲しみ方の違いが露呈した。
それがことさらにショックだった。

妊活においては問題解決志向だけでも足りない。妻との人間関係を維持し、共感する志向も必要だ(撮影:鬼頭志帆)
子供がいるからこそ見えないことがある
「一般に、男性は『問題解決志向』が強く、女性は『人間関係維持志向』が強い」と言うのは、前出・生殖心理カウンセラーの平山さん。
真由美さんのケースで言えば、「できない」状態を変える方法を探るのが「問題解決志向」。「できない」状態の中で夫婦でどう共感し、支え合うかに重点を置くのが「人間関係維持志向」。人間には問題解決志向も人間関係維持志向も必要だが、夫婦が別々の立場から向き合えば、話がかみ合うはずがない。

一言で「不妊」といっても、その中身は一様ではない(撮影:鬼頭志帆)
すれ違いを防ぐ心得として、平山さんは、(1)お互いの思いが違うことを恐れない、(2)相手の気持ちを思い込みで決めつけない、(3)わからないからこそわかりあえると信じて自分の気持ちを伝え相手の思いを聴く、の3点を挙げる。
同じ風景を見ていても、立場が違えば受け取る意味合いは違ってくる。「不妊」の当事者である夫婦間でさえ、感じ方には濃淡がある。ましてや「不妊」の当事者ではない人々が、彼らの心の叫びに気付けることは少ない。いつも笑顔の同僚が、あるいは電車の中でたまたま目の前に座っている人が、もしかしたら「不妊」の当事者であるかもしれない。
「子供を育ててみないとわからないことがある」とはよく言われるが、逆もまた真なり。「子供がいるからこそ見えなくなっていることがある」「子供がいないからこそわかることがある」。そんなふうに思うと、いつも見慣れた風景が、ちょっと違って見えてくるかもしれない。

おおたとしまさ
ジャーナリスト。1973年東京生まれ。上智大学英語学科卒業。リクルートで雑誌編集に携わり、2005年に独立。著書に『ルポ塾歴社会』(幻冬舎)、『追いつめる親』(毎日新聞出版)、『ルポ 父親たちの葛藤』(PHP研究所)など45冊以上。
[写真]
撮影:鬼頭志帆
写真監修:リマインダーズ・プロジェクト
後藤勝