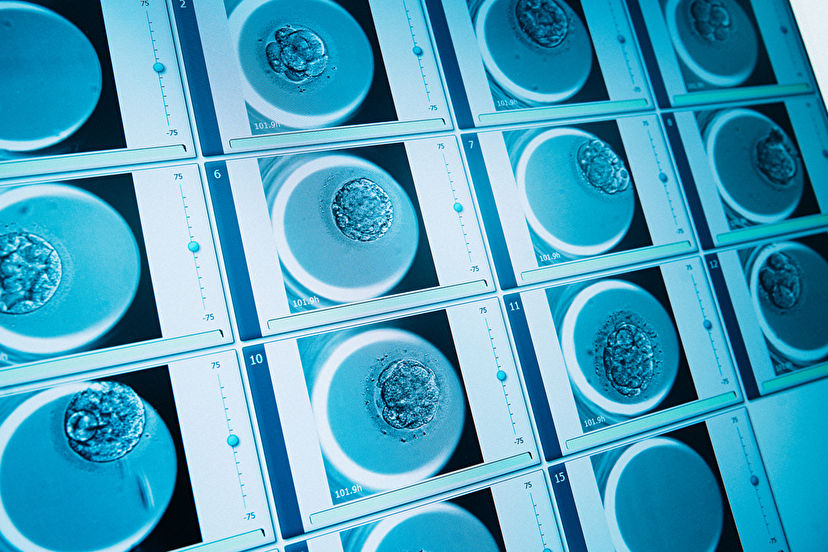女性アスリートにとって「出産後の競技復帰」は大きな課題だ。リオ五輪では、日本代表164人の女子選手のうち5人が母親だった。一定期間競技を離れることへの不安はある。「結婚したら引退」「子どもができたら引退」という空気も根強い。出産後も現役続行を選んだ2人の選手と、彼女たちを支える人たちを取材した。(ノンフィクションライター・西所正道/Yahoo!ニュース 特集編集部)
「出産でこんなに体が変わるものか」
「これでチームをやめなければいけないかもしれない」。女子ハンドボール元日本代表の高木エレナさん(28)は、妊娠が分かったとき、そう思った。
高木さんは、日本ハンドボールリーグに加盟するチーム、三重バイオレットアイリスに所属している。本拠地は三重県鈴鹿市。運営はNPO法人で、ほとんどの選手が地元企業で働きながらプレーしている。高木さんも、物流会社ホンダロジスティクスで働いている。

練習中の高木エレナさん(中央)。ポジションはゴールキーパー(写真:伊藤菜々子)
2017年8月に、同じハンドボール選手と結婚した。妊娠が分かったのは2018年4月。恐る恐る監督に報告した。「チームにいていいですか? 会社に怒られないですか?」
当時の監督で、現在はチームマネジャーを務める櫛田亮介さん(42)は、拍子抜けするほどの笑顔で言った。「おめでとう! よかったやんか! チームにいて全然オッケー。会社と話をしながらやっていこうよ」
高木さんは、当時のことを話すと今でも泣き出してしまう。実は、引退しようかと気持ちが揺れ動いていた時期の妊娠だった。出産を機に引退という考えもよぎった。
「おなかの子が『いまは気持ちが疲れているからちょっと休んだら』と言ってくれたように感じたんです。この子も応援してくれている……だからもう一度頑張ってみようかなと思ったんです」

高木エレナさん(写真:伊藤菜々子)
取材中、感極まる高木さんを、櫛田さんと、現監督の梶原晃さん(36)がニコニコと見守る。櫛田さんはこう言う。
「やっぱり、スポーツ界はまだまだ、女性選手が結婚したり、子どもを産んだりすることが、祝福される雰囲気ではないですからね」
プライベートなど顧みず、スポーツに打ち込め――。スポーツ界にはそんな考え方が根強い。高木さんは結婚したとき、「結婚したからプレーのレベルが落ちたと言われたくなくて、それまで以上に練習に取り組んだ」と言う。
「シュートの阻止率が上がって、よしっ!と思いました。だから今回も、苦しくても現役を続けようと。そうすれば、後輩も好きなことを諦めないでいられるから」

チームマネジャーの櫛田亮介さん(左)と監督の梶原晃さん(写真:伊藤菜々子)
2018年12月に男の子を出産。3カ月後に練習を再開した。が、体が動かない。高木さんは「久々に体育館を走ったんです。すると膝が痛くなって10分で終了。こりゃあヤバいなって」と振り返る。
妊娠前の体重は68キロ。妊娠中、いわゆる食べづわりで一時85キロまで増えた。出産後、授乳と運動で落ちたが、練習再開時はまだ75キロあった。チームトレーナーを務める理学療法士の佐久間雅久さん(45)は、出産でこんなに体が変わるものかと驚いた。
「筋肉に触れると、妊娠前と比べて弾力が低下していました。トレーニングによってまた体を作っていくわけですが、出産後に現役復帰をするアスリートを担当したことがなかったので、どう運動メニューをつくればいいのか、手探りでした」

トレーナーの佐久間雅久さん。鈴鹿回生病院に理学療法士として勤務する(写真:伊藤菜々子)
「長く現役を続けるために先に子どもがほしい」
佐久間さんの声を受けて、櫛田さんは、日本ハンドボール協会監事の東海林(とうかいりん)祐子さん(51)に相談した。東海林さんも元ハンドボール選手で指導歴もあり、現在は慶應義塾大学総合政策学部准教授としてコーチングによる人材育成と組織作りの研究をしている。女性アスリートの地位向上にも務め、バイオレットアイリスの選手にアスリートのキャリアデザインの講義をするなど、付き合いがあった。
東海林さんは櫛田さんに、国立スポーツ科学センター(JISS)が実施する「産後期トレーニングサポートプログラム」があることを伝えた。国の委託事業「女性アスリートの育成・支援プロジェクト」の一環である。

東海林祐子さんは「JISSにはこれだけ素晴らしいシステムがありながら、現在の支援対象は強化選手のレベルに限られます。東京に集中しがちにもなる。もっとサポートの機会を広げていけるといい」と話す(写真:長瀬千雅)
JISSは、日本オリンピック委員会や各競技団体、大学などと連携し、日本の国際競技力を向上させるために、各分野の調査研究やアスリート支援をしている。JISS所属のスポーツドクター・土肥美智子さん(54)は産後アスリート支援を始めた背景をこう説明する。
「スポーツ医学の発達で、けがの予防、治療やリハビリテーションが改善されてきました。その結果、現役を続けられる期間が長くなりました。以前なら、出産は引退してからと考えていたのが、長く現役を続けるために先に子どもを産もうと考えることができるようになったのです」

土肥美智子さん(写真:伊藤菜々子)
2018年度は、6人の選手がJISSの産後期トレーニングプログラムを利用した。今年度利用している選手の一人が、女子ラグビーの中嶋亜弥さん(33)である。2019年4月30日に女の子を出産した。
学生時代はバレーボールの選手だった。ラグビーを始めたのは遅く、23歳のとき。2014年に埼玉県熊谷市の7人制チーム「ARUKAS KUMAGAYA(アルカス熊谷)」の創設に参加、初代キャプテンになった。30歳で7人制の日本代表としてリオ五輪に出場したが、不完全燃焼だった。
「もっと長く現役を続けることを考えたとき、子どもがほしいと思いました。2021年の女子W杯に出ることが目標なので、逆算すると(出産は)今年が最後のタイミングだと考えていました。無理ならば、W杯のあとにしようかとも」
夫はラグビーコーチ。出産後の現役続行を応援すると約束してくれた。

中嶋亜弥さん(写真:伊藤菜々子)
中嶋さんは、妊娠期のトレーニングについてチームトレーナーに相談したが、分からないと言われた。自分で文献を集め、体と相談しながらトレーニングを重ねた。
「ジョギングやバイクこぎ、ウエイトトレーニングをしましたが、脈拍数が140以上に上がらないように気をつけていました。やはりおなかの子どものことが心配だったので」
JISSのサポートは「産後1カ月からが大事」としている。産後のトラブルがなければ、一般的に運動を始めてよい時期だからである。妊娠期のトレーニングが産後の復帰を早めることはおそらくないだろうと考える。土肥さんによれば、世界を見渡しても、妊娠期や産後のトレーニングに関して、医学的エビデンスのあるデータは極めて少ない。JISSのプロジェクトチームは、土肥さんを中心に、理学療法士、トレーニング指導員、管理栄養士、心理スタッフなど多分野の専門家で構成される。出産経験のある選手にインタビューしたり、一般社団法人日本マタニティフィットネス協会に取材したりして、プログラムを構築していったという。

復帰戦に臨む中嶋さん(写真:伊藤菜々子)
中嶋さんへの支援プログラムで、最初に実施したのは身体機能の評価だ。骨盤の状態、姿勢、筋力などをチェックする。特に重要なのは骨盤底筋で、産後の緩んだ状態のままで練習を再開すると、腰痛や膝痛を引き起こす。土肥さんは言う。
「けがをした後に身体機能を評価するのは当たり前です。復帰のためのトレーニングメニューは、その評価に基づいてつくられる。なのに、(けがと同様に体が大きく変化する)出産後の選手に対する評価の必要性を、誰も言っていなかった」
中嶋さんは「確信をもってトレーニングに取り組めるようになった」と言う。
「自分でやっていたときは、これをやっていいのか分からないという不安を抱えながらでした。でも、専門家であるJISSの方にメニューを出していただくことで、トレーニングに集中できました。運動している最中に、筋肉にしっかりと刺激が入る感覚が持てました」

JISSの土肥さん(中央)と、プロジェクトのメンバーのみなさん(写真:伊藤菜々子)
出産から約6カ月後の10月20日。中嶋さんは復帰戦のグラウンドに立った。関東女子ラグビーフットボール大会。中嶋さんは、大学・クラブ合同チームABISの選手として、日体大ラグビー部女子と対戦した。後半からフランカーとして出場すると、果敢にタックルし、スクラムに入り、周囲に目を配って大きな声で指示を出した。試合は後半に逆転して勝利。試合後、中嶋さんはこう振り返った。
「怖くなかったし、プレーに集中できました。体に不安は全然なかったです」

復帰戦でタックルする中嶋さん(写真:伊藤菜々子)
「出産・子育ては選手として成長するチャンス」
三重バイオレットアイリスの高木さんも、中嶋さんと同様のサポートを受けているが、スキームが少し異なる。中嶋さんがJISSの直接の支援対象選手であるのに対し、高木さんのサポートの主体はチームにある。
高木さんの出産から5カ月後の今年5月、「エレナサポートチーム」が結成された。チームトレーナーの佐久間さん、監督の梶原さん、チームマネジャーの櫛田さんを中心に、JISSのコーディネーターと土肥医師、東海林さん、さらに栄養面や心理面、産婦人科の医学的な知見については、三重県の大学の専門家にアドバイスを求める態勢が組まれた。

体育館は、もともと物流倉庫だった建物を改装したもの。チームを支援する地元企業が提供してくれている(写真:伊藤菜々子)
最初のミーティングで、佐久間さんは、JISSのドクターから機能評価の方法を教わった。佐久間さんは「産後のトレーニングで骨盤底筋が重要であることや、ホルモンの変化によって現れる症状、血液バランスの変化については、勉強になりました」と話す。
その後一度、JISSの理学療法士とトレーナーが鈴鹿に出向き、佐久間さんの指導方法を確認したが、一貫して、佐久間さんが、高木さんの状態に合わせてトレーニングメニューをつくっている。

(写真:伊藤菜々子)
高木さん自身は、「早く復帰しなきゃ」と焦る気持ちが落ち着いたと言う。
「JISSの方に『出産はけがと同じ』と言われたんです。出産は多くの女性が経験することだし、けがとは違うから、さほどリハビリしなくても復帰できると思われているけれど、それは誤解で、けがをしたのと同じぐらい、体にダメージがある。だから、リハビリをしっかりしないまま復帰しようとするとけがをしやすい。そのことをチームのみんなにも理解してもらえたので、精神的に楽になりました」
高木さんも中嶋さんも、「『出産前の体に戻すというより、新しい体をつくるというイメージでいなさい』と言われて楽になった」と口をそろえる。

(写真:伊藤菜々子)
高木さんは、7月に本格的に練習を開始した。当初は子どもを体育館に連れてきて、隅に寝かせておいた。ところが8月に子どもがRSウイルスに感染した。高木さんの両親も夫の両親も離れたところに住んでいるので頼れず、やむなく子どもと一緒に家にこもった。練習は中断せざるを得ない。ようやく治って練習を再開したが、今度はハイハイして動くようになり、落ち着いて練習ができない。高木さんは「心が折れそうでした」と言う。
意を決して、鈴鹿市のファミリーサポートを利用することにした。「知らない人に預けるのは不安で……」と、利用をためらっていたのだ。いざ預けてみると、子どもも預け先の家庭に慣れてくれた。高木さんはようやく練習に身が入るようになった。
10月中旬。鈴鹿市の体育館に、チームメートと汗を流す高木さんの姿があった。念入りにウォーミングアップしたあと、ゴールの前に立つ。6メートル足らずの距離から次々に打たれるシュートに反応する。「なんか動きが中途半端なんですよ」と首をかしげる。「体がスローモーションみたいで」。実戦復帰の目標は来年1月。はやる気持ちを抑えて「いまできることを精いっぱいやる」を心がける。

チームメートや、櫛田チームマネジャー(左)と(写真:伊藤菜々子)
現役復帰を目指すなかで、職場であるホンダロジスティクスとも話し合いの場を持った。同席した櫛田さんが振り返る。
「総務のスペシャリストの方が来てくださって、社内規定に照らして2年間の育休が使える、試合に出るのも問題ないとおっしゃってくださった。エレナが『会社をやめなければならないかと心配したんです』と言うと、その方は『おめでたいことなのになんでやめるなどと考えるんだ。君がハンドボールをやろうとする限り、会社は応援するに決まっているだろう』と言ってくださって、エレナはまたドワーッと泣いていました(笑)」
東海林さんはこう言う。
「選手は一生現役を続けるわけではありません。女性としての人生のなかに、スポーツ選手としての期間があります。出産や子育てによって、行政サービスを利用したり、まわりの人に助けてもらったりなど、地域社会との関わりを築いていく。そのことが自立を促し、主体性を育てるし、選手としても成長できるチャンスなのです。こうした体験は人間として本当の強さになっていくし、のちの人生にも役に立つと思います」

試合終了後、勝利を祝う(写真:伊藤菜々子)
西所正道(にしどころ・まさみち)
1961年、奈良県生まれ。ノンフィクションライターに。著書に1964年開催の東京オリンピック出場選手たちのその後の人生を追った『五輪の十字架』、『「上海東亜同文書院」風雲録』、『そのツラさは、病気です』『絵描き 中島潔 地獄絵1000日』、共著に『平成の東京 12の貌』がある。