かつて「日雇い労働者の街」として賑わった横浜市中区の寿地区は、現在住民の約半数が65歳以上、その大多数が生活保護受給者という状況にある。そんな寿地区の独居高齢者に足掛け15年寄り添い、訪問診療や看取りに尽力してきたのが、総合内科の診療所「ポーラのクリニック」院長の山中修医師(64)だ。寿地区ではどのように看取りが行われているのか、その現場を取材した。(取材・文:堀香織/撮影:yOU〈河﨑夕子〉/Yahoo!ニュース 特集編集部)
(文中一部敬称略)
望む最期を聞き取る
金曜日の13時。山中は、クリニックの事務員と看護師を乗せ、自ら運転する車で寿地区へと向かった。簡易宿泊所(簡宿)や高齢者住宅などに住む独居高齢者10人を訪問診療するためだ。
簡宿とは、二段ベッドなどを大人数で利用したり、狭い個室を単身で利用したりする宿泊施設のこと。宿泊料は1日およそ1,500〜2,500円で、主に日雇い労働者などに利用されている。

訪問診療で寿地区を歩く山中修医師と事務員(撮影:yOU)
1軒目の簡宿に到着するや、山中は目指す部屋へと階段を急いだ。上層階であっても、体力維持のためにエレベーターは使わない。ノックをして戸を開くと、3畳ほどの部屋の大部分を占めるベッドに酸素吸入器をつけた正木政光さん(75)が腰掛けていた。
「お変わりない?」
そう言いながら小さなトートバッグから聴診器を取り出し、さっと胸の音を聴いてから、血圧計を正木さんの右腕に装着する。正木さんが脚が痛むと告げると、「どういうときにいちばん痛みますか?」と尋ねた。
「曲げ伸ばしするとき」
「動かすと痛いのか……。この腫れ方を見ると、たぶん変形性膝関節症かな」

船乗りだった正木政光さんが簡宿に住み始めたのは4年前。普段は自室でテレビを見て過ごす。隣人との交流はないが、「安心して暮らしています」とのこと。山中については「神様です」と答えた(撮影:yOU)
事務員はそのやり取りに耳を澄ませ、血圧や体温、患者の状態などを次々とメモしている。一方の看護師は、点滴や採血など必要に応じて処置を行う。山中は正木さんに「注射を打つと痛みが取れるからね」と言って、看護師に交代した。

山中は、院内でも訪問診療中も、白衣は着ない。生活がすさみがちな患者たちに、ときに優しく、ときにざっくばらんな口調で話す(撮影:yOU)
別の簡宿に住む関トシ子さん(91)は、寿町で生まれ育った女性だという。部屋に着いた山中はまず窓を全開にし、テレビの音量を下げた。関さんはたばこをいまもやめない。
聴診し、血圧を測った山中が、「便秘ないよね? 腰も大丈夫?」と尋ねると、関さんは笑いながら「大丈夫よ」と返した。

「歌うたい」だったという関トシ子さんは『無法松の一生』を披露してくれた。山中については、「言いたいことを勝手に言って、さっと帰る。でも先生が来るの、いつも楽しみなの」と笑った(撮影:yOU)
訪問診療は患者1人につき、3〜5分。山中いわく、「生存確認」だ。
「変わりがないことだけ、確認しに行っているんです。それ自体は非常に簡単。でも、変わりがあることを見つけるには、変わりがないことを見続けておく必要がある。ずっと変わりがないということを確認に行って、変わりがあったときにどうトリアージ(重症度に従って、治療の優先度を決める)するかを決めるんです」
真新しい集合住宅の一室に住む宮間英次郎さん(83)の病状は、かなり深刻だった。「僕のこと、見覚えある?」という山中の問いにほとんど答えられない。

山中は宮間英次郎さんを抱き起こし、ストローのささったペットボトルのお茶を「飲めるかどうか見せて。自分で持って」と差し出した。これも状態確認の一つ(撮影:yOU)
この日は「患者宅カンファレンス(関係者による情報共有や問題解決の会議)」だった。医師、看護師、事務員、介護支援専門員(ケアマネジャー)などそれぞれの見地から、今後の介護方針、診療方針、看取りの方向性を洗い出し、決定していく。ケアマネによれば、朝昼晩と1日3回介護福祉士が訪問しても足りないほど、宮間さんは日常生活が困難な状態になってきたという。現在3の要介護度を5まで上げる必要があると判断した山中は、クリニックに戻ってすぐに書類を作成することを決めた。
「宮間さん、何か食べたいものはない? 食べないと死んじゃうがね」「点滴は嫌でしょ? それははっきりしてるよね。じゃあ、缶の栄養ドリンクを飲まないといかんよ」
そんな山中の声掛けは、励ましでもあり、患者が最期に何を望むかの確認でもある。宮間さんの場合は、食べる希望があるなら、それを叶える。点滴はしない。

患者の自宅で行うカンファレンス(撮影:yOU)
「この状態であれば、2週間後には餓死するでしょう。昔なら入院して胃ろうを導入するか点滴で保たせるかしたけれど、そんなことをしたくないという人もいる。僕たちがやっているのは、日に日にうつろう患者の希望をその都度聞き、あるいは察知し、できるだけそれに沿う最期をみんなで伴走して見届けるということなんです」
宮間さんが亡くなった場合、発見した管理人が警察や救急車を呼ばないよう、山中は管理人に再度確認してほしいとケアマネに頼んだ。亡くなった場合は、山中が呼ばれ、死亡が確認される。そうすれば不審死扱いではなく、病院で解剖されることもなく、自宅で死ぬことができるのだ。患者の希望通りに。
役割を横断して行うチームの看取り
山中は医師の家庭に生まれ、順天堂大学医学部に進学。卒業後、救急医療の現場、アメリカのクリニック勤務を経て、帰国後の1992年に国際親善総合病院(横浜市泉区)の循環器内科部長に就任した。
寿地区に隣接する横浜市中区不老町、横浜文化体育館の真裏の古いビルの2階にある「ポーラのクリニック」(撮影:編集部)
会議や講演、学会など、診察以外の仕事に追われる日々を一変させたのは、一枚の写真だ。1999年、ホームレスに毛布を届ける慈善活動を通して寿地区と関わり、その際に簡宿で孤独死した男性の遺体写真を目にした。かつては東京の山谷、大阪の釜ケ崎と並ぶ日雇い労働者の街として栄えた寿地区は、時代が下るにつれ、日雇い労働は減少し、失業や家族との絶縁などの事情から独居高齢者や路上生活者が増加していた。管轄の伊勢佐木警察署から「住民の約8割が生活保護受給者」「3日に1人が孤独死」という現状を聞き、山中は衝撃を受けた。
「自分で自分の面倒をみてきた方も、最期だけは助けが必要なのではないだろうか」
2004年3月に辞職し、8カ月間、無給で皮膚科、整形外科、泌尿器科の研修を受けた。同年、総合内科の診療所「ポーラのクリニック」を開業。50歳だった。

簡宿の間を移動する(撮影:yOU)
現在、外来患者は1日50〜60人。週2回の訪問診療で診る患者は約30人。金曜は午後をまるまる使って10〜15人、火曜は昼休みに一人で軽症者を1〜4人診る。患者1人につき月2回が基本で、看取りが近づくと週に2回となる。
訪問診療から看取りまでの「見守り活動」は、開業まもなく山中が一人で始め、2007年からはチームで行うようになった。現在の「みまもりチーム」は、かかりつけ医の山中、訪問看護師、ケアマネ、介護福祉士(またはヘルパー)、生活保護担当ケースワーカー、薬局、連携病院、簡易宿所帳場(ホテルでいうフロント)で構成されている。
介護保険のケアプランを担当する「ふれあいの丘クリニック」のケアマネ・安藤立(りつ)は、みまもりチームの強みを「それぞれが役割をしっかりと果たしつつ、ときとして役割を横断して患者に関わるところ」と話す。

看護師が患者に食べたいものを尋ね、介護福祉士に買ってきてもらうことも。大根餅を所望した患者には、焼いた薄い餅に大根をすりおろして持参したそうだ(撮影:yOU)
病状が進み、死期が近くなれば、患者はさまざまな希望を胸に秘めるようになる。「(簡宿を含む)自宅で死にたい」「痛みだけは取ってほしい」といった医療面の希望、「山下公園に行きたい」「甘いお菓子を食べたい」などの生活面の希望。そうした患者の思いを、誰がどんなタイミングで聞いても叶えてあげられるよう、チームの連携も密になっていく。
「訪問介護ステーション ふぁいと 寿」の介護福祉士、濱田紀江は「細かく連絡をすることに尽きるんです」と説明する。
「メールではなく、電話ですね。相手が出られないときは必ずかけ直す。もちろん、言った、言わないにならないよう、連絡帳にも書き留めます。とにかくチーム全員で情報を共有することが大事なんです」

患者の情報共有にはタブレットを使う(撮影:yOU)
「ポーラ訪問看護ステーション」の看護師、宮沢三奈子は、タブレットを使って看護記録を残す。
「ご自宅に訪問し、全身状態の観察、バイタルサインの測定、床ずれの処置、入浴介助、リハビリ、オムツ交換、内服管理などをしています。そうした中で異常の早期発見をして、関係各所に連絡をする。それがその状態を早く改善するきっかけになる」

左が訪問看護師の宮沢三奈子、右が介護福祉士の濱田紀江(撮影:yOU)
患者が簡宿にいる場合、チームの連携の要になるのが宿泊の管理をする帳場だ。寿地区では長期宿泊者や高齢者が多いため、帳場担当者は宿泊者の金銭や服薬の管理まで買って出る人が多い。ある簡宿の帳場を務める高橋ナツミ(仮名)は「普通は家族がしているようなことを、皆さんにしているだけなんですよ」と笑う。
この簡宿は本館と新館合わせて100ほどの部屋がある。素泊まり、ツーリスト宿泊、短期宿泊、女性は断っており、生活保護受給者の男性の長期契約がほとんどで、20代から90歳近くまでが暮らしている。
「私がみまもりチームから求められているのは、住人側の立場の代弁なんです。病気に対する知識がないとか自分の希望をうまく伝えられないとか、そういう人が多いのが私の実感。例えば、ある男性は先生の前ではいい格好して『痛い』と素直に言えなかったりする。そういうときに、『いま彼は大丈夫そうですが、この時点ではこういう痛がり方をしていました』などとチームの方に伝えるようにします」

100ほどの部屋がある大型の簡宿に住む人たちと帳場担当の高橋ナツミ(左から2人目/仮名)(撮影:yOU)
それは、”住人”の状態を日頃からきちんと見ていないとできないことだ。
「もちろん私だけでは全員には目が行き届かない。でも……」と続ける。「同じ階の人が『◯◯さん、最近食事残しているよ』とか『△△さん、夜中にトイレに何回も行っていたよ』とか教えてくれるんです。それが大事な情報になるんですよね」

玄関口のこの場所で、たばこを吸ったり、本を読んだり、会話したりして過ごす住人も多いという(撮影:yOU)
「安心」という思いが認知症改善に
『横浜・中区史 人びとが語る激動の歴史』によれば、簡宿街の形成は寿地区一帯が戦後、米軍に接収されたことに始まる。
米軍は横浜市の中心部や港湾施設、隣接する中区の埋地(うめち)地区(松影、寿、扇、翁、不老、万代、蓬莱という7つの町)など広範囲を接収した。特に横浜港は軍貨の集積基地や穀物輸入窓口の拠点として栄え、単身の港湾・土木建設労働者が全国から多数集まった。さらに1950年の朝鮮戦争勃発により、軍需輸送の労働需要が増大。1957年、埋地地区の接収解除後に桜木町にあった横浜公共職業安定所が寿町へと移転したことに伴い、港湾労働者を対象とした簡易宿泊所の建設に拍車がかかり、「日雇い労働者の街」が形成されていく。
だが、バブル崩壊後、土建需要が減っていく中で日雇い労働者が高齢化し、横浜市中区社会福祉局によれば、1990年代末ごろから「生活保護・高齢者の福祉の街」へと徐々に変わっていったという。

寿地区の一角。ほんの10年前までは路上で酔って寝入る人も多くごみも散乱していた。いまでは高齢者や看護師、介護福祉士らの姿が多い(撮影:yOU)
いまなお寿地区には120軒余の簡宿が立ち並び、約5700人が定住、そのうちの約87%が生活保護受給者だ(横浜中区福祉局による平成30年11月の調査)。そうした人の中には、ギャンブルやアルコールの依存症者、違法薬物の元常用者も少なくない、と山中は言う。全身入れ墨が入った者や、刑期を終えてやってきた者、身寄りもなく、アパートが借りられなくなった後期高齢者や、うつや引きこもりなどで就職できず、家族とも住めない20〜30代の人もいる。サポートを必要とする人たちが、医療や介護、食事などの支援ネットワークが充実している寿地区に転入してくるケースが増えているというのが、山中の実感だ。
そんな中、みまもりチームが訪問診療を行うのは主に独居高齢者だ。全員がすぐに心を開いてくれるわけではない。訪問診療の回数を重ねても、山中以外の入室を拒む人や返事もしない人もいるという。

2階建ての古い簡宿。20部屋ぐらいあるが、数人しか住んでいない(撮影:yOU)
ただし、死期が近づくことで、受け入れるようになることも多い。
例えば、末期がんだった70代前半の男性。訪問看護の際、カーテンを閉めきり、電気もつけさせず、話し掛けても返事をしない。ポーラのクリニックの看護師・西村節子は仕方なく自らペンライトをつけて点滴をしていた。
「それがある日、『見えるか?』と言って、カーテンを開けてくれたんです。点滴後も『ありがとう』って……。許しの気持ちになってきたっていうのかな」
男性は2週間も経たないうちに亡くなった。
また介護福祉士の濱田によれば、自尊心が高く、自分ですべてやりたがった84歳の男性は、看取りの時期に入ってから看護や介護に感謝を表すようになり、「無理せずにもっと早くにお願いすればよかった」と悔いたという。
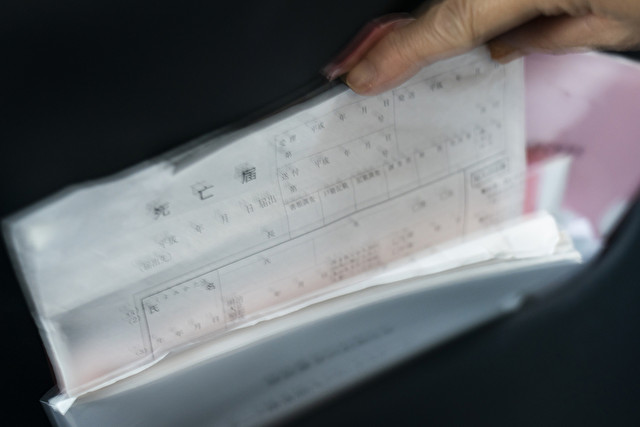
山中の車の運転席ポケットに無造作に差し込まれている死亡届(撮影:yOU)
みまもりチームの存在は認知症の改善にも役立つ、と山中は指摘する。
「俺はここにいていいんだ、この人たちがずっと診てくれて、最期は先生が来てくれるんだ、と安心したときに、認知症がぐっとよくなる人が多いんです」
つまり、見守りや看取りに欠かせないのは、「安心」なのだろう。
「患者本人の安心できる居場所、みまもりチームの支援、チーム内での個人情報の積極的共有。この3つが丁寧に担保されれば、家族不在といえども、独居高齢者の在宅看取りは決して不可能ではない」
死に際の尊厳を全力で守る
ポーラのクリニックの診療統計によれば、2005年1月〜2018年2月の13年間の外来受診患者総数は約6700人。追跡し得た患者数402人(4人の自死を除く)のうち、予期せぬ簡宿内死亡(いわゆる孤独死)は59人、簡宿での看取りは133人、加療や急変などの入院搬送先死亡は210人だった。人口動態調査(2015年)によれば、死亡の際、医療機関や高齢者施設と比べた在宅の看取り率の全国平均は12.7%。ところが、山中のチームの在宅看取り率は33%と全国平均を大きく上回る。

年季の入った簡宿の、住人が死亡した部屋。荷物の引き取り手がない上、オーナーも処分する余力がなく、放置された状態のまま、3年が過ぎた(撮影:yOU)
山中は、「孤独死」を「社会との関わりを失った先の死」と定義する。
「看取りとは、死に目に立ち会うことではなく、患者が納得できる死に方、死に場所を周囲が理解し、その意志を尊重すること。死に際の尊厳を全力で守ってあげることなんですよ。僕が訪問診療で診ている方々も死に目には間に合わないことがほとんど。でも、彼らは決して孤独死ではないんです」
帳場の高橋が“初めての看取り”を涙ながらに思い出してくれた。肝臓がんを患っていた50代後半の男性は、自分よりずっと若い高橋のことを「かあちゃん」と呼び、最後まで「ここ(簡宿)で死にたい」と言っていた。

最新式の簡易宿泊所(撮影時は工事中)。4.52畳の部屋にはナースコールが完備。車椅子も入れる広い共用の浴室や、ストレッチャー対応のエレベーターも設置されている。山中も「俺も最後はここに入居したい」と冗談半分で話していた(撮影:yOU)
「ある日、昼前に部屋をのぞきに行ったら、もう駄目で。かかりつけの先生が来るまで約束した歌を歌ったら、反応してくれたんです」
高橋は歌の好きな男性のため、最後に歌ってほしい曲を尋ねていた。
「生い立ちも複雑で、生まれてすぐに教会に預けられた方で。もともとはAKBが大好きなんだけど、『AKBなんて、逝くときに明るく歌えない』と言ったら、『じゃあ、故郷(ふるさと)がいいな』と……」
男性は高橋が震える声で歌う「故郷」を聴きながら、逝った。

(撮影:yOU)
山中は、寿地区と関わってきた約20年を振り返り、自身がつくったみまもりチームというモデルケースはそのまま各地で使えると断言する。思いをもった医療者、看護者、介護者、行政、地域住民、民生委員が連携し、その土地独特の独居者への対応方法を考えれば、孤独死は激減できるのだと。山中の経験をもとにすれば、大きな施設も多額の人件費も必要としない。費用は患者の年金や生活保護費で十分に賄えるのだ。
2016年には、地域で献身的な医療活動に取り組む医師を顕彰する日本医師会「赤ひげ大賞」を受賞。だが本人は「俺は“赤ひげ”なんかじゃないんだよ」とうそぶく。患者は生活保護受給者だから、医療費は公費負担になる。住所が決まっていない患者の場合は、区役所の住所で医療券を発行してもらう。つまり、「患者の踏み倒しがないから、医師として取りっぱぐれがないんです」。

(撮影:yOU)
看取りの現場を通して得られたものを尋ねると、間髪を入れずに「自分が死ぬのが怖くなくなった」と言った。
「日夜、救命センターで行われる急性期の救急を目的とした医療は、人の生死を変えるだけ。訪問診療や看取りは、人の生きる価値観を変える。僕は寿でいちばん素朴な死をたくさん見せてもらった。人にはいろんな生き方があり、いろんな死に方があり、自らコントロールできるようなものではないけれど、死はそんなに怖いものでもないということを教わったんです」
(編集部注:宮間英次郎さんはその後回復。2019年2月現在、自ら食事をとり、リハビリも始めている)
堀香織(ほり・かおる)
ライター。大卒後、『SWITCH』編集部を経てフリー。『Forbes JAPAN』ほか、各媒体でインタビューを中心に執筆中。単行本のブックライティングとして、是枝裕和著『映画を撮りながら考えたこと』、三澤茂計・三澤彩奈著『日本のワインで奇跡を起こす』など。鎌倉市在住。
最終更新: 2019年2月26日(火)18時32分






































