テレワーク時代の“評価フィードバック”は「言語化力がすべて」…しかし、日本人にはちと難しい
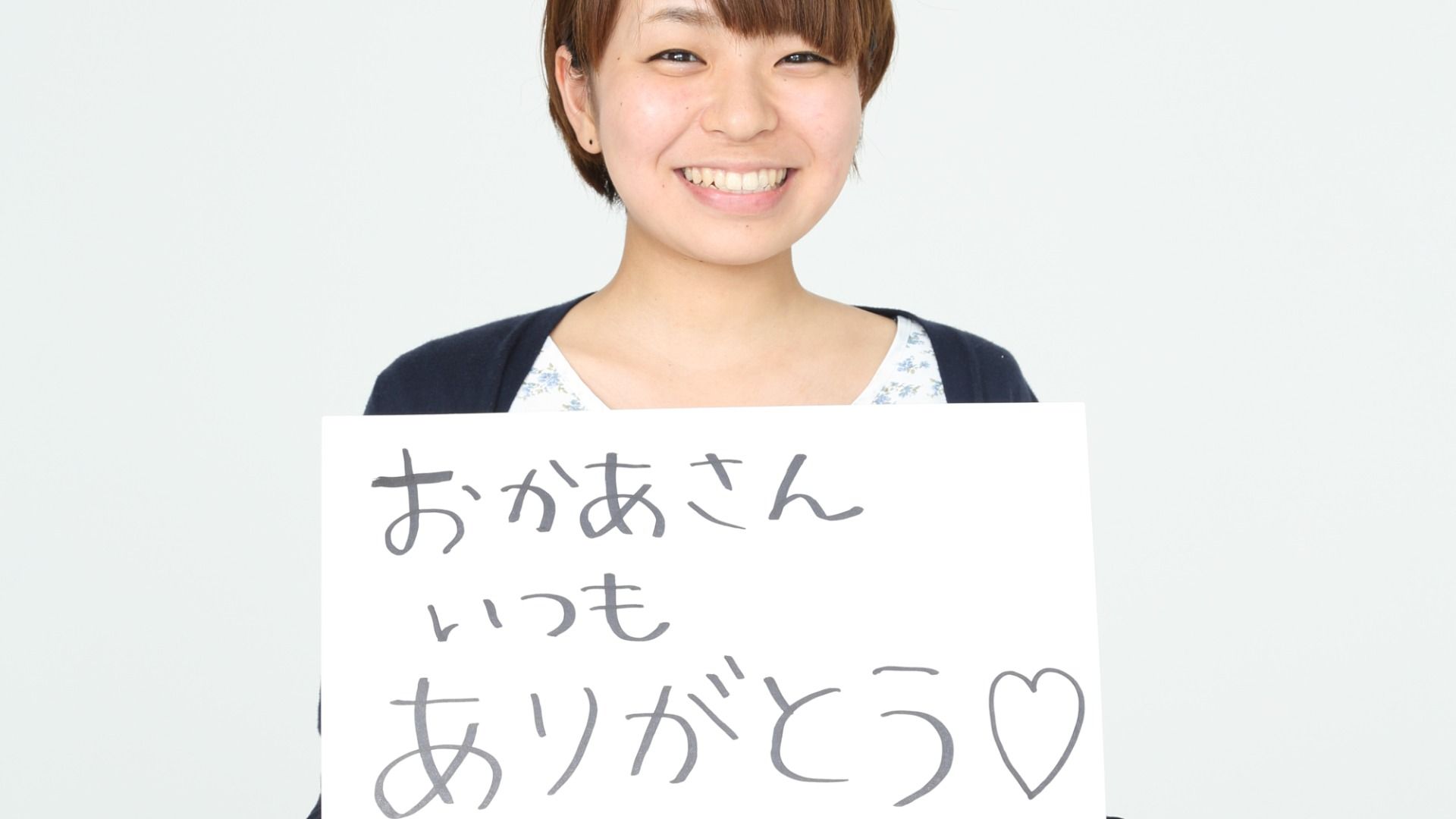
■テレワークは完全に定着した
コロナ禍をきっかけとして日本で急速にテレワーク/在宅勤務が進んでいます。通勤時間や交通費の削減ができたり、会議もオンラインで代替できることが多いことが判明したり、これをきっかけにして業務の効率化が進んだという声もあります。
一方で、オフィスという「リアルな場」とは異なるマネジメントが必要となることも徐々にわかってきて、その対応を進めようとしている会社も増えてきています。
いずれにせよ、コロナ禍が落ち着いたとしても、当分の間はテレワークが完全に終わることはなさそうです。これらの組織マネジメント上の問題は引き続き対応を迫られるものであり続けるでしょう。
■テレワークでのコミュニケーションの成否は「言語化力」で決まる
テレワークを前提としてマネジメントを行っていく際に必要なことは、できる限りすべてのことを「言語化」「明確化」していくことです。
テレワークはそもそも基本的には姿が見えない中での協働ですし、オンラインでのコミュニケーションでも、表情や姿勢、身振り手振りなどの非言語的情報が極端に減ります。そのため、これまでの日本の組織の特徴であった「あうんの呼吸」「以心伝心」「空気を読む」というようなことが、すべてやりにくくなります。
「皆まで言わずに、非言語的情報を通じて、相手に察してもらう」ことで成り立っていたマネジメントは通用しなくなるのです。
つまり、とにかく何でもかんでも「言語化」してマネジメントを行うことが必要ということです。
■「言語化」は改善の機会であり、基本的には良いこと
「言語化」に自信がなく、自分が動いている姿を見せることで指導をしてきたようなマネジャーにとっては、なかなか厳しい状況になりました。
が、私は「言語化」によって、マネジメントにおける様々なものが「明確化」することによって、改善の契機になるのではないかと考えており、基本的には良いことではないかと思っています。
というのも、組織の中で最も変えにくいものが「言語化」されない「不文律」だからです。既に賞味期限を終えたルールでさえ、「言語化」=「明確化」されていなければ、それを変えようという意識もなかなか芽生えにくい。
言葉にしてみる過程で「あれ、もうこのルールは不要では」となれば、マネジメント全体の断捨離が行われ、合理的なマネジメントへとなっていくことでしょう。
■言語化の難しい最たるものが「フィードバック」
ただし、「言語化」はよいことばかりではありません。私達日本人にとって、最も「言語化」をしにくいものがあります。それは、人事上の「フィードバック」です。フィードバックとは「仕事における目標を達成のため、行動の修正をしたり動機付けをしたりするために行う評価、指導、教育」のことを言います。
要は「あなたはこういうところはよい」「しかし、これはもっとこうした方がいい」というような話を伝えることです。褒めるのも難しいとは言いますが、ポジティブなフィードバックはまだマシです。難しいのは「注意して改善を促すようなネガティブなフィードバック」です。
■日本人は「直接的なネガティブフィードバック」が嫌い
数年前にベストセラーとなったエリン・メイヤーの著書『異文化理解力』(日本版2015年刊行)によれば、「評価のスタイル」という側面で、部下などへのネガティブなフィードバックについて、イスラエルやロシア、オランダのように、直接的に、単刀直入に伝える国に対して、日本はその真逆で、最も柔らかく、やんわりと伝える国、とされています。
日本人は言葉による直接的なネガティブ・フィードバックを避けて、相手に改善して欲しいことがあっても、できるだけそれも相手に察してもらうように、それとなく振る舞ってきたのです。
そんな中で、いきなり「あなたはこういうところがダメなので改善してください」とストレートに言って(言うことはできますが)、感情面も含めてスムーズなマネジメントとなるでしょうか。
■既にギスギスし始めている「チャットマネジメント」
IT企業の社員など、もう長年ビジネスチャットなどでマネジメントをしてきているリテラシーの高い人達には「本当かよ」と思うでしょうが、多くの日本企業は現時点ではそれほどビジネスチャットを代表とした「徹底的に言語化したわかりやすいマネジメント」に慣れていません。
コロナ禍によって「仕方なく」ビジネスチャットの浸透が進んだという段階です。そこで各社での「あるある」は言語化能力の低い人が、婉曲的な表現も使わずに、ストレートな言葉を相手にぶつけて、それによって人間関係が悪化するということです。テレワークの負荷の一つにもなっている可能性もあります。
■「言語化」は単なる「明確化」ではない
つまり、とても面倒くさいと思われるかもしれませんが、日本という国においては、テレワークでいかに言語化・明確化が必要だと言っても、歯に衣着せないストレートな明確化を行ってはいけないということです。
少なくとも、故事で言う「人を見て法を解く」で、相手のコミュニケーションスタイルの好悪をみて、言葉を選んでいかなければなりません。
「ビジネスは結果がすべて」なのですから、フィードバックもそれによって相手の行動が改善されなければ失敗なわけです。
フィードバックをする人は、「自分がどういう物言いが好きか」ではなく、相手にどう伝えれば、本意が伝わり行動が変容するのかを考えて言葉を使う必要があります。それが日本のテレワークを成功させるための隠れたポイントかもしれません。
※BUSINESS INSIDERより転載・改訂










